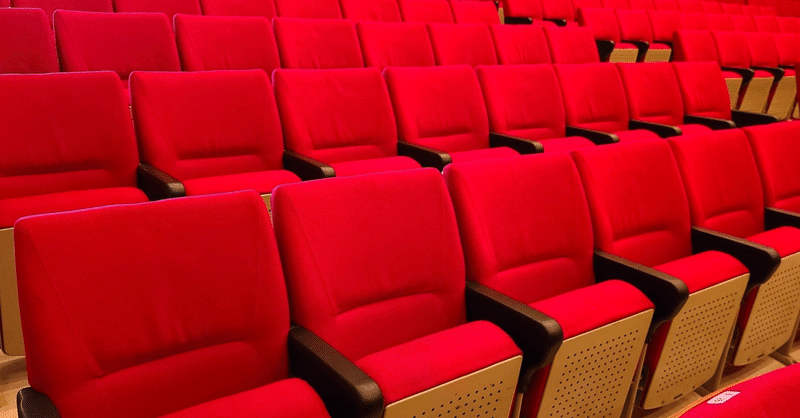
経験値ゼロの私がヨーロッパから役者を呼び、英語劇のツアーを回っている話。
今、オーストリアからAlessandro Visentin(アレッサンドロ・ヴィセンティン)という一人の役者が来ている。
3週間の小さなツアーを日本で回るために。
彼が遠く日本へと運んできたものは、「英語劇」だ。
ただ英語で演じるだけの劇ではない。
中学生から大学生までの観客たちに、英語のレベルに合わせて即興で言い回しを変えながら、たっぷり英語に浸る90分間を提供する。それが英語教育劇と言われるものだ。
ヨーロッパでは、教育に演劇を活用する動きが盛んである。演劇は体の動きや感情と言葉を統合させてくれるし、相手に伝えるためのコミュニケーション力も磨いてくれる。
日本では「英語教育劇」という言葉は耳慣れないが、ヨーロッパは陸続きに異なった言語の国が並んでいるので、こういう実践的な教育が盛んだ。
当然こういった劇を生み出すための工夫や研究も盛んで、それに特化した劇団があったりもする。アレッサンドロはその種の劇団で演技や演出の訓練を受けたプロフェッショナルだ。
しかも、現在一人で活動しているアレッサンドロの劇がユニークなのは、この英語劇を「ワンマン・ショー」として演じる上に、総勢15人ほどの観客をステージに引っ張り上げて即興で演技をさせてしまうところだ。
確かにせっかくの英語劇も、客席に座ったままただ観ていただけでは、リスニング力しか高まらない。役者としても、英語圏でない国で黙って自分を見つめる観客が、どの程度この劇をわかっているのかを確認できないまま終わることになる。
なぜこんな面白い演劇が生まれたのかといえば、それはアレッサンドロが、演技だけでなく脚本や演出も全て自分で手がけるアーティストだから、ということになるだろう。
2020年、等しくコロナ禍に見舞われたザルツブルグの自宅で引きこもり、大勢の役者と仕事ができなかった期間に、たった一人でも演じられるワンマン・ショーを作りたい…と実験的に生み出した即興劇だという。
作ってみれば、それは観客に「体験」を生み出す、これまでの英語劇とは全く違った新しい感触の劇であった。
偶然生まれたのかもしれないが、そもそも自由であるために役者という道を選び、固まることを拒んで流れるように旅をして生きているアレッサンドロというアーティストの気質から、必然的に生まれたものなのだろう。
「ジキル博士とハイド氏」。
イギリス文学の古典であり、しかも一人の人物の中に二つの人格が存在するという、サスペンスで尚且つ複雑なストーリー。
これをたった一人の役者と、観客席から急に「You!」と名指しされた観客が一緒に作り上げていく驚きの90分。
このスリリングなショーを持って、この秋に私は、彼と一緒にあちらこちらの学校を回っている。
*
私が度重なる偶然から彼のコーディネーターとなり、ツアーを作るようになったのは、半年前の3月のことだ。
そもそも私がツアーの仕事などしたことのない全くの初心者であることは、このnoteを見てきてくださった方はよくお分かりだと思う。
全くゼロの経験値であったとしても、できないことなんてこの世には何もないんだよ…と叫びたいのが、今回このnoteを書いている私が最終的に行き着く気持ちだ。
ということはひとまず置いておいて。
3月、PCの画面越しに挨拶をしたのが、彼との最初の出会いだ。
狭い画面の中に私を含めて4人。もう80歳にもなろうとする私の叔母と、彼女の旧ママ友であり40年ほどの付き合いとなる友人女性。そして当時ツアーの途中でオランダにいたアレッサンドロと、何者でもない、子供を寝かしつけた後のボサボサ頭の私。(欧州との時差7時間)
最初に断っておくが、私は英語が苦手だ。それなりのコミュニケーションは取れるが、多分相手には「私、昨日ココ行キマシタ」と聞こえるようなブロークン・イングリッシュ。とてもじゃないが、こんなオンライン・ミーティングに参加するような実力は持ち合わせていない。
叔母が、もう25年以上も続けているこの英語劇を招致する活動を、こんなに英語力があやふやな私に譲り渡そうと思ったのは、ただ一つ「他に継いでくれる人が見つからなかった」という理由だ。
その理由は今、「私でなければならなかった」というものに、嬉しいことに徐々に変わりつつあるのだけど。
正直に言って、英語劇は儲かる仕事ではない。演劇に多くの(とは言えないかもしれないが日本よりはずっと多くの)補助がある欧州を回る分にはまだ良いのかもしれないが、全くの補助がない上に、飛行機に役者と舞台装置を乗せて運んでくるような日本ツアー。この仕事をやりたいと手を挙げる人は、顔の広い叔母の周りであっても流石に見つからなかったようだ。
だが、この演劇を日本でやる「べき」だという気持ちは、一度英語劇を教育現場で観た人は必ず持つと思う。それくらい、これを知っているのと知っていないのとでは、大きな違いがある。
コロナ禍で3年もの間休んでいたこの活動を再始動させるとっかかりを見つけるべく、今は大きな英語教育劇団を卒業してフリーになっているアレッサンドロを紹介してもらったのが、あの3月の夜だった。
とても穏やかな口調のアレッサンドロ。
イギリス英語で、PCのスピーカー越しでも聞き取りやすい。
セダン型のバン1台でツアーが回れるという…え、バン1台?! 少なくともハイエースは必要という先入観が吹っ飛んだ。
荷物はスーツケース4つ。この中に舞台装置の全てと、3週間日本に滞在するための荷物が収まる。
できればアシスタントを連れてくることを許して欲しい。一人で遠い日本でツアーを回ることは、精神的にとてもナーバスになるんだ。アシスタントがいれば、この面は大丈夫。
彼のゆっくりとした説明を聞きながら、私はもう頭の中で、秋の日本中をセダン型バン1台で回っているアレッサンドロの姿を思い描いていた。
これ、やってみたらすごく面白そう!
*
それから、思いつく限りの学校に電話をかけた。やってくれそうなところ、ダメそうなところ、感触は色々。
あれ? 彼の劇がぴったりなのはどんな英語レベルの学校なんだろうか。まずは脚本を読み込んで私が売り込むものがどんなものなのかを把握しなきゃいけないな、と早々に気づいた。
原価は? 何公演集まったらツアーが成立する? チケット代は? 利益率は? 彼とギャランティの交渉もしなければ…。
そんな商売の基本中の基本のようなことを、動き出しながら学んでいった。
仕入れ先(役者)との信頼できる関係性を作ること、良質なものを仕入れること、それを最適な相手に届けること、関わる人全員が納得できる利益を上げること。まさに商売の基本中の基本だ。
思い返しながら、どれだけ危なっかしい道を渡ってきたんだろうとヒヤヒヤする。どこか一つの歯車が間違っていたら大変だけれど、でも絶対にどこかでカバーできる。できるようにする。そう言い聞かせながら、一つ一つの局面を慎重に進んだ。
カレンダーの日付が飛ぶように過ぎていく中で、入国管理局に労働許可を取りに行き、なかなか下りない許可にやきもきし、その間に地図上の学校にマークを付け、移動時間を計算し、ホテルの予約を取る。
疲れ過ぎないように、大きなお風呂のあるホテルを取ろう。ベッドに慣れているだろうけど、たまに和室で靴を脱ぐ時間を作ってはどうだろう?
せっかく日本に来てくれるのだから、良い土地を見せてあげたい。休日の旅程も考える。
ツアーの一覧表を作ると、その中に大きなストーリーが見えてきた。ここでワクワクし、ここで休み、ここで盛り上がり、ここでしみじみする。ツアーの設計というのも、一つの演出のようなものだ。最終日のセルに出国時間を入力した時、まだまだ先にある寂しさに涙が滲んだ。
絶対に良いツアーになる、という確信は、具体的になってくるにつれ育つものなのだ。
長く続く不安や心配、不確かさ。それに耐えるためには、胸に大きなビジョンを描くことが必要だ。仕事だけでなく、日常と全く同じこと。
*
今週は4つの公演があった。客席から沸く歓声が思ったよりもずっと大きい。
拍手。笑顔。
ショーが終わった後もステージに残り、役者を質問攻めにし、写真を撮りたがる学生さんたち。
いいな、若い頃にこんな体験ができて。私の過去にもこんな体験が欲しかった。自分の娘の顔も思い浮かぶ。彼女にも観せてあげたい。
こういう体験があることとないことは、ちょっとした差だけれど大きな影響を人生に及ぼしたりする。
そして公演後の夜、役者からこんなメッセージが届いた。心の中がじわりと芯から温かくなる夜。
Thank you for the night in Yokohama. It's a beautiful city and we had the best ramen ever in a restaurant hidden in a side road. So tasty!
You really have organized a fantastic tour with all these special sights!! Thank you so much for all your hard work!
これだけで、ああ、やって良かった…と心底思えている。
*
こんな感じでまだまだ、今月の中旬いっぱいまでこのツアーは続いていく。
上演していった学校には感想を聞き、来年以降の活動のフィードバックにしていこう。
ようやく、3月から描いてきた円が閉じようとしている。そしてまた新しい円を、描き始める時期になっている。
「The show must go on」。昨日、雑談の中でアレッサンドロの口から出た言葉。大きなビジョンだけを先に描いて、あとは続けていく日々がある。
まるい円が閉じようとしている今に思うことは、こんなやり方ではあるけれど、私にもできたんだなぁという実感。そして、経験ゼロの私にできるんだから、きっと誰にでもできるはず、という感触。
「そう簡単にはいかないよ」と思われるかもしれないけれど、思い描くだけはタダなのだから、ぜひ誰でもどんな分野でもやってみて欲しい。
思い描いた時には、すでに何かが始まっている。
あちこちでビジョンが叶っていけば、この世は少しずつ、良い方向に変わっていくだろう。
タラントン、去年自分の会社をこう名付けた。人が持って生まれた自分の役目(=タラントン)に気づき、世に生かせるようにとの願いを込めて。
これは私自身にも言い聞かせてのことだ。
役目、そんなものをいきなり見つけるのは難しい。人生かけて追い求めていくのかもしれない。
それでもまず、思い描くことは大事だ。これが最初の一歩なんだろうなと、そう思っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
