
Photo by
kiyokari43
さざ波の詩、他 【詩作5編】
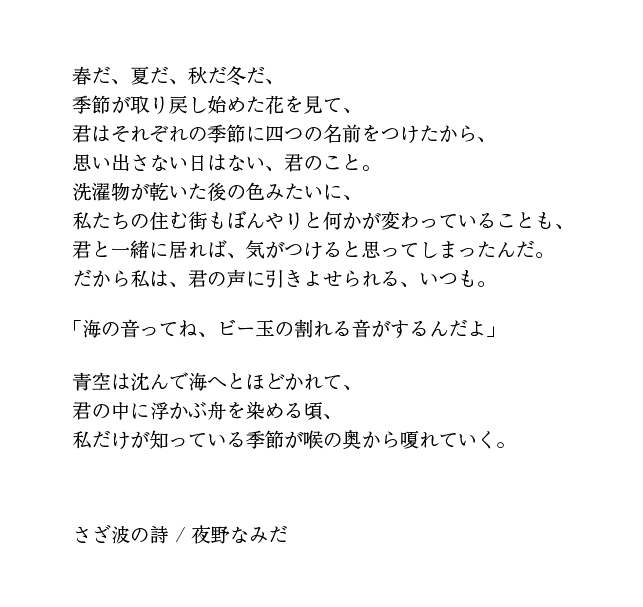
残夏
日向に立つ夏が、花を交換していた、
あれは二人の憶い出だった、
忘れないように形に残すことで、
忘れないことを、信じていた、
海の残像みたいに、空が頭上を埋める、
美しい景色はいつも透明で、
呼吸はいつまでも、きみのためのものだった。
嘘をついてくれようとしたんだ、
永遠があることを、太陽が、
光が、わたしを呑み込んで、
覚えている、雲や風が願うほどの日々中で、
知っていた、夏も空を見上げていることを。
明日に向かって、小石をひとつ蹴飛ばした。
ぼくは夕立の水滴のひとつだった。
中央線がぼく以外の人を運んで、
乗車駅でドアが開いて、
夕立が車内に乗り込んで来たけれど、
居場所がないと思って空に戻る姿を見て、
ぼくは一瞬の、この夏の一部になった。
あの雲も、あの波も、あの花にさえ、
居場所があって、ひとり佇むぼくは、
居場所をなくした、一滴の雫だった。
夕方五時の音楽が鳴るのを合図に、
空は一斉に赤くなり始めて、
行き場を無くした子供たちはみんな、
光に姿を変えていく。
どこまでも深い川がぼくを見失わず、
九月の模様がはっきりと、
ぼくの胸には縫いこまれていた。
夕屋敷
ここから先は
751字
¥ 1,000
きみのために風は吹いている そう思えるのはきみのかけがえのない生活が、日々が、 言葉となって浮かんでくるからだと思う きみが今生きていること、それを不器用でも表現していることが わたしの言葉になる 大丈夫、きみはきみのままで素敵だよ 読んでいただきありがとうございます。 夜野
