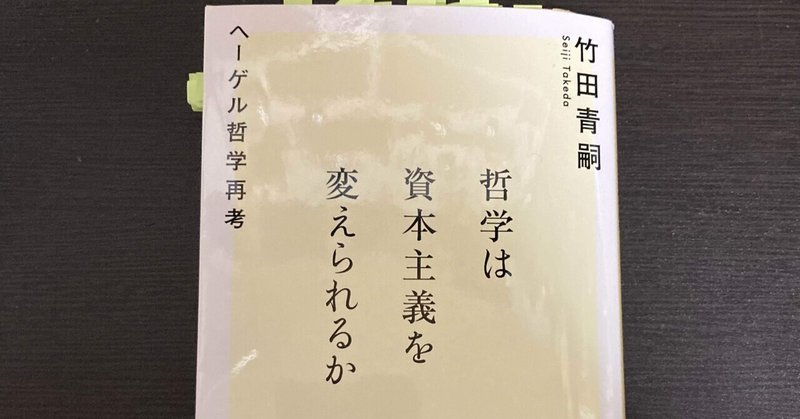
書評:竹田青嗣『哲学は資本主義を変えられるか』
「最高」の近現代哲学「再考」の書 社会原理を巡る哲学の矜持
今回ご紹介するのは、竹田青嗣『哲学は資本主義を変えられるか』という著作。
はじめに、本当に素晴らしい著作であった。
2021年7月にして早くも「2021年下期(上期ではない)の読書No.1に決定!」と評したい。
また、これも著作の内容のことではないが、竹田先生は西洋哲学の初学者にとっての入門的な著作に定評があり、私も大学1年の時から『ニーチェ入門』をはじめいくつかの著作でお世話になってきた。
本著もその内容は高度ながら、「難しい言葉や言い回しが一切ない」という竹田先生らしさは変わらず、哲学系の著作としては大変読みやすいと言える。
それでは本論を始めよう。
①本著の趣旨
まず、本著はタイトルに「資本主義を」とあるのだが、その内容は「資本主義」に関してだけではないことをお伝えしておきたいと思う。
本著の内容は、その対象に「資本主義」も含みつつ、哲学が近現代という社会全体の「原理」をどのように構想し、現実の社会とどう向き合ってきたかを「再考」する、というものとなっている。
ここで言う近現代社会の「原理」とは、「社会という概念が拠って立つところの「理念」や「モデル」の本質」という意味である。
言い換えれば、「社会原理」とは、「社会という概念の本質についての有力かつ強力なアイデア」とでもなるだろうか。
後に詳述するが、本著では「近代国家」の「原理」を「社会契約論」というアイデアの系譜に見る。
「近代資本主義」の「原理」については、「普遍的な交換・分業・消費」というアイデアに見る。
ここで大切なのは、「こうした「原理」のアイデアが真実であるかどうかが重要なのではなく、そうした「原理」を本質と置いた時に如何に社会の概念全体を体系的に説明できるかが重要」という点だ。
哲学の使命は、社会を実証学的に検証することにあるのではない。
実証学的な社会科学が拠って立つことができる「社会の原理」を提示することにある。
もちろん哲学が提示する「原理」は一般化・抽象化されたものであるため、実証学が対象とする現実の個別具体的な事象には多かれ少なかれ「原理」とのズレが確認されることとなるだろう。
これは一見「原理」と「現実」が異なるため、「原理」の誤り・非真実性が示される事態のように思われるが、「原理」の役割は全ての個別具体的な現象を説明できることではない、という点が重要だ。
「原理」は1つの「理念型」「モデル」、言わば「理想」なので、個別具体的な事象が「原理」と乖離した事態は、「原理と現実のズレ・差異・乖離の部分がその現実の特徴や属性、問題にあたる」と捉えられれば良く、そのための「基準」となることが「原理」の役割なのだ。
さて前置きが長くなったが、議論の対象である「近現代社会」を本著では大きく2つの側面から、即ち「近代国家」と「近代資本主義」という側面から再考していく。
②「近代国家」としての近現代社会
近現代社会の「国家」性という側面を再考する上で、著者はホッブズ、ルソー、そして特にヘーゲルという3人の哲学者が、「近代国家」という「社会原理」の定立に重要な業績を残したと指摘する。
彼らに見られるのは、「近代国家の原理」を「社会契約」という「理念」でまとめ上げたという業績でだ。
3人が織り成した業績を本著に従い俯瞰するならば、「万人の万人に対する闘争」と宗教的権威に依拠した超越的支配権からなる伝統社会の「原理」を、「暴力」の抑制(秩序の形成)による各人の「自由の発現」を世俗的手続き(社会契約)に依拠した「国家」によって実現するという「原理」として描き直した、というものとなろう。
殊にヘーゲルにおいて、人々は理念上「自由」を発現するスタートラインに立つに至ったとされる。
しかしながら、「近代国家の原理」と現実における「近代国家」の登場だけでは、人々は「自由」を発現させる方法をまだ持ち合わせていない状態、即ち「自由」を発現できる条件を欠いた状態に留まる。
この不足した条件を充すには、「近代資本主義の原理」が登場する必要があった。
③「近代資本主義」としての近現代社会
近代以前の伝統的経済社会は、大前提として「恒常的な価値の不足」の状態にあったと言うことができる。
モノが少ないからそれを巡る奪い合い(暴力)や権力的搾取が生まれる。
ある意味ではホッブズ的な「万人の万人に対する闘争」状態はこの「恒常的な価値の不足」を原因の1つとしていると見ることができるかもしれない。
こうした伝統的経済社会の制約を「原理」的に変革し得る哲学を最初に提示したのは、アダム・スミスであったと著者は指摘する。
スミスの思想でよく取り上げられるのは「市場の概念」や「市場における神の見えざる手」などであるが、著者はむしろ「生産における分業」という概念の提示こそが「近代資本主義」の「原理」に対するスミスの最高の業績だと指摘する。
これは、「恒常的な価値の不足」との関連から捉えると容易に理解できるだろう。
端的に言えば、「分業」の登場によって社会の生産力が爆発的に向上したのだ。
更に「分業」による作業の細分化は各作業の機械化を容易にし(小さな工程単位だから機械化が容易)、このことが生産力の向上を後押しする。
このように、スミス以降の「分業」の登場が伝統社会の「恒常的な価値の不足」という制約を打ち破っていくこととなったのだ。
しかし、「分業」による生産力の向上だけから「近代資本主義の原理」が定立されたわけではなかった。
大量に生産されることが可能となった価値が、普遍的に「交換」され、そして価値が充足されてしまわないように普遍的に「消費」されること、即ち「交換」「消費」が「分業」に加わり相互に組み合わされることが「原理」には必要であった。
著者によると、「分業」「交換」「消費」が相関的に体系化されたのは、ここでもヘーゲルにおいてであったとされる。
以上を踏まえ、著者は「近代資本主義の原理」を、「普遍分業」「普遍交換」「普遍消費」という3つの要素からなるものと要約する。
このような「近代資本主義の原理」が定立されることで、人々は「自由」を「自由市場における行動」として発現するという、「自由の発現方法」を手にすることと考えることが可能となった。
このように、ヘーゲルによって②③で示した形で「理念化」された「近代国家」と「近代資本主義」の「原理」は、それらが相関することではじめて「近代社会」の「原理」を浮かび上がらせ、「自由の発現」のための条件を整えることになる。
④「近代国家」と「近代資本主義」の相関としての「近代社会の原理」
「近代国家の原理」は、人々が伝統的な「普遍闘争社会」から解放されるに至る基本構造を提示した。
そして「近代資本主義の原理」は、人々が「自由」を「自由市場における行動」として発現するという具体的な方法論を提示した。
ここで押さえるべきは、両者は相補的であるということだ。
どちらか一方だけでは、人々が「自由」を発現できる「原理」となることはできない。
「近代国家の原理」が「近代資本主義の原理」を可能としており、また同時に、「近代資本主義の原理」が「近代国家の原理」を可能にする、という関係にあることを捉える必要がある。
殊に、現代のように「脱資本主義」や「脱成長社会」という社会批判が一定の影響力を発揮するに至った時代においては、後者の関係性、即ち「近代資本主義の原理」が「近代国家の原理」を可能にするという条件関係を捉えることが特に重要になる。
この点については最後に改めて考察する。
話を戻しまとめるならば、「近代社会の原理」とは、「近代国家の原理」と「近代資本主義の原理」の相補によって人々が「自由」を発現する構造が提示されたもの、と捉えることができる。
さて、ここまでの議論で、特にヘーゲルの業績によって体系化された「近代社会の原理」は、社会の「理念型」「理想形」を示すものであった。
言わば「社会の理想モデル」の提示である。
ヘーゲルの業績が理想を巡る「理念」の体系化であったならば、他方で「社会」の「原理」や「現実」に対する「批判の原理」の登場が期待されることとなる。
こうした背景から、「理念のヘーゲル哲学」に対し、「近代批判哲学」として登場したのがマルクスであった。
⑤「近代批判の原理」の登場 マルクスとその誤謬
ヘーゲルの業績以降に登場したのは、マルクスによる「近代批判」の「原理」であった。
それは即ち、「社会の問題や矛盾の根本的で本質的な原因(社会の根本問題)に関するアイデア」と言うことができよう。
余談だが、ヘーゲル的「理念」に「原理」があるように、マルクス的「批判」にも「原理」があるということだ。
マルクスによる「近代国家批判」と「近代資本主義批判」は強力で、現在に至るまで「社会批判」の基本的な構造・枠組みを規定し続けている。例えば、ポストモダン思想等の「近代批判」も基本的にはマルクスによる「近代社会の根本問題」を巡る認識を踏襲していると著者は指摘する。
特にその「近代資本主義批判」は、「資本主義の原理的不可能性」までをも提示するものであった。
まさしく「近代社会批判」の「原理」と呼ぶに相応しいアンチテーゼをマルクスは残したと言うことができるであろう。
しかし著者は、マルクスの「近代批判の原理」にはある誤謬が存在すると主張する。
それは、本来「近代社会の理念・原理に対する「現実」のあり様」に向けられた批判だったものが、いつしか「近代社会の理念・原理そのものに対する批判」、即ちヘーゲル的な「近代社会の原理」に向けられた批判へと転化してしまったという点にあるという。
「原理」と比較した際の「現実」を批判するのならば、本来は「原理」が基準となり、「原理」からの現実の乖離に対し批判が向けられ、現実の改善を目指すべきとなるはずだ。
しかし、「資本主義の原理的不可能性」のような「原理」批判となるならば、例えば「近代社会の原理批判」であれば、「近代国家」や「近代資本主義」そのものへの全否定と撲滅を目指す方向に向かうこととなる。
事実、マルクスの思想はその後「近代社会の原理批判」であるとして受け止められ、現実における社会主義国家(「近代国家の原理」とは異なる原理に則る国家)の登場や、近現代における社会批判哲学の隆盛をもたらした。
しかし著者は指摘する。
マルクスが「近代社会批判」として指摘した根本問題は、本当に「近代社会の原理」の本質を穿つものだったのかと。
例えばマルクスは、「近代資本主義は本当は搾取のメカニズムであることが原理なのだ」というような批判をする。
このような批判を目にした時、我々はそれが「それまで原理とされてきたものが嘘であったことを暴くものなのか」、それとも「それまでの原理や理念が間違っていたのではなく、現実が理念の描くところに至っていない(現実の方に問題がある)という批判なのか」を、マルクス自身の認識を一旦脇に置いて丁寧に精査せねばならない。
このような精査の立場から著者は、マルクスの批判はマルクス自身がどう思っていたかに関わらず、決してヘーゲル的な「近代社会の原理」そのものへの批判とはなっておらず、現実が抱えていた問題を批判したものであったと主張する。
では、著者は何故そのように判断したのだろうか。
⑥「近代社会の原理」の再々考
著者は改めて、ヘーゲルによって定立された「近代国家の原理」と「近代資本主義の原理」からなる「近代社会の原理」を再考する。
「原理」を一つのメカニズムと捉えるならば、メカニズムとは「入力→プロセス→出力」という構成を取ることになる。
では、ヘーゲル的な「近代社会の原理」における、特に「出力」(即ち「原理」の目的)とは何であったか。
それは既に見てきたように、人々の「自由の発現」だ。
伝統的社会の楔から人々が解放され、人々が「自由」を発現できる条件を整えることが、「近代社会の原理」の欠かせない一部をなしているのである。
このような「近代社会の原理」の文脈にとっては、「そのような「原理」では「自由の発現」は不可能である」という論旨の批判がなされるのであれば、それは「原理」批判たり得るだろう。
しかし、マルクスの「近代批判」はそうではなかったというのが著者の判断であった。
つまり、マルクスは「近代の本質」ではなく「近代の属性」を批判したものであったにも関わらず、それが「近代の本質批判」であると認識されてしまったという誤謬を抱えることになった、というのが著者の主張するところである。
⑦現代の社会批判を巡る私の試論
「近代社会の原理」を本著のように捉えるならば、それを基準に「現代の現実社会」や「現代の社会批判」を検証することができるはずだ。
前者の「現代の現実社会の検証」は、ヘーゲル的「近代社会の原理」と照らし合わせることで、その相違や乖離が現実の問題という意味を帯びて浮かび上がることを意味する。
問題は、後者の「現代の社会批判の検証」だ。
ヘーゲル的「近代社会の原理」を基準とするならば、前者によって浮かび上がった「現実上の問題」を「現代の社会批判」が適切に対象としているか、が検証されるべき重要なポイントの1つとなるはずである。
より具体的には、「自由の発現」を阻害するような現実問題を指摘する批判であるか、はたまた批判の内容そのものが「自由の発現」を軽視するものであったり阻害するものとなり得るものであるか、を問うことが重要なポイントになるはずということだ。
ここではテーマを「資本主義」に絞って見てみたい。
現代は、いわゆる「新自由主義」が猛威を振るった経験を有することから、その反省や批判としてのラディカルな資本主義批判が流行する傾向にあると言えよう。
ここで先に、ヘーゲル的な「近代資本主義の原理」の再確認をすると、ヘーゲル及び著者にとって「資本主義の原理」の「本質」とは、「普遍分業×普遍交換×普遍消費による価値の生産力が人々の自由の発現を可能にする条件の1つとなる」という点にあった。
大胆にシンプルにまとめるならば、「資本主義は自由の必要条件である」ということだ。
これは裏を返せば、資本主義がなくなれば人々は「自由」を発現できなくなり、社会そして人々は前近代的な普遍闘争状態に回帰してしまう、という認識を意味している。
この主張の含意を大胆に示すならば、「安易な資本主義の「全否定」は「自由の発現」にとって誤りである」との認識を含むものと言えるだろう。
まさにこの誤謬に陥ったのがマルクス以降の近代批判哲学であったと著者は指摘している。
話を「現代の資本主義批判」の検証に戻すと、「現代の資本主義批判」には、大きく2つの傾向があるように思われる。
1つは、何らかの現実上の制約、例えば資源の枯渇だとか、人口問題、食料問題、環境問題、エネルギー問題のような、「自由の発現」以前の「人間や生命の生存基盤」上のの問題・制約から、現実の資本主義を修正し、持続的な成長を目指さねばならない、という立場である。
もう長くなり過ぎたので乱暴になるが、可否を別とするならば、これは理念としては良いと私には思われる。
「「生産力の向上」という経済成長が人々の「自由の発現」の条件」というヘーゲルの理念を踏襲しており、経済成長を否定せずむしろ成長の持続が必要という立場だからだ。
この立場は、あとは実現可能な方法論を巡って喧々諤々を議論を続けていけば良い。
問題はもう1つの傾向だ。
「脱成長社会」論や「定常化社会」論のような、経済成長の否定を孕む立場である。
こちらの主張をどう判断するかが非常に難しい。
「現代資本主義批判」を巡る哲学的な難問だと思われる。
それは明らかにヘーゲル的な「近代資本主義の原理」の成長肯定的側面への否定を孕んでおり、「自由の発現」への阻害的立場に至り得るものだ。
しかしながらこちらの立場も出自や論拠は現代の現実上の問題(資源問題や人口問題等)にある。
異なるのは、何よりも「生存基盤」の死守を最重要とする点である。
人間や生命の生存基盤が失われてしまったら「自由の発現」なんて言ってられない、「自由」よりも「生存」が何よりも大切、という訳だ。
これには非常に説得力がある。
しかも温暖化問題などは人類及び地球生命の存続にとって極めて重要度と緊急度が高い問題である。
そうした問題が登場し始めたことを考慮するならば、この立場は「もう人類は「自由の発現」という理想を求めていられない状況にまで来てしまっている。ヘーゲル的「近代社会の原理」はいよいよ見直されねばならない」という、「原理」批判の可能性を内包していると考えることもできるのだ。
改めて、この立場をどう判断すべきかは、今の私には手に余り過ぎるテーマです。
しかし、「資本主義の全否定は社会と人々を普遍闘争社会へ回帰させる」という本著の指摘が、判断のヒントになるのではと感じている。
突然の幕引きとさせていただくが、本著を読めて本当によかった。
今向き合うべきテーマが輪郭を帯びることとなった読書体験であった。
読了難易度:★★☆☆☆
近現代哲学「再考」のラディカル度:★★★★☆
ヘーゲル的「近代社会の原理」の明確度:★★★★★
トータルオススメ度:★★★★★
#KING王 #読書 #読書ブログ #読書感想 #読書記録 #レビュー #書評 #人文科学 #哲学 #西洋哲学 #竹田青嗣 #哲学は資本主義を変えられるか #近代社会の原理 #近代国家の原理 #近代資本主義の原理 #自由の可能態としての近代 #ヘーゲル #マルクス #近現代哲学 #ポストモダン思想 #批判哲学
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
