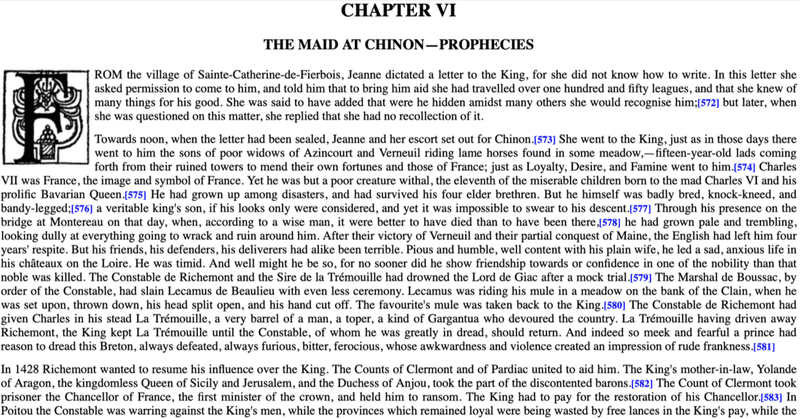
【教皇庁†禁書指定ジャンヌ・ダルク伝】上巻⑥シノンの乙女 -予言
アナトール・フランス著「ジャンヌ・ダルクの生涯(Vie de Jeanne d'Arc)」全文翻訳を目指しています。原著は1908年発行。
1920年、ジャンヌ・ダルク列聖。
1921年、A・フランスはノーベル文学賞を受賞しますが、1922年にローマ教皇庁の禁書目録に登録。現在、禁書制度は廃止されていますが、教皇庁は「カトリック教義を脅かす恐れがある禁書だった本を推奨することはできない」という立場を表明しています。
目次一覧とリンク集↓↓
Chapter VI.
The Maid at Chinon-Prophecies
(シノンの乙女-予言)
字数が多い(2万4000字)ため、訳者の裁量で「小見出し」をつけています。
6.1 シャルル七世の生い立ち
聖カトリーヌ・ド・フィエルボワの村で、ジャンヌは口述して書いてもらった手紙を王太子(シャルル七世)に送った。
この手紙の中でジャンヌは、王太子のもとへ行く許可を求め、王太子を助けるために150リーグ以上も旅をしてきたこと、そして王太子のためになることをたくさん知っていると伝えた。
さらに、「もし王太子が多くの人の中に隠れていても、私はあなたを見分けるだろう」と付け加えたと言われているが、のちにこの件について質問されたとき、ジャンヌは「そんなことを言った記憶はない」と答えた。
手紙が封印された正午頃、ジャンヌと護衛たち一行はシノンに向けて出発した。
当時、アジャンクールやヴェルヌイユの戦いで戦死した騎士の遺児たちは、困窮する未亡人(母親)に育てられ、15歳ほどになると草原で足の不自由な馬をつかまえて廃墟から王太子のもとへ向かった。自分たちとフランス王国の運命を立て直すために。
彼らと同じように、ジャンヌも王太子のもとへと向かった。
王太子ことシャルル七世は、フランスのイメージでありシンボルであった。しかし、彼は狂気の王シャルル六世と淫乱王妃イザボー・ド・バヴィエールの間に生まれた悲惨な子供たちの10人目で、不幸な人間のひとりに過ぎなかった。王子は災難の中で成長し、4人の兄たちに先立たれて唯一生き残った。だが、発育の悪い体つきをしていて、膝が曲がり、脚は細く鰐足(内股またはガニ股)で、王子らしい顔立ちでありながら王統の血脈を疑われていた。
あの日、モントローの橋の上で王太子を見かけた賢者によると、そこで生きているよりも死んだほうがマシかと思うほどに青ざめて震えていた。王太子の周りが荒れ狂い、すべてが破滅していく様子をただじっと見つめていた。
イングランドはヴェルヌイユで勝利してメーヌの一部を征服した後、王太子に4年間の猶予を与えた。だが、彼の友人も、彼を守る者も、彼を救う者もみな同様にひどい状況だった。王太子は敬虔で謙虚な性格で、平凡な妃(マリー・ダンジュー)との生活に満足しながら、ロワール河畔にある城で悲しみと不安に満ちた生活を送っていた。
王太子は臆病だった。貴族のひとりに友情を示したり信頼を寄せたりすると、その貴族はすぐに殺されてしまうからだ。リッシュモン伯とラ・トレムイユ卿は模擬裁判のあとでジアック卿を溺死刑に処した。
ブサック卿は、リッシュモンの命令でル・カミュ・ド・ボーリューを、さらに簡単に略式的な裁判もなく殺害した。ルカムスはクレイン川のほとりでロバに乗っていたときに襲撃を受けて倒され、頭を割られ、手を切り落とされた。可愛がっていたロバだけが王太子のもとへ連れ戻された。リッシュモンは新たな寵臣としてラ・トレムイユ卿を王太子に与えた。樽のような巨漢で、伝説の巨人ガルガンチュアのように国を食い荒らした。
ラ・トレムイユ卿がリッシュモンを追い払い、王太子はあの恐ろしいブルトン人(ブルターニュ出身のリッシュモンのこと)が戻ってくるまでラ・トレムイユを手元に残した。
優しくて怖がりな王太子が、このブルトン人を恐れるのは理由があった。いつも打ち負かされ、いつも怒り狂い、苦々しく、苛烈で、気まずさと暴力行為が、厚かましくて無礼なイメージを作り上げていた。
1428年、リッシュモンは王太子への影響力を取り戻そうとした。クレルモン伯とパルディアック伯はリッシュモンを支援するために団結した。王太子の義母ヨランド・ダラゴン(シチリアとエルサレムの実権なき女王で、アンジュー公夫人)は、不満を抱いていた貴族たちの味方となった。クレルモン伯はラ・トレムイユを捕らえて身柄を拘束したが、王太子はラ・トレムイユを解放するために身代金を支払った。
イングランド軍がロワール川に向かって進軍している間、ポワトゥーでリッシュモンは王太子の家臣と戦い、王家に忠誠を誓っていた地域では「無所属の騎士(フリーランサー)」たちが王太子の財産で浪費に明け暮れていた。
このような悲惨な状況下で、小柄で小心な王太子はますます小さく痩せ細り、人間不信をこじらせて臆病になり、哀れな姿をしていた。しかし、彼は他の王にも劣らない優れた存在であり、おそらく当時、必要とされていた王だったのではないだろうか。
ヴァロワ王朝の初代フィリップ六世や第二代国王ジャン二世なら、剣を交えて領地を奪い合う戦いを楽しんだだろう。貧弱なシャルル王太子は、武勇を振るう腕力も欲望もなく、群衆の前で馬にまたがって戦いに出ようなどとは考えもしなかった。
王太子にはひとつ美徳があった。彼は武勇を好まなかった。勇敢な偉業を誇るために戦争を仕掛けたり、侠気あふれる騎士にはなり得なかったことだ。
王太子の祖父シャルル五世も騎士道精神に欠けていたが、イングランドに大きなダメージを与えていた。孫(シャルル七世)は智謀知略に長けていなかったが、祖父譲りの小賢しい知性を失っていなかった。槍の切っ先を交えるよりも、政治的な交わりで条約を調印する方が得られるものは大きいと考えていたようだ。
6.2 困窮するシャルル七世と家臣たち
困窮する王太子(シャルル七世)を嘲笑する話が流行っていた。
聞くところによると、王太子は靴を新調する金銭さえなく、靴屋は新しい靴を足から引き抜いて古い靴を残して帰ってしまったという。またある日、ラ・イルとザントライユが王太子に面会を求めると、王太子は妻と食事中で、二羽の鶏と羊のしっぽが唯一のご馳走だったという話がある。しかし、これらは単なる微笑ましい話に過ぎない。
オーヴェルニュ、リヨン、ドーフィネ、トゥーレーヌ、アンジュー、そしてギュイエンヌとガスコーニュを除くロワール以南のすべての地域など、王太子は依然として広く豊かな領地を所有していた。
王太子の主な財源は、各地の総督(代官)を招集して徴税することだった。
貴族たちは「税金を差し出すのはプライドに関わる」と主張して何ひとつ出さなかった。聖職者たちは貧しいながらも何かしら献上したが、取り分以上に財政的な負担を強いられるのは第三身分であった。
(訳者注:第一身分の聖職者、第二身分の貴族、第三身分の平民が出てくることから、三部会を指している)
「人頭税(タイユ)」が課されるようになった。王太子は毎年、時には年二回、地方三部会を招集したが困難がつきものだった。街道はとても危険で、国中いたるところで旅人が襲われたり殺されたりした。町から町へ徴税する役人には武装した護衛が付き添った。
1427年、アンジェに駐留していたサバットという名の「自由兵(フリーランサー)」がトゥレーヌとアンジューを恐怖に陥れたため、町の代表者たちは三部会を欠席した。自分たちが納めた税金が王国のために使われると信じていれば、状況は違っていたかもしれない。しかし人々は、王太子がまず貴族への借金返済に充てることを知っていた。
代表者たちは、略奪を抑制する対策について話し合うために招集された。だが、王太子に仕える将校たちは口を開けば「川に投げ込んで溺死刑にするぞ」と脅した。
1425年にメアン=シュル=イェーヴルで開かれた三部会で、良心的な町の人々は「喜んで王太子を助けたい」と言ったが、その前に略奪を終わらせることを望んでおり、ポワティエのユグ・ド・コンベレル司教も賛成した。ジアック卿は王太子に、「もし私の忠告を受け入れるなら、コンベレル司教は同じ意見の仲間たちとともに川に投げ込まれるでしょう」と進言した。そこで、町の人々は特別税26万リーヴルを決議した。
1427年9月、シノンでは戦費として50万リーヴルを決議した。
1428年1月8日、王太子は「半年後の7月18日にトゥールで地方三部会を招集する」と王令を発布したが、当日は誰も出席しなかった。7月22日に新たな召喚状が出され、9月10日に改めてトゥールで開くように命じられたが、その三部会は10月に入ってやっとシノンで開催される有様だった。
ちょうどその頃、ソールズベリー伯が率いるイングランド軍がロワール川に進軍していたため、シノンでは50万リーヴルが決議された。
だが、善良な人々がこれ以上税金を納めることができなくなる日は遠くないだろう。戦争と略奪の時代は、多くの畑が休耕地になり、多くの商店が閉まり、町から町へ旅する行商人もほとんどいなかった。
このような時勢だったので税収は悪く、王太子は実際に金欠に苦しんでいた。恥じ入るほど貧乏だった王太子が急場をしのぐには、三つの金策があった。
第一に、義母ヨランド・ダラゴン、寵臣ラ・トレムイユ、宰相、肉屋、ブールジュ司教座の参事、鮮魚屋、料理人、従僕など——王太子はあらゆる人から借金をしていたため、ほとんどの収入を債権者に渡していた。
第二に、王太子は王領を明け渡し、彼が持っていた土地や町は他人のものになっていた。
第三に、王太子は偽の貨幣を造った。といっても、悪意があったのではなく必要に迫られてやったことで、貨幣の質を下げる習慣はごく普通に行われていた。
何にしても、慢性的な赤字を根本的に解決する方法は何もなかった。
寵臣ラ・トレムイユの唯一の称号はコンセイエ・シャンベラン(助言役の侍従)のみだったが、王国の偉大な高利貸しだった。債務者は王太子をはじめとする多くの貴族たちで、そのために強い影響力を持つようになった。困難な時代背景を利用して、彼は私腹を肥やす目的で王室に仕えていたが、そのような下心を差し引いても価値のある人物だった。
1428年1月から8月にかけて、ラ・トレムイユは2万7000リーヴルもの大金を融資し、その担保として土地と城を受け取った。
幸いなことに、王室の評議会には、商売上手な法学者や聖職者が何人も参加していた。
その中の一人であるアンジュヴァンのトレーヴ卿ロベール・ル・マソンは平民出身で、摂政時代から評議会に参加していた。シャルル七世に仕えていた下級身分の中で最初の人物であり、「よく尽くされた人(Le Bien Servi)」と呼ばれるきっかけとなった。
二番目の人物にあたるゴクール卿は、軍事関連で王太子をよく助けた。
私たちが可能な限りよく知ることを学ばなければならない第三の人物がまだいる。彼はこの物語の中で重要な役割を果たすことになるからであり、彼の全体像を知るほどに、さらに大きな意味を持つだろう。
レグノー・ド・シャルトルは宰相に上り詰めた人物として知られている。
ノルマンディーの森と水辺の領主だったヘクトル・ド・シャルトルの息子レグノーは、ボーヴェの大司教になり、その後、教皇ヨハネ23世の侍従となり、1414年、34歳の時にランスの大司教座に昇格した。
翌1415年、三人の兄弟がアジャンクールの戦いで戦死した。1418年に父ヘクトルはパリでブルゴーニュ派に殺され、レグノー自身も投獄されて死刑を覚悟していた。
レグノーは獄中で「もし生きてここから出られたら、私は死ぬまで毎週水曜日は一切食べずに断食し、毎週金曜日と土曜日の朝は水のみを食事にします」と誓願を立てた。非常時の行動で人を判断してはならない。それにもかかわらず、このような誓いを掲げた彼を無神論者と同一視することはためらわれる。彼の知性は、当時の一般的な信念に従っていただけだと結論づけることができる。
アルマニャック伯の悲劇的な忠誠心を受け継いだレグノーは、王太子の重臣として頭角を表し、王太子はレグノーにラングドック、スコットランド、ブルターニュ、ブルゴーニュなど各地への重要な任務を託した。ランスの大司教は、非凡な能力と不屈の熱意でその任務を遂行した。
12月、大司教は王太子への献身と自分の健康状態を理由に「ブルゴーニュ派の獄中での誓いを守れなくなったことをお許しください」と聖なる神に祈った。王太子にはレグノーが必要で、任務のためにしょっちゅう過酷な長旅をしていた。
1425年、王太子と王国がルーヴェ総統に統治されていた時、博識な弁護士であり愚かなところもあったかもしれないが、クレルモン司教シャルパイニュのマルタン・グージュに代わってレグノーが宰相に任命された。しかし、その後まもなく、フランスの元帥アルテュール・ド・リッシュモンがルーヴェを解任・失脚させたため、レグノーはマルティン・グージュにその任命を売り渡して2500リーヴルの金貨を得た。
ランス大司教であるレグノーは、ラ・トレムイユほど金持ちではなかったが、自分の持っているものを最大限に活用していた。レグノーも王太子に金を貸していた。しかし当時、王太子に金を貸さない者はいなかっただろう。王太子は1万6000リーヴルの金貨と引き換えに、レグノーにヴィエゾンの町と城を与えた。
ラ・トレムイユがリッシュモンをルーヴェと同じように失脚させると、レグノー・ド・シャルトルが宰相に返り咲き、1428年11月8日に就任した。この頃までには、王太子の評議会はオルレアンに武器と大砲を送っていた。ランス大司教は宰相に任命されるとすぐにオルレアンのために身を投じ、何も問題を起こしていない。
レグノーは聖職者でありながら財産にこだわる俗物だったので、情けない人物に見えるかもしれない。だが、フランス王家に対する大義と献身について疑う余地はないだろう。豹と赤十字(イングランドの紋章)の旗下で戦う者たちを憎んでいたのも事実である。
【※誤字脱字・誤訳を修正していない一次翻訳はこちら→ローマ教皇庁†禁書目録に指定されたジャンヌ・ダルク伝】
ここから先は
¥ 100
最後までお読みいただきありがとうございます。「価値がある」「応援したい」「育てたい」と感じた場合はサポート(チップ)をお願いします。
