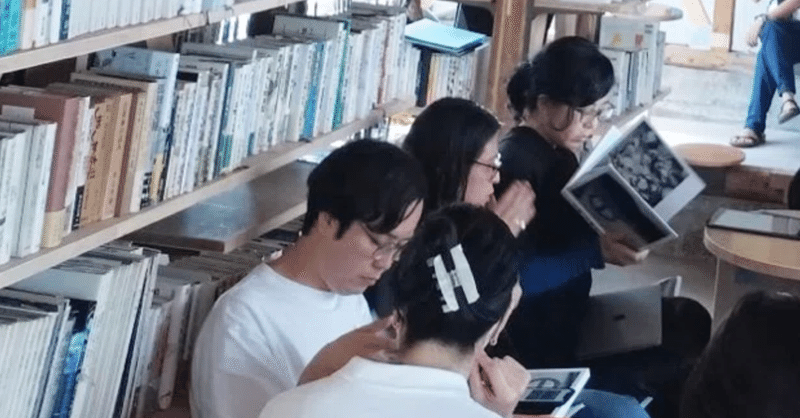
連続トーク「何故、写真なのか」 金川晋吾×川崎祐(聞き手 清水裕貴) “何故写真家が文章を書くのか”
2024/5/3~6 蒲田のさいとう読書室にて行われたイベント「写真を読む読書室」内のトーク企画「何故、写真なのか」の記録です。
何故写真家が文章を書くのか
写真集のデザインの謎
清水「金川さんが『長い間』を作る時に、川崎さんの『光景』を参照したとちらっと聞きましたが、どの点を参考にしたんですか」

金川「具体的に参考にしたというより、この本はすごく変で妙な魅力があるよねという話をデザイナーの宮越さんとしていました。(デザイン:宮越里子)何がどう具体的に反映されているのかはわかりませんが、僕はこの本を宮越さんにしばらく預けていました。不思議な本ですよね。例えば、この表紙のマークとかよくわかりませんよね。これはなんなんでしょうね」」

清水「これなんなんだろうね」
川崎「これ、僕はまずデザイナーに寄藤文平さんを指名してお願いしました(デザイン:寄藤文平+岡田和奈佳)細かい仕事をしつつ、見え方を大胆にずらす仕事をする印象がありました。長島有里枝さんのSWISSとか」
川崎「微妙なずれを溜めていくところが『光景』という作品にはあって、それを見逃さない人だろうと思ったから頼みました。最初の打ち合わせで、「一旅終えた感がある」という感想を言われたんです。『光景』自体はどこにも行かない作品だけど、まるで旅をしたような感覚を覚えたようで、そういう感覚なり、読む前と後とで微妙に変わっている心の変化をあらわすものとして、このマークを裏表に置いたようです」
清水「それじゃ、このマーク川崎さんが作ったんじゃないんですね」
川崎「僕はデザインには口を出さないと決めているので。マークってなんだ?と思ったけど」
清水「表1と表4で90度回転してますけど」

川崎「文章と写真の接点を想像のなかで補っていく作業が必要な本なんです……すなわち、重ならないんですよ。このマークがずれているというのは、そういうところをコンセプチュアルに表現している」
金川「写真とテキストがあるけど、ずれてるよっていうことを」
川崎「なので力技というか、デザイナーさんの設計が重要な機能を果たしている本だった」
清水「この本の不思議なところは、川崎さんの文章と、堀江敏幸さんが写真集に寄せて書いた文章が全く同じ体裁で連続して入ってるとこなんですけど、これは川崎さんの指示ですか?」


川崎「いや、僕はデザインに口は出さない。写真を撮る人だから。デザインは全部任せてる」
清水「川崎さんの文章は作品とセットの文章で、堀江さんの文章は写真集に寄稿した文章じゃないですか。性質が違うのになんで同じ風に入れてるのかなって不思議に思うんですけど、じゃあその意図は川崎さんは「知らない」ってことですね」
川崎「そうです」
清水「ふうん。私は、変えた方がいいと思いました。だって性質が違うじゃないですか。たとえば私の『岸』という写真集、うすっぺらい小さい紙にテキストが数枚入ってるんですけど、あの感じで誰かの書評が入るって変でしょう。文章を作品の一部として扱うなら、他人の文章とは体裁を変えた方がよかったのでは。まあでも堀江さんの文章の方が分かりやすいから、この文章がこの位置に入ってると、写真集として読解しやすい」
金川「なるほど。僕は堀江さんの文章は、川崎さんとの個人的な関係性の話もしてるし、川崎さんがかつて文学をやっていたことなんかも書かれていて、いわゆる評論とは違う立ち位置なのかなと思いました」
清水「堀江敏幸さんは川崎さんの先生だった人ですよね。だからデザイナーさんが堀江さんの文章を読んで、川崎さんの文章と同じように並べてみたんだろうなって」
金川「そうね。でもそれによってより捉え難い本になってるっていう(笑)」
清水「変わってるよね。でもよくよく読むと、シンプルの話なような気も……。人生がうまくいかない時に、くさくさした気分で実家に帰って、きれいな田園風景とかが広がっててお母さんが夕飯なににするとか聞いてきた時に死にたい気分になる、っていう本ですよね」
川崎「いや、いろんな読み方があるから」
野蛮な世界で文章を書くことの困難さ
清水「川崎さんはそもそも小説勉強してたんですよね」
川崎「最初は中上健次を扱っていたんですが、彼はとても濃密な文章を書く作家なのでまとまった時間深く読んでいたら日本語が嫌になって、大学院ではアメリカ文学に専攻を変えてカリブ海の作家を扱いました。大学時代の先生でもある堀江敏幸さんは、僕が学部三年生の時に通っていた大学に赴任されました。学科は違っていましたが、同じ学部の学生なら誰でも志望できる『創作指導』という科目があって僕はゼミ形式のその授業を受講しました。だけどその授業を受けるには課題があって、その課題に通らなくてはダメだった。正直“小説”なんて書けないなと思っていたけど、現代作家で一番好きな作家だったのでどうしても出たかった。その時に出された課題が独特で、たしか「三十枚の短編小説もしくは散文作品、それに加えて二千字の書評を書きなさい」というもの。それなら書けると思って応募しました。堀江先生がまさにそういう書き手で、評論、エッセイ、小説、批評が行き来するような文章を書いていた」
堀江敏幸『郊外へ』
川崎「『郊外へ』は、仏文系の雑誌でフランス文学の紹介を依頼されたけど、紹介だとかしこまっちゃうからもともとの通しタイトルだった“郊外へのびる小説”をやめて"郊外へ"として書いたものであると『あとがき』に書かれていたように思います。だから通しタイトルを『郊外へ』とすることで“紹介”の制限がなくなりつつも“郊外へのびる小説”を紹介する書評のニュアンスも残されていて、なおかつ、モーパッサン以来の“エセー”の伝統、小説的なフィクションの要素、エッセクリティック的な雰囲気を混ぜ合わせたような、とても複雑な、美しい文体で書かれていると受け取りました。そんな堀江さんらしい課題の出し方だった。でもそんな超ハイブローなことを学生ができるわけがなく、小説みたいな文章を書くということを一年間続けていた。なのでこう……小説っていう形で書いていたわけではない。でもそういった経験は後に続くもので、その頃と今と、書くものが変わらない」
清水「そうですね。話聞くかぎり、目指すところがあまり変わらなそう」
川崎「ジャンルの行き場ってのが……今は写真撮ってる人ってことになってるんだけと、そこに腰を据えたくないってのがあって」
清水「ほう」
川崎「なんていうかこう、埋没してたいんですよ」
清水「は? 腰を据えたくないとは逆じゃないの」
川崎「たとえば写真一生懸命やってて、同時に文章もやってると、いい感じにこう……目立たない(埋没できる)」
金川「写真の人なのか文章の人なのかよくわからなくて、結果的に目立たないということかな」
川崎「そう。同じくらいの感じで二つのジャンルをやっていると、いい感じに波が立たないうか」
清水「波が立たないっていうのは、他の作家たちと比べて突出しないということですか?」
川崎「そう、高低差あまりなく、世間から見た時に、いい具合に、何やってるか分からない人になる」
清水「ふうん?」
金川「なるほどなるほど」
清水「川崎さんは意外と結構社会性が強い人で、世の中から自分がどのように位置付けられるのかっていうのを慎重にジャッジするのかな」
金川「意識的であると」
清水「珍しいタイプですよね。もっとこう向こう見ずな人が多いじゃないですかアーティストって……そんなことない?」
金川「いや、うーん。どうでしょう。今、清水さんはたまたま一昨日会ったうつさんとかIkaさんとかが頭に浮かんでるんじゃないのかな(笑)」
清水「そう。あと私も向こう見ずな方だから」
金川「なるほど」
川崎「凪の人生を目指してる」
清水「え?」
川崎「凪のために、一生懸命やるっていう……一生懸命動いて、凪状態を目指す」
清水「へえ、よく分からない。早速不思議なんだけど、とにかくもともと文章から始まったし、その頃と変わらずに書き続けているということですね。でも文学はうんざりして一回やめたって以前言ってませんでした?」
川崎「就職したのがひどい場所だったんで。長時間労働すると何も読めないじゃないですか。大学院で文学理論をやり、社会的、歴史的なものも視野に入れて批評的に物事を考えていたんですが、大変な職場環境だったし忙しかったりしてそういうことは何もできなくなって……」
清水「広告業界でしたっけ」
川崎「十年くらい前に過労自殺の事件が社会問題化したことでだいぶ改善されたようですが、その前は人間がまともに働けるような状態じゃなかった。ほんとうにひどかった。セクシズムにまみれた世界で企画が成り立っていて、その中で、いい意味でも悪い意味でも適応できず、文学理論や人文知が何の役に立つんだっていう苛立ちがありました」
清水「じゃ、社会人になってアカデミアの世界で語られる理想があまりにも通用しないから、一旦絶望したということですね」
川崎「あと堀江さんの授業で、みんなが三十枚書いてお互いに感想を丁寧に述べるというのを繰り返していくうちに、おそろしく上達したんです。堀江さんは具体的なテクニックの指導はしないんだけど、嘘だろっていうくらい変わる。あの頃に書いていた三十枚はどこに出ても文章として独り立ちした立派なものが書かれていたと思います。ただ、それはああいう場があったから書けたのであって、その後はみんな苦しむんです。その兆候は、僕にもあった。社会人になる以前、院生の時から散文は書けなくなっていた」
清水「じゃあ、さっきの「埋没したい」っていうのは、外からの評価をそのようにコントロールしたいっていうことじゃなくて、ご自身が一個のジャンルを続けるのが困難な気がするから、なんですかね」
川崎「うーんと、どうなんでしょうかね。作業量だけはずっとある……埋没するための作業量が」
清水「目立つ目立たないの問題じゃなくて、書き続けるのが苦痛ってことなんじゃないんですか」
川崎「書き続けるんだけど、撮り続けるんだけど、なんていうか、こう……」
金川「えっと、写真はどのタイミングで撮り始めたの?」
川崎「2013年に過労とひどい労働環境で体を壊して、目が見えにくくなったんですよ。たとえば忘年会って、楽しいものでしょ。あの業界における忘年会っていうのは、ちゃんと予算がついてイベント会社が入っているイベントくらいの感じなんですよ。たとえば偉い人の最寄駅の分布を調べて、一番利用者の多い駅を中心に一次会を設定し、そこから最も雨に当たらないルートで二次会、三次会と移動してスムーズに駅に到着できるようにする。たとえば、七十人、三十人、十人、と規模を小さくして、それぞれのコンテンツを考える。その企画のために徹夜するっていう世界。仕切りが悪いと、そのうち詰問される」
金川「ええー。やばいね」
清水「川崎さんのその、退職して何年も経ってるのに癒えない傷が残ってる感じ、すごいですよね」
川崎「人間はあんなことしちゃだめですよ」
清水「そうだね。で?」
川崎「過労で自律神経がおかしくなって、重度の扁桃腺炎で手術手前の状態になった。今思うとそこまで深刻ではない状態だったんだけど、当時は「見えなくなるんじゃないか」と思って、それを理由に写真を撮り始めた」
清水「じゃあ最初から実家まわりを撮っていたんですか」
川崎「いや、最初はコンパクトカメラで身の回りを……。押せば写るものを使うんです。デジタルカメラって色々自分で設定するじゃないでか。でもフィルムはISOが固定されてるし、押せば写る。僕がフィルムを使うのは、今もそれが理由」
清水「文学を勉強しようっていうのは子供の頃からあったんですか」
川崎「親が歯科医なのでもともとは医学部に行こうとしてたんですが、途中で文学的なものに触れて、小説を読み出して、そこからいろいろ右往左往して……。受験勉強的なものはゲーム的にできていたところがあったんですけど、小説を読んで、そんな簡単なロジックで成り立たない何かが沢山あるという迷路に迷い込んで、勉強ができなくなりました。そこから文学にはまっていった。だから高校くらいからですね、文学は」

清水「難しいから、はまったってことですか」
川崎「そう。人の心とか描写とか、よく分からないっていうところから。簡単に言うと、感動っていうのを知ることによって、それがどういうことなんだろうと、知りたくなった」
清水「美術への興味はさらにもっと後ってことですよね」
川崎「そうですね、美術は全然」
状況から切断する写真から、関係性を語りうる写真へ
清水「金川さんも最初は美大じゃないですよね」
金川「そう、神戸大学。高校の頃は何も考えていなかったというか、大学がどういうところかまったく知らなかった。美大に行くという選択肢はまったくなかったですね。一応雑誌で写真家の仕事は見たりして、一眼レフでぱしゃぱしゃ撮ってたりはしたけど」
清水「金川さんがお父さんを撮りはじめたのは、大学出てからですか?」
金川「そう。写真をはじめて最初の五、六年は、スナップを撮っていました。見たものを、写真に撮った時に、状況から切断されてよくわからなくなるっていう感覚が面白かった。写真で、ある対象について物語ることには面白さを感じていなかったし、そんなのできないじゃんと思ってた。でもずっとスナップ撮ってると行き詰まって……。「ちょっと分からなくする」方法が自分のなかでパターン化してしまって。それ繰り返してもな、と思って。しかも、その行き詰まった時にフリーターになって。このままじゃまずいってなと思って藝大受験したら入れて、そのタイミングで親父がいなくなったんですよ」
川崎「すごいタイミング」
金川「そう、ちょうどなんですよ」
清水「それまでも何回かいなくなっていた人ですよね?」
金川「僕が中高生の時はよくいなくなってたんですけど、僕が大学生になった時に両親が別れて、親父は一人で生活していたんですよ。2000年くらいから。一人になってから、普通に楽しく暮らしているのかなと思っていたけど、2008年に久しぶりにいなくなりました。二週間くらいで戻ってきたんだけど、仕事に行かなくなって。この人、どうするんだろうっていう状況になり……それに加えて僕自身の問題として「何撮ればいいのか分からない」という状況が合わさって撮りはじめました。もともと、僕は写真をはじめたときは父のような関係性の強い対象を撮りたいと思っていなかった。でも、今までやりたくなかったことだからこそ、自分と既に関係のある対象を撮ってみようと思った。自分のなかで、写真をどう続けるか、という問題があり、親父も、誰かが関わらないとやばいっていう状態だったんで、その二つが合わさった感じです」
鑑賞に逸脱と複雑性を与えるための言葉
清水「日記はもともと、作品とは関係なくつけていたんですか?『father』の写真展をやっていた初期の頃は、日記を展示していなかったですよね」
金川「そうなんです。写真は2008〜2009年に撮っていて、日記もリアルタイムでほぼつけてたけど、僕は最初は写真だけを見せようとしていた。写真に言葉を添えちゃうと、見方を制限しちゃうんじゃないかと思って。写真の純粋性みたいなものにこだわっていたのだと思います。あと日記には親父の生活の細部が書いてあるから、発表するのはどうなんだろうとも思って……だから最初は写真だけを展示していた。テキストは短いステートメントだけ添えて。でも、ずっと親父に関わっていくうちに、関係性の変化もあり。テキストを見せても大丈夫かっていう気持ちになった」
清水「あ、『father』は2016年発行か。タイムラグがあるんですね」
金川「そうそう。最初は日記を出すことに抵抗があったんだけど、博士で博論みたいなのを書いたけどそれがあまり面白くないと感じたこともあり、日記の方が面白いなと思って。あと親父との関係性の変化で、テキスト見せちゃっても大丈夫かと思った。それで、写真と日記をセットにしたら本として面白いんじゃないかと思って、青幻舎に送って本にしてもらった」
清水「じゃ、ある種「分かりやすさ」をとって、日記を公表することにしたってことですか」
金川「うーん。分かりやすさをとったというわけではないですね。写真を見ることって簡単でもあるけどむずかしくもあるというか。言葉がない方が自由っていう言い方とか可能性もあると思うけど、言葉がないからって本当に自由に見れるかというとそうでもなくて、むしろ見ることのパターンとか習性にはまってしまうこともあると思います。むしろ言葉を添えることで、写真に写っていないことも想像できるし、見る経験がより複雑になりうるかなと」
清水「面白さは増しますよね。人間の写真と日記を一緒に見ると」
川崎「不純物が持ち込まれる感じですよね」
金川「そうそう。最初は写真の純粋性みたいなのにこだわってたけど、その純粋性があやしいっていうか、どうでもいいのかなって思うようになった。むしろ写真に含まれる不純ものを見せたいという気持ちがあります」
清水「そこで気になるのが日記という形式なんですけど、この人たちの生活を日記という形で詳細に示すことによって、この二人(お父さんと静江さん)の人生をよりキャッチーに消費しやすくなりますけど、そのことについての危惧というか、配慮の仕方というか、どんな風なこと思ってますか」

金川「僕は日記で書いたからと言って必ずしも誰かの人生をキャッチーに消費することになるとは思ってなくて。日記には静江さんがこういう人間だったっていうことを書いてるんじゃなくて、僕が会った時に起きたこと、見たことを書いています。そういうことのために、日記っていう形式が合っているんだと思います。その日あった出来事っていうフレームが」
川崎「設定が持ち込まれますもんね」
金川「説明しなくてもいい。『father』の日記も、何故会いに行くのかの説明をせずにいきなり会いに行くところからはじまっています」
清水「幼少期の関係とかは書かず」
金川「そう。そういふうに説明したいわけではないので。そういう時に、日記という形式がいいなと思ってやってる」
清水「でも言葉ってそんなにフラットに扱えなくないですか。写真とは逆で。日記は起きてから寝るまでの全てをフラットに記録するわけじゃない。金川さんが何かしら気に留めたことを書く。そこには意図も感情もある。そこに意図がないとはいえないですよね」
金川「もちろん、そんなことをいうつもりはないよ」
清水「写真はフラットすぎて読み取りにくいんだけど、文章は一言二言でも、その奥にあるものを読み取っちゃうし、書き手としても差別意識や自分の感情が簡単に表出する道具。で、金川さんの日記は、金川さんが思ってるよりウェットなんじゃないんですかね、と思うんですけど。だからみんな面白く読めるんですけど。その自覚はないってことですかね」
金川「え、ないってことですかねっていうのは……その質問はどういうことやろ」
清水「日記っていうフレームを、エッセイや私小説よりは「僕の感情や意図は入りませんよ」っていう意識で選択したんじゃないんですか?という意味の質問です」
金川「いや、そんなことはありえないですよ。日記だからって感情や意図が入らないなんてそんなことはありえない」
清水「そうですよね。でもさっきおっしゃいましたよね。日記は金川さんのお父さんのヒストリーを語るわけでもないし……」
金川「いや、ヒストリーを語るために日記を見せているわけではないってことが言いたかったことでした。日記っていうのは、この日こんな出来事がありましたよっていうフレームがあり、その中で僕が感じた、こう思ってるっていうことを書いてる。だから当然感情も書いてある」
清水「うん、書いてある」
川崎「文章を書いていると即物的になりきれないっていうところがありますよね。言葉は想起させるものだから。たとえば金川さんがすごく仲のいい人について、その人のことを語る時には、トーンが違っていて……そういう言葉が、より読まれるんじゃないかな」

川崎「『いなくなっていない父』は、日記という矩形を与えられている文章と、そうでない文章を行き来しています。で、日記の方が文章がノっている気がしました。それは滑らかになっているということでもあるし、一方で違う意味があるのかもしれません。矩形を与えられていない時の文章には手探り感というか、ごつごつしたところがややあって、その感触と日記を読んだ時に感じた感触との違いっていうものは、わりかしクリティカルかもしれないって、この本を読んで思った。日記って一見即物的に見えるけど……」
金川「いや、僕は、日記を即物的に書こうなんて思ってないです。そんなことを日記であればやれるなんて思ってるわけじゃない。むしろ、写真を撮ってると、自分のなかで起こっていることが記述できない。その記述できないことを書いているんですよ。なんで書くかっていったら」
清水「思いを書きたい?」
金川「すごくシンプルにいうとそうです。その時思ったことを書きたい」
清水「で、そのための形式として、その日に起こったことを日付とともに書くっていうのがやりやすいってこと?」
金川「父の写真を撮る日っていうのが、父に会った日でもあるから、その日にあったことをつけておきたいってのがあった。親父とのやりとりが面白いなあ、残しておきたいなあと思って書いていた」
清水「じゃあ、お父さんの人間性を外に伝えるためではなく、金川さんの心の中に起きたことを整理するための……?」
金川「いや、そこは分離しないですね。お父さんのことと自分のことは、ぱっきり分けられるものではないです」
川崎「日記をつける時は、大きな目的をもたない。焦点化されていない状態で書く。それが方法の一つということですね」
清水「え、日記書く時、目的ないの? 日記って、なにがしかのクリアな目的をもって書くものだと思っていました。悩みを整理したいとか、怒りを吐き出したいとか、忘れたら困ることを書き留めるとか」
金川「いや、それは色々……。もちろんそういうこともあり、そうでない人もいる」
川崎「撮影日誌に近い感じですか。撮るという作業と同時に不可避的に発生する作業として」
金川「そうですね」
川崎「シャッターを押すことは一瞬だけど、撮影という行為はもっと時間の幅がありますよね。そこで撮影者が感じたこと、もしくは撮影者が対象に対して思ったことを、金川さんは日記という形式で書いているんだと思いました。作業日誌としての目的はあるけど、“書く”っていう行為に大義的な目的は持たせずに書いていると言うのかな……何言ってるんだろう(笑)」
日記と文学のあわい
清水「日記は、必ず撮影に紐づいてる作業なんですか」
金川「日記を書くっていうのが? えっとまず『father』の日記はその日につけてません。写真を見て後から書いているものもあります」
清水「えっ。その日のうちに書くのが日記じゃないの?」
金川「色々なのよ日記って」
清水「私全然日記書かないから日記界のこと全然知らない」
金川「日記っていうのはこう書くものっていう決まりはないと思っています。日付があるかどうかだけなのかなと」
清水「金川さん、日記への熱い思いっていうか、執着ありますよね」
金川「いや執着はないよ。でも日記ってこういうもんですねって言われた時に、そうじゃないです、とは言いたくなる。誰かにいきなりあなたってこういう人ですよねって言われた時に、そうじゃなかったら、違いますっていいたくなるでしょ」
清水「ふむ?」
金川「こうですよねって言われた時に、そうじゃなかったら、そうじゃないですとはすごく言いたい」
川崎「日記っていう言い方がよくなくて、要はスタイルなのかな。文体というか」
清水「スタイルって言い方は金川さん嫌がりそうと思うけど、とにかく、日記っていう形が、最も金川さんが感情を発露しやすい、自分を表現しやすいから選択したんだろうと思った」
金川「日記っていう形式だから書けたんです。これは」
清水「うん。でしょ? 抜群に書きやすい形式の、文学って言っていいと思うんですよ。単なる記録ではなく」
金川「もちろん。そもそも単なる記録っていうのがなんなのか」
清水「それがあるない問題は置いておいて、まあそういうことで作品集がまとまってる。一方で、金川さんは別の人の日記を読んだり、すんごい昔の人の日記をZINEにしたりしてるじゃないですか。それはどういう心で探求してるんですか? 他人の書いた日記を」
金川「それは探求とか、目的とかって問われると……。よし、これは探求しようっていう心で始めてるんじゃなくて、始めてみたら面白かったという感じ。僕がやってるワークショップは、十人とか十五人とか集まって、三ヶ月くらいGoogleドキュメントで日記を共有するということをやっています。僕は人がもっと個人的なことを語れたらいいって思ってます。その時、日記っていうフレームはとてはもじめやすいし、書きやすいと思っています」
清水「金川さんが日記というフレームを表現の上で使ってみたら、すごく書きやすかったから、他の人も書いてみたらいいんじゃないか、ってことですかね」
金川「そう。それもあるし。日記っていうフレームで書かれたものは面白いなって思った」
清水「他人の文章も読みやすくなると」
金川「小説っていうフレームで書かれた時に、ウッてなってしまうことがあります。それぞれの頭のなかにある、小説らしいものを書こうとしてしまうからなのか、その人の言葉っていうより、何かを目指して書いているような言葉になっていると感じることがある。日記なら、もう少し違う言葉が出てくる気がしていて。さっき言ってくれたみたいに、書く時の最初のフレームとして、日記っていうのが使いやすいっていうのは……うん、あると思いますね」
川崎「僕は日記書かないんだけど、多くの人が表現をしたり自分を捉えるための方法や手段として用いるのはいいことだろうなと思います。その一方で、書くという行為には常に対象との対話が水面下で起こっているはずだから、もちろん「面白い」という感覚からしか始まりはしないのだけど、その面白がり方が時に危うい方に転ぶこともあるかと思います。書くことの複雑さ、読むことの複雑さに、どの程度触れていくのかっていう問題がたぶんあって、自分はそっちの方に関心があるのかな。『カフカの日記』や、津島佑子の『あまりに野蛮な』とかありますけど。言葉が拾われない場所で切実に残されてしまった日記を読むことと、表現としての日記を読むこと……その感触には、たぶんずれがある。表現としての日記が、より複雑な方に転んでいくと面白いなと思っているところがあります」
フランツ・カフカ『カフカの日記』
津島佑子『あまりにも野蛮な』
清水「日記文学はさまざまなグラデーションで存在してる。日記ってそもそも読みやすい。時間経過もわかりやすいし。ただ、読みやすい書きやすいってだけで利用し続けるのは難しいと思う」
川崎「何も焦点化していない文章は存在しなくて、なにかを面白いと思ってそれを書いていくことを続けながら、でも同時に、それへの反芻をずっと続けていく必要があるんだろうなと思います。でも逡巡し続けるだけでなくて、決断して書くこともやっぱり必要で……。お話を聞きながら、日記という写真にとっての不純物を持ち込むことで鑑賞の体験を複雑化させようとしてるんだな、と。自分も含め鑑賞者は特定の文化やメディアによる影響を慣習として受けているから、所与のフレーム=規範の中にいてそのフレームによって写真を判断しがちになってしまう。そして写真だけではそのフレームからは脱却できない、少なくともそんなふうに感じる。だから私たち(今日の三人)はそこに言葉という不純物を持ち込むことで、フレーム=規範から少し自由になった鑑賞体験を示そうとしているようだけど、そこには魅力も罠もやっぱりたくさんあるよね、ということを話してましたよね」
清水「そうですね。写真を鑑賞する時の複雑性を作るために文章添えるっていうのは、私たち三人とも同じだと思うんですけど、複雑性っていうと何も言ってないのと同じで。そこでさらに何を想起させようとしているのかっていうのが、各々考えていることが全然違うんでしょうね」
金川「次に作っている本は、日記っていう形式では書いてない。今暮らしている日々についての作品(ハイムシナジー)は、撮った時に起きたことが重要じゃなかったので。日記ではない、まあまあの長さのものを書いています」
清水「あ、そうそう。金川さんて、恋人や友達と複数人で暮らし始めてから、日記じゃない形式の長い文章を発表しはじめましたよね? お父さんと静江さんは親族といえども他人で、金川さんがお世話をしているけど金川さん自身の生活とは違う。でも、同居人との関係は金川さん自身の生活で、そこを表現する文章は日記という形式じゃなかったんだなってとこが不思議で。その理由ってなんですか」
金川「まず撮影自体ののりというか意味がだいぶちがって」
清水「自分が写ってますしね」
金川「基本的にずっと一緒にいる人を撮ってるわけなので、撮影自体の緊張感がない。記念写真的に、ぱっと撮るって感じ。だから、この日こんなことがあって、とか、その時その瞬間にこう心が動いた、みたいなことは書いてない。僕たちの関係性について、思うことを書いてる。作品の形式として、日記という形式がしっくりこなかった」
清水「ふむ」
金川「あと、来週から始まる長崎の写真も、撮影日誌にはしてない。もうちょっと僕自身の信仰の話と、平和祈念像に対して考えていることを書いてる」
川崎「なんか……全然関係ないんですけど……僕、ちょっと違う角度から話したくて。コンペで制作意図書かされるじゃないですか。あれ、なんなんだろって思って。言語によって写真に立体性を持たせようということなんだろうけど、言葉は指示作用が強いので、その指示作用を持ち込まない書き方をしたくて三百字で書いて、それが「光景」の文章にもなってるんだけど。もちろん指示作用から逃れられないってのは分かりつつ」
清水「川崎さん指示作用が発生しやすいテーマ設定と、しかも本という形式で、指示しないようにするっていうことやってますよね。堀江さんがそれをうまいこと言語化してるんですよ」
現在と、これから来る現在の噛み合わせを意識しないかぎり生まれないその軋みが、映し出されている。しかし川崎祐はそれに気づかないふりをつづけるだろう。もう覚悟はきまっている。鈍さの持続という最も難しいふつうに向かって、光景はこれからも更新されていくにちがいない。
川崎「とにかくその三百字を書くことで文章を書き始めたから、写真と文章を両方やるのは必然だった気がします」
清水「なるほど」
川崎「すみません関係ない話して」
清水「いや、まとまったんじゃないですか。(会場の方に)質問あります? あれ、ない? ありそうな雰囲気なんだけど」
川崎「じゃあ続きを……あ、ちょっとトイレいっていいですか」
清水「今?」
(川崎離席)
その語りは誰のもの?
金川「いやー……だから……ちょっと」
清水「だから、金川さんの日記ってなんか、もやるんですよ」
金川「そこの話をもうちょっとつっこんで聞きたいんやけど」
清水「あやういところですよ、多分」
金川「うん」
清水「ある一人の人物を撮るということは、その人の属性や、金川さんとの関係性を示すことから逃れられない。で、いくら限られた日の日記とはいえ、その人の生活の細部を載せるということは、その人をかなり赤裸々に見せていることになる」
金川「赤裸々?」
清水「日記っていう形式はあまりにも、一人の人生を暴露しすぎている。で、金川さんは、何か引くべき一線は持ってるのかなと思って」
金川「清水さんには、僕の作品が誰かの人生を赤裸々に暴露している危険性があると、そういうふうに見えてるってことね」
清水「そうです。この二作に関して」
金川「それはそういう危険性はあると思います。それへのためらいがあって、『father』も写真集になるまでに時間がかかった」
清水「何年もかかってるね」
金川「それで、もし誰かから、これは赤裸々だからよくないんじゃないか?って言われたとして……ええと、まず僕はこれが赤裸々でよくないものなのかどうかは、個別的な問題だと思っています。危うさがあることは考慮したうえで、僕と父の個人的な関係においてこれは、出していい、出した方がいい、という判断をしています。ただ、まず僕はそもそもこれが赤裸々に暴露しているとは思っていない。そういうものにならないようにしているつもりです。僕は赤裸々という言葉をあまり使いたくないんですが、それはこの言葉が何か明らかにすべきではないこと、隠すべきことがあるけどそれが隠されていないというような意味で使われると思うのですが、隠さないといけない恥ずべきことを暴露しているとは思っていません」
清水「お父さんが、こういう形で表現されているってことは理解し、承認しているからOKということですね?」
金川「いや、親父はこの作品を完全には理解できていないと思います。でも、まあやったらええやんっていう態度を示してくれている。了解を得てはいるけど、そこに本当の理解があるわけではないとは思う」
清水「まあ、よっぽど写真作品に詳しいとかでないかぎり、本当には理解できないでしょうね」
金川「おばさんの作品も「こんなものが世に出ない方が静江さんにとってはいいのに……」と言われてしまうものにならないようにしているつもりです。でも、誰かからそうなっちゃってるんじゃないのって言われたら、それについては考えたいし話がしたいと思っている」
清水「あ、そこは「考えたい」なんだ。「俺がいいと思ったからいいんだよ」じゃなくて」
金川「うん、そのもやりは大切だと思う。だから、どこのどういう部分が問題に感じられたのか教えて欲しい」
清水「やっぱり金川さんが作家で、静江さんが撮られる側、語られる側にならざるを得ない。そこがひっくり返らない状況でさ……」
金川「うん。それはそうですよね。言っていることはわかります。本にも書いてあるけど、この人は認知症で、父の場合と同じようには了承できているわけでもない。だからこれは一方的なもの、搾取的なものなので作品にすべきではないかというと、やっぱりそうではないんじゃないかと僕は判断しました」
清水「うーん」

(川崎戻る)
川崎「ディディエ・エリボンという人の書いた自伝『ランスへの帰郷』という本があって、昔書評を書いたんですけど、その本を思い出しました。要は体験は誰のものかっていう問題がすごくあって、そこには相当な繊細さ、配慮が必要になる、ということなんだろう、と思いました。どう振る舞うかというか。文章書くことが面白いってだけではよくなくて、技術も必要になってくるし、たしかに内的独白は語る人のものだけど、語っているものは、語っているあなただけのものではないとも言えます。たとえばピエール・パシェという人も自伝を書いていて、そこで認知症の母親を丁寧に書いていきます。母親が自分の愛した母親じゃなくなっていく、っていうことを……非常に素晴らしい文章で書いていくのだけど、常にその部分には触れている気がします。最近読んだものでいうと、アニー・エルノーがやっぱり最後は認知症になったお母さんについて書いたものもその部分と格闘しています」
ディディエ・エリボン『ランスへの帰郷』
ピエール・パシェ『母の前で』
アニー・エルノー『ある女』
私が書きたいと願っているものは、厳密にはたぶん、家族的なものと社会的なもの、神話と歴史の接点に位置している。私の企ては文学的なものだ。母について、言葉によってしか摑むことのできないひとつの真実を求めようというのだから。(つまり、私が求めているのは、古い写真からも、自分の記憶からも、親戚の者たちの証言からも得られないようなひとつの真実なのだから。)それにもかかわらず、私はある意味で、文学以下のレベルにとどまっていたいと思う。
現実への信頼
清水「金川さんの話を聞いてると、これは写真家の性なのか……いま現在、対面している現実への信頼が厚いんだなって思いました」
金川「うーん。なるほど」
清水「川崎さんは逆にそれを信じられなくて、逃れ続けて、なんかもやーっとしてんのかな」
川崎「そう、文学研究とかしてると、すべてがテクストになるから」
清水「なんかもやーっとしてる」
川崎「もやーっとして終わる」
金川「一応、いなくなった父を書いたのは、撮って、語ったことによって、父が了解されちゃったことに対して申し訳ないっていう気持ちと、それ以上に、僕自身がもうちょっと……そこから語りたいことがでてきたから書いた本」
川崎「語ることはたぶんいいことなんですが、一方で、語りが作用してしまうということもあるのかなと思いました。また毛色の違う話ですが、たとえば女性芸人の方が、世間一般でコンプレックスとされるようなものを笑いの武器に戦っていて、それを本人はいじられていいって言いますよね。だけどそれがこう……表象として作用してしまう側面もあって、そこがとても複雑な問題だなと」
清水「重箱の隅突きすぎるとなにもできなくなるし、もやーっとしすぎるのもどうかと思うんだけどさ……。ま、時間だから終わりますね」
川崎「切断した」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
