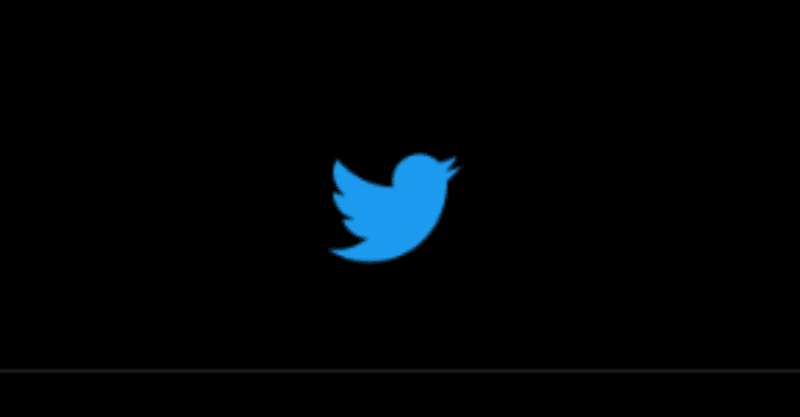
憧れのフォロイーと心中オフ会する話
生き損なったまま死んでいく
Chapter:0 -アカウントを復活させますか?-
2021年10月某日
その日、消していたアカウントを復活させた。今回、アカウントを消していた期間は5日。持った方だ。
人間関係から逃げて、逃げて、逃げおおせて。そのくせ孤独が嫌いな僕に残された、たった一つの社会との繋がり。それがTwitterだった。そんな僕だけど定期的にアカウントを消している。きっかけは沢山あるけど、はっきりとしたものは無い。でも、そのうちTwitterが出来ない不自由さ故に、数日で復活させる。
ある者は手首を切るように、ある者は薬を多量に摂取するように、僕はアカウントを消す。
Chapter:1 -メッセージを作成-
Twitterの仕様上、アカウントを消していた間のフォロイーのツイートはTLに表示されない。だから、過去のツイートを見るためにはプロフィールまで飛ばなきゃいけない。面倒だ。だからただ、そのときは惰性でTL更新をしていた。
ドゥルルルルルルポロッ。ドゥルルルルルルポロッ。この更新音、未だに慣れないな。なんて思いながら何度か繰り返していたら、ひとつのツイートがTLに表示された。
「みやさんの……」
数年前からの一方的なフォロイーがしたツイートだった。
「……心中オフ会?」
そのツイートに書かれている内容は今まで見た事も無いものだった。思わず自らの目を疑ったくらいには。
心中オフ会やります
詳細はDMで
僕は、そんなツイートに目を惹かれてしまった。そういうのもあるんだ。お世辞にもメンタルが安定しているとは言えない僕。だからとりあえずいいねをして、僕はそのツイートをタップした。けど、
『このツイートは削除されました』
なんだったんだろう。気になって仕方ない。血迷った僕は、暫しの逡巡の後、気づけばみやさんとのDMの画面を開いていた。
開いたはいいものの。初めてのDMだし、ましてやFFでもない。
キモいとか思われないかな。なんて声掛けたらいいんだろう。色々考えた挙句、僕が送信したメッセージは
突然のDM失礼します
さっきのオフ会のツイート見ました
詳細知りたいです
なんて無難なものだったはずだ。今となっては確認する術は無いけど。まぁ、いきなりキモすぎるよかマシだよな。そんな益体もないことを考えていたと思う。みやさんからの返信が来た。危うくスマホを取り落とすところだったのは覚えてる。
わ
DMありがとうございます
すぐ消したつもりだったんですけど
見られちゃってたんですね笑
文面からはみやさんの考えてる事はわからない。
なんかすみません、急にDMしてしまって……
少し興味があったので……
三点リーダが多すぎる。オタクの文か! いやまぁ、そうだけど。
え〜笑笑
なんかただの病みツイだったんですけど笑
それともホントにしちゃいます?笑
思っていたよりも高いテンションにちょっと困惑した。
このみやさん(アカウント名は『新庄みや』)という方、当時のツイート内容から察するに、かなり可愛い女性だと予想していた。実際そうだったし。絵も上手けりゃ、漫画だって最高の作品しか描けない。そして何よりも、僕と悉く推しが被っている。ゲームのやアニメのキャラ、挙句の果てには既に引退してしまっているVTuberなどの絵を定期的に提供してくださっている、いわば神だ。そんな方とお近付きになれるだけでなく、一緒に死ねるなんて。本来は地獄や奈落に落ちるべき僕に、そんな幸運があるんだろうか。そう思いながらも僕は返信をした。
ぜひお願いしたいです!!!
わ!
テンション高いね君笑笑
すみません
みやさんのことフォローしてからずっと憧れてて……
話せたの嬉しくてちょっとテンション上がってますwww
何それ笑笑
てかさ
いつも絵いいねしてくれてるよね
まさか認知されているとは思ってもいなかった。僕みたいな稀にTwitterやpixivに駄文を投稿する、字書きの端くれにも満たない人間を。
認知してくださってたんですか!?
もちろん!
○○とか好きだよね!笑笑
僕の最推しの名前が、憧れの人から出てきて僕は心底驚いた。もっと言えば、動揺し感動した。と言ってもこの会話も思い出しながら書いてるから、細部は違うかもだけど。
本筋としては間違ってないはず。だから、そんな会話したんだな程度で読み進めて欲しい。この自己満足極まりない文章を読んでくれている読者がいれば、の話だけど。
それからはテンションが昂ったままやり取りを続けたからあんまり覚えていない。とりあえず、場所と時間の約束をして、ぼんやりとしたまま貯金を全額下ろしたことだけは覚えてる。
Chapter:2 -ダイレクトメールを送信-
オフ会当日。やり取りは全部詐欺で、僕はただ騙されたのかもしれない。とか考えながらみやさんとのDMを何度も何度も確認した。少なくとも10回は見た。10時に某駅前。何度見てもその文面は変わってなかった。時刻は10時5分。みやさんらしき姿は見当たらない。と言ってもみやさんのことを直接見た事は無いからどれが本人かなんてわからないけど。
当日どんな格好で来る?
全身黒ぽい、いかにもオタクっぽいヤツいたら多分僕です
え〜笑笑
絶対そんなやついっぱいいるじゃん笑
的なやり取りしてから数分。みやさんから急にDMが来た。
スマホばっか見てんなよ!笑
驚いて目をあげると、みやさんがいた。
「来てたんなら声掛けてくださいよ」
「本物かわかんないしそんなことする訳ないじゃん。陰キャだし、わたし」
「それもそうですね」
「ひっど〜」
なんてやり取りをしてたらみやさんはスマホを見始めた。それから僕のことをしげしげと見つめる。ちょっと目が合って、逸らす。
「僕の格好、なんか変すか……?」
「え〜、なんか。もうちょいオフ○コ狙いのホスト崩れみたいなのか、モサいオタクが来ると思ってたから、その中間みたいなの来たからさ、『オフ会したら普通のオタク来てびっくりしてる』ってツイートした笑」
「何それ酷い」
「うそうそ、てっきり来るのおっさんだと思ってたからさ」
「僕も、みやさんがほんとに女の子だとは思ってなかったですよ」
「えー、自撮りとか上げてたのに?」
「インターネットのオタクのこと、全員おっさんだと思ってるんで。僕」
「それはえらい笑 でも、おっさんと死ぬつもりだったの?」
「まぁ推し絵師なら……? 顔が良ければギリ……」
「っぱ顔だよなぁ、世の中。わたしもこの顔で産まれてなかったらもっと苦労してたと思うし」
「顔面マウントやめてくださいよ。ブスの前で」
「ブスの前でダメならどこでするのさ笑 それに別に君も悪くは無いと思うけどなー」
「褒めてもなんも出ませんよ……」
「ちぇ……」
「……」
お世辞かい。いや別に期待してないけどね。別に。別にさ。
「あー、なんかそいえばね。もう2人来る予定だったんだけどねー」
「え」
そんな話聞いてない。
「ドタキャンされたわ」
「えぇ……」
もっと聞いてない。僕の知らないうちに話が進んでいる。
というか、僕以外にもあのツイートに反応した人がいたということだろうか。それともツイートするアカウントを間違えたからツイ消ししてたとか? その可能性は高い。だとしたら僕はかなり空気の読めないやつだ。死にたくなってきた。これから死ぬけど。
「ま、いっか。どうせこれから死ぬんだしわたしら」
あっけらかんとした態度で言い放つ。少し忘れていた、というか、意識の外に追いやっていた思考が戻ってくる。
「ですね……」
僕はただ、なんの面白みもない返事で茶を濁した。少し、胸がざわめいていた。
「で、どうするんすか」
「敬語やめようよ君。心中するんだからさ、仲良くしようぜ」
「じゃあ君って呼ぶのもやめてくださいよ」
「それもそっか。なんて呼んだらいい?」
「一応『アキ』って名前でTwitterやってますけど」
「ん〜じゃあそれでいっか! アキくん、いい名前だね」
「どーも。みやさん?」
「敬語もさん付けもダメだよ。みやでいーからさ」
なんというかかみやさんはずっと語尾に笑がついてるかんじだ。ニコニコというかにやにやしてる?そんな感じだ。僕みたいなオタク、心の底では見下してるんだろうな。
「じゃあ、みやちゃんで」
「ん〜。ちょっとキモいな〜」
「……1人で死のうかな」
シンプルで傷ついた。
「冗談じゃん〜。そんなノリじゃ関西で生きていけないよ〜」
「みやちゃん関西出身なの?」
「え、違うけど」
は?
「なんなんだよ……」
この人適当すぎる……。
「あははっ! いいねーノリ合うじゃん」
「そりゃどうも……」
「じゃ、行こっか!」
「え、どこに?」
「とりまカラオケっしょ。オフ会だし」
「あ〜」
そういうのもあるのか。僕はオフ会が初めてだ。
Chapter:3 -フォローリクエストを送信・リクエスト承認待ち-
結論から言えば、みやちゃんはメッッッチャ歌うまかった。96とか平気で出すし、最高99.988点出して『前なら100だったのに〜』とか言ってた。かたや僕は頑張っても89点とかで、最高は92点だった。
「アキくんもけっこううまいじゃ〜ん」
「いや、それみやちゃんに言われてもお世辞にしか聞こえないから……」
「まじまじ。AIの伸びは悪いけど、カラオケって言うより歌が上手いタイプだね、アキくん」
「みやちゃんは歌もカラオケも上手いじゃん!」
「まーね。伊達に専門通ってないから」
「あ、そういう系なの?」
「言ってなかったっけ?」
初耳だ。Twitterでも似たようなことは言ってなかった気がする。
「初耳なんだけど」
「あ〜じゃあ鍵の方だったかも? いるっけ?」
「鍵垢ってこと? それならいない」
「あ〜教えるからフォロリク送ってもいーよ」
「これから死ぬのに?」
「これから死ぬから、だよ」
そう言ってみやちゃんは少し俯いた。
「知っといて欲しいじゃん? わたしのこと。アキくんとは今日初めてだけど、あきくんならいいかなって」
「ん……ありがと」
教えられたアカウントにフォロリクを送っておいた。
「あ〜! 腹減った! たこ焼き食べよたこ焼き! カラオケと言えばたこ焼きっしょ!」
「ポテトじゃない?」
「は〜? たこ焼きだが? 喧嘩か〜?」
「あ、じゃあたこ焼きでいいです」
「ざっこ笑」
なんか楽しそうだな。みやちゃん。ケタケタと笑って注文用のタブレットをとる。
「……ね」
注文を終えたら、急にソファーに座る僕の隣に座ってくる。
「な、何」
15cmくらい、後ずさる。
「そんなビビんなよ〜」
そう言って僕の肩に手を置く。
「アキくん。ちゅー、したことある?」
そう言って流し目でこちらを見つめてくる。漫画なら目の中にハートがある感じ。
「……っ。あ、ある」
僕がそう答えると急に立ち上がるみやちゃん。
「は! 嘘つくな童貞!」
「どどどど童貞ちゃうし!!!」
「見栄張んなよぉ……オネーサンが優しく手ほどきしてやろってのにさぁあ?」
「そういうの、いいんで!」
「は〜、ねんまつ」
そう言いながらみやちゃんはマイクを取る。
……別にそういうことするふん紀伊でもなかったのに。てかまだ歌う気なのかこの子。僕なんかもう声カスカスなのに。
しばらくして、店員が入ってきた。そうか。たこ焼き頼んでたんだっけ。もしあのまま続けてたら……とか想像しちゃって必死に頭を振って脳から思考を追い出した。
Chapter:4 -フォローリクエストを承認・フォロー-
「いや〜歌った歌った!」
「みやちゃん化け物?」
結局2人で4,5時間は歌ってたんじゃないかな。それでもTwitterとか見てた時間はあったけど、2/3以上はみやちゃんだ。体力がヤバすぎる。専門学生は伊達じゃない。
「ヒドいなぁ〜笑 アキくんも結構行けるタチだね〜」
「いや、僕声カッスカスなんだけど……」
喉痛すぎるし。
「ふふ、ショタボっぽくていいじゃ〜ん。わたしその声の方好きかも」
「なんだよそれ……」
みやちゃんはたまに意味わからんこと言う。なんかのネタかもしれないけど、網羅しきれてない。
「いいや〜? ただの本心!」
「はいはい……」
この数時間でこの手のノリも慣れてきた。ドギマギしてたのがバカみたいだ。僕の純情を返せ。
「んじゃ、行きますか」
「え、どこに?」
「目的、忘れたの?」
「あ……」
そうだった。今回の目的は……。
「するんでしょ? "心中"」
「……うん」
不覚にも、というか、不本意ながら。この楽しい時間が少しでも長く続くことを祈ってしまっている自分がいた。みやちゃんといるのが楽しくて、自殺願望も希死念慮も薄れていた。
「あ、あの……」
何か言わなきゃ。少しでも呼び止めなきゃ。そう思った時、僕の口からは既に呼びかける言葉が出てしまっていた。
「何?」
怪訝そうに僕を見る。何も考えてないのに。えっと、何か言わなきゃ。
「……みやちゃんはさ、死ぬ前にやり残したこととか、ないの?」
「んー。特には思い当たらないかな」
涼しげな顔で言う。街の灯りも、夕日も、僕たちを照らしてはくれなかった。そんな中途半端な時間。今の僕はかける言葉を、みやちゃんを繋ぎ止める言葉を探している。
「じゃあ、さ。僕のやり残しに付き合ってよ」
「ん〜、何?」
でまかせの言葉だったが、みやちゃんの興味を引いたようだ。なにか僕のやり残しは……。あ───
「……蟹。蟹、食いたい」
「……は?」
「北海道で美味い蟹食いたいんだよね、僕」
「……正気(バカ)?」
Chapter:5 -アカウントの切り替え-
「……バカ寒い」
「上着いる?」
「いらん」
10月の札幌は寒かった。旅行の着替えを買って、一番早く乗れる便を取って、宿を取って。驚くほど早く札幌に着いた。冬の足音を感じさせる空気に僕も身震いをした。それにしてもみやちゃんは寒そうだ。ニーハイだけど。なんかもうちょい着ればいいのに。
「マジでバカでしょ、アキくん」
「……そうかも」
「そうかもじゃねぇよバカだよお前」
「ぇん」
「泣き真似すんな! キモい!」
マジでみやちゃんはずっとご機嫌ナナメだ。当たり前だけど。1日遊んで死ぬつもりがオタクと泊まりの旅行だ。でもなんだかんだ断らずに来てくれるのは、優しさというのか憐れみというのか。
「札幌着いたし、ラーメン食うからね!」
「わかってるって……」
これはみやちゃんが飛行機の中で一生言ってたことだ。付き合わされるんだから宿代と着いたらラーメン奢れって。今の僕は富豪だからね。それくらいは許すよ。みやちゃんが可愛くなかったら許してないけど。って言ったら思い切り肩を叩かれた。
「店は?」
「こことかどう?」
僕が塩ラーメンが有名な店を出すとみやちゃんは足を踏んできた。
「マジで使えないなお前。塩なんざ食いたかったら東京でサッポロ一番でも食ってろ!」
厚底の靴なのでかなり痛い。小指折れる。
「冗談だから。ここ、本当は」
「ふ〜ん。味噌ならまぁ……」
どうやらお姫様は納得してくれたみたいだ。やれやれ。御屋敷の執事とかはもっと大変なんだろうな。機嫌を損ねたのは僕なんだけど。
「ん〜、なかなかやる」
「んね」
有名なだけあって、と言うよりも、ここまで来た苦労のせいでかなり美味しく感じる。
「コーン、合うね」
「バター最高すぎる」
北海道が味噌ラーメンの本場かは知らないけど、美味い。
「味噌ラーメンしか勝たんかもしれん」
「それはある」
もし次があるなら……なんて思う僕は覚悟がまだできてないだけなんだろうか。
「とりあえず、宿行こか」
「ん」
バスを待ちながら、これからの話を少しする。
「バスは?」
「15分位だって」
「なっげ〜」
「そうでも無いよ」
都会暮らしのみやちゃんからしたら新鮮らしい。僕なんかは1時間近くバス来ないのがざらだったしな……。それともシンプルにバス慣れしてないのか。社不だろうし。
「アキくんチョイスにしてはマシな宿じゃない?」
着いて開口一番、辛辣な言葉が僕を襲う。かなり雰囲気のいい旅館なんだけど、バス移動が長かったせいなのか。
「みやちゃんの中の僕のイメージそんなに落ちてるの?」
「うん。カス」
「ひどい〜」
「ほら、行くよ」
荷物を抱えるように持って旅館の中へ入ろうとする。僕はキャリーケースを引き摺って後を追う。ふと振り返ると今しがたバスで昇ってきた坂道が見えて、奥には海が見える。断崖絶壁、というのだろうか。そんな高い崖に波がぶつかっているのが見える。天気は曇り。心中にはもってこいの天気だな。なんて考えた。
「はよ来いや! 予約したのアキくんでしょ!」
「は〜い!」
少し景色に後ろ髪を引かれながらみやちゃんを追いかけた。
Chapter:6 -新しいアカウントをフォロー-
「畳くせ〜笑」
「情緒もクソもないこと言わないでよ……」
部屋についてそうそうまた毒を吐いた。なんかどんどん遠慮とかなくなってきてない? この人。
みやちゃんの言う通り、部屋には畳の匂いが充満していた。窓を開けて深呼吸をすると潮風の匂いがして少しマシになった。それでも、ふと香る畳の匂いは窮屈だった実家、ひいては地元を思い出させるには十分すぎた。
「……アキくんの希望のとこに来た割には暗い顔だね。どしたん?」
「あー、いや。ちょっと思い出したくないこと思い出してさ」
「そか。ま、風呂でも入ろうよ」
「……聞いたりしないの? なんで暗いかとか」
「聞いたってしょーもないでしょ。これから死ぬんだし」
「ま、それもそっか……」
「温泉行こうぜ、温泉」
「ん」
「っ〜〜〜!」
熱い湯につま先から入ると全身が強ばる。ぷるぷるしながら肩まで浸かると全身に入っていた力が抜けていく。
「ふぅ〜〜〜」
平日の昼間から温泉に入れる幸せを享受するべきだろう。もう夕方近いけど。辺りを見渡すと疎らに人がいる。どれもジジイばっかだ。年金暮らしでいい生活してんだろうなぁコイツらは。アニメとかなら貸切状態で大声で女湯のみやちゃんと会話したりできるのになぁ……。
「……湯あたりしたかも」
旅館の浴衣に身を包み竹のベンチに腰をかける。とりあえずコーヒー牛乳を買って飲み干した。多少マシになったものの、ふらつきながら男湯と女湯を隔てる通路を出る。そこには入ってくる時には気づかなかった謎の滝が流れている。なんで室内に滝? この手のセンスはよく分からない。
少し休んでいるとみやちゃんがやってきた。僕の理想としては髪拭きながら来てくれると非常に助かった(何が?)のだけど、さすが女の子というか、髪はすっかり乾いていた。ただ、やや赤くなった頬に、浴衣のおかげでガードが甘めの首周りは非常に助かる(だから何が?)。というか、すっぴんなのに可愛すぎる。むしろ目に毒まである。ショッキングピンクの髪に落ち着いた色合いの浴衣が神がかり的に似合っている。みやちゃんやっぱり……。
「かわいいなぁ……」
「……! 風呂出てきて開口一番褒められると悪い気はしないねぇ」
「流石みやちゃんだなって」
「え、マジでどうしたの? これまでの失点取り返そうとしてる? それとも風呂で垢だけじゃなく理性まで流してきた?」
うーん。このみやちゃんクオリティだ。なんかこの毒も気持ちよくなってきた。
「いや、改めてビジュの良さに感動してる」
「かぁ〜っ! オタクくんはさぁ! わたしみたいな美少女と旅行来といてそれだけかよ!!!」
大きな声を出されて反射的に謝罪の言葉が出る。
「ご、ごめん……」
「泊まりとかならともかく旅行来たオタクなんてお前だけだぞ! 全く……」
沸点がよく分からない。何に怒ってるんだろう。
「飯まだ〜?」
なんかもう色々見える座り方でみやちゃんが僕に尋ねる。気にするのもアホらしくなったので気にせずに僕は答える。
「もうちょいでしょ。なんか色々準備とかあるんでしょ」
「おなかへった〜」
「さっきグミ食ってたじゃん……」
売店で買ったグミを僕にくれた2個を除いて全部食べたのに。しかも僕が買ったやつ。
「あんなもん腹にたまんないよ〜」
「まぁいいからそこで休んでな。寝ててもいいから。ご飯来たら起こすよ?」
「ん〜、確かに。それがいいかも」
そう言ってみやちゃんは積まれた座布団を押し入れから出してきて寄りかかった。
「じゃ、起こしてね〜」
「はいはい。おやすみ」
フリフリと手を振ってそのまま目を瞑る。数分もしないうちにみやちゃんはすやすやと寝息を立て始めた。どこでも寝れるっていいな。そういやバスでも飛行機でも結構寝てたしな。寝すぎだろコイツ……。
「みやちゃん。起きて。ご飯の準備できたよ」
屈んで声をかける。
「……すぅ」
反応がない。疲れが溜まってたのか眠りが深いみたいだ。
「ねえって……」
肩を叩いて揺らしてみるが、それでもみやちゃんは起きない。無防備な寝顔を見ていたら邪な気分になってきてしまいそうになるのを堪え……きれずにスマホで寝顔盗撮した。この数日中になんかで使えるかもしれない。
「みーやーちゃん!」
さっきより大きめの声と強めのゆらし方で声をかける。するとうっすらと目を開け、僕の奥に見える晩御飯を視界に捉えたらしく、ガバッと起き上がった。
「……! ごはん?」
だいぶ眠そうな声で聞かれる。
「うん。蟹だよ蟹」
「ウッヒョ〜! 人の金で食う蟹だ〜!!!」
そう。ここまでバス代以外は全部僕が出してる。まぁいいんだけどね。
「じゃ、食べよっか」
「ん!」
「いただきます」
「……」
じっとこっちを見てくるみやちゃん。
「何?どうかしたの?」
「あー、いや、そういうのちゃんと言うのすごいなって。ちょっと感心した」
「あー、そうかな?」
言われてみれば完全に習慣になってるかもしれない。
「実家暮らしだっけ?」
「いや、今はひとり」
「家でも言ってんの?」
「そうかも。癖なってんだ、いただきます言うの」
「育ちのいいゾルディック家やめろ笑」
機嫌良さそうににこにこしながらみやちゃんも「いただきます」と呟いて蟹を剥き始めた。ラーメンの時は気づかなかったけど、箸の持ち方が少し変な感じがした。
「……」
「……」
語り尽くされたあるあるだけど、蟹食ってる時無言になるよね。
「……」
「……」
「んま……」
「それな」
たまに聞こえるのは独り言みたいな感想だけ。蟹はめちゃくちゃ美味い。ただ、うん。やっぱり『この後死ぬんだ』という思考が過ぎる度に味覚がしなくなるような気すらする。
「……ん。アキくん顔暗いね」
「そう?」
「うん。北海道着いたあたりからずっと」
「バレてたか」
「まぁ、そんな辛気臭い顔されたら嫌でもわかるよ」
「ごめん……」
「責めてるわけじゃくて、さ」
みやちゃんはテーブルの向かい僕の頬に両手を添えて正面を向き直させられる。
「大丈夫。わたしら死ねるよ」
「……うん。ありがと」
曇りのない目で僕を射抜くみやちゃん。目をそらすことすら許さない。もう逃げられないんだろうな。そんなことを頭の片隅で考える。
Chapter:7 -アイコンの画像をアップロード-
「美味しかった?」
みやちゃんに訊ねる。食器を寄せて壁にもたれかかった状態で天井を眺めていた。
「んー、うまかったよー」
「大丈夫?」
「や、こんな美味しかったっけって思ってさ」
「あー、蟹?」
「それもそうだけど」
少し言いづらそうにこっちを見るみやちゃん。
「や、その。誰かと食べるご飯? 的な……」
は? 可愛いかよ。
「は? 可愛いかよ」
「うるさ〜」
照れてるなぁ可愛い。
「誰かとご飯食べたりとか久しぶりかもなって思っただけだから」
「確かにそうだね……」
思えば一人暮らし始めてからはそんなもんかもしれない。
「なんか、寂しくなっちゃった」
「アキくん大丈夫?」
「大丈夫だよ」
自分に言い聞かせるように呟いた。
「大丈夫だ」
「……そか」
カチカチと壁掛け時計の音が室内に響く。
「っしゃ。なんか描くか」
「マ?」
「マジマジ。一応スケッチブック持ってきてるし」
「遺作?」
「的なね」
ごちゃごちゃとキャリーケースを漁るみやちゃん。中からスケッチブックとペンケースみたいなのを取りだしていた。
「何描くの?」
「ん〜。風景画とか苦手だしアキくんでも描くか」
「やば。照れるわ」
「早くポーズ取って」
「いやポーズとか急に言われても」
「じゃああんま動かないことしてて」
「……うん」
紙の上をペンが滑る音、実は結構好き。みやちゃんを見ると止まることなくペンを動かしていた。
「どんな感じ?」
「完成するまで見んな」
「え〜。順調そうだしいいじゃん」
「普段デジタルばっかだから慣れなくて」
「の割には描けてるくない?」
「これでも中高美術部だったからね。一応アナログも描けるよ」
なんて口ではおちゃらけつつも、真剣な眼差しでスケッチブックに向かっているみやちゃんは、とても、とても。
……カッコいいなぁ。
かたや僕は売店で買った有名な作家のまだ読んだことの無い小説を読んでいた。旅先の旅館で事件が起こるなんて言う在り来りな推理小説だ。みやちゃんには「……そんな物騒なの辞めたら?」なんて怪訝そうな顔をされたけど。
何分経ったかな。文庫本が1/3くらい読み進んだ頃。
「よし! 出来た!」
元気な声でみやちゃんが言う。
「お、見して見して!」
「ふふっ、ははは! ちょっとイケメンすぎない? コレ」
「……こんなもんだよアキくんは」
「そうかな……」
「今からチー牛に書き直そうか?」
「それは困るなぁ」
「……でしょ?」
「……うん」
Chapter:8 -このアカウントは存在しません-
散々語り明かして、僕らは眠りにつくことにした。確かもう東の空は白み始めていたと思う。律儀に2つ、並べて敷いてある布団に背を向けて別々に入った。布団の中は少し冷たくて、僕の体温であったまっていくのが、眠くなって敏感になった肌の感覚でわかった。眠りにつく数秒前の、まどろみが僕は好きだ。この現実と夢の狭間で曖昧に揺れる感覚を堪能したいのに、それは出来なかった。僕の体温によって十分に温まり、空気の籠った布団の中に、冷たく新鮮な空気が入ってくる。それから背中に感じる、人のものと思しき体温。あ、少し暖かい。こんな温かさを感じたのは、いつぶりだったか。人間って、生きてる人間ってこんなに暖かかったっけ。あるいは、生まれてからずっと、これを待っていたのかも知れない。そうとすら思えるほどに心地よかった。いい匂いがする。風呂に入った僕と同じはずのシャンプーの匂いと、それとは違う、人の匂い。 僕のぼやけきった無防備な意識の中に入ってくる、心地よい甘い声。
「宿泊費、払ってもらっちゃったし、タダってわけにはいかないでしょ?」
みやちゃんの手が布団の中で蠢く。僕の脇腹を、腹を、這って。そして、下腹部で止まる。僕のそれは、反応を示していない。初めから期待していなかったというのもある。不意の感触に、僕の意識は微睡みから剥ぎ取られる。冷たい指先がまさぐる様に這い回る。
「正気?」
声を潜めて僕は尋ねた。
「本気と書いて、マジ」
少し低い声。中低音というのだろうか。いつぞやのTwitterスペースで聞いた声だ。これがきっとみやちゃんの本来の、というか、地声なんだろう。電気を消したはずの室内だが、朝焼けで少し明るい。窓際に布団を陣取ったみやちゃんの顔が、逆光で少し見えづらくはあるが、はにかむように、あるいは妖艶に笑っているように見える。 モゾモゾと布団の中で、僕の下着の中でみやちゃんの手が動く。僕は性行為に少しの抵抗がある。というか、本番では勃たなくなってしまっている。が、特殊な自慰だと思うと不思議と抵抗はなかった。つまるところ、勃ってしまった。
「アキくんはこーゆー事、カノジョとシたの?」
「……した」
嘘ではない。前の彼女とはしなかったが、それより前に経験はある。
「へぇ、童貞だと思ってた。ウソじゃなかったんだ、アレ」
耳元で囁くみやちゃん。僕は別にマゾでは無いからそう言われても返答に困った。
「僕も、自分のことそう思ってる」
だから何となく曖昧で意味不明な答えしかできなかった。意味も意図も伝わらなくていい。これはただの自慰だから。
「なにそれ笑 意味わかんな笑」
ケタケタと笑ってから、それから。
「そっ、か」
みやちゃんは何か言いかけたように見えたが、その言葉は口から出ることがなかった。
「……ん、ねぇ」
「……っ、な、なに?」
「こっちのも、触ってよ」
予想外とまではいかないが、意外な言葉だった。
「……そういうこと、言わないと思ってた」
僕は寝返りを打ってみやちゃんに向き直る。
「え〜なんで笑」
へらへらしながらも答えるみやちゃん。
「プライド高いから、みやちゃん」
「は、うっざ。やめよっかなコレ」
「うそうそ。じょーだんだから」
そんなやり取りをしながら僕はみやちゃんに触れた。喘ぎにもならないような吐息が漏れ聞こえて、それは次第に水音にかき消された。壁掛け時計の音が薄れていく。何度か、みやちゃんがぶるっと震える。
「き、もちい、かも」
8割くらいが吐息というか囁き声でみやちゃんが言う。唇は耳元に限りなく近い。というか触れているのか吐息なのか分からなかった。みやちゃんの声で脳幹から脊髄、そして末端の神経まで甘い痺れが走ったような気がした。正直、あまり上手いとは思えない扱きだったが、興奮なのか罪悪感なのか分からない感覚のうちに、僕はみやちゃんの手の中で果てた。いつの間にか掛け布団は剥がされて、僕の種は自身の下腹部方向に、つまり上側に飛んだ。
「んぁ、口入った、まっず」
「ぷふ、ざまぁ笑」
そう言いながら手馴れた様子でティッシュを使い手に付いた僕の種の残滓を拭いているみやちゃんを見て、僕は少し萎えた。今まであまり考えないようにしていた思考が僕の脳を支配していく。他のオタクたちにも、こんなことをしているんだろうな。いや、きっとオタク共だけじゃなく……。その先はもう、考えるのをやめた。みやちゃんの頭を軽く撫でる。
「ん〜、どした?」
「いや、可愛いなって」
ショッキングピンクに色づいた髪を撫でると、地肌に近い部分は黒かった。なんとなくそれを見て生きているんだな、なんて思った。
「知ってる笑」
ニカッと笑うみやちゃん。眩しく見えるのはさっきより高くなった朝日のせいだけじゃないのかもしれない。
ちょっとトイレで吐いた。夜食った蟹が出てきて、もったいない気分になったのだけは覚えてる。
Chapter:9 -パスワードの確認-
朝起きると、背中が少し痛くて、隣にはみやちゃんがいなかった。通話をかけても出ない。時計を見ると5時を少し過ぎていた。フロントの人に聞いたら外へ出かけたと言うから、急いで旅館を出た。海の砂浜へと下る階段とも呼べないような岩を切っただけの急な段を駆け下りると、みやちゃんがそこにはいた。
日の出前の海はまだ暗くて、私服を着たみやちゃんを海の水面が照らしている。ああ、僕に手を伸ばしてくれたらな。その手を掴んでそっちに行けるのに。
「あ、アキくん」
「よかった。心配したよ」
「探しに来てくれたんだ?」
みやちゃんは嬉しそうに笑う。
「そりゃ……」
「ふふ。ありがと」
海を指さすみやちゃん。
「もうすぐさ、日の出だって」
「そっか。夜寝れなかった?」
「ううん。なんか起きちゃって。アキくんぐっすりだったから起こしちゃ悪いと思ってこっそり出てきたのに、割とすぐ追いかけてきちゃった」
「……邪魔だった?」
首を横に振る。
「少し、寂しかった」
「そっか」
「……アキくんと見たかったのかも」
「それなら間に合ってよかったよ」
「……ありがとね」
少しづつ昇ってきた朝日が、水面に反射していた。心做しかみやちゃんの顔が赤い気がした。朝焼けのせいかもしれない。
自然と、みやちゃんの手が伸びてきて、僕の手に絡んだ。
「昨日、夜遅かったからさ。帰って二度寝しよ?」
僕はその提案に頷いた。
2人でひとつの布団にどちらからともなく入った。依然、指は絡み合っていた。少しの無言の後、微睡みが襲ってきた頃、みやちゃんが口を開いた。
「ね、最悪なこと言っていい?」
「ダメ」
「え〜」
「いいかって聞いたってことはダメって言われてもいいってことでしょ」
「でも言いたいもん」
「それ言って気持ちよくなるのみやちゃんだけじゃん。僕が最悪な気分なるだけのやつ」
「うん」
「ならダメ」
「ヤだ。言う」
「え、ちょ」
「君みたいな人と恋人になれたら楽だったのかな?」
「……はぁ」
「最悪な気分なった?」
「……死にたい」
「ならいいじゃん」
「みやちゃんがそれでいいならいいよ」
「……」
「……」
「ねぇアキくん」
「……ん?」
「起きてる?」
「……僕なら寝てるから、独り言ならいいよ」
「そか」
「うん」
「……今日わたしさ、結構楽しくってさ」
「……」
「わたしらちゃんと死ねるかな……」
「死ねなくてもいいじゃん」
「寝言?」
「あー、うん。寝言寝言」
「そか」
「死ねなかったら、生きてきゃいいよ」
「……」
「僕もホントは死ぬの怖くなってきた」
「……」
「死ぬの怖くなってきた、とは違うかも。なんて言うのかな、これ」
「……明日が来てもいいかもって、思った?」
「うん。みやちゃんとならだけど」
「そか。それなら無理だね」
「そうなん?」
「うん。わたしはさ、死んじゃうから」
「……わかった」
「うん」
「うん。」
Chapter:10 -アカウントを削除しますか?-
昼の11時頃。目が覚めるとみやちゃんはいなくて。旅館のテーブルの上には昨日描いていた僕の似顔絵と、『ありがと』の文字。
僕はチェックアウトを済ませてバスを待った。Twitterを開くと、みやちゃんのアカウントは消えていた。生きているかも死んでいるかも分からない。けど、数ヶ月経つとみやちゃんによく似た絵柄の絵がTLに流れてきて、案外どこかで元気にやってるのかもしれない。
Side:新庄みや
Chapter:0.5 -もう病んだ-
わたしは『新庄みや』。ここ数年は本名よりもそう呼ばれることの方が多い。専門学校に通いながら趣味でTwitterに絵を投稿している20歳の学生。ってことになってる。本当は専門学校もあんまり行ってないし、連日遊び歩いてる。おじさんとかちょろそうなオタクからご飯や服を奢ってもらったりして生活してるし、なんなら歳だって本当はまだ19だ。満たされない承認欲求のままに動いた結果、成り行きで付き合うことになった彼氏は月に1,2回会ってセックスするだけの仲だ。通話は時々するけどもはや付き合ってすらいるのかわからない。そんな状況だった。そんな中、些細なことで喧嘩になって、彼の部屋に置いていた私物を放り出されて、わたしも部屋から追い出された。
「はぁ、死にたい」
ネットカフェの中でTwitterの画面を見ながら口をついて出たのはそんな言葉だった。思えばここ一年近くは口にしていないかもしれない。それくらい都会での生活は私にとって満たされるものだった。というか地元での生活が地獄だった。父は地元では名家の出身らしく、母親と離婚してからというもの、わたしのことを厳しく躾けた。私が手がかからないような年頃になると途端に放任主義になり、仕事場にいる時間の方が長くなった。その分、家では会う度に小言を言われた。やれテストの点が低いだの、化粧なんかするなだの。成長した私に妻の面影を感じたのか、口調や態度が横柄になることも多かった。手を挙げられることも決して少なくはなかった。これ以上この土地にいたら私は腐ってしまう。そう思ってこっそり知人伝てにバイトをして、高校卒業と同時に東京の専門学校へ通うと言って家を飛び出した。東京ではなりたい自分になれた。メイクもあの頃よりずっと上手くなったし、それに比例するようにモテ始めた。だけどどこか埋まらない穴が心にあった。
Chapter:1.5 -オタク、キモ-
心中オフ会やります
詳細はDMで
いつもの裏垢で気がついたらそんなツイートをしていた。
すぐにいいねが着いた。『アキ』。見覚えのある名前だ。だからそこで気づいた。
「っべ、垢間違えた」
慣れた手つきで雷よりも早くツイートを消した。本垢では結構清楚な感じでやってたのに不味ったなぁ。なんてことを考えているとDM通知が来た。
突然のDM失礼します
さっきのオフ会のツイート見ました
詳細知りたいです
送信者はさっきの『アキ』とかいうアカウント。たまに短いSSなんかを投稿しているのは知ってたし、多分わたしのツイートの通知も入れてる。ここ数日はいいねがなかったけど、垢消しでもしてたんだろうか。いつもなら今日みたいに秒でいいねが着いていたのに。そんなことを考えた。それとは別で覚えた感情は『マジかこいつ』だった。わたしに向けられる『気持ち悪い感情』。これがわたしは嫌いじゃなかった。まぁ会うだけあってイケメンか金持ちそうなら遊んでやるか。そんな気持ちでDMを返信した。
わ
DMありがとうございます
すぐ消したつもりだったんですけど
見られちゃってたんですね笑
めんどくさいやつなら困るから、下手に、穏便に。そんなつもりで返信した。
なんかすみません、急にDMしてしまって……
少し興味があったので……
キモ。Twitterのオタクの文章じゃん。ほんとこういうオタクキモくて……面白い。こういうバカそうな童貞Twitterオタクを見るのは本当に面白い。
(釣っちまうか……)
そんな思考が脳裏を過ぎる。本来なら別の半分乞食みたいな垢でやってたことだ。そろそろ『新庄みや』にも飽きてきた。わたしにしては持った方だ。アカウントも名前も変えずによくやったと思っている。こういう関係も増えたし、そういう関係の相手も増えた。今の彼氏は普通にリアルで会ったけど、寝たオタクは1人や2人じゃない。妙に女慣れしてない、最低限の清潔感があるオタク。自分の事を『他のオタクとは違う』そう思っているオタクほど、女との関係にアイデンティティを依存する。そのささくれを少し触ってやるだけで、オタクたちは直ぐに金を出す。そこにだけ価値を見いだしてもらおうとしている。
「オタクちょれ〜」
思わず独り言が口をついて出る。それ以上でもそれ以下でもない。彼氏だって構ってくれないのが悪い。そうだ、ちょっと遊んでやろう。少しは気も晴れるかもしれないし、彼氏の機嫌も治ってるかもしれない。どーせあいつはわたしがどこの男と何してたって気にしない。このわたしの穴も、いつか埋まるかもしれない。イカ焼きみたいになったわたしの腕を愛おしく撫でる。そろそろ髪染め直さなきゃな。
Chapter:2.5 -悪くない。けど、感傷-
駅前で全身黒ずくめでスマホを覗いてる奴がいた。こいつだ。勘でわかった。DMを開いてメッセージを打ち込む。
スマホばっか見てんなよ!笑
驚いたように体をビクッと震わせスマホから視線を離した。
……少し、驚いた。元カレに似ている。しかも、こんなクソ女になる前の、まだ純情な、清純な異性交遊をしていた頃の。当時の感情が胸に溢れて、危うく涙となって出てくるところだった。抑圧された環境で、それでも等身大の女子中学生の恋愛をしていた頃の、思い出したくもない時期の、忘れたくない時間。今の今まで忘れていた気持ちが、濁流のように私の体の中を流れ、満たしていった。それでも何とか、笑って見せた。
「来てたんなら声掛けてくださいよ」
『アキ』が喋った。少し高い、甘めの声。媚びてい様子のない自然体の声。あぁ何から何まで……。
(……似ている)
彼は今、どこで何をしているんだろう。そんな感傷に危うく耽りそうになる。言葉を返さなきゃ。
「本物かわかんないしそんなことする訳ないじゃん。陰キャだし、わたし」
やっとそれだけ絞り出した。ネットの人間と話す時の、作った声。自分が少し嫌になった。
スマホを開く。それからアキとか言うやつのことをしげしげと見つめる。ちょっと目が合って、逸らす。
今日会ったオタク
元カレに激似で鬱
今度は間違えてない裏垢でつぶやく。つぶやいて自分の心の中にある気持ちを何とか整理しようと試みる。蟠りを流そうとする。だけど、ふるいにかければかけるほど、色んな思い出だけが胸の中に残っていた。
「僕の格好、なんか変すか……?」
アキが口を開く。デフォルトで敬語だ。恐縮してるんだろう。少し高圧的でもいいか。
「え〜、なんか。もうちょいオフ○コ狙いのホスト崩れみたいなのか、モサいオタクが来ると思ってたから、その中間みたいなの来たからさ、『オフ会したら普通のオタク来てびっくりしてる』ってツイートした笑」
「何それ酷い」
オタクのくせにコミュ障ではないみたいだ。吃りもないし、早口でもない。好感が持てる。何より見た目がストライクだ。いや、その言い方は違う。私の好きなタイプとは違うけど、もっとこう、私のストライクゾーンに楔を差し込まれたようなそんな感覚だった。
後、別のやつなんか誘ってない。オマエ1人でいいと思ったし、ネット上でオタクに囲われるのはいいけど、リアルでなんかごめんだ。オタク同士の色恋(しかも自分が中心)なんて、碌なもんじゃないことをわたしは既に知ってた。
色々と話をしながら歩いた。
「じゃあ、みやちゃんで」
「ん〜。ちょっとキモいな〜」
「……1人で死のうかな」
結構弄りやすいしボケにも反応してくれるから話しやすい。早口でマジレスするタイプが1番嫌いだ。
ただ、『死ぬ』という単語に引っかかった。そうか。自殺オフって名目なんだっけ。テキトーにオタクに金出させて帰る予定だったから、いざ言われると何となく背筋が伸びる。心中か……。まじまじと『アキくん』の顔を見る。
(この子となら……)
そんな考えがわたしの脳裏に焼き付いた音がした。少なくとも今の彼氏よりはずっと気楽だ。そう思った途端、わざと考えないようにしていたことが思考を支配した。
(わたし、アキくんのこと結構好きかも……)
頭をブンブン振って思考を追い出す。良かった。アキくんには見られてない。こんなの一目惚れもいいとこだ。1番好きだった元カレに似てるからとか……わたしのキャラじゃない。
Chapter:3.5 -少し痛い-
カラオケしてて気づいたけど、アキくんはめっちゃ声がいい。少し鍛えればその辺の企業V(笑)なんかよりよっぽど食っていけそうなくらい。普通に上手い人よりも普通に上手い。そんな感じの歌に、よく通る声。欲する人なら喉から手が出るレベルのものだろう。それを持て余してる。磨けば光りそうな原石だ。意外だった。
「アキくんもけっこううまいじゃ〜ん」
「いや、それみやちゃんに言われてもお世辞にしか聞こえないから……」
そんなこと、ないんだけどな。このアキくん、結構壁が厚い。自己肯定感の低さというシールドで他者を拒んでる。それじゃダメだよ。わたしたち、これから死ぬんだから、仲良くしないと。
「まじまじ。AIの伸びは悪いけど、カラオケって言うより歌が上手いタイプだね、アキくん」
「みやちゃんは歌もカラオケも上手いじゃん!」
「まーね。伊達に専門通ってないから」
「あ、そういう系なの?」
言ってないから知らないのも当然。まぁ鍵垢とかでは呟いてるけど、きっと存在も知らないだろうから。
「言ってなかったっけ?」
白々しい……。自分でもそう思う。
「初耳なんだけど」
知られてる方が怖いわ。
「あ〜じゃあ鍵の方だったかも? いるっけ?」
「鍵垢ってこと? それならいない」
「あ〜教えるからフォロリク送ってもいーよ」
魔が差した。破滅願望に突き飛ばされて、言葉が出た。
「これから死ぬのに?」
「これから死ぬから、だよ」
でも、嘘じゃない。
「知っといて欲しいじゃん? わたしのこと。アキくんとは今日初めてだけど、アキくんならいいかなって」
「ん……ありがと」
この気持ちは、名前をつけるに値しないくらいグズグズで汚くて、純情さの欠けらも無いそう思っていた気持ちに、嘘は無い。アキくんにならいいって思っちゃったんだ。
少しお腹がすいたからわたしのゴリ押しでたこ焼きを注文した。それからふと、また破滅願望に突き飛ばされた。
「アキくん。ちゅー、したことある?」
明らかに狼狽し始めるアキくん。可愛いかもしれない。
「……ある」
嘘つくなよ。童貞の癖に。オタクのしょーもない見栄がいちばん嫌いだ。それから少し攻めたけど、ガードは崩さなかった。黙って騙されときゃいいのに。そんな下衆の考えと同時に……すこし胸が痛んだ。
正体の分からない胸の痛みに疑問を覚えながら、たこ焼きを食べた。
それでもイライラは治まらないので歌うことにした。アキくんが少しびっくりした顔をしてて、少し溜飲が下がった感じがする。
Chapter:4.5 -男はみんなバカ-
カラオケを出る頃にはアキくんの声はカッスカスになってた。なんでそうやって……。いや本人に言ってもしょうがないんだけどさ。どうしても中学時代の青春がフラッシュバックする。スマホを開くと今彼からの鬼LINEが来てる。
(だる……)
聞こえないように呟いてブロックした。
今思えば、その時点でわたしの気持ちはもう自分ではわかってたのかも。
「んじゃ、行きますか」
「え、どこに?」
「目的、忘れたの?」
「あ……」
忘れてた、なんて言わないよね?
「するんでしょ? 心中」
「……うん」
うん。つまり肯定の意を評したはずのアキくんは少しの間言い淀んだりしていた。なんだろうと思いながら待っていると、まぁ、ギリ予想内の返事が来た。
「……みやちゃんはさ、死ぬ前にやり残したこととか、ないの?」
そんなの、あるに決まってる。でも、そんなのどうでもいい。今じゃなきゃ、なにか致命的なことに気づいてしまって死ねなくなる。その前に早く終わらせたい
「んー。特には思い当たらないかな」
「じゃあ、さ。僕のやり残しに付き合ってよ」
これもギリ想定内。死ぬ前だし少しのワガママくらいなら付き合ってもいい。
「ん〜、何?」
1分くらい考え込むアキくん。そんなにあると困るんだけど……。
「……蟹。蟹、食いたい」
「……は?」
「北海道で美味い蟹食いたいんだよね、僕」
男ってみんな馬鹿なんだ。思い出した。だからあえて聞いた。
「……正気(バカ)?」
Chapter:5.5 -カス-
北海道についてすぐラーメンを食べた。美味かったけど、クソ寒かった。旅館までも結構距離があったし、死ぬほど疲れた。
「みやちゃんの中の僕のイメージそんなに落ちてるの?」
宿について、わたしがした反応に対してそんな返事をするアキくん。いや、初対面の女の子を急に泊まりがけの旅行に誘うとか意味わかんないし常識ないから。って言ってもすぐ予約取れたし、裏では色々頑張ったのかも知んないけど、それにしたってありえないから、これでも結構褒めてるつもりなんだけど。
「うん。カス」
「ひどい〜」
「ほら、行くよ」
キャリーケースを引っ張って宿に向かってると、アキくんがついてきてない。振り返るとなんか黄昏てる。
「はよ来いや! 予約したのアキくんでしょ!」
「は〜い!」
呼ばれたらドッグランの子犬みたいにする走ってくるところは可愛くて少しポイント高いかも。
Chapter:6.5 -わたしら死ねるよ-
「……ふーん。そんな名前なんだ」
ホテルのフロントで名前を書いてるアキくん。ペンネームとか偽名でもいいのに、変なとこで律儀なんだ。
「いや、なんか癖で……」
「意外と普通の名前だね」
「そういう反応の方逆に気まずいし、見なかった事にしといてよ……」
「いーけどさ」
「温泉行こうぜ、温泉」
「ん」
部屋の中で温泉の準備をしながら、空港で買ったグミをバッグに戻した。
「わたしの名前、知りたい?」
反応が気になったのかひとつ。意図せずに本名知っちゃったのがもうひとつ。そんな理由をつけてアキくんに聞いてみる。
「別にいいよ。僕とみやちゃんの間ではアキと新庄みやでいようよ」
……ふーん。やっぱ変なとこで律儀で、わたしだけ弱み知っちゃった見たいじゃん。
「……ずる」
「なんか言った?」
「な〜んも! ほら! 大浴場行くよ!」
オタクのくせに、アキくんのくせに、生意気。
「かわいいなぁ……」
お風呂あがり、待ち合わせた場所で合流してから開口一番。アキくんはそんなことを言った。心臓が止まるかと思った、ってのは言い過ぎだけど、ドキッとした。……彼氏はそういうこと言わないから。
「……! 風呂出てきて開口一番褒められると悪い気はしないねぇ」
なんか早口かも自分。やだな。照れ隠しだと思われて……いや、照れ隠しなのバレてなきゃいいけど。
「流石みやちゃんだなって」
畳み掛けてくるアキくん。ほんとに心臓に悪いからやめて欲しい。そんなこと言ってもアキくんだってお風呂上がりのせいで……なんて思ってても言わないけど。
「え、マジでどうしたの? これまでの失点取り返そうとしてる? それとも風呂で垢だけじゃなく理性まで流してきた?」
ああ、顔熱い。お風呂上がりで助かったかも。
なんだかんだ話したあと、念を押すように付け足しておく。
「泊まりとかならともかく旅行来たオタクなんてお前だけだぞ! 全く……」
“泊まること”を目的に男と2人で宿泊したのは初めてかもしれない。そう思うと逆にドキドキしてくる。やめろ。
「───やちゃん。起きて。ご飯の準備できたよ」
体を揺すられる感覚と、優しい声で意識が戻る。お風呂から上がって部屋に戻ってから、ご飯まで寝かせてもらったんだっけ。肩を揺すられる感覚が、ゆりかごみたいで少し心地いい。
「ねえって……」
だから、ほんの少しだけ寝たフリをする。優しいアキくんが悪いんだよ。
「みーやーちゃん!」
相変わらず優しいけど、少しだけ大きくなった声と、比例して強めに揺らされる肩。そろそろ起きてやるか。
「ごはん?」
「うん。蟹だよ蟹」
「ウッヒョ〜! 人の金で食う蟹だ〜!!!」
言い終わらないうちに飛び上がる。そういえばここまで全部出してもらっちゃってるんだよね。他のキモオタとかおっさんならなんとも思わないけど……。なんかこれだとアキくんのこと特別みたいじゃん。何考えてんだ自分。
「……ん。アキくん顔暗いね」
せっかくアキくん希望の蟹なのに。
「そう?」
「うん。北海道着いたあたりからずっと」
本当は今気づいた、というか思い出したんだけど。
「バレてたか」
「まぁ、そんな辛気臭い顔されたら嫌でもわかるよ」
「ごめん……」
「責めてるわけじゃくて、さ」
テーブルの向かい、アキくんの頬に両手を添えて正面を向き直す。柔らかい肌と未発達な表情筋の感触がする。
「大丈夫。わたしら死ねるよ」
半分くらいは、わたし自身に言い聞かせてる。
「……うん。ありがと」
アキくんは素直でいい子だな。
……せめてこの子だけでも生きてて欲しいな。
Chapter:7.5 -寂しいから-
後片付けをしながらアキくんが口を開いた。
「美味しかった?」
「んー、うまかったよー」
本心からの言葉だ。久しぶりに食べた。
「大丈夫?」
複雑な顔をしてたのがバレたのか、それともただの違和感からか、質問された。
「や、こんな美味しかったっけって思ってさ」
「あー、蟹?」
「それもそうだけど」
少し言いづらい。察して。そう思いながらアキくんの顔を見るけどキョトンとしてる。あほ。
「や、その。誰かと食べるご飯? 的な……」
「は? 可愛いかよ」
「うるさ〜」
言わなきゃ良かった……このボクネンジンがよ〜。ニヤニヤしながらこっち見んな!
「誰かとご飯食べたりとか久しぶりかもなって思っただけだから」
今更言い訳にもならない。たった数時間で、何となくお互いに考えてることが少しわかるようになったかもしれない。
「なんか、寂しくなっちゃった」
そっか。アキくんも寂しいんだ。わたしだけじゃなかった。
「大丈夫?」
「大丈夫だよ」
自分に言い聞かせてるみたいに言うアキくん。
「大丈夫だ」
「……そか」
アキくんがそう言うなら信じるよ。
「っしゃ。なんか描くか」
なんか辛気臭くなってきたから、気分を変えよう。
「マ?」
「マジマジ。一応スケッチブック持ってきてるし」
「遺作?」
「的なね」
遺作か。言われてから気づいたけど、そうなるのか。何描こうかな。
「何描くの?」
「ん〜。風景画とか苦手だしアキくんでも描くか」
遺作なら、ちょうどいいかも。何となくわかってきた。わたしが、新庄みやが、最後に恋した人。
「やば。照れるわ」
「早くポーズ取って」
「いやポーズとか急に言われても」
「じゃああんま動かないことしてて」
「……うん」
そう言うとアキくんは荷物から文庫本を取り出して読み出した。
アキくんの息遣い、ページをめくる音。様になるな。無音の室内に響く音を作業用BGMにしながらペンを走らせる。
「どんな感じ?」
「完成するまで見んな」
絶対。
「え〜。順調そうだしいいじゃん」
「普段デジタルばっかだから慣れなくて」
「の割には描けてるくない?」
「これでも中高美術部だったからね。一応アナログも描けるよ」
実は結構自信あるんだよね。
途中でアキくんが読んでる本が○○旅館殺人事件みたいなタイトルなのに気づいて、さすが(「……そんな物騒なの辞めたら?」って言ったけど。それでも構わず読み進めるもんだから、つい本を読む目線を追ったりなんかしちゃって。
「よし! 出来た!」
45分くらい経った頃。何とかできた。ワンドロならだいぶフライングだな〜とか考えたり。
「お、見して見して!」
膝立ちでよってくるアキくん。
「ふふっ、ははは! ちょっとイケメンすぎない? コレ」
「……こんなもんだよアキくんは」
少なくともわたしにはこう見えてるけど?
「そうかな……」
「今からチー牛に書き直そうか?」
不満そうやなので提案してみる。
「それは困るなぁ」
「……でしょ?」
わたしも遺作がチー牛とか嫌だもん。
Chapter:null
いまきみにすきっていったら、きみはどんなかおするのかな
Chapter:9.5
朝起きると、隣が人肌で暖かくて。思わず涙が出そうになる。と同時に自己嫌悪に襲われる。昨日のことを無かったことにしたいけどしたくない。そんなモヤモヤをスッキリさせるために、アキくんをおこさやいようにそっと布団を出て、部屋を抜け出した。フロントの人に「少し外で歩いてきます」って言ってから、昨日バスから降りた時に見えた海岸に向かった。朝焼けにはまだ早い深い藍色の空は、わたしの心を投影するには色が少なすぎた。しばらく砂浜で座り込んでると人の気配がした。
「あ、アキくん」
振り返ると心底心配そうな顔でアキくんが立ってた。そんなに心配そうな顔しなくてもわたしはいるよ。まだ。
「よかった。心配したよ」
その顔見ればわかるよ。
「探しに来てくれたんだ?」
だとしたら、嬉しいな。
「そりゃ……」
「ふふ。ありがと」
海を指さす。
「もうすぐさ、日の出だって」
ついさっき、スマホで調べた。
「そっか。夜寝れなかった?」
「ううん。なんか起きちゃって。アキくんぐっすりだったから起こしちゃ悪いと思ってこっそり出てきたのに、割とすぐ追いかけてきちゃった」
「……邪魔だった?」
首を横に振る。
「少し、寂しかった」
独りだと、夜と海の闇に吸い込まれそうで。
「そっか」
「……アキくんと見たかったのかも」
「それなら間に合ってよかったよ」
「……ありがとね」
朝焼けが海の向こうからやってくる。海の水面に反射する光の道みたいに、わたしの方からアキくんの手に自分の手を重ねる。
「昨日、夜遅かったからさ。帰って二度寝しよ?」
アキくんはその提案に賛成した。
朝焼けを見終わって、2人でひとつの布団にどちらからともなく入った。依然、指は絡み合っていた。少しの無言の後、微睡みが襲ってきた頃。
口を開いて、わたしは少し素直になって、狡くなった。
Chapter:Final -あ り が と-
朝の10時頃。目が覚めると隣にはアキくんがいて。旅館のテーブルの上には昨日描いたアキくんの似顔絵と、『ありがと』ってだけ書いた手紙を置いておく。
それから直ぐにチェックアウトを済ませてバスを待った。Twitterを開いて、『新庄みや』のアカウントを消す。これで新庄みやは死にました。アキくんならきっと、わたしが居なくても強く生きていけるから。アキくんには、わたし以外の人を幸せにして、わたし以外の人と幸せになって欲しいから。さよなら、わたしの、新庄みやの一番大好きな人。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
