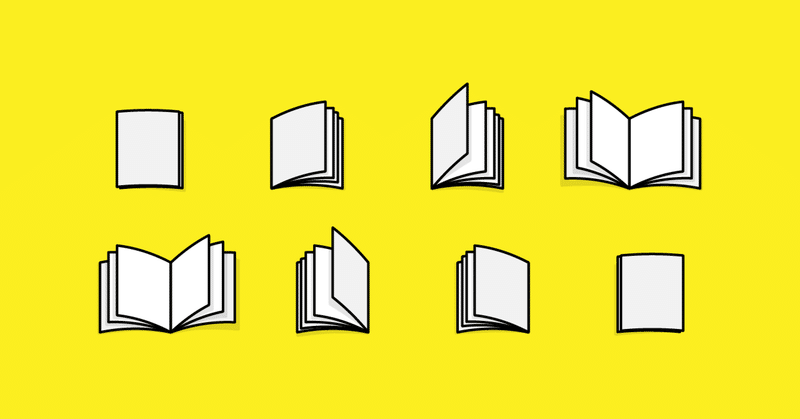
読むのはつらいよ|ひよこ家の読書交換日記⑧
大変ご無沙汰しておりました。ひよこ家の読書交換日記、日々の忙しさにかまけて後回しにしていたところ、すっかりと筆に根とカビが生えてしまい、筆を取るのに難儀しておりました。さて、日記の再開をここに高らかに宣言いたします。
こういうことって日々の暮らしの優先順位の常に3位くらいにはランクインしているのですが、締め切りを一度逃すとトップに上がることはなかなか難しいですね。さて作者失踪未遂シリーズの読書交換日記、第8回目です。
▼前回の記事
課題図書⑦の感想
臨床心理カウンセラーの著者が大学院で博士号を取得後、初めて勤めた沖縄のデイケアでの4年間の日常を、エッセイとして出来事を紹介しながら、時に先人の哲学者や心理学者たちの言葉を引用しつつ考察していく。
心に病を抱えた患者さん達が集う「デイケア」という場所はなかなか想像しにくいが、そこはなにかを「する」ための場所ではなく、「いる」という場をもたらすところだという。朝8時半からやってきて、何をするでもなく過ごして、お昼が来たらご飯を食べて、また何かして過ごして、夕飯を食べて夜18時半には帰り、一日を穏やかに終えていく。たまにソフトボールをしたり、浜辺に出かけたりもするが、何か予定をたくさん組まれることなく、日常を穏やかに過ごすことで「いる」場所をじっくりと構築してくことがデイケアの役割らしい。
人は余裕がなくなると、何かを「する」ことで解決しようとする。おいしいものを食べたり、旅をしたり、買い物したり、行動を起こして非日常な刺激を得て気分転換しようとしたりする。でも、そういうことは日常の生活としての「いる」が確保されているから、「する」ができるのだ。何らかの形で心の安定を崩してしまった人たちは、日常の「いる」ができなくなってしまっているので、何かを「する」ために助言するのではなく、デイケアでスタッフに支えられながら「いる」を作って日常を作り出す(取り戻すのではなく、新たに作り出す)というところから始める必要がある。「する」ことに急いている人にとっては、「いる」は暇で退屈な暮らしのように見えて「居るのはつらい」と思うこともあるが、心の安定には必要なことなのだ。
一方で、患者の「いる」という日常を提供し支えているスタッフたちの働き(依存労働)は社会的な評価が低い、とこの本では指摘されている。人は完全に何かに依存しているとき、自分が依存していることに気づかない。だからうまくいっているときほど依存を支える側は感謝も評価もされない。気がつく時は、その依存が危ぶまれるときだ。「なんでもないようなことが、幸せだったと思う」と気づくのは、それが失われた時ということ。だから従事者として支える側からも「いる」ことの価値が見いだされにくく、「居るのはつらいよ」と作者はタイトルに込めている。
さて話を少し戻そう。文字を「読む」ということも「いる」と同じような日常だ。日々の生活において文字を「読む」ということは当たり前に行われている。毎日刺激を求めて文字を追い続けているわけではなく、のんびりと文字を「読む」日常があったうえで、たまに本を読みこんで理解を深め、それについてnoteで呟いてみたりすることが「する」という行為だ。
では、こうした読書交換日記というルールを決めて、本の感想をnoteに書くという「する」を急かせる行為、これは心を不安にさせる行為ではなかろうか?人はもっと穏やかに「読む」という日常が必要ではないか?noteを書くために本を「読むのはつらい」のではないか!?もっと人は穏やかに文字と寄り添って日常を過ごしたっていいではないか!!「読む」のが慣れてきたころに、そっと思ったことをnoteに書いてみるくらいが、人の営みにちょうど良いのではないか!!!
などと投稿が遅れに遅れた言い訳に無理矢理結び付けて感想を締めようと思う。次回からはちゃんとします。ごめんなさい。
課題図書⑧
さて、読むのをつらくさせるまで私を追い込んだ本を課題図書に指定してきた妻には、私も本気を出さざるを得ない。今まで妻の読みやすそうな本を渡してきたが、今度こそは私が好きな本にしてみよう。
COSMOSという科学番組を通じて、長年科学をわかりやすく人々に伝えてきた宇宙物理学者カール・セーガンによる20世紀末の地球観。色褪せた部分もあれば色褪せない部分もある。とくとご堪能あれ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
