
市民の暮らしを守る警察官から、子どもの学び場を守り、育む教員へ。「第2の人生」を生きる元・警察官の挑戦
警察官から教員という異色の経歴をお持ちの荒石将司さん。柔らかな語り口の中にも、こちらの背筋が伸びるような芯の強さを感じられるお人柄が印象的です。
警察官になりたいという子どもの頃からの夢を叶え、12年間にわたり大阪府民の暮らしを守るため情熱を注いできた荒石さんが、なぜ教育の世界に身を転じ、教員として「第2の人生」を歩き始めようと思ったのか。
警察官だった頃のまなざしは、教員という職業にどう活きているのか。お話を聞きました。

理想と現実の壁にぶち当たって気づいた「教育」の重要性
——前職は警察官だったそうですが、警察官から小学校の先生へ転職を決意されるまでのストーリーを聞かせていただけますか?
現在は大阪市浪速区の小学校で5年生の担任をしていますが、教員になる前は、地域住民の安全な暮らしを守る警察官として12年半務めていました。
警察官になることが子どもの頃からの夢で、頑張って勉強して公務員試験に合格し、大学卒業後は念願だった警察学校に入校しました。毎日が警察官に必要な知識や技能、体力を身につける熱い日々で、「すごくいい仕事につけた」とやる気に満ちていましたね。
ただ、警察学校を卒業して現場に配属されて間もなく、理想と現実のギャップを感じ始めたんです。
——それはどんなギャップだったのでしょうか?
例えば、何か事件が起きたときに犯人を捕まえて、一度交番に戻ってから、また別の事件の捜査をするために再び街に出ようとしますよね。すると、同僚から私の身体を考えてのことだと思うのですが「たった今捕まえてきたところなんだから、もう少しゆっくりすればいい」と言われたり、「自分で決めた、今月の交通違反の目標件数を取り締まったのなら、もうそれでいい」と言う人もいたりして、違和感を抱きました。
「警察官がそんな意識でいては駄目だろう」という気持ちが自分の中で次第に大きくなり、消化できなくなっていって…。悩みながらも職務を果たすために働き、最終的にはそれなりの職位に就かせていただきましたが、やりがいよりも満たされない気持ちの方が大きくなってしまい、最終的には他のキャリアを意識し始めるようになりました。
——小さい頃からの揺るぎない理想があったものの、それがなかなか叶わない現実があったのですね。そこからどのような経緯で「教育」の道を目指されたのでしょうか?
あるとき異動で、警察学校に配属になったことがありました。若い警察官に交番勤務の仕事を教える中で、再び大きなやりがいを感じたんです。
また、警察沙汰になるような事件を起こす人たちを長年見てきた中でも、教育について考える機会がだんだん強くなっていったように思います。残念ですが、どれだけ更生の機会があっても、何カ月後かに同じようなことを繰り返してしまう方がいます。それはなぜなんだろうか?と考えると、やはり多感な子ども時代に何を吸収するのかが影響するのではないか。結局は教育が重要なのではないか、という答えに行き着きました。
それからは、もう教育という選択肢以外は考えられませんでした。たくさんの「理想と現実」の壁にぶち当たってきたからこそ、出会えた決断だったように思います。
警察官としてのまなざしが活きたこと
——畑の異なる教育の世界に転職する上で、不安も大きかったのではないですか?
もう不安しかなかったですね(笑)。
警察官はずっと目指してきた仕事だったので、悩んでいたとはいえ、「誰にも負けない。自分は精一杯頑張って修行している」という自負がありました。それが、ひとたび大阪府警という組織を出たら、果たしてこれまで自分のやってきたことが他でも通用するのか、はたまた常識外れで何も通用しないのか、まったく分かりませんでした。
自分としては「絶対通用する」と思っていても、実際に飛び込んで全く通用しなかったらどうしよう…。そんな、自分自身に対する不安が一番大きかったですね。ちなみに、教員免許は警察官を辞めてから取りに行きました。
——不安を抱えつつも晴れて教員として小学校に入職されて、最初に驚いたことはどんなことだったかお聞きしたいです。
これも本当にいろいろあって、驚き出したらきりがないほどです。
例えば、学校では子どもたちが走っていたら、先生方は「歩きましょう」という言い方をしますよね。歩くことを促す言葉を使う。ところが、警察官の場合は「走ってはいけません」という言い方をします。その人が「走っている」という行為を認識できるような言葉がけをするんです。
こうした言葉の使い方ひとつをとっても、全く違いました。「自分自身が変わっていかないと、まともに子どもを育てられないな」と本気で思いましたね。
——一方で、警察官としての経験が活きていると感じることはありますか?
2つあります。1つは、学校の安全対策に関する問題点に気づきやすいということ。警察官としての目線で校内を見ていると、学校の安全対策における問題点がいろいろと浮かび上がってきます。
校側も、子どもの安全対策についてはいろいろと取り組んでいますが、やはり教員は学習指導や授業作りといった、教育ど真ん中の部分が中心です。ですので、警察官と同じレベルの問題意識を持って学校の安全対策作りに取り組むことは、なかなか難しいなと感じます。
そこで、警察官の頃の経験が活かせると思い、大阪市教育研究会生活指導部の中に危機管理を担う班を立ち上げて、学校の安全管理や指導に関するソフト面での取り組みの広報をしつつ、学校内にも浸透するように少しずつ整える活動をしています。
——学校の安全対策に関する気づきは、まさに元警察官ならではの着眼点ですね。
もう1つは、人と接するときの立ち回り方が活きています。前職ではよく「警察官は役者だ」と言われてきました。
日々現場に立っていると、老若男女、さまざまな方と出会います。子どもには子ども、大人には大人に合った話し方や接し方がありますし、また、その目的もいろいろです。落とし物の届け出をしたいだけなのか、ただ話を聞いてほしいだけなのか、もしくは切羽詰まっていて助けを求めているのか。それらを判断しながら仕事をしないと、形だけのお巡りさんになってしまうので、相手の根底にあるニーズを把握することは徹底して鍛えられました。
現場が小学校に変わっても、このスキルは役立っていると感じます。1年生を接するときと6年生と接するときとでは、やはり話し方は変わってきますし、教職員の方々と話すときもまた違う。さらに、自分の言いたいことを言う前に、保護者が何を不安に思っているのか、何を分かってほしいのかをとにかく聞いて、要望やニーズを把握する。そうしたコミュニケーション面で困ることは全くなかったですね。
学校に新風を吹き込む存在でありたい
——小学校教諭に転職して良かったことや、やりがいを感じることはどんなことですか?
この仕事を始めて6年になりますが、私にとっては「第2の人生」と位置づけて、またイチからやり直す機会を与えられたと捉えているんです。
長年同じ仕事を続けていれば、小さなことでは今更感があってなかなか人に聞けないし、失敗もできなくなってきますよね。でも私の場合は、異業種からの転職だったので、教育に関しては全くの初心者。右も左も分からないけれど、逆に守るべきものや変なプライドがなく、失敗を恐れずに積極果敢にチャレンジできました。
そのおかげで、前職では知り得なかったことをたくさん学ぶことができ、いろんな人とのつながりも生まれました。それは転職して良かったことだと思います。
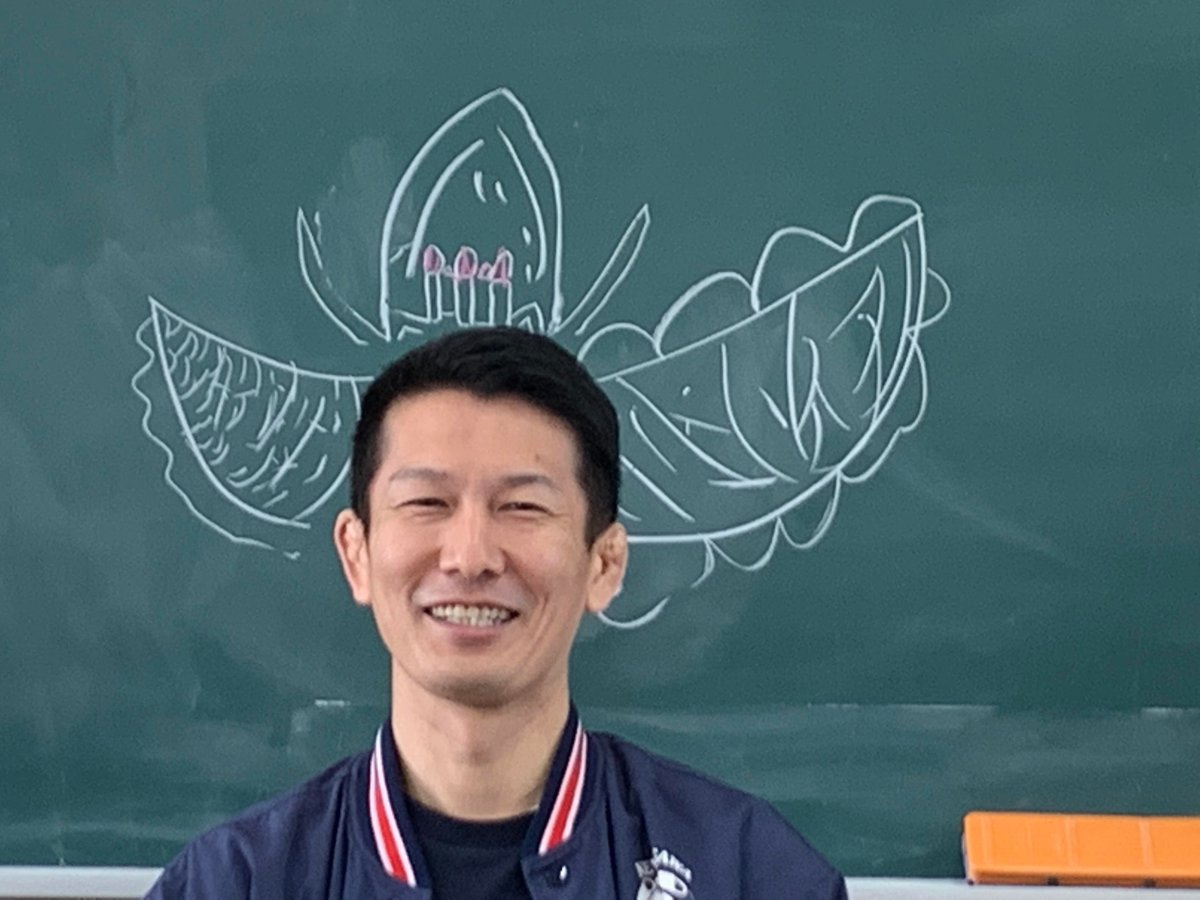
やりがいは、卒業していった子どもたちが連絡をくれて、近況報告や相談をしてくれることですね。今どんなことを頑張っているのかとか、進学先についての相談話なんかを、先生と子どもとしてではなく、一人の人間同士、対等な関係性でやりとりできることが、この上なく楽しいですし、先生という職業の大きな喜びややりがいの部分だと感じています。
——これから先、荒石さんが教員として実現したいことや今後のビジョンがあれば教えてください。
いずれは教頭や校長の立場から、誰一人取り残さない、全ての子どもたちが学べる学校づくりをしていきたいと思っています。
さまざまな学校を見させていただいて感じるのは、多くの子どもが学べていたらそれでよしとする状況が多いこと。それでは、多くの子どもよりも学ぶのに時間をかけたい2〜3割の子どもたちは、取り残されたままになってしまいます。
もっと一律な学習に困難を感じている子どもたちもしっかり学べるような学校を作らないとダメだと思うんです。それは例えば、子どもの学ぶ姿を見とって授業を作る研究スタイルだったり、子どもの自己決定・自己選択による学校行事や児童会活動が行われたりする学校だと思います。
形はいろいろあると思いますし、半年後や1年後にはまた違う課題が見えているかもしれませんが、とにかく悪い意味でサラリーマンっぽく仕事をするのは嫌なので、日々、何かに気づいていけるような熱い心は持ち続けたいと思っています。
——最後に、かつては転職することを迷われていた荒石さんですが、ご自身の経験を経て、異業種から教育現場に入った人にこそできることは何だと思われますか?
自身の経験を振り返ると、警察にしろ、学校にしろ、やはり“閉じられた世界”だなと思います。だからこそ、新参者である自分が教育現場に新しい風を吹き込み、より良い方向へ向けて変化をもたらすために貢献できればと思っています。
私のように、全くの異業種から教育現場への転職を考えられている方がいれば、不安も大きいとは思いますが、「迷わずに、自分の考え通り突き進め!」とお伝えしたいですね。
取材・文:小林 由芽 | 写真:ご本人提供
