
4 「移民国家」アメリカ——「文明人」はどちらなのか 白岩英樹
早くも2回目の番が回ってきた。とはいっても、手を挙げ、光嶋さん-青木さんとつながってきたバトンを受け取ることを所望したのは、わたし自身だ。そうせずにはおれない自分がいた。その理由は、かつて不可視化された存在からの「呼びかけ(call)」に対して、「応答(response)」せねばならないという「責任(responsibility)」を腹の底で感じたからである。
たとえエッセイとはいえ、自分に嘘はつきたくない。死者が眠る「ゲート(gate)」の向こうへ行く人間が現れたら、ちょっと待って! と声をかけ、巡礼の道行きにお供したい。それが、死者の声を聴いた「ゲートキーパー(gatekeeper)」としての使命というものである。いったん見聴きしてしまった以上、彼らはわたし自身の血肉と化したのも同然であるのだから。
無数の声を内に取り込むことで成立する自己から、他者をクリスタルクリアに切り分けることなどできない。ましてや、黙過したり放下したりすることは、自己を邪険に突き放し、葬り去るに等しい。自他の対話の場においても、不可視化された他者の声をそこから抜き去ってしまえば、後に残るのは独断と放言に満ちたエコーチェンバーとフィルターバブルだけになってしまう。
そのような惨状はなんとしてでも避けたい。光嶋さんがいみじくも語ったように、わたし自身も「わからなさの中でためらいながら対話することによって生成されるフレッシュな意味を丁寧に汲み取っていきたいのである」。そうして、お互いの言葉から醸成される思想や精神性から「学び(learn)」えたことを、3つの椅子をゆっくり移動する過程で、自らの言葉で「学びほぐし(unlearn)」ていきたいのだ(鶴見俊輔『教育再定義の試み』)。そして、それら一つひとつの手ざわりを確かめながら、バトンとして次の仲間に手わたせれば、と思っている。
そのためにも、違和を感じるところがあるならば、放言の一歩手前で伝え合い、自他の足場を確かめ合うことが、より誠実な対話の前提になろう。それは相手が誰であろうと変わらない(大学でも、そのようにして学生や同僚との対話の基盤を日々築き直している、つもりである)。せっかく言葉を紡ぎ合っていくならば、そのような相互省察を介した「成熟」を、「遅熟」でも「追熟」でも、追究していきたい。わたし自身は本リレーエッセイの意義をそのように捉えている。

アメリカの内外には矛盾が残存する
一神教が生まれる以前の古代地中海史を専門とする青木さんにとって、考古学や歴史学の視点からすれば「アメリカははっきり言ってアウトオブ眼中」であり、「本流」とされるヨーロッパの歴史や文化から見れば「アメリカの歴史はそこから派生した一支流に過ぎない」。そして、「ある意味純粋に考古学や歴史学を研究しようとすると、アメリカは視界に入ってこない」という。にもかかわらず、思考が現代社会におよぶと、「視界に急にアメリカがフェードインしてきた」とも。
今日、「帝国」アメリカの深部を透視するのは困難を極める。もちろん、「属国」さながらの立場におかれた日本に対する「圧政」は、青木さんが語る沖縄米軍基地の問題を含めて、つねづね感じられる。けれども、それらと「本来」のアメリカに潜在する問題を接続して考えることが、非常に難しくなっている。あまりに悲惨な過去があったこと、さらには歴史の遺却がいまなお継続しているがゆえに、幾重もの曇りガラスを通したような状態でしか、アメリカをまなざすことができないのだ。
9.11同時多発テロ事件が起きた後、アメリカ先住民族のあいだで、「国土安全保障(自分たちの土地を守る)、1492年からテロと戦ってきた(Homeland Security, Fighting Terrorism Since 1492)」と胸に書かれたメッセージTシャツが広まったという(阿部珠里ほか『アメリカ先住民を知るための62章』)。1492年とは、いうまでもなく、コロンブスがアメリカを「発見」した年である。先住民族のメッセージは、2001年の同時多発テロだけでなく、彼ら自身を先祖伝来の土地から引き剥がし、排除し続けてきた入植者たちにも向けられていた。彼らの怒りはアメリカの内と外に残存する矛盾を鋭く突き刺すものであった。
にもかかわらず、というべきだろうか。2011年に遂行されたオサマ・ビンラディンの掃討作戦でビンラディンに使われたコードネームは「ジェロニモ」。「帝国」アメリカによる迫害に、最後まで抵抗を続けた先住民族長の名であった。そして、攻撃ヘリコプターにはアパッチ、ステルス・ヘリコプターにはコマンチと、さまざまな兵器に先住民の部族名が使用された。国内では彼らの排除を推し進めながら、国外では勇猛な先住民族名を誇示し、アルカイダの指導者に対して、先住民の英雄の名前を付与する。はたして、アメリカの主体は那辺に存在し、どこを向いているのか。
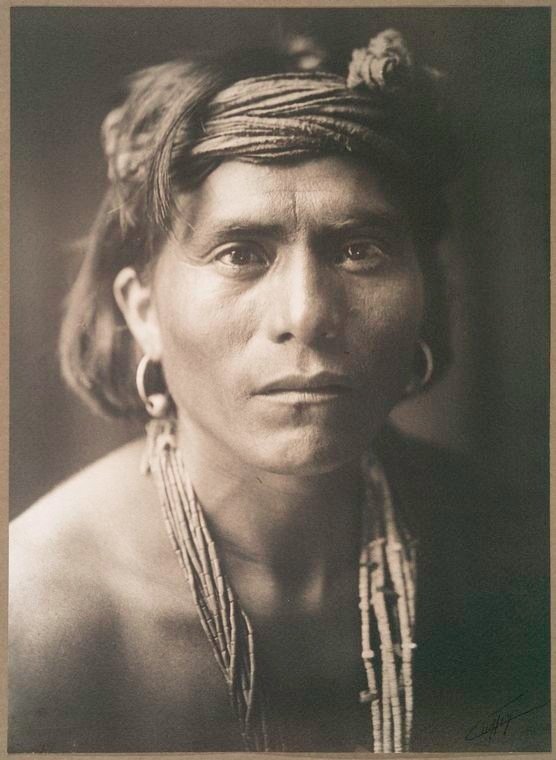
建国の礎には先住民へのリスペクトがあった
建国当初のアメリカは、ヨーロッパからの差別を押し返すのに躍起だった。というのも、フランスの生物学者ビュフォンが、新大陸アメリカの動物はヨーロッパの生物よりも劣っているという仮説を唱え、それらをアメリカの先住民族にも適用したからである。曰く、アメリカの先住民は身体が弱く、感覚も鈍い。怯懦かつ臆病で、敏捷さも精神の活力もない......。
ビュフォンの説や手法は、現在顧みれば、似非科学を用いたレイシズムの典型にすぎない。しかし、20年近くにわたってアメリカ学術協会の会長を務めたトマス・ジェファソン(第3代大統領)は、彼の蔑視に満ちた仮説に対し、一つひとつ丁寧に反論を施していった。そして、「実に心痛む描写であるが、私は人間性の名誉のために、ここに描かれた情景には原型がないということを喜んで信じたいと思う」と書き、先住民族の尊厳を守った(『ヴァジニア覚え書』)。
また、合衆国憲法の民主主義や連邦構造に関する条項は、「建国の父」ベンジャミン・フランクリンが、イロコイ族の部族同盟から深くインスパイアされてできたことが知られている。彼らの連合体は、単なる垂直方向の支配構造ではなく、かといって水平方向への連帯や和解だけでもない。フランクリンが感心するほど、その組織形態は絶妙だった。それは「自然と人間との結合の意識」に根ざしており、当時のヨーロッパ人や入植者たちにはとうてい理解できるものではなかった(鶴見俊輔『北米体験再考』)。
セトラー・コロニアリズムが奪ったもの
しかし、19世紀に入ると、入植者たちによる先住民政策は大きく舵を切る。いわゆる「明白なる運命(Manifest Destiny)」による、「西漸運動(Westward Movement)」が推し進められたのである。彼らは圧倒的な武力で虐殺を繰り返し、先住民の土地を収奪しながら、西へ西へと「帝国」アメリカの領土を拡張していった。その所業を今日の倫理と言葉で捉え直せば、「民族浄化(ethnic cleansing)」のそしりを免れえないだろう。
入植者たちが持ち込んだ感染症の影響も甚大であった。コロンブス到来時には、少なく見積もっても500-1,000万人の先住民が北米大陸に暮らしていたと推計されている。それが、「インディアン戦争(American Indian Wars)」終結から10年を経た1900年の国勢調査では、24万人弱にまで激減していた。度重なるジェノサイドと伝染病の蔓延による人口減少は凄惨を極めた。
ひとくちに先住民族といっても、使用されていた言語は部族ごとに異なる。ヨーロッパから入植者がやってくる以前には、北米には300もの言語が存在していた。先住民族は文字を持たなかったが、彼らの口承文化は、「国家」的な支配から逃れるために選びとられた戦略であったともいえよう。事実、17世紀後半から18世紀にかけて、五大湖周辺には入植者の支配から逃れた多様な先住民族が集い、文字の代わりに、サインランゲージがコミュニケーションの手段として用いられていたらしい。
そのように抵抗に抵抗を重ね、権力的な支配を免れた部族も、権謀術数の限りを尽くした暴力を前に、次々と滅亡していった。彼らの死は、彼らが使用していた固有言語の絶滅のみならず、その言語自体に潜在していた叡智の喪失をも意味する。生き残った先住民族も、19世紀以降の同化政策によって、英語の使用を強制された。入植者によるジェノサイドは、先住民の身体のみならず、精神文化にもおよんだ。
先住民族がいまなお苦しむ諸悪の根源は、「セトラー・コロニアリズム(settler colonialism)」である。「入植植民地主義」と訳されるセトラー・コロニアリズムは、その名のとおり、植民地に入植者が定住する過程で、先住民から土地を奪い、彼らを体制の周縁へと排除することで成立する。先祖伝来の自然から切り離された彼らが追い込まれる居留地は、生活インフラも整っておらず、核開発や汚染物質の廃棄による環境破壊が深刻な土地である。
国家が「発展」するための「犠牲区域(Sacrifice Zone)」として供出された居住指定区域は、アメリカ総面積のわずか2.4%。しかしそこには、凝縮されたアメリカの撞着が吹き溜まっている。元々は残りの97.6%を含めた100%が、彼らとは切っても切れない縁のある土地だった。「本来」のアメリカは、彼らでさえ駆け回り尽くせないほどの豊饒な自然を持ち、それらを介して、あらゆる動植物の「精霊(spirit)」とつながりうる大陸だった。「帝国」アメリカの軍事主義や資本主義になど包摂されえない、別の可能性に満ちた場所だったのだ。

沖縄についても同様のことが言えまいか。沖縄県は日本の総面積のたった0.6%にすぎない。にもかかわらず、米軍専用施設が占める面積は、日本全体の7割を超える。沖縄県民の負担面積は他の都道府県民ひとりあたりの約200倍である。しかも、米軍基地の集中化が進められたのは、太平洋戦争末期に字義通りの「犠牲区域」とされた沖縄が本土に復帰するまでの27年のあいだであった。「本土の基地負担を軽減するために、日本国憲法が及ばない沖縄への基地集中が進められたのです」、玉城デニー沖縄県知事はそのように陳述する(「辺野古代執行訴訟 沖縄県知事の意見陳述」)。
ネイチャーへの憧憬が呼び戻したリスペクト
先述したジェファソンは、先住民族に対するレイシズムを押し返した。だが、そんな彼でさえ、「インディアンの偉大なる記念物」の存在は知らないと述懐する。そして、「ただし、わが国全土にわたって数多く存在する土墳だけは別である」と(『ヴァジニア覚え書』)。先住民が死者を葬り、先祖とつながる場でもあった土墳は、古くは3,000年以上前のものと推測され、今日も10万以上が遺る。
我々は自分たちの文化を、意識・無意識を問わず、自らの言語に組み込んでいる。同じように、土や草木を用いた暮らしや家屋にも、我々の文化は必然的に埋め込まれている。しかし、石や鉄を用いた生活や「大建築」で文化を遺した先住民族はまれだ(K・デイヴィッド・ハリソン『亡びゆく言語を話す最後の人々』)。アメリカの先住民族も「古インディアン(Paleo-Indians)」と呼ばれた時代から、石で出来た矢じりを狩猟に用いてはいた。それでも、「大建築」は遺さなかった。
だが、その事実を単なる技術文明の度合いとしてのみ捉えることに、はたしてなんの意義があるのだろうか。それは結局のところ、知性の用い方のバリエーションにすぎないのではないか。周辺環境としてのネイチャー(自然)を、自らの内なるネイチャー(本性)によって征服・支配し、搾取する、のではなく、前者と後者との呼応に有機的な結びつきを見出し、むしろそれらの調和を目指す。そのような文化的志向が顕著な人々が、石や鉄の「大建築」ではなく、人間と自然とが文字通りに融合する場所としての土墳しか遺さないのは当然のことではあるまいか。

先住民族の権利回復が本格的に始まったのは20世紀も半ばを過ぎてからである。1990年には「ネイティヴ・アメリカン墓地保護および返還に関する法(Native American Graves Protection and Repatriation Act, NAGPRA)」が制定され、研究機関等に所蔵されていた遺骨や埋葬品等の返還が義務付けられた。先住民族自身も、土地への「自決権」を主張し、環境正義を求める多くの人々と連帯しながら闘いを拡張していった。
そして、2021年10月8日には、ジョー・バイデンがアメリカ大統領として初めて「先住民の日(Indigenous Peoples’ Day)」を認定。「先住民族コミュニティや部族国家に対して、我が国全土で何世紀にもわたって継続された暴力、強制移住、同化政策、恐怖政治を決して忘れてはならない」と語り、従来「コロンブス・デー(Columbus Day)」としてのみ制定されていた10月第2月曜日に、先住民族に対して敬意を表し、祝典等を執り行うよう、アメリカ国民に求めた(“A Proclamation on Indigenous Peoples’ Day, 2021”)。
だが、社会制度が整ったとしても、それらを具現化していくのは我々である。そうでなければ、「万人の平等」をうたう合衆国憲法も、「人権、平和、民主主義、地方自治」を掲げる日本国憲法も、画餅にすぎなくなってしまう。周縁に追いやられた境遇や押しつけられた負担義務を、ほんの1%ずつでも「我がこと」として捉え直し、責任の転嫁を止めねばならない。そうしなければ、我々の内側に巣食った「帝国」は、いつか我々自身を植民化して食い尽くすにちがいない。
そのうえで、わたしは夢想するのだ。技術文明の粋を尽くした殺傷兵器が、先住民族の祈りとともに土に溶解し、そこから草木がにょきりにょきりと自在に伸び行くさまを。それらをむしゃりむしゃりと食む動物たちの糞尿にまみれた軍事施設が、ゆっくりと大地に還り、愚蒙な遺物が眠る土墳と化すことを。
最後に、精霊を介して世界が調和するさまを詠った、北米先住民族の「魔法のことば」を引用して、次の仲間にバトンを手わたすことにする。
魔法のことば
ずっと、ずっと大昔
人と動物がともにこの世に住んでいたとき
なりたいと思えば人が動物になれたし
動物が人にもなれた。
だから時には人だったり、時には動物だったり、互に区別はなかったのだ。
そしてみんながおなじことばをしゃべっていた。
その時ことばは、みな魔法のことばで、
人の頭は、不思議な力をもっていた。
ぐうぜん口をついて出たことばが
不思議な結果をおこすことがあった。
ことばは急に生命をもちだし
人が望んだことがほんとにおこった——
したいことを、ただ口に出して言えばよかった。
なぜそんなことができたのか
だれにも説明できなかった。
世界はただ、そういうふうになっていたのだ。

〈参考文献〉
グレーバー、デヴィッド『民主主義の非西洋起源について——「あいだ」の空間の民主主義』片岡大右訳、以文社
http://www.ibunsha.co.jp/books/978-4753103577/
〈プロフィール〉
白岩英樹(しらいわ・ひでき)
1976年、福島県生まれ。高知県立大学文化学部准教授。専門は<比較文学/芸術/思想>。博士(芸術文化学)。AP通信、東京都市大学、国際医療福祉大学等を経て、2020年より高知市に在住。著書に『講義 アメリカの思想と文学――分断を乗り越える「声」を聴く』(白水社)、共著に『ユニバーサル文学談義』(作品社)、翻訳書に『シャーウッド・アンダーソン全詩集』(作品社)などがある。
◉この連載は、白岩英樹さん(アメリカ文学者)、光嶋裕介さん(建築家)、青木真兵さん(歴史家・人文系私設図書館ルチャ・リブロキュレーター)によるリレー企画です。次のバトンが誰に渡るのか、どうぞお楽しみに!
◉お3方が出会うきっかけとなったこちらの本も、ぜひあわせてお読みください。
◉アメリカ開拓時代の歴史や人々の暮らしの実際がもっと知りたい方は、こちらもぜひ!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
