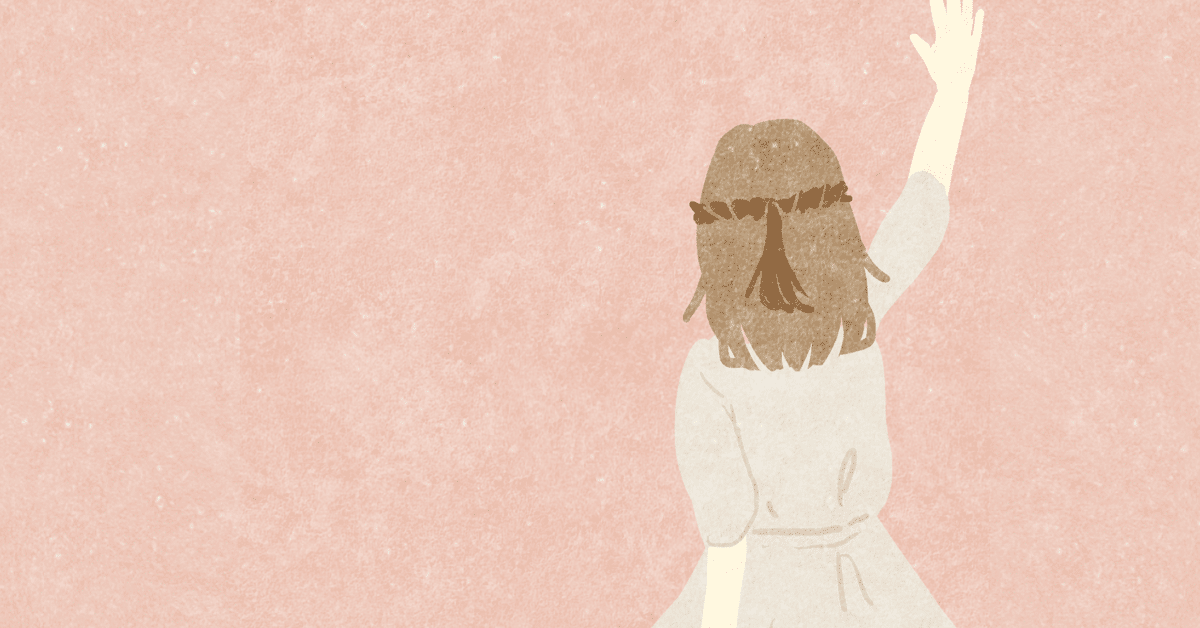
あの先輩にインタビュー! ~環境科学研究科 松八重一代先生~ (前編)
東北大学サイエンス・エンジェル (SA) の やま です。女子学生の皆さんは、高校や大学を卒業した後の将来について、どのようなイメージをもっていますか?就職して働いて、プライベートでは結婚して、出産、子育て...というような、ライフイベントを想像する方が多いでしょうか。女性の社会活躍が進んできた現代において「プライベート(ライフイベント)と仕事をどのように両立していくのか」は、女子学生に限らず若い世代全員が気になることかと思います。とはいっても、ロールモデル(※)となる方が身近にいるとも限らないですよね。そこで読者の皆さんに、社会で活躍する女性を紹介すべく、新連載記事として「あの先輩にインタビュー!」シリーズを始めます。
社会で活躍する女性の中でも、私たちサイエンス・エンジェルにとって身近な存在である「大学教員」や「研究者」として活躍されている方々に、これまでの選択や仕事のこと、ちょっとプライベートなことまで直撃インタビューしていきます。
(※)ロールモデル 将来こうありたい」と目標にする存在
記念すべき第一弾は、東北大学大学院環境科学研究科教授の松八重 一代 先生です。松八重先生は経済学分野で博士教育を修めた後、東北大工学部に赴任された経歴をお持ちです。「女性研究者」としてのお話の他にも分野選択や進路選択に関してもお話を聞いていきます。前編では経済学から工学へ踏み入れた分野選択や進路選択に関するお話を、後編では研究者と子育ての両立に関するお話をお聞きします。後編はこちら。
![]()
松八重一代先生のプロフィール

・ご経歴
1998年3月 早稲田大学 政治経済学部 政治経済学科卒業
2000年3月 早稲田大学大学院 経済学研究科 修士課程修了
2004年1月 早稲田大学大学院 経済学研究科 博士後期課程(理論経済学・経済史専攻 計量経済学専修)単位取得の上退学、博士(経済学)
東京学芸大学教育学部非常勤講師などを経て、
2004年2月 東北大学大学院 環境科学研究科 環境創成計画学講座ライフサイクル評価学分野 助手
2007年4月 同 助教
2008年10月 同 准教授
2011年4月 東北大学大学院工学研究科 金属フロンティア工学専攻 材料・資源循環学分野 准教授
2015年10月~2016年7月 Center for Social Responsibility in Mining, Sustainable Minerals Institute, University of Queensland, Australia, Visiting Associate Professor
2016年8月 東北大学大学院 環境科学研究科 環境政策学講座 環境・エネルギー経済学分野 教授
・研究分野・キーワード
廃棄物・資源経済学、産業エコロジー、ライフサイクル分析
・研究室HP
http://web.tohoku.ac.jp/matsubae.lab/
![]()
現在の研究やお仕事について
やま)インタビューをお引き受けいただきありがとうございます。さっそくですが、松八重先生のご専門は「計量経済学」とのことですが、どのようなものか簡単にご説明いただけますか?
松八重先生)「計量経済学」は、経済学の理論に基づいて経済モデルをつくり、モデルのパラメータを省庁や調査研究機関が出す各種統計を用いて推計・検定することによって妥当性チェックしつつ、経済行動の予測や検証を行うという実証研究です。
私が行なっているのは、計量経済学の王道的研究からやや離れておりますが、産業エコロジー学という分野で発展してきたマテリアルフロー分析や産業連関分析といったツールを用いて、消費活動、生産活動といった経済活動を通じてどのように資源を消費し、どのような環境負荷を発生しているのかを定量的に明らかにする研究です。
鉄鋼の原料採取から製造、流通、廃棄、リサイクルに至るライフサイクル全体の環境負荷を評価する「ライフサイクルアセスメント」とか、鉄鋼生産に伴う副産物に随伴する未利用資源の活用に向けたシステム提案とか、廃自動車処理、資源化に関わる稀少資源散逸を抑えるための「スクラップソーイングティング」の研究などを中心に取り組んできました。鉄鋼産業の活動に着目しつつ、素材循環の中で不純物や介在物となるような元素の流れや、廃棄物や未利用資源の流れなども解明する中で、特に「リン」という元素に着目した研究にも取り組んできました。

( イラスト 松八重研究室HPから引用)
やま)ご説明いただきありがとうございます。経済学の手法を用いて、鉄鋼プロセスなどの工学分野の課題に取り組んでいるのですね。
![]()
経済学から工学分野に踏み入れたきっかけは?
やま)「経済学」と「工学」は、かけ離れたものに感じますが、経済学の畑から工学部に赴任なさったのはどのようなきっかけだったのですか。
松八重先生)博士課程の時に、後の就職先の上司となる先生と当時の指導教員がお話をしていて、その縁ですね。東北大工学部への赴任の声をかけていただいた当初は、驚きました。でも、他に職のあては無かったし、とりあえず行ってみようと思い、お話を受けました。
もともと私は「計量経済学」というデータを中心として、統計データを当てはめて、パラメータを抽出するということに取り組んでました。伝統的な経済学の枠組みでは廃棄物はコストや環境負荷なしで処分できる(Free-disposal) の仮定をおく分析も多かったのですが、廃棄物の発生・処理に関わる費用は無視できないものと考え、環境廃棄物の排出と再資源化を明示的に扱うモデルの開発と応用に取り組んでいました。当時から、ライフサイクルアセスメントのようなことをしている感覚はありましたが、工学に関連した研究を自分がしていくという感覚はなかったです。

(イラスト http://www.kankyo.tohoku.ac.jp/から引用)
![]()
文理の違いを感じたことはありますか?
やま)文系理系の双方をみてきた松八重先生だからこそお聞きしたいのですが、文理の違いってなんでしょうか。
松八重先生)学問分野でここまでが理系ここまでが文系っていう境目があるわけではないと思います。入試制度として受験科目の違いで文系理系と言っているだけであって、何をやりたいかによって学ぶべきツールが変わりますしね。経済学部では、関数解析、統計学、確率論など数学は欠かせないものですし、理系だといっても、材料科学とか材料物理学では統計学や確率論はそれほど使わないですよね。
やま) たしかに、高校で学ぶ科目という意味で文理選択はありますが、大学での学びは文理の境目はありませんね。私は工学部でいわゆる理系ですが、文系科目も大切だと感じることが多いです。例えば、論文を書いたり発表したりする際には論理的に物事を伝えるため国語が欠かせないし、国際交流には英語が上手なことが有利だと日々感じています。

やま) 文理の境界がはっきりないとすると、日本で理系に進学する女性が少ないのはなぜだと思いますか。
松八重先生) 理系に進学する女性が日本では少ないのは、ライフイベントを含めていわゆる理系就職をしたときに長く働くことがイメージしづらいからかと思います。スキルを持っている方が有利に進路・職の選択ができるから、理系の中でも看護師や薬剤師など資格取得が見込める学部学科を志望する女性が多いのではないでしょうか。
やま)鋭い考察をありがとうございます。女性が少ない就職先では、産休・育休がとれるか、その後の職場復帰はできるのか、など不安に思うのかもしれませんね。
そんな不安ゆえ「理系に進学して大丈夫かな...?」と考えている学生さんのためにも、ロールモデルとなる女性の先輩の姿を伝えることが大切だと改めて思いました。この記事もその一環となれば幸いです。
![]()
前編はここまで!!
出産や子育てなどプライベートなことについてお聞きした後編もぜひご覧くださいね。
記事へのコメントや質問などは、こちらのフォームからお願いいたします。
゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+
編集後記
文系、理系がはっきり分けられているものではないように、物事はすべてが
白・黒、0・100のものではないですね。多角的な視野をもって灰色や20、50、80など中間的、融和する部分も見つめられる人になりたいです。(やま)
東北大学サイエンス・エンジェル
次世代の研究者を目指す中高校生に「こんな女性研究者もいるんだ!」「理系って楽しい!」という思いを伝えるため、2006年に結成。年度毎に学内で公募され、総長に任命された 東北大学の自然科学系10部局に所属する女子大学院生が、中学・高校での出張セミナーや科学イベントで科学の魅力と研究のおもしろさを伝えている。メンバーは宇宙・自然・ロボット・環境・ヒトや動物の身体のしくみなど、それぞれの専門分野で日々研究中。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
