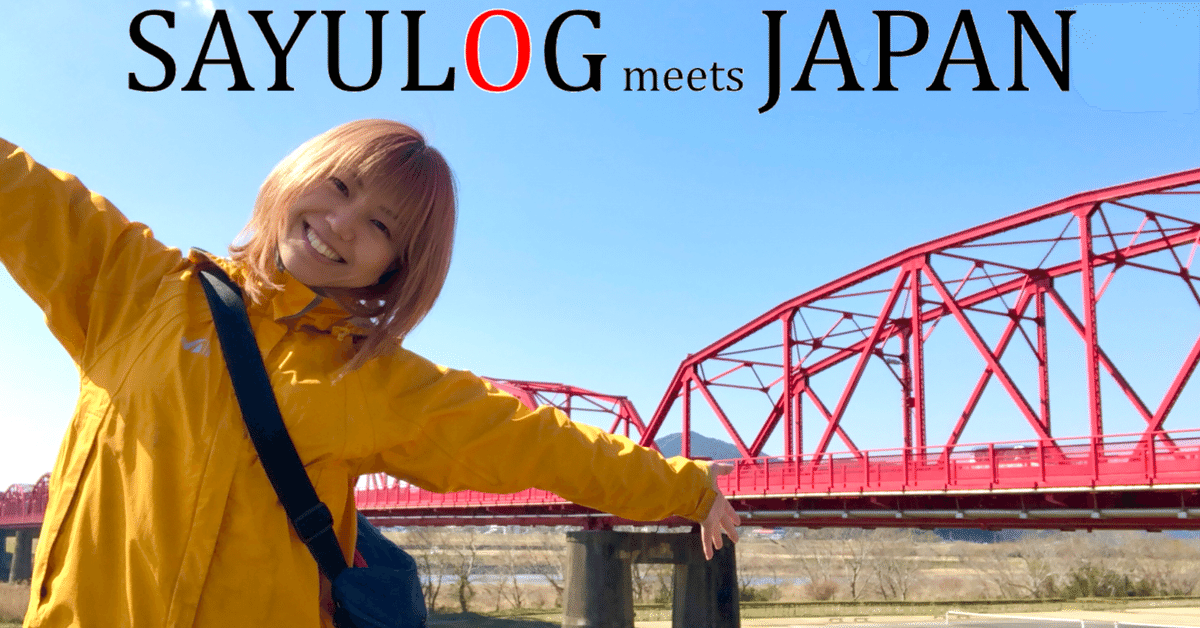
新企画「SAYULOG meets JAPAN」がスタートするまで
2021年2月23日、ようやく発表に至った新企画「SAYULOG meets JAPAN」。この企画がこうして始動するまでには、実は約半年の歳月がかかっていることを、noteでこっそりみなさんにお伝えしたい。
YouTuber、3年目の葛藤

2021年9月26日。私がYouTuberを始めて丸3年を迎えた。チャンネルは2年前からずっと伸び悩んでいた。じわじわは伸びていたが、私の思うような伸び方はしていなかったし、その数字に私のメンタルも左右されて、コンスタントに動画が挙げられていなかった。私のやりたいこととチャンネルで求められていることにも差を感じるばかりで、楽しさもあるけれど、正直直近2年はしんどかった時間の方が長かったように思う。
台湾では既に外国人、特に日本人インフルエンサーの市場が出来上がっている。私がいくらひとりでもがいたって到底敵いっこない市場が出来上がっていたので、そこに切り込んでいかないとやっていけないというのが本当に嫌だった。その上、私はテレビ向きでもない。原稿があって、それを上手に話せる技量もない。YouTubeは自分がハンドリングできるけれど、テレビとなったら毎回撃沈。面白いこともろくに言えず、キャラも尖っていない私はすぐにテレビからお声がかからなくなる。
YouTubeにどんなに自分がいいと思うものを発信しても数字が伸びない。良くも悪くも数字が全てな世界でもある。そもそも私が発信したいのは台湾だけと限定するのではなく、相互にいろんな情報をもっと手に取りやすいように発信したかった。2019年にトルコへ行ったのも、台湾という枠に縛られて身動きが取りづらくなって模索していたからだった。何とか変化させたかった。
ちょっとしたことを知ることができるのは楽しい。そして、知っているから摩擦が減る。そんなきっかけとなるようなことをYouTubeで発信したかったけれど、うまくカタチにできず、それでも生活基盤は基本台湾にあるので、内心は悶々としながら、その中でも自分の伝えたいことを自分の出せる限りのポテンシャルで発信し続けた。
ちょうどその頃、「SAYULOG meets JAPAN」の企画を思い立った。企画スタートの約半年前、当時の私はまだ台湾で生活していた。
このひと月前、台湾の夏の終わりと共に入院した母のために、退院のタイミングがおおよそわかったら帰国して、少しそばにいてあげたいと思った。母の病院の方々とやりとりをする中でわかったのは、どうやら母の状況は私の想像以上に良くなさそうだということ。これはしばらく帰った方がよさそうだ。でも、このコロナの時期に帰国するというのは、すぐちょちょいとまた台湾へ戻って来る、という選択はないな、と思っていた。行き帰りで隔離2週間ずつ、約1ヶ月潰れるのは痛い。
とはいえ、台湾を中心にYouTuberとしての仕事がメインになっていた私。ここでひとつの壁にぶち当たる。
「さて、日本にいる間の仕事はどうしよう?」
物理的に私自身が台湾にいないと撮れない動画というのが存在する。特に、これまでやらせていただいていた、台湾の観光局系や企業さん系のコラボ動画は私が現地にいないと撮れないものばかり。その上、日本の市場は未開拓。
けれど、なぜだか自信があった。YouTuberになる前の仕事で培ってきた感覚と、YouTuberを始めてからカタチにしてきたもの。これらはきっと日本へ行っても役に立つ。私自身の、というよりも、地域の人たちやクライアントさん、将来的にクライアントさんのお客さんになる人、そして何より、動画を観てくださる視聴者さんたちにとって、きっと役に立つ。私が発信することで、誰かを元気づけられたり、楽しませたり、ほっこりさせられるかもしれない。私は基本、自己肯定感の低い人間だけれど、今回の自分の感覚だけは信じられた。
日本での実績を0→1にするために

「SAYULOG meets JAPAN」の企画を思い立ってからはずっとワクワクしていた。とはいえ、日本でそれをカタチにするには、まずはこれを人に目で見える形でまとめなければいけない。すぐに企画書を作り始めた。
出来上がった荒削りな企画書をいろんな人に見せては、私には見えていなかったような角度からのアドバイスをいただいた。お忙しい中、私の企画書を見てくださり、アドバイスをくださったみなさま、また、「こんなことやろうと思ってるんです!企画書見てください!」と突然企画書のリンクを送らせていただいたにもかかわらず、熱い応援メッセージをくださったみなさま、この場を借りて改めてありがとうございます!またご意見ください!
ときには営業経験のある海外在住の友人の力を借りて、資料をアレンジしてもらうこともあった。いまの時代はどこにいてもすぐに繋がれるし、本当にいい時代だと思う。マレーシアと日本でリアルタイムで会話をしながら資料に手を加えていける日が来るなんて、子供の頃に想像もしていなかったことが現実に起きている。
やはり元リク●ートの営業さんは資料作りが上手い。「お客さんのために、視聴者さんのために、さゆりんができることって、こういうことだと思うの。」と、自分では見えていなかった自身の強みなど、彼女からアドバイスをたくさんもらった。
私はずっと企画書とか提案書とかいうものを作ることに強い苦手意識があった。これまであまりそういった「THEパワポ」的資料を自ら作ることもそんなになかった。あったとしても、自分が提案内容を強くイメージできる案件以外は過去資料をベースに真似して作ったものが多く、説得力に欠けるものが多かったように思う。
そんな私がいっちょまえに、Googleスライドで用意した自分の企画書を見せながら、多くのクライアントさんたちに1件1件、オンラインで企画への熱をぶつけ、プレゼンしまくる。そんな日々が続いた。
自主隔離期間の過ごし方
日本へ帰国後の2週間の自主隔離期間。こんな動画も撮っていたが、この隔離期間=母が退院するまでの2週間ちょっとは、1日8時間の打ち合わせやブレストするのもザラで、1日プレゼン4件、うち、後半にプレゼン3件が3時間続いた日には、口の中がパッサパサになった。これほどまでによくしゃべる私がとうとう「もうしゃべりたくない(´Д` )」と数日黙るという奇跡さえ起こった。人に思いを伝えるというのは、こんなに頭を使って無になるのか、という新たな発見もあった。
「自主隔離期間は孤独だ」という人もいる。でも私は結果として、自分の好きなことと、ZoomやLINEでのビデオ通話を挟みながら、母の部屋の大掃除ばかりしていて、とてつもなく充実していた記憶しかない。オンラインで顔を見ながら人と話して、お掃除で体を動かす。食料や生活用品はUberEatsとAmazonを駆使して生活。意外と健康的で便利な自主隔離期間だった。
収束が見えないコロナに撮影を延期

こういう仕事をしている以上、やはりコロナの状況には敏感。特に、早々とコロナの抑え込みに成功した台湾からきている私としては、抑え込みまでのピリピリとしていた台湾での撮影でどのような対策をして撮影してきたかも経験してきていたので、状況は違えど、注意に注意を重ねつつ、その上で仕事をすることを最優先に考えてきた。自分自身が感染しない、移さない、はもちろん、母が既往症が多く体も弱いので、なおさら気をつけなくてはならない。それに、視聴者さんや関わってくださる皆様の不安を煽ったり心配をさせてはいけないし、私が撮影に伺うことで各地域の方々を不安にさせてはいけない。
12月中旬から開始しようとしていた撮影は1月スタートに延び、緊急事態宣言発令により、それを更に2月8日に延ばした。
先延ばししているうちに、どんどん時間だけが過ぎていった。その間、自宅で何本か撮影はしたけれど、心はすでにこの企画一色だったので、自分が届けたいと強く思える動画が作れずお蔵入り。自分ができることは何か、どうしたらなんとか安全に撮影が進められるか、いろいろ考え、ルール決めをしていった。
私なりに決めた撮影ルールと大事にしたいもの

撮影をいつから始めるか?
そもそもこの状況で、この企画を始めてもいいのか?
ものすごく悩んだ。東京を含めた一部地域の緊急事態宣言が1ヶ月延長され、もしかしたら日本に一時帰国している5月半ばまで撮影できないなんてこともあるんじゃないのか、とさえ思った。
年末の時点ですでに今回の企画をサポートしてくださっている企業さんのひとつである多拠点コリビング(co-living)サービスのADDressさんとのコラボのお話は決まっていた。どうしたら安全に、安心して撮影を進められるかを考え、ADDressさんと何度も何度もお話をさせていただき、私のタイミングでスタート時期を決めさせていただくことも賛成してくださった。
東京を起点として私が撮影に出ることを嫌がる人は多いだろう。では、どうしたらいいのだろうか。
私が悶々としている中、SAYULOGのチームメンバーから助言があった。
「まず、さゆりんが、この企画を始めるのと延期したのとで、どういうメリットとデメリットがあるんだろう?考えてみたら?どちらか大きい方で決めたらいいと思う。」
それを考えてみたら、結果はシンプルだった。
撮影を始めた方が断然いいとわかったのだ。
その代わり、安全に進められるようにするための方法は考えなければならない。そこで私は、この撮影におけるルールを決めた。
SAYULOGにおける撮影ルール(2021年2月版)
1. 都道府県を跨ぐ他地域への移動2日前以内の検査実施
私だけでなく、撮影スタッフを同伴する場合は、彼ら、彼女らにも同様に検査をお願いしている。
2. 毎日の検温、パルスオキシメーターで体調を確認
パルスオキシメーターはアメリカの家庭や様々な場所で導入されているということを知り、海外基準でいいものは取り入れていこうということで採用。現在、大人気のようで発送待ち。
3. 基本的に、サージカルマスク着用の上で撮影
野外でソーシャルディスタンスがしっかりと確保されていたり、周囲に人がいない場合、また写真撮影時のみ、外す場合もあるが、基本はマスク着用。
4. 食レポが必要な場合もコメントは、極力マスク着用
おいしさはすぐ伝えたいので、これが結構大変ではあるけれど、極力もぐもぐし終わってマスクするか、抑えめでコメントする。
5. ソーシャルディスタンスを確保の上、撮影
6. どうしてもソーシャルディスタンスが確保しづらかったり、撮影上必要であると判断した場合には、フェイスガードを着用の上、撮影
この場合、マスク着用の併用も考慮する。
7. 消毒グッズを常に持参し、こまめに手指の消毒
アルコールスプレー、消毒ジェルなど、どこへ行っても必ず持参。
とにかく自分はもちろん、周りの方々の安心、安全も確保しながら、いま自分のできることをしていきたい。これが前提。企画発表の時、ただ「こんな企画やります!」ではなくて、企画をしようと思い立った背景や、撮影でどんなことに気をつけているかについてもちゃんとお伝えして安心いただきたかったので、こんな風に動画で伝えている。
今週から本編も少しずつお届けしていこうと思う。新たな試みなので、きっと最初から全てうまくはいかないだろう。機材も高額ないいものを使えているわけではないので、目の肥えた視聴者さんからはお叱りを受けることもあるかもしれない。でも、みなさんのご意見に耳を傾けながら、少しずつブラッシュアップしてカタチにしていけたらと思っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
