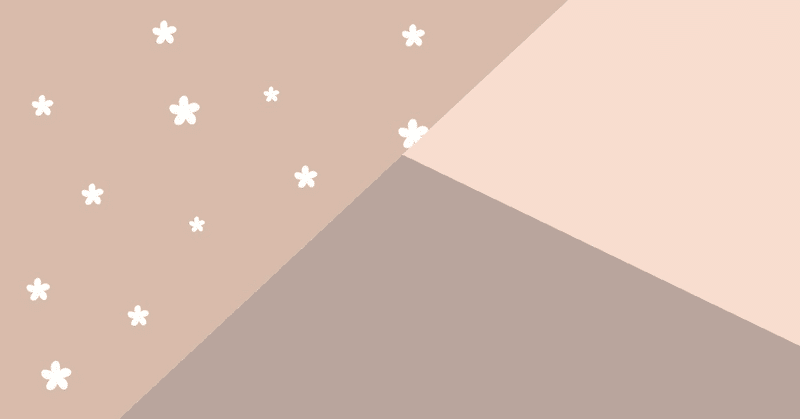
【短編小説】バルコニーも付けてね
「好いた男から愛されなくなったら、二人で家でも建てて仲良く死んでく?」
あはは、とマリーは笑った。マリーは本当は鞠恵(まりえ)というのだけれど、いつもMARIEというクッキーを食べているから、あたしは彼女をマリーと呼ぶ。
「建てるならいっそ庭付きね」
話に乗ってくれたマリーに、”そう、バルコニーも付けてね”と、あたしはそう言いたかった。バルコニーさえあればガーデニングやらバーベキューやらプールやら、家でもできることがうんと増えるものだ。洗濯物だって太陽をめいっぱい吸い込んで完璧に乾くだろう。だから、”バルコニーも付けてね”と言いたかったのだ。
言えなかった。
その代わり、あたしは彼との関係が終わったら死のう、と思った。
それは本当に突然の閃きで、自分で酷く驚いた。けれど、不思議と恐れは感じないのだった。
「大丈夫?庭の妄想し過ぎてない?」
「夏にはミニひまわりを咲かせたい、とか?」
やだ、ミニひまわりの話はしないでよ、とあたしは慌てた。
マリーがルイボスグリーンティーが並々注がれたマグカップに口をつける。彼女はいつもルイボスグリーンティーを飲む。あたしも飲んでみたのだけど、えぐみが無く、程よくルイボスの香りを残しつつも緑茶の味がした。きっと何を食べても味の邪魔をしないお茶なのだ。クッキーのマリーの素朴な卵の味も、上手く引き立ててくれるのだろう。
思考はミニひまわりへと戻される。マリーと小学校のミニひまわりの種を毟って用務員のおじさんに叱られたことがある。収穫した種を全校生徒に配ってやりたかったんだよ、と悲しそうに言われた。おじさんの優しさに泣いてしまったことも覚えている。もうすぐ二十年前の話になるのだろうか。
あの頃はさ、あたしは言う。
「あの頃は、命を投げ出してまで愛したい人との出会いを絶対に信じなかったよね」
それでいて、いざその人に愛されてもどこかで寂しさを背負っているような感覚がある。それはきっと孤独というもので、結局のところ孤独は、何処で誰といてもあたしのことを逃したりはしないのだ。夜と同じように。夜が満ちるとあたしは、いつも逃げきれずに足を取られて夜に溺れる。夜は冷たく、憂鬱だ。
旦那と喧嘩したのよ、と泣きながらマリーが電話をかけてきたのが今朝の話だ。だからあたしはマリーの家にお茶しに来た。彼女の左手薬指と違って、あたしのは空っぽだ。マリーがいくら今の不幸を嘆いたって、愛し愛される人と永遠を誓った過去があったことには変わりはない。それに、喧嘩したのと電話がかかってくるのもそろそろ十回目程になるはずだ。あたしはそれすらも少しだけ羨ましい。何せ、近頃なんだか憂鬱で自分のことで精一杯なのだから。
「あんたも私と家を建てるだの言ってないで、もっと貪欲に自分の幸せ追っかけてみたら?」
「ほら、私を慰めてる場合じゃないでしょうに」
遠回しに帰れと言われてしまった。全く、泣きながらあたしを呼んだのは誰だと思っているのだろう。だけどそれがマリーだ。そして実際、もう彼と住んでいる家に帰って夕飯を作る時間だ。
彼と二人で作りあげてきた住み良い幸せな世界のことを考える。凄くシンプルなことなのだけど、あたしにはあたしの幸せがあること、忘れちゃいけないなと思った。仕事ばかりの彼だからデートは滅多にできないけど、日々の中でとびきり楽しいことを見出すのが得意な彼だから、あたしも毎日がささやかな幸せでいっぱいになったことも忘れないでいよう。
今夜はデザートも買って帰ろう。彼の好きなコーヒーも淹れよう。これからも彼と同じ甘さと苦さを啜って美味しいと言いたいものだ。結婚なんてその先にあるもののゴールじゃあるまいし。
マリーに見送られながら、あたしは叫ぶ。
「あんたと住むならバルコニー付きの家がいいけど!当分はそんなこともないから安心してよね!」
サポートいただけると励みになります。よろしくお願いいたします。
