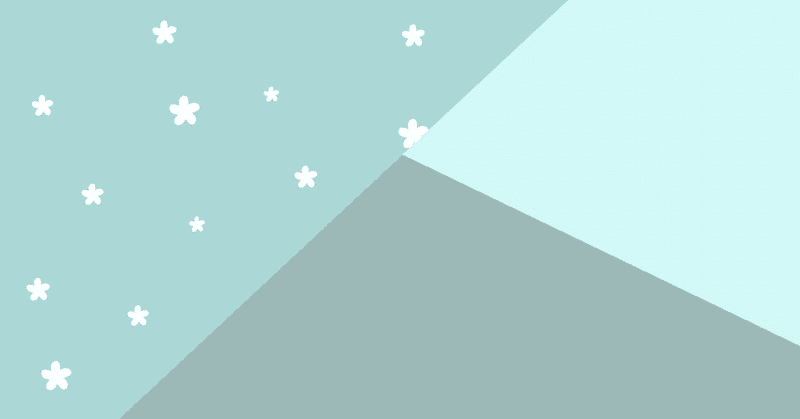
【短編小説】お姫様の鏡
ガラスの器に移したヨーグルトに、砂糖をスプーン山盛り二杯分も加えてしまってから手を止めた。
「ヨーグルトにこのくらいたっぷり砂糖を加えるだろ」
「で、溶けるまでひたすら混ぜる」
久しく聞いていない声が蘇る。
目の前にマーマレードの瓶を置いたにも関わらず、あたしが器に入れたのは大量の砂糖である。
いつも、晴人のヨーグルトを作ってから自分の方にマーマレードを加えていた。
だからだ。もう一人分しか必要ないのに。
朝から甘ったるいヨーグルトを何とか食べ切ったところで、やっとカーテンを開けた。眩しさに一歩下がったところで、ジャリ、と嫌な音がした。
昨夜割れた鏡の破片がまだ残っている。
「痛っ……」
昨日も今日も散々だ。
あたしにとっては、あれは間違いなくお姫様の鏡だった。
現実はそんな夢見心地なものじゃない。
あの鏡にはちゃんと商品名があり値段があり、大抵の店舗に置いてあったはずだ。
ジルスチュアートのハンドミラー、お値段三千三百円。
先月別れた晴人からのプレゼントだった。その鏡の絶妙な大きさが、そのキラキラが、並ぶカラフルな化粧品の可愛さにも圧倒されずに、妙に目立ってなんだか無性に特別な物に見えた。これはきっとお姫様の鏡なんだと、あたしは本当に信じきっていた。
晴人はお姫様でもないただのあたしに、その鏡を買ってくれたのだった。
忘れないと思う。迷わず店員さんに「贈り物です」と言った彼の横顔を。
だけど実際お姫様になってみると、あたしには片手が塞がる鏡を使う場面がよく分からなかった。メイクはドレッサーで済ませてしまうし、持ち運ぶには小ぶりなコンパクトミラーが向いている。勿論晴人にそんなことは言えなくて、せめてもの気持ちでベッドサイドに置いて大切にしていた。別れてからも、そのまま。
「君は僕のことをちゃんと見られていないと思うんだ」
彼の最後の言葉。あたしにはあまり理解ができなかった。
だって晴人のことを、あたしはほんとうに好きだったから。
鏡が壊れるのは一瞬だった。
ハンドクリームを塗り過ぎてしまった手で、鏡を手に取ったのが悪かったのだ。
鏡があたしの元に来たあの日を思い返す。あんなにキラキラとした可愛らしい物を、晴人があたしに似合うと思って買ってくれたという気持ちが一番嬉しかった。しかし今となってはただのガラスの欠片でしかない。無残な破片の一つ一つを手に取っていく。その度にあたしは少しずつ晴人にとっての特別じゃなくなっていくみたいだった。愛の終わりって目に見えたりするんだなあ、なんてどこか他人事のように思った。
あの鏡、別れという現実を映すためにあたしの手元に来ていたのだろうか。甘酸っぱい匂いを放つガラスの器に目をやる。
あたしは、本当に晴人のことをちゃんと見ていなかったのだろうか。多分、そんなことはないと思うのだ。思うのだけれど、今更納得のいく理由を聞き出すのはなんだか気が引けた。
ごめんね、と声が出た。
自分の声を聞くと涙が出た。謝ると泣いてしまうのは、自分が可哀想だからだと聞いたことがある。だとしたら結局あたしは、今も自分が一番かわいいのだろう。そういうところかな。
さっきのごめんねも、晴人に対してか鏡に対してか、自分でもよく分からないのだ。ただどちらに対しても自分に非があって壊してしまったことだけは解る。
晴人の目に映っていたのが我儘なお姫様だったとしたら。鏡を与えるのは結構な皮肉だ、なんて思った。
自分と向き合って自分を知った先に、きっと忘却が待っている。あたしが晴人に投げてきた3年分の言葉達。晴人をどう傷つけたのか、あたしは納得して初めて、別れの現実を受け止められるのだろう。
「ごめんなさい」
今度は何処にもいない晴人に向かって言った。
涙は、やっぱり出てくるのだった。
サポートいただけると励みになります。よろしくお願いいたします。
