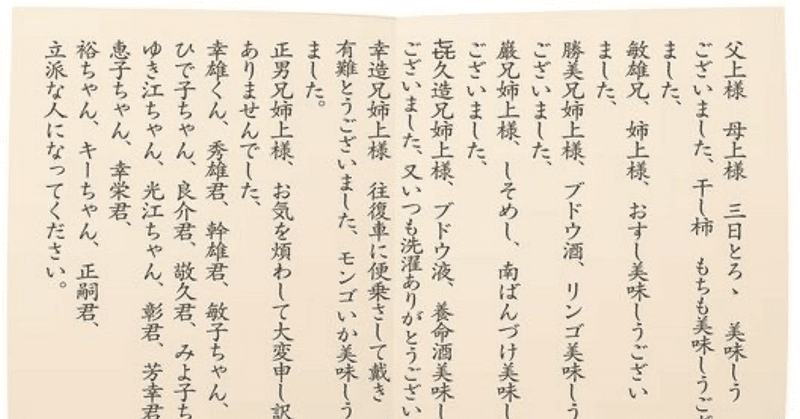
反復と比喩─詩とリテラシー・スタディーズ(1)(2009)
反復と比喩
─詩とリテラシー・スタディーズ
Saven Satow
Apr. 22, 2009
「あらゆる花が、花飾りに入っているわけではない」。
トマス・フラー
1 世間もあんがいぬるいの~
同じテーマを取り扱ったとしても、それぞれに固有のリテラシーがあるため、詩と小説では創作が異なる。ある詩を読んで感動したとき、それは主題や作者の思い、言い回しに起因しているわけではない。暗黙のうちに、詩特有の規範を理解し、その作品の持つ意味や効果に心動かされている。
詩は、原則的には、小説のような具体的・固有的な描写を使わない。それは、主題に基づき、比喩や反復を通じて、抽象性・普遍性をとり扱う文学形式である。詩を読解する際に、その種類を把握する必要がある。詩は用語上の文語詩=口語詩、形式面の定型詩=自由詩、内容による叙事詩=劇詩=抒情詩=叙景詩=象徴詩などに分類できる。しかし、いずれの種類であっても、比喩と反復という基本的方法は備わっており、その意味と効果を認識するのは詩特有の読解である。
近代以降の詩と散文の区別は、比較的、容易である。近代に入って以降、詩は、事実上、抒情詩に収束、叙事詩は散文に吸収される。抒情詩は世界の内部に視点がある。その声は主観的で、ミクロ的である。他方、叙事詩は世界の外部ないし境界に視点を置く。その声は、主観的なものを内包しつつ、客観的あるいは鳥瞰的で、マクロ的である。ただ、近代以前も考慮すると、詩と散文の区別を抒情詩と叙事詩の特徴だけで論じられるものではない。
映像が映し出す光景は単独的である。何の変哲もない机の写真だとして、それは机一般ではない。他方、「机」と書き記した場合、映像と違って、そこに具体性や固有性はない。それはあくまで机一般である。描写を通じて一般的なものを単独的なものにするのが小説であり、比喩や反復を用いて物自体を把握しようとするのが詩であろう。
議論の際に、一般論に終始する作家や詩人もいるが、2009年2月17日の村上春樹のエルサレム賞受賞スピーチがその典型であるけれども、彼らには文学者の資格はない。
“I have only one thing I hope to convey to you today. We are all human beings, individuals transcending nationality and race and religion, and we are all fragile eggs faced with a solid wall called The System. To all appearances, we have no hope of winning. The wall is too high, too strong—and too cold. If we have any hope of victory at all, it will have to come from our believing in the utter uniqueness and irreplaceability of our own and others’ souls and from our believing in the warmth we gain by joining souls together”.
(村上春樹『エルサレム賞受賞スピーチ』)
一般論は、いつでも、反転する。「テロとの戦い」を標榜する勢力も同様の論理を自らに見出している。それにしても、このスピーチが2009年1月29日の夜のダボス会議の出来事の後になされていることは信じがたい。トルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン首相は、ガザでのことを正当化するイスラエルのシモン・ペレス大統領に、トルコ語でこう糾弾している。
“You killed people. I remember the children who died on the beaches, and I remember two former prime ministers in your country who said they felt very happy when they were able to enter Palestinian territories in tanks, and they felt very satisfied with themselves. I find it very sad to see that people applaud what you have said, because there have been so many people who have been killed, and I think that it is very wrong, and it’s not humanitarian to applaud any actions that have had that kind of result”.
詩は、概して、散文よりも短いため、全体像を把握しつつ、一語一語に注意しながら、精読しなければならない。日本語の詩であっても、倒置や省略、連用中止法、体言止め、文字や句読点といった表記、季語や枕詞等の独特の用語など注意点は多い。しかし、これらはあくまでも詩読解の拡張であって、やはり基本は比喩と反復である。
反復にはリフレインや対句、押韻、音数律、内在律などリズムやテンポ、アクセント、ハーモニーを生み出す方法が含まれる。定型詩は言うまでもなく、自由詩にもこの技法がよく見られる。繰り返しを見出すとき、それを詩だと判断することも少なくない。詩における反復は形式だけでなく、しばしばその当該言語の特徴とも結びついている。
国破山河在
城春草木深
感時花潅涙
恨別鳥驚心
烽火連三月
家書抵萬金
白頭掻更短
渾欲不勝簪
(杜甫『春望』)
夏草や兵どもが夢の跡.
(松尾芭蕉『奥の細道』)
孤立語である中国語に基づく漢詩では、一行あたりの文字数が綺麗に揃えられている。漢字の音は、伝統的には、「声母」と「韻母」によって構成されている。「馬」は「ma」だが、「m」が声母、「a」が韻母に当たる。この韻母をそろえることが押韻である。漢詩では、原則的に偶数句の終わりの字に押韻する。さらに、「平仄」の規則を守らなければならない。平らな音を「平声」、上がったり下がったり、またつまったりする音を「仄声」と呼ぶ。この二種類の音の配置に関して細かな規則があり、それに従って漢字を選び、配置しなくてはならない。漢詩は字句として見るだけでなく、声に出して読むことを前提としている。
なお、中国語の音節構造は、現代的には、IMVE/Tで表わす。I(Initial)は頭子音、M(Medial)は母音の一種である介音、V(Principal Vowel)は主母音、E(Ending)は韻尾、T(Tone)は音節における高低アクセントの声調として把握する。Iが声母、MVE/Tが韻母に当たる。
一方、日本語は膠着語であるため、文章を語で区切るのが難しい。伝統的な詩歌では、音数に規則を設け、句切れや切れ字が作品構成の重要な要素となっている。日本語の語彙は三拍と四拍単語が多く、五と七を詩歌の音数律の基本となるのも、不思議ではない。字余りが認められていたり、押韻への関心が乏しかったりするなど漢詩ほど定型の厳密さは要求されない。
詩の表現は、散文のような進行が持続ではなく、継起や連想であるため、原則的に、「明示的(Explicate)」ではなく、「暗示的(Implicate)」である。詩で用いられる比喩は、時として、何を指し示すのかはっきりせず、解釈がわかれる。そうした暗示を明示化していく作業は詩読解の幅を広げてきたことは確かである。比喩は個人的志向・背景のみならず、通時的・共時的な蓄積・共有されている知識を踏まえている。たんなる思い込みや思いつきで記された比喩を見かけるが、それは共通理解を無視した自惚れの強い独善性と衝動性にすぎない。
次の谷川俊太郎の『かなしみ』は彼の名を最初に詩壇に知らしめた作品であるが、リテラシーを考慮するならば、詩と認めることは困難である。
あの青い空の波の音が聞えるあたりに
何かとんでもないおとし物を
僕はしてきてしまったらしい
透明な過去の駅で
遺失物係の前に立ったら
僕は余計に悲しくなってしまった
これは反復が抑えられた連想に基づく抒情詩である。しかし、『かなしみ』というタイトルのわずか6行の短い詩であるにもかかわらず、「僕は余計に悲しくなってしまった」と書いている。短編の抒情詩であるならば、「かなしみ」を暗示させるべきであろう。これでは「頭痛が痛い」と言っているようなものだ。この作品を「詩」と呼ぶことはできないし、そもそも評価している人たちは詩のリテラシーを理解していないと言わざるをえない。
作者と読者は「かなしみ」を共有する。しかし、この感情は両者においてその内部にあるものだから、一致しているとは限らない。そこで作者はその外部にあるものを自分の「かなしみ」を喚起するとして語る。読者はそれをたどりつつ、共感し、自らも「かなしみ」を覚える。ところが、谷川俊太郎は「かなしくなった」と書き、自分の内部に舞い戻ってしまう。読者は彼に「かなしみ」を押しつけられる。
リテラシーから読み解くとき、評判のいい作品がなっていないことが明らかとなる場合も少なくない。それは暗黙知を明示化する際に、他者の観点を十分に考慮しないまま、思い込みの説明が蔓延してしまったときに生じる。他者のいない世界はリテラシーを意識しない傾向がある。暗黙知を明示知とする必要を感じないからである。他者の質問は暗黙知を明示化して欲しいという要求だ。
いわゆる「こそあど」の使い分けを日本語のネイティヴ・スピーカーは苦もなくできるが、それを説明するとなると、たいてい間違う。「これ」は近いもの、「あれ」は遠いもの、「それ」はその中間と思いこんでいる人が多い。しかし、「これ」は自分のテリトリー、「それ」は相手のテリトリーにおのおの属するもの、「あれ」はいずれにもないものに使われる。人生の先輩のご夫婦が「あれ」だけで会話することも、車内の噂話で「彼女は社長の『これ』だよ」と情報通が小指を立てることも、内定を取り消された大学生が「それはねえだろう!」と怒りを爆発させることも納得できる。
こうした事態は詩に限らない。芸術を含め、あらゆるコミュニケーション活動に見られる。村上春樹の小説の世界的評価はその典型である。リテラシーが理解されていないまま、読まれている。この現状を見たおじゃる丸なら、第11シリーズ第78話の「すてきなほんやさん」の時と同様、こう言うことだろう。
「世間もあんがいぬるいの~」。
2008年11月20日にNHKデジタル教育で放映されたこの番組は、文学に携わるなら、絶対に見ておくべきである。内容をここに記すのは、その趣旨に反してしまうので、ご自分の目で確認することをお勧めする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
