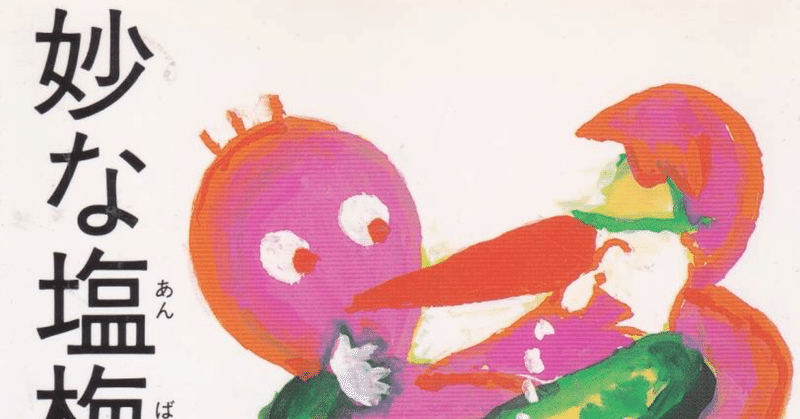
えのきどいちろう、あるいはStand By Me(1)(2004)
えのきどいちろう、あるいはStand By Me
Saven Satow
Nov. 30, 2004
「『あの、それじゃ、カッコよすぎませんか。もっとこう、おちゃらけたっていうか、スキのあるタイトルがいいんですけど』
『というと、例えば』
私は少し考えてから、一つ案を出した。
『アナ尻娘。とか』」
水谷加奈『ON AIR─女子アナ恋モード、仕事モード』
1 コラムの歴史
こうしたコラムの歴史は18世紀に遡る。コラムは、1751年3月11日、イギリスの『ロンドン・アドバイザリー・リテラリー・ガゼット(London Advisory Literal Gazette)』紙が連載を開始したのが最初とされている。3月11日は、それにより、「コラムの日」と一部で、祝われているかどうかは別にして、認められている。新聞紙面上に縦の欄を利用して掲載されていたので、ラテン語の「柱」を意味する「コラム(Column)」と呼ばれたのがその由来である。
コラムは、エッセイ同様、物語性の弱い告白である。告白は知的で、主観性、すなわち「私」に基づき、倫理を扱う。医学や法学の領域では、専門的な読者を説得するために、アカデミックな手続きの順守が不可欠である。けれども、倫理に関しては、大学や研究機関、三権の専門家のみならず、政教分離に伴い価値観の選択が個人に委ねられた以上、一般の誰にも語る資格がある。決して論理的ではないが、その隙間を読者が補わなければならない。
15世紀半ばのヨハネス・グーテンベルクの印刷術により出版産業が誕生し、エッセイは文学ジャンルとして確立されていく。印刷という書籍の記号化は「私」も同様に記号的にする。
16世紀の半ばから終わりにかけて、王侯貴族・政府や銀行・商人のネットワークに印刷業者が結びつき、近代的新聞の原型が生まれる。書籍が個人としての読者に向けられていたが、新聞は党派性・階級性が強く、また、商業主義的傾向がある。
エッセイが出版によって派生したジャンルであるとすれば、コラムは大量生産の新聞が生み出している。エッセイの「私」は印刷技術=ルネサンス的であるのに対し、コラムでは、産業革命的な大量生産される「私」である。新聞はたんに記号的ではなく、ネットワーク的であり、それがコラムの「私」にほかならない。
Three wise men of Gotham,
They went to sea in a bowl,
And if the bowl had been stronger
My song had been longer.
(“Mother Goose”)
コラムの歴史は新聞の三面記事を物語化した近代小説の発展とパラレルである。どちらもお堅い記事と違い、読者は気楽に読むことができる。ニュースでもなく、社説でもないコラムは、その親しみやすい文体によって、安定した人気を得ていく。
コラムと密接な関係があるアメリカのユーモア文学は庶民的と都会的の二つに分類されるが、どちらにしても、話し言葉をとりいれている。これは今日まで続くその文学的傾向の一つである。
2 コラムニストたち
19世紀の半ばから後半にかけて、庶民の言葉遣いが講演や新聞のコラムに登場している。当時のコラムニストの中に、『ニューズレター(Newsletter)』紙のアンブローズ・G・ビアス(Ambrose Gwinnett Bierce)がいる。彼は『悪魔の辞典(Devil’s Dictionary)』(1911)によりその辛辣さが現在に至るまで広く知られている。1902年から12年にかけて自ら全集を編纂し、13年にメキシコに渡って以降、消息不明となり、伝統的なコラムニストの偏屈さといかがわしさを具現化する。
1920年代になると、アメリカではもはやコラムは新聞に欠かせない記事の一つになっている。タブロイド紙においては、ハリウッドの内幕のゴシップなどを書いたコラムがシンジケートを通じて各紙に配給・転載され、著名コラムニストを生み出している。その後、三〇年代からは政治論評を展開するコラムニストが人気を得ている。
そういったコラムニストとしてリング・ラードナー(Ring Lardner)やウォルター・リップマン(Walter Lippmann)があげられる。
ラードナーはシカゴやミューヨークの新聞コラムニストやスポーツ記者から出発し、若い野球選手を主人公にしたペーソスな物語を雑誌に連載して注目を集めている。これは『オルよ、おれを知ってるな(You Know Me, Al: A Busher's Letters)』(1916)として出版される。『奴らを乱暴に扱え(Treat 'Em Rough)』(1918)と『ビッグ・タウン(The Big Town)』(1921)では、一般的なアメリカ人の生活を諷刺的に描いたが、後年の作品では、そのユーモアが辛辣になっていく。
ボクサーやセールスマン、演劇人、作詞家を扱った物語においては、登場人物に関する情報と普通のアメリカ人の言葉遣いやアクセントをめぐる記述に溢れている。『短編作法(How to Write Short Stories)』(1924)や『それがどうしたというのだ(What of It?)』(1925)、『愛の巣(The Love Nest and Other Stories)』(1926)、『ラウンド・アップ(Round Up)』(1929)などの短編集はシニシズムとリアリズムが混在し、今日の『サタデー・ナイト・ライブ(Saturday Night Live)』のようなきついジョークのテレビ番組のプロトタイプと言ってよいだろう。
A good many young writers make the mistake of enclosing a stamped, self-addressed envelope, big enough for the manuscript to come back in. This is too much of a temptation to the editor.
("How to Write Short Stories”)
一方、リップマンは政財界の不正を暴くマックレーカーズの取材の助手から頭角を現わしている。1914年にはリベラルな週刊誌『ニュー・リパブリック(The New Republic)』の創刊に参加している。1919年、世界情勢を鋭く指摘する彼の能力に注目したウッドロー・ウィルソン大統領の要請により、第一次世界大戦のパリ講和会議に随員として出席している。
学者あがりの大統領は彼の主張にかなり影響を受けて、政策を実施したと見られている。「最も古い、最も強力であった民主政治を見るならば、世論というものを神秘的な存在にしてしまったのはその民主政治であったことがわかる。世論の組織化にすぐれていた者たちはこの神秘的な存在を十分に理解して投票日に過半数を獲得してきた。ところが、このような世論の組織者たちは、政治学においては低級な連中とか『問題人物』と見なされ、いかに世論を生んでこれを操作するかについて、当時、最も有効な知識を持っている人たちとして考えられることはなかった」(ウォルター・リップマン『世論』)。
1929年から、『ニューヨーク・ワールド(New York World)』紙の主筆を務めたものの、2年後に廃刊となってしまい、『ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン(New York Herald Tribune)』紙に移っている。「報道界の問題が混乱しているのは、その批判者も擁護者も共に、新聞がこうしたフィクションを実現し、民主主義理論の中で予見されなかったものすべての埋め合わせをすることを期待しているからだ。そして読者も、自身は費用も面倒も負担しないでこの奇跡がなしとげられることを期待している。民主主義者たちは、新聞こそ自分たちの傷を治療する万能薬だと考えている」(同)。
そこで始めたコラム「今日と明日(Today and Tomorrow)」は、同時掲載の契約を結んだ多数の新聞にも配信され、全米のみならず、国際的にも注目され、六七年まで続いている。「新聞は世論を組織する手段としては不完全だということを否応なくさらけ出し、多かれ少なかれその事実を強調すらしていることがわかるように思われる。私は、もし世論が健全に機能すべきだとするなら、世論によって新聞は作られねばならない、と結論する。今日のように新聞によって組織されるべきではない」(同)。
リップマンの活動は広範囲に及び、政治学のみならず、社会学や心理学、哲学にも示唆に富む著作を発表している。『政治学序論(A Preface to Politics)』(1913)、『推進力と熟練(Drift and Mastery)』(1914)、『世論(Public Opinion)』(1922)、『モラルの序文(A Preface to Morals)』(1929)、『良い社会(The Good Society)』(1937)、『戦争の目的(War Aims)』(1944)、『冷戦(The Cold War)』(1947)、『公共の哲学(Essays in the Public Philosophy)』(1955)などがよく知られている。
ラードナーとリップマンはアメリカにおけるコラムニストの二つの系譜の確立者である。ピート・ハミル(Pete Hamill)は前者の代表的な後継者であろう。在野の立場から、スポーツや文学、音楽、アート、政治、時事問題など多岐に及ぶ領域をユーモアを交えて、書いている。他方、政治的コラムの執筆者には、権力中枢に近い者も少なくない。
日曜日の『ニューヨーク・タイムズ・マガジン(New York Times Magazine)』に20年以上に亘り連載されている「言葉について(On Language)」のコラムで知られるウィリアム・サファイア(William Safire)はリチャード・ニクソン大統領のスピーチ・ライターを務めている。彼は2004年11月24日を最後に31年間続けた『ニューヨーク・タイムズ(New York Times)』紙のコラムニストを引退したが、「言葉について」の連載は継続している。この二つの流れは続き、コラムニストはアメリカ社会に影響を及ぼしている。
一般的にはコラムニストと見なされていないけれども、コラムを手がけている作家も少なくない。カール・マルクスが『ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン』の前身『ヘラルド・トリビューン(Herald Tribune)』紙の特派員兼コラムニストだったことは、その愛読者の多くはともかく、有名である。
他にも、ホセ・オルテガ・イ・ガゼットやエルンスト・ブロッホ、スーザン・ソンタグ、ラングストン・ヒューズ、エレノア・E・ルーズヴェルト、ポール・アンソニー・サミュエルソン、Y・B・マングンウィジャヤ、ステファン・J・グールドなども新聞や雑誌のコラムで優れた能力を発揮している。さらに、アレン・スチュアート・コーニンバーグも「ウッディ・アレン」のペンエームで新聞のコラムを執筆し、後に彼はその名前で知られることになる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
