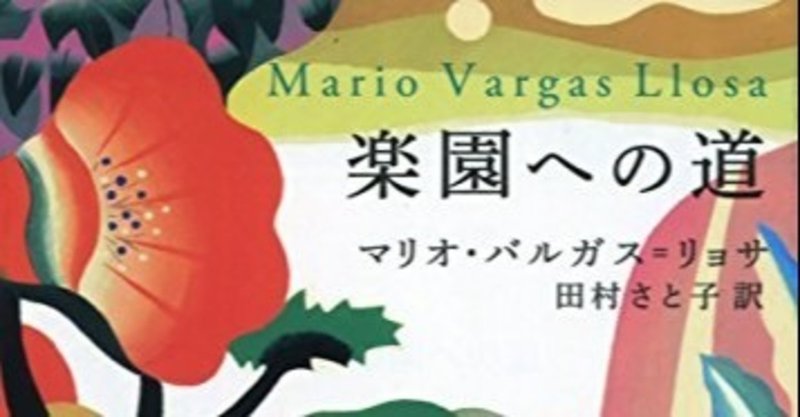
【考察】バルガス=リョサ「楽園への道」で苦難な選択を考える
・周りから反対されているのに、どうしてもやりたい事が出来てしまった。
・家庭や世の中のイメージを捨ててまで成し遂げたい事が出来てしまった。
・絶対に苦しい選択なのに、なんでこの職についちゃったんだろう。
こんな事を考えたことがある人は、「楽園への道」を読んでみると、人生が変わるかもしれないです。
何故ならこの小説は、世の中の敵になり、苦難な選択だとわかりつつも、それでもその選択を選ばずにはいられない、不器用に自分の意思を貫いた人のための小説。
人間誰もが、自分がやりたいこと、世の中に対して理不尽だと思うことがある。問題はその理不尽を受け入れるのか、それとも断固反対して戦うのか。
今回の小説は、どんなに苦しい状況でも反逆者として戦った二人が主人公の作品を取り上げました。
池澤夏樹はこの小説を紹介する時に、こう書評しております。「小説は常に反逆者の味方」だと。
少々とっつきにくいラテンアメリカ文学。その中でも巨匠に位置づけられるバルカス-リョサの傑作、「楽園への道」をご紹介していきます。
1.ラテンアメリカ文学という謎ジャンル
●そもそもラテンアメリカ文学って何?
まず、「楽園への道」を解説する前に、ラテンアメリカ文学について解説していきましょう。文学には色々なジャンルがありますが、今回ご紹介する「楽園への道」はラテンアメリカ文学に位置付けられます。スタンダール・バルザック・プルーストなどのフランス文学、ゲーテやトーマス・マンが代表的なドイツ文学など、国別ならわかりますが、ラテンアメリカってなんだよ!って思いません?大学生の頃の僕は思っておりましたよ。笑
それではラテンアメリカ文学とは何か。まずはWikipedia先生に聞いてみましょう。
ラテンアメリカ文学(ラテンアメリカぶんがく)とは、ラテンアメリカ圏(メキシコ、西インド諸島以南のアメリカ大陸)で書かれた、および出身者の文学。おもにスペイン語またはポルトガル語で書かれている。おもに20世紀後半、ラテンアメリカ文学の特徴とされるマジックリアリズムの傾向によって世界的に注目され、最も高い境地に達したと評されている。
場所に関してはWikipedia先生が丁寧に教えてくれていますが、気になるのが「マジックリアリズム」と「最も高い境地に達した」の2つの言葉だと思います。ラテンアメリカ文学に関しては、ある程度の場所と、この2点を抑えておけば、多少は読みやすくなるでしょう。
ラテンアメリカ文学が生まれた背景など細かい解説は、Wikipedia先生が細かく解説してくれています。ぜひ気になる方は覗いてみてください。
●マジックリアリズムとは
では謎フレーズである「マジックリアリズム」に関して。「マジックリアリズム」とは日常にあるものが日常にないものと融合した作品に対して使われる芸術表現技法のことです。このタイプの小説で一番有名な作品はガルシア=マルケスの『百年の孤独」でしょう。こちらに関しては私も読んだことがないのでまた別の機会で。。
日本人では村上春樹の「1Q84」や「海辺のカフカ」や、大江健三郎の「同時代ゲーム」などが近いと思われます。
今回紹介する「楽園への道」は、残念ながらマジックリアリズムの手法は出て来ないですが、ラテンアメリカ文学を読んでいくのであれば知っておいて損はないでしょう。
●「最も高い境地に達した」と言われる所以とは
こちらも文学者が本気で語ろうと思えば、ずっと語れる内容かと思いますが、あえて点でまとめるとこんな感じかと。
・反逆的で前衛的。
・政治的混乱、または軍事または独裁政権下にいた作家が多い。
・非常で実験的で伝統的な境界を超越し、従来の規則を無視するような作品も多め。
・アメリカやヨーロッパの作家たちの影響を巧みに受ける。
・混血文化を背景にしたアイデンティティへの強烈な追求力。
私なりに一言でまとめるのであれば、「様々な文化・政治背景が混在するカオスな状況によって、名作が生まれやすい環境になっちゃった文学」って感じですかね。笑
日本文学も「戦後」というカオスな状況によって、一気にノーベル賞受賞レベルの人気作家が生まれたように、カオスな状況は文学を発展させる能力があるみたいです。
2,概要:ノーベル文学賞受賞作家:バルガス=リョサ
それでは作者紹介。今回ご紹介するバルガス=リョサは84歳のペルー国籍の方です。ラテンアメリカ文学の代表的な作家でありジャーナリスト、エッセイストでもあります。また受賞歴も凄まじく、プラネータ賞(1993)セルバンテス賞(1994)エルサレム賞(1995)ドイツ出版協会平和賞(1996)ノーベル文学賞(2010)など国際的に有名な、THE巨匠of巨匠でございます。

そしてこの巨匠が後期に手掛けた作品が「楽園への道」です。後にじっくり紹介しますが、主人公の2人もペルーに関連します。まさにカオスが入り混じるラテンアメリカ文学だからこそ生まれた作品だと思います。
3,世間の反弱者となった2人の主人公
●めちゃくちゃ正義感の強い不器用な人
いきなり解説に入る前に、ちょっとクエスチョン。
「あなたの人生でめちゃくちゃ正義感の強い不器用な人っていませんでした?」
例えば、いじめられっ子を守る正義感の強い子ども。もちろん、いじめは良くないですし、いじめられっ子を守るような正義感を持つことは非常に素晴らしいことです。
しかし、いじめは数の暴力や権力構造で成立するもの。いくらその正義が正しくても、正義を振りかざす子どもが弱ければ解決しませんよね。正義がいくら正しくても、強くなければ、悪とは戦えないのです。
ただですよ。自分が弱い、世間が認めてくれないとしても戦わずにはいられない人は世の中にいるのです。今回の主人公の2人はまさにそのタイプ。周りにいくら反対されようとも自分の意思を貫き社会と戦います。
そして面白いことに、そのような「反逆者」と呼ばれる人達が世界を変えたりするのです。
前述したように、「楽園への道」では、主人公は2人います。そして2人の主人公の物語が交互に展開される形態をとっております。それぞれが非常に面白いですし、交互に読むことで相互の物語がさらに楽しめます。
3.スカートを履いた反逆者フローラ・トリスタン
まずはフローラ・トリスタン。別名「スカートをはいた扇動者」。こんな人です。

舞台は19世紀半ばのフランス。
当時のフランスはフランス革命が終わり、王と貴族からは解放されましたが、男性と資本家と教会の支配が続いていた時代です。
現在では考えられないですが、もし結婚した女性が離婚したら、どんな男性に酷いことをされたとしても、社会的地位が急激に下がり、世間から罵られます。
フローラはその典型例。旦那のアンドレ・シャザルに暴虐され、酷い仕打ちにあっても、フローラの親は離婚に反対します。またどんなに裁判で訴えても男性側の有利で終わるのです。
またフローラは労働者としても劣悪な環境でした。そして、労働者の過酷な状況を利用する教会の存在。「苦労すれば来世で報われる」と伝え、労働者が劣悪な環境で働かせるように仕向けます。
本当に酷い時代ですよね。。
しかしこの時代ではこの状況が「当たり前」だったのです。そして皆がこの「当たり前」を「当たり前」だと自覚し、目の前の幸福に縋り暮らしていました。
この考え方が怖いのです。客観的に見ると明らかに劣悪なのに、人間はその場の環境に幸せを求めようとする。それが権力を持った人達の狙いであり策略なのです。
この状況下で、あなたは社会を変えようと戦えますでしょうか。フローラもフランスだけで暮らしていれば、その場の幸せを頑張って探すような生き方を考えたでしょう。
しかし彼女を変えたのはペルーでの経験でした。ペルーはフランス以上に酷い環境だったのです。奴隷制度が当たり前のように存在し、お金持ちは権力を見せびらかせることに必死。
海を渡ると人が変わると言いますが、彼女は社会改革運動を始めます。教会権力、社会を相手に。そして「家庭を捨てる女は売春婦にも劣るんだよ」と非難する母親を相手に。
社会主義という「楽園への道」を具現化するために戦います。
4.芸術のために家庭を捨てたポール・ゴーギャン
次は彼女の孫にあたるポール・ゴーギャン。そうです。この主人公達は血縁なんですよ。またポール・ゴーギャンの名前は聞いたことある方は多いのではないでしょうか。
またこのような絵をみたことありません?フランスを代表する芸術家です。


彼の場合は19世紀後半のフランス・タヒチが舞台。
プリミティヴィスムの発祥者として数々の作品を残した画家ですが、彼もまた社会に反抗します。
ゴーギャンはまず、パリ証券取引所での職を得て、株式仲買人として働きます。その後11年間にわたり実業家として成功までします。ゴーギャンの場合、特に虐待や金銭面で困っていたわけではないのです。そして株式仲買人としての仕事を始めた1873年頃から、ゴーギャンは、余暇に絵を描くようになります。
転機となるのが、1882年、パリの株式市場の大暴落。ゴーギャンの収入は急減し、彼は、その後の2年間、徐々に絵画を本業とすることを考えるようになります。
ここからが怖いポイント。ゴーギャンは絵画としての生活を諦めないのです。そして、自由になるべく、家族を捨て、ポリネシアの小島、タヒチへ移住します。そこで彼は、様々な絵を描き、自由に暮らし、タヒチの娘達とセックスを愉しんでいます。
「ゴーギャンやばいやつだな。。」と思ったそこのあなた。なんでゴーギャンはそこまでして自由を手に入れたかったのでしょう。
池澤夏樹は書評でこのように言及しています。
ポールという男を動かした多くの衝動や欲望を無視しない。むしろその役割を強調するのがバルカス=リョサの姿勢だ。それもまた19世紀末のフランス社会の偽善に対する個人の生を賭しての反逆であり、西欧的なるものの全部に対する反逆である。官能はポールにとって最も大事な生の原理だった。
少しセンセーショナルなことですが、そもそもゴーギャンには「自由を求めて家庭を捨てる自由」があるはずです。(僕がそう思っているわけではないですよ。笑)そしてなぜ人間は欲望に素直に成れなくなってしまったのでしょう。官能や欲望が悪いことだと決めつけるような西欧的な考え全てにゴーギャンは反逆します。
おわりに:「楽園の道」だからこそ効く二人称での語り
ちょっと物語を整理しましょう。主人公の二人はこんな感じで世間に反逆します。
●フローラの場合は、「虐待や不遇な環境に生きる人たちのために先頭を戦って」反逆する。
●ゴーギャンの場合は、「好きなことや自由にやりたいこと、官能的なことを咎められる西欧的な社会に対して」反逆する。
そしてこの反逆により、フローラは社会主義をマルクスが提唱する前から提唱し、ゴーギャンは100年後も見られるような作品を世に出しました。
まさに「反逆によって世界を変わる」が体現された瞬間。しかし、彼らは2人とも世間から罰を受け、惨めな死に方で人生の幕を閉じます。
おわりにお伝えしたいのが、この物語で登場する二人称での語り。この作品では頻繁にこのような語りが登場します。
笑顔だよ、フロリータ。すごくうまくは行かなかったけど、それほど悪くはなかったじゃないか。人間に奉仕することは辛い仕事だよ。アンダルシア女。
これはナレーションでもなく、フローラやゴーギャンでもない、別の誰かです。いわば、反逆者である2人を空から見守ってくれる神様的な視点での会話が文中で登場します。世間はこの2人を見捨てましたが、この語り部は絶対に2人を見捨てません。
「小説は常に反逆者の味方」だと、この小説から学びました。そして、私はフローラやゴーギャンのように戦えるのか。
将来がどうであろうとしても、他者に寛容である気持ちは忘れないようにしたいと思っています。
小説の価値を感じてくれる人が、一人でも増えてくれたら幸いです。
よろしければサポートよろしくお願いします!書籍代などクリエイターとしての活動費に充てさせていただきます。
