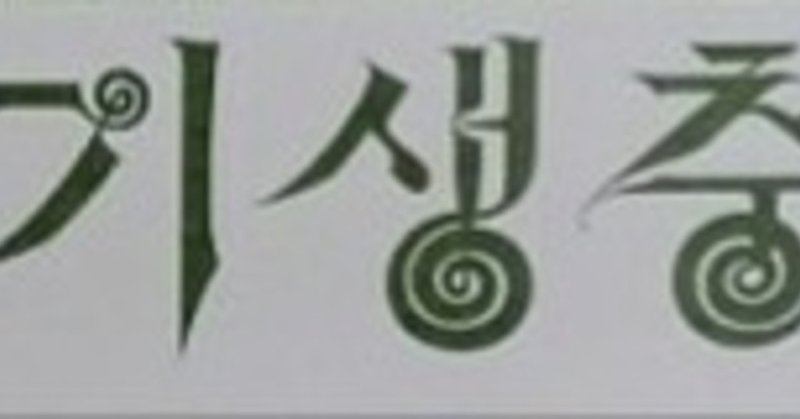
【徒然なる雑感】3.映画と研究と教育とー2月10日の気付きー
ポン・ジュノ監督の「パラサイト 半地下の家族」がアカデミー賞を受賞したニュースが話題ですね。映画はほんとに面白かったです。たぶん、今年はこれ以上の作品は見られないのではないかと思うくらい、最高のエンターテインメントにして様々な現代の問題を提起する社会的作品でもあります。それにしても、外国語映画でありながら、というか、アメリカ資本が入っていない作品がアカデミー賞を、しかも作品賞、監督賞を受賞するということは、今の日本で女性が総理大臣になるというくらい稀有なことだと思います。それだけ、ポン・ジュノ監督の才能が素晴らしいということなのですが、受賞のスピーチでマーティン・スコセッシ監督のことばを紹介されたのが印象的でした。
『最も個人的なことが、最もクリエイティブなことだ』
その場にともにノミネートされていたマーティン・スコセッシ監督もおり、マーティン・スコセッシ監督にも花をもたせるということまでスマートにできちゃうポン・ジュノ監督の姿勢にまたまた脱帽です。
ところで、話はちょっと、いや、だいぶ変わりますが、現在、卒論を査読中です。卒論を読んでいて思うのは、研究も『最も個人的なことが、最もクリエイティブなことだ』なということです。私は卒論指導は自分の身近なことから問いを立てさせるようにしています。そういうわけで、お笑いやLINEで使うことばが研究対象となることは普通のことで、そこに言語の一般性や特性などが見いだせれば卒論として上出来です。ゼミ活動を始めて間もない3年生の頃は、「研究」の仕方や内実がわからないので、最初の頃はそれらしい論文を2、3本テキトーにまとめてきて発表することが続きます。でも、それは自分の「研究」ではなく、他人の「ケンキュウ」です。だから、全く創造的なものになりません。そこから、しつこく「個人的に気になることは何?」「自分がわからないことは何?」「あなたが不思議だなと思うことは何?」と問い続け、「自分自身」に向かわせる苦行が始まります(笑)。それがすんなりできる子もいれば、相変わらず他人のフンドシでゼミ発表をし続ける子もいます。他人のフンドシ、もとい、他人のケンキュウで卒論を書くことは実は簡単で、でもそこにはクリエイティブなこと、つまり「発見」はありません。けれど、「自分」と向き合って出した問いとそれを突き詰めていった先には、小さいかもしれないけれど、ほんの一部かもしれないけれど、「発見」があり、それはクリエイティブに他ならないのです。
さて、話はまたまた一転しまして。私は中高と文芸部に所属していたこともあり、「創作活動」はわりと身近なことだったのですが、物語や詩歌の「創作」は一般的なことではないようです。中高の国語の時間に物語や詩歌を「創作」したという経験を持つ学生は多くありません(忘れているだけかもしれないが)。しかし、これからの国語教育に必要なことは「創作活動」ではないかと思っています。教育の課題が挙げられるとき、「予測困難な時代に、一人一人が未来の創り手となる」必要性が説かれます。それに関わって「主体的で対話的な深い学び」ということがキーフレーズとしてよく言われます。「主体的で対話的な深い学び」の具体的な方策や教育内容は様々にあって、各教員が自分の考えや信念にしたがって実践すればよいのだと思います。そして、私自身はその方法として「創作活動」が重要で、それは「主体的」ということに大きく関わるものだと考えています。「主体的」とは個人的なことであると言えます。つまり、物語や詩歌を「創作」することは個人的な活動であり、『最も個人的なことが、最もクリエイティブなことだ』と言えます。「創造」こそ人間の人間たる所以であり、何かを生み出せる力を誰もが持っているということを子どもたちが確信できる教育ができれば素敵なことだと思うのです。
映画も研究も教育も、なんか繋がっているなぁと感じた1日です。それでは、おやすみなさい。いい夢を☆
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
