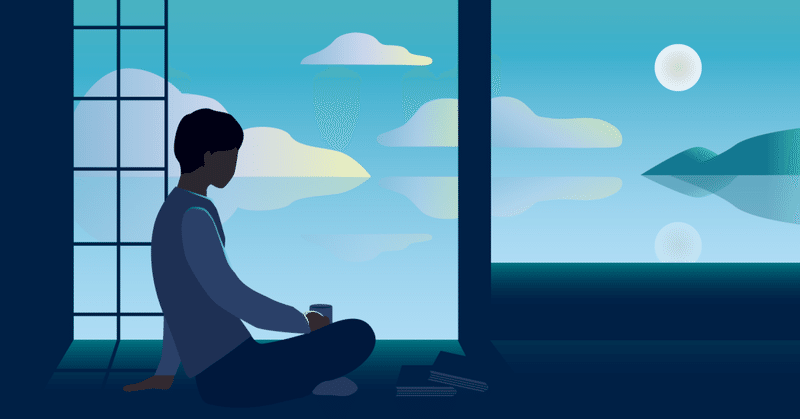
なぜ僕は証券会社を辞めて外に出たのか?
こんにちは。東京都練馬区で活動をしているファイナンシャルプランナー(FP)の佐藤彰です。
今まで証券会社の営業員がどんな仕事をしているかについて書いてきました。その証券会社には実は様々な課題があります。
もっといえば、証券会社だけでなく金融機関全般に今当てはまる課題なんですが、今回はその点について書いてみます。
証券会社の営業姿勢は昔から社会的に批判されている
証券会社は昭和の時代から営業姿勢について様々な課題を抱えています。
それは証券会社の営業員の資質よりも、ビジネスモデルそのものに問題があります。
その課題の本質は手数料中心のビジネスモデルです。
証券会社の主な収益源は手数料収入です。
投資信託であれば、お客様に新しく商品を買っていただく際に入ってくる販売手数料がその手数料になります。(投資信託であればたいてい3%程度)
販売後に新規の販売がなければ、ずっとそのお客さまからは手数料収入が入ってきません。
営業員からすると販売回数を増やせば増やすほど手数料が入ってくるので、販売回数を増やそうとします。
本来であれば、新規のお客さまと出会って新しく取引をしていただくことで販売回数を増やすのが本来の形です。
しかし、証券会社では新たにお客さまとなっていただく方を見つけ、実際に取引してもらうまでのハードルが非常に高いです。
ですので、すでに取引していただいているお客さまに何回も取引をしていただく形になります。
証券会社の営業員の営業方法
以上のような状況から何が発生するかといえば、一人一人のお客さまに頻繁に売買を促す、いわゆる回転売買です。
昭和の時代はこれが株式で行われ社会問題となりました。
それが平成の時代になると株式の手数料が自由化され、一気に手数料が引き下げられました。
そうなると、株式では収益を稼げないので、営業員による対面営業をメインとする伝統的な証券会社では、徐々にメイン商品を投資信託にシフトさせました。
この投資信託の回転売買が平成の時代では社会問題となり、令和の時代になった今も十分に是正されていないのが実情です。
僕が証券会社に勤務していたときも、お客さまが保有している投資信託をいかに売って新しい投資信託に乗り換えていただくか。その巧拙で営業成績が概ね決まるというのが現実でした。
僕自身が証券会社の所属しているときにやっていたこと
僕自身は、証券会社では珍しく営業よりも管理部門が長い人間です。
具体的には、こういう取引を繰り返したり、必要のない乗り換え取引をチェックするコンプライアンス推進の立場で働いていました。
最初は営業員自身の資質の問題だと思っていたのですが、営業員の活動をよく見てみると必ずしもそうではないことがわかりました。
このような方法を取らないと個々の営業員としては営業成績につながりにくく、会社としては収益につながらず継続的な活動ができなくなる、まさに、会社の仕組みに課題があることに気がついたわけです。
僕は、収益を稼ぐこととコンプライアンス推進の板挟みに状況でずっと悩みました。
証券会社の外で金融教育を実践するのが僕の道
以上にように証券会社(これはおそらく他の金融関連の会社もそうだと思いますが)は構造的な問題を抱えています。
「営業員はけしからん!」
「営業員の資質には問題がある」
とかそういう問題ではないということが、読んでいただいた方に少しでも伝われば幸いです。
こういう状況を変えるために業界内でも動きがあるのも事実ですが、すぐに変化するかというと疑問です。
そう考え、僕は証券会社を退職し金融機関外で活動を始めました。
最近は、証券会社自体もこのようなビジネスモデルは課題だと考えており、新しい試みをする動きもあります。
そういった動きを何か支援できないかという思いもありますが、今自分ができることは、証券会社の外でファイナンシャルプランナーとして金融リテラシー向上のための教育活動だと考えています。
自分にできることがどれだけあるかはわかりませんが、noteでも金融教育につながる、そんな記事を書いていこうと思います。
道のりは遠いですが、地道にコツコツやっていこうと思うので、いい記事があったらぜひリアクションをいただければ嬉しいです。
2022年元旦から連続100日更新に挑戦中!
スキやフォローなど応援していただければ嬉しいです。
サポートありがとうございます✨みなさんに支えていただき、今日も記事を書けています!いただいた資金は、今後の金融教育の活動資金に充てさせていただきますね📚
