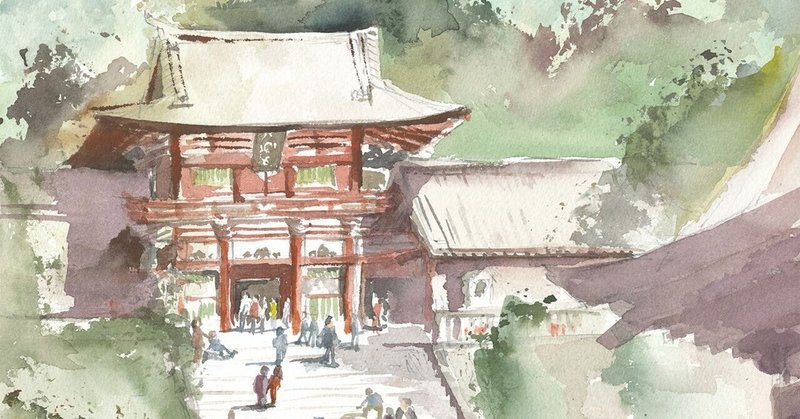
2023.12.19 【全文無料(投げ銭記事)】源頼朝だけではない知られざる鎌倉幕府の立役者
源頼朝は天皇家の子孫だった?
貴方はご存知でしょうか?
鎌倉幕府を開いた源頼朝が、天皇家の子孫だったことを…。
源頼朝というと、平家との争いに勝ち残った勇ましい”武士”としてのイメージや兄弟・一族に冷徹非情といったイメージが強いかもしれませんが、実は、天皇家との関係が鎌倉幕府の樹立に大きな影響を与えていたのです…。
今回は、教科書では語られない鎌倉時代初期に構築された徳―権威―権力の三層構造が、民を大切にする国づくりの基礎となった源頼朝と天皇家の知られざる関係について書き綴っていこうと思います。
封建制度⇒地方分権⇒法治社会
さて、今年10月7日の朝、イスラム系過激派組織ハマスの戦闘部隊がイスラエルに侵入し、民間人に向けて銃を乱射しました。
近くで開催されていた野外フェスティバルの参加者も多数が犠牲になり、少なくとも260人の遺体が見つかっています。
また200人ほどの市民が人質として連れ去られました。
21世紀の現代に起こったとは信じられないような蛮行ですが、ロシアのウクライナ侵攻、中国のチベット、ウイグルでの住民弾圧、北朝鮮の自国民餓死も無視する圧政などを考え合わせると、逆に日本や欧米諸国のような安全安心な社会の方が、珍しくなっているのかも知れません。
今や国際社会は、日本や欧米のような人権を尊重する法治国家と中・露・北朝鮮などの人権など歯牙にも掛けない専制国家と、大きく両極端に分裂しています。
この違いはどこから来ているのでしょうか?
すぐに気がつくのは、日本も欧州もその歴史の中で、封建制度という名の『地方分権』政治を数百年規模で経験していることです。
日本の江戸時代は徳川幕府という共通の枠組みの中で約260もの諸藩があり、相当の自治を行っていました。
欧州も多くの小さい国々に分かれ、英仏などの大国も地方領主が相当の財産と武力を持っていました。
封建制では領主が領民と同じ地域で生活し、地域を発展させることが自らの繁栄ももたらすという一種の運命共同体を築きます。
また隣接した地域との領地争いを平和的に収めるために、土地の所有権の明確化や裁判制度などを求めます。
封建制こそ地方分権をもたらし、人権国家・法治国家の基盤になったと言えそうです。
一方、ロシアや中国などは中央で皇帝が独裁政治を行い、帝国全体のことしか考えません。
各地方の発展や住民の幸福などを考えるのは、余程の賢帝でも現れない限り望みは持てません。
日本で封建制度が始まったのは鎌倉時代からです。
初代将軍・源頼朝⇒第2代執権・北条義時⇒第3代執権・北条泰時のリレーを通じて鎌倉幕府が確立され、その制度は江戸時代末まで700年近く続きました。
この長い間に、武家による幕府体制が日本の国柄を形成してきました。
この3代が、どのように幕府体制を築いたのかを見ることで、その幕府体制とはどんなものだったのか。
そして、日本の国柄にどう影響したのかを考えてみたいと思います。
頼朝が生んだ幕府体制の叡知
東京書籍の中学歴史教科書では、
<鎌倉幕府の始まり>
と題した節で、こう記述されています。
平氏の滅亡後、源義経が源頼朝と対立すると、頼朝は、義経をとらえることを口実に朝廷に強くせまり、1185年に、国ごとに軍事・警察を担当する守護を、荘園や公領ごとに現地を管理・支配する地頭を置くことを認めさせました。
こうして頼朝は、本格的な武士の政権である鎌倉幕府を開きました。
これ以後、鎌倉に幕府が置かれた時代を鎌倉時代といいます。
さらに頼朝は、義経が平泉の奥州藤原氏の下にのがれると、義経と奥州藤原氏も攻めほろぼし、東日本を支配下に置きました。
史実を坦々と記述していますが、世界の歴史から見れば、幾つか疑問が湧きます。
例えば、鎌倉に本拠地を置いて、
<東日本を支配下に置きました>
というなら、なぜ頼朝は独立国家を作って、その王にならなかったのでしょうか?
中国の実力者なら、必ずそうしたでしょう。
実際に、歴史家の中にも『東国国家論』として、
幕府と朝廷はそれぞれが独立した存在だった
という主張があるようです。
しかし、これは“権力の所在”しか見ない議論です。
例えば、589年に中国を統一した隋は、2代皇帝煬帝が三度に亘る高句麗遠征などで国内が混乱したのを機に、高官の一人が挙兵して唐を興して隋を滅ぼしました。
実力あるものが独立して前王朝を倒すというのは、中国史のみならず世界史で何度も繰り返されたパターンです。
日本の皇室が世界最古の王朝であるというのは、言い換えれば、実力のある者が新王朝を開くという『世界標準』に日本が従っていなかったからです。
そして、源頼朝こそ、その『世界標準』から逸脱して、日本固有のシステムである『万世一系』の下での幕府開設を行った人物でした。
全国を支配しながらも朝廷の形式的臣下に甘んじた義時
頼朝が、何故自らの権力で独立王国を作らず、朝廷の下で征夷大将軍に甘んじる選択をしたのか?
それは、皇室の『権威』に関する配慮からでした。
本編では、同様の配慮を頼朝の後継者である第2代執権・北条義時の例で見ておきたいと思います。
義時は頼朝の死後、執権として鎌倉幕府の実権を握りました。
その過程で起きた承久の変について、東京書籍版歴史教科書は次のように説明しています。
朝廷の勢力を回復しようとしていた後鳥羽上皇は、朝廷に協力的だった第3代将軍源実朝が暗殺されると、1221(承久3)年、幕府をたおそうと兵を挙げました。
しかし幕府は大軍を送って上皇の軍を破り(承久の乱)、後鳥羽上皇を隠岐(島根県)に流し、京都に六波羅探題を置いて朝廷を監視しました。
また、上皇に味方した貴族や西日本の武士の領地を取り上げ、その場所の地頭には東日本の武士を任命し、幕府の支配を固めました。
しかし、この圧勝の後でも、 天皇に任命された征夷大将軍が幕府を率いるという基本構造には、義時は手を付けませんでした。
後鳥羽上皇の兄にあたる守貞親王の第三皇子を皇位につけ、この後、 堀河天皇の下で第4代征夷大将軍・藤原頼経が任命されました。
義時はその部下になったのです。
天皇を指名できるほどの権力を得たなら、外国であれば、ここで義時が新しい王朝を始め、自分が新しい王だと宣言するところでしょう。
しかし、義時はそのようなことはせず、 天皇の地位にも、天皇に任命される征夷大将軍の地位にも手を付けていません。
西日本に幕府の支配を広げただけです。
頼朝も、義時も、実質の権力を手に入れ、東日本或いは日本全体の支配を確立しながらも、なぜ形式上、幕府は朝廷の一機関であるという建前を変えなかったのでしょうか?
義時は親王を次期将軍として迎えて権威を上げようとした
『権力』だけ見ていては、この疑問は解けません。
問題を解く鍵は『権威』にあります。
義時が朝廷の権威をどのように見ていたのかを示す良い事例は、3代将軍・実朝に実子ができないため、 後鳥羽上皇の皇子を次期将軍として迎えるという構想を進めたことです。
この構想は、義時にとっても願ってもない話でした。
上皇の皇子を将軍に戴けば、鎌倉幕府の権威は更に上がります。
そして、 後鳥羽上皇との太いパイプで、幕府内の最高実力者としての自分の地位も上がります。
実朝が暗殺された後も、義時は皇子下向の約束を果たして欲しいと 上皇に嘆願しています。
しかし、 後鳥羽上皇は和歌を通じて親しくしていた実朝の後見を前提として皇子を送る事を考えていたので、その実朝亡き後、幼い皇子を送ればどうなるか。
信州大学の呉座勇一特任助教はこう解説しています。
『愚管抄』は、後鳥羽院が「日本国を二つに割ることになる」との懸念から親王将軍を拒否したと記す。
実朝が存命ならば彼を介して幕府を制御できるが、実朝不在の状況で親王将軍を下向させれば、幕府の権威が高まり独立志向が強まるだけだ、と後鳥羽は考えたのである。
義時にしろ、 後鳥羽上皇にしろ、如何に皇室の『権威』を重要なファクターとして考えていたかが、よく窺えます。
こういった当時の人々の心理を無視して権力構造だけを見ていたのでは、歴史の実像は見えてこないでしょう。
後鳥羽上皇の怒り
上皇は親王下向は拒否しましたが、摂政関白の家柄である西園寺家の幼児を下向させると妥協し、幕府と合意が成立しました。
しかし、ここで摂津源氏の名門・源頼茂が自ら将軍になろうと謀反を起こし、在京の幕府武士たちと御所で戦い、最後は御所に火をかけて自害しました。
内紛続きの幕府内の争いが都まで持ち込まれたのです。
上皇は大内裏の再建に取り組みましたが、そのための費用負担に各地の地頭が抵抗します。
その地頭を指揮すべき幕府は一向に動きません。
後鳥羽上皇が義時に対して苛立ったのも当然でしょう。
ここから、遂に幕府の元凶である義時を追討せよとの院宣を下すのです。
これが承久の変の発端でした。
ただ、東京書籍の言うように、 後鳥羽上皇は倒幕を目指したということではなく、あくまでも義時の排除を狙っていただけで、その証拠に幕府の中で義時に叛旗を翻す可能性のある武将たちに院宣を出しています。
幕府は大軍を京に送りますが、その指揮を執ったのが義時の長男である泰時でした。
いざ出撃したものの、泰時が途中で鎌倉に引き返し、義時に、
「もし、 後鳥羽上皇が御自ら出陣されたら、如何致しましょう」
と聞き、それに対して義時が、
「その場合は止むを得ない、弓矢を捨てて降参せよ」
と指示しましたが、ここにも二人が皇室の権威を如何に畏れていたかが窺えます。
承久の変によって進んだ権力と権威の垂直分担
承久の変後、朝廷と幕府の関係は大きく変わりました。
まず、今まで朝廷は『北面の武士』として武力を持っていましたが、承久の変後、朝廷の武力は大幅に縮小されて御所の警備隊とされました。
また朝廷と畿内・西国武士を監視するために『六波羅探題」が置かれました。
即ち、軍事・警察の権限を朝廷は取り上げられ、幕府が全てを取り仕切る体制になりました。
また、今まで幕府は主に東国武士の所領を統括していましたが、承久の変後は幕府の勢力が西日本にも伸び、日本全国の多くの荘園で幕府の御家人が地頭となって、現地で徴税や警察の役割を果たしました。
こうして、幕府が全国の徴税・警察・軍事の権力を握ることで、国家の行政機構が一元的に整備されたということができます。
そして、朝廷は純粋に権威を担うようになっていきました。
“朝廷の権威の下での幕府の権力”という垂直分担が、更に明確化されたのです。
権力を支える権威、権威を支える徳
権力と権威の垂直分担が実現したところで登場したのが、第3代執権に就いた北条泰時でした。

泰時の生涯におけるその政治の特長は、『撫民』と『御成敗式目』にありました。
この2つは、幕府が全国に地頭を置く制度が正しく機能するためにも必要なものでした。
現地の徴税や警察の役割を果たす地頭が民に過酷な税を課したり、不正な逮捕をしたのでは安全安心な世にはなりません。
そこには、統治者として民を思う『撫民』の精神と、また何が正しいか道理を示す法が必要でした。
北条頼政・義時等の北条一族は、幕府内部の血みどろの権力争いに勝ち抜いてきました。
そこから、どうして泰時のような深い思想を持つ人間が出てきたのでしょうか?
東京大学史料編纂所の本郷和人教授は、泰時が京都で出会った二人の人物に感化されたと説きます。
一人は明恵上人で、その教えが泰時の元々無私な性格に共鳴して、民を思う気持ちを更に引き出したのでしょう。
もう一人は、承久の変後、関白となった九条道家です。
道家は4代将軍頼経の父でもあり、朝廷と幕府の両方に影響力を持つ人物でした。
その道家が、
「有徳の政治、即ち徳政を推進する。・・・徳政の実施こそが、乱れた世を正す方途である」
と宣言し、有能な中級貴族を集めて、道理に基づいた徳政を行うようにしました。
泰時は、この道家に倣って武家の法としての『御成敗式目』を制定し、徳と道理に基づく政治を目指しました。
徳-権威-権力の三層構造が築いた日本の国柄
権力とは、“人に言うことを聞かせる力”と定義できるでしょうが、言うことを聞こうとしない人を動かすためには、その抵抗を押し退けなければなりません。
そこから戦いが始まります。
中国や欧州で戦争ばかり続いたのはこのためでしょう。
一方、『権威』とは、“人々がこの人の言うことなら聞こうとする信頼”です。
頼朝が武装蜂起した時点では、単なる地方の武士集団の頭目に過ぎませんでしたが、朝廷から征夷大将軍の命を受けた後は『官軍』となりました。
朝廷の権威を受けて、頼朝の許に馳せ参じた武士も多くいました。
しかし、権威が人々から受け入れられるには『徳』が必要です。
歴代 天皇が民の安寧を無私の心で祈られてきた伝統があるからこそ、民は皇室を信頼するのです。
その徳は、初代 神武天皇が、
『大御宝を鎮むべし』
と、国民を安寧な暮らしができるようにしようという建国の詔から始まっています。
その徳を基盤として培われた皇室の権威を土台として、鎌倉幕府が権力を得て全国に御家人を配したのです。
この封建体制によって、地方分権がある程度の徳を以って行われるようになりました。
これを数百年経験することによって、日本の安全安心な国柄が築かれました。
その骨組みを築いたのが、頼朝―義時―泰時の鎌倉幕府の始祖たちでした。
最後までお読み頂きまして有り難うございました。
投げ銭して頂けましたら次回の投稿の励みになります!
ここから先は
¥ 168
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
