
“甘えるな!自分に喝!“と思ったときに読む本「私の幸福論」(ちくま文庫)
読みたくなる本をぼーっと探し、YouTubeを流し拝聴していた時にたまたま出会った1冊です。
ちなみに、著者である福田恆存という方を私は全く知らず、(“恆存“つねあり”と読めなかった)『私の幸福論(ちくま文庫)』という本の存在も知りませんでした。
1998年出版の本ですが、歴史は古く、1955年(昭和30年)「若い女性」という雑誌の連載コラムをまとめたもので、68年前の価値観がそのまま1冊に凝縮されてました。
女性向け雑誌の連載なので、優しい内容かと思いきや、
え〜っ!ちょっと、
ちょっと待ってください!激しすぎて・・。
福田先生の投げるボールはすべて“直球ストレート”。
冒頭から容赦なく読者である私に〝直球ストレート“は襲いかかり、ボーッとする暇はありません。
必死でボールに食らいつくしかないのです。
福田先生は、全ての章で
『人としてどのように生きていくことが大切か』
を説かれています。
先生のボールを受け止めるうちに、胸の奥にズンズン響き、心が揺さぶられていくのを感じ始めました。
幸福になる権利よりも、幸福になる責任について、私は語りたいとおもいます。私はやさしく書くつもりですが、幸福になるみちのむずかしさについて語るつもりです。(中略)女性は、人間は、幸福になれるものではありません。幸福というものはもっとむずかしいことです。それは、たった一人の孤独なたたかいでもあります。それは大変困難な道ではありますが、しかし、私は無責任なことを言いだそうとしているのではない。私は自分のことばに責任をもちます。
ここ最近の厳し過ぎる規制の中、
万人受けする、無害で本心の見えない文章が溢れている現代。そんな文章に慣れ切っている自分に気づき、まずショック!
いきなりの切り込みに衝撃を受け、思わず背筋が伸びました。福田先生のオブラートに包まない、ぶれない本音の言葉は、本を通じて福田先生の講義を受けているようで・・そうそう、こんな真剣に本と向き合えたのは何年ぶりだろうか。昭和の時代の凜とした匂いが蘇ってきました。
「教養について」「職業について」「美醜について」「自由について」等々、唸った章は多々ありますが、今の私にとって、特に大切に思えた章を書き留めておきます。
醜く生まれついた女性に生涯つきまとう不幸という現実を無視するわけにはいかないのです。いくら残酷でも、それは動かしがたい現実なのであります。いや、現実というものは、つねにそうした残酷なものであります。機会均等とか、人間は平等であるとか、その種の空念仏をいくら唱えても、この一片の残酷な現実を動かすことはできないのです。
「美醜について」なんて、平成や令和世代からは怒号が来そうで心配です。
昭和ど真ん中の子供世代は、「ブス」「デブ」「バカ」等々(もっとすごい言葉もありました)、美醜に関する言葉を普通に使っていました。子供の無邪気な一面は時には残酷で、言われて傷つき、言って傷つけを繰り返す中で、自分を取り巻く現実を知り、自分の立ち位置を自覚することを学んでいきました。小学校低学年の頃には、人は平等じゃないことも知っていたように思います。
昭和はNGワードだらけの野蛮な時代に見えますが、たくましさを育んでくれた時代でもありました。その時代が残酷な現実に立ち向かえる大人への醸成の時間だったとしたら、今の子供達は大丈夫なんだろうか・・。動かしがたい現実からは逃げられないことを子供達に教える大人がいなくなったように感じますね。重度の事なかれ主義というか、本音を見せない勇気のない大人ばかりになってきているようにも思えます、私を含めて。福田先生の真剣な言葉にはっとします。
顔の美醜は生まれつきのものだ。人格は努力でなんとでもなる。立派な人格は、その持ち主が称賛されるべきだが、美しい顔なんてものは、別に持ち主の手柄ではない。
私の考え方には救いがあると思います。私は「とらわれるな」といっているのです。醜、貧、不具、その他いっさい、持って生まれた弱点にとらわれずに、マイナスはマイナスと肯定してのびのびと生きなさいと申し上げているのです。(中略)自分には長所がひとつもなくても、自分の弱点だけはすなおに認めようということです。もちろん長所のない人間などいるわけはありません。しかし、弱点を取り返そうとして、激しい気持ちで長所の芽生にすがりつき、それを守ろうとすれば、必ずそこに歪みが生じます。
まず、自分の弱点を認めること。またたいていの人は、自分の長所よりは先に弱点に気がつくでしょう。そしたら、それをすなおに認めること。そして、それに拘らぬように努めること。そうすれば、他に埋め合わせの長所を強いて見つけようとあがかなくても、その素直な努力そのものが、いつの間にか、あなたの長所を形づくっていくでしょう。無理に長所を引っ張り出そうとしなくても、現実の自己に甘んじる素直さとそのものが、隠れた長所をのびのびと芽生させる苗床となるでしょう。
福田先生は、「美醜について」「ふたたび美醜について」と2章にわたり、現実の残酷さを自覚し、その上で自身は何をするのかを繰り返し説かれています。加えて、誰もが自分に限界があることを認めたがらないとも説かれていました。福田先生の言葉は、噛み締めば噛み締めるほど深いところに染み込んでくるんですよね・・。弱点ばかりに執着したことで、自己の内面の葛藤と、良い格好を見せたい弱点を隠した外面との乖離を実感しています。
根本的には、私たちは私たち自身の過去を否定してはなりません。どんな失敗をしても、どんな悪事を働いても良いから、それが自分の本質と関わりがない偶然のもの、あるいは他から強いられてやったもので、本来の自分の意思ではないというような顔をしないこと、自分の過去を自分の宿命として認めること、それが真の意味の自由を身につける第一歩です。
福田先生に全てを見透かされているようで、図星すぎて恥ずかしい。
過去の出来事を記憶から消していた自分。
他人や環境のせいにして逃げていた自分。
自分の意思じゃないという顔をして誤魔化していた自分。
根底から、私の考え方や思考過程を覆された章でした。
自由であるためには、私たちの精神はたえず緊張していなければなりません。
自由とは、無期限、無制限、当たり前にあるものと思っていたし、緩くリラックスしたイメージでもありました。
自由であるためには、緊張が必要とは全く考えたこともありません。ここでもまた、私の考えは福田先生にごろっとひっくり返されました。
自由というものは、なにかをしたいという要求、なにかをしうる能力、なにかをなさねばならぬ責任、この三つのものに支えられていなければなりません。
ここが一番衝撃的でしたし、同時に、
甘え過ぎな自分を認識した瞬間でもありました。
福田先生は、自由の3つの要素に加えて、自分のやりたいことをやり、もうこれ以上無理だという限界にぶつかることが重要であるとも言われています。そもそも無制限の自由なんてものはない!とも。
私は逃げる口実で勝手に限界を作っていたのかも・・。
私は限界にぶつかる手前で逃げていたのかも・・。
福田先生のおっしゃる通りです。
もう一度、やれるところまでやってみないといけないなと腹が据わりました。
最後に福田先生からのエールがあとがきにありました。
究極において、人は孤独です、愛を口にし、ヒューマニズムを唱えても、誰かが自分を最後まで付き合ってくれるなどと思ってはなりません。
じつは、そういう孤独を見極めた人だけが、愛したり愛されたりする資格を身につけえたのだといえましょう。冷たいようですが、皆さんがその孤独の道に第一歩を踏み出すことに、この本が少しでも役だてればさいわいです。
もっと早くにこの本に、福田先生に出合いたかったとしみじみ思います。
若い世代の人たちには、「母性について」「結婚について」など、人生の機微に触れる瞬間に読んんでもらいたいな〜とお節介したくなります。
「教養について」「職業について」の章は、仕事のキャリアを上がるタイミングで、響く所が変わるかもしれません。
昭和の大人は、本当に本当に厳しかったけれど、真の優しさを最後に(後ろ姿で見せるイメージがあります)必ず見せてくれたことを思い出しました。
今この本に出合えたたことは、これからの私の大人としての人生の歩みを変えるものでした。
これからも、時々、喝を入れてもらいにページをめくらせていただきます。人生の愛読書になりました。
福田先生、ありがとうございました。
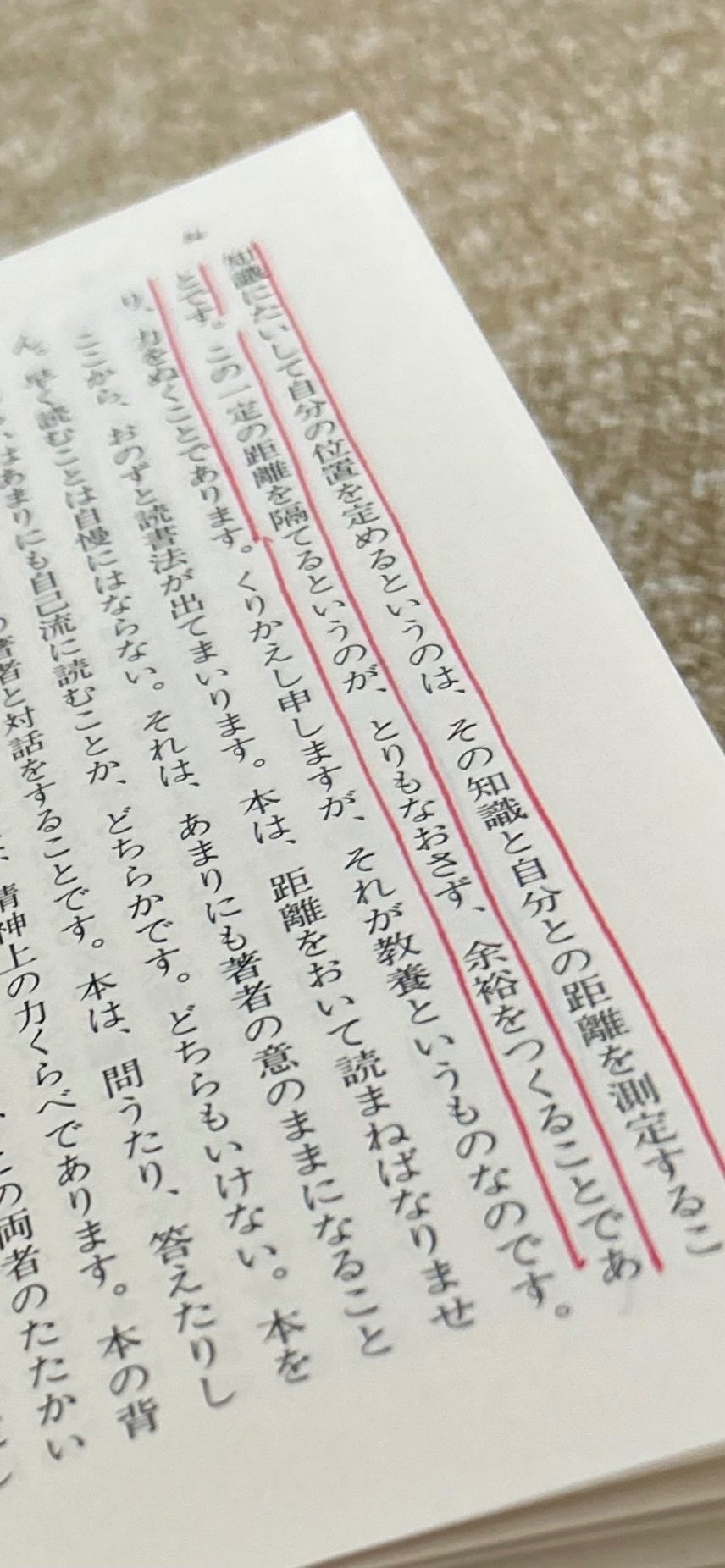
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
