
【ミステリーレビュー】卒業-雪月花殺人ゲーム-/東野圭吾(1986)
卒業-雪月花殺人ゲーム-/東野圭吾
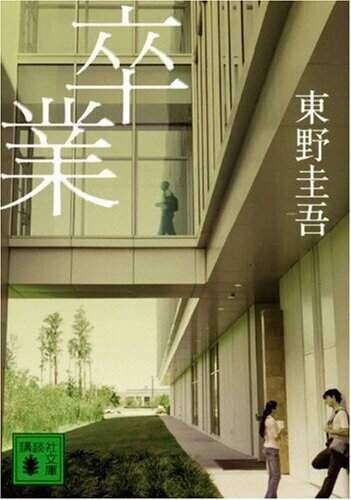
加賀恭一郎シリーズの第一弾となった、東野圭吾のロングセラー作。
単行本の発表は1986年。
2009年に新装版が発表されると、2013年に100万部を突破。
実に、発売から23年をかけての快挙となった。
刑事として、数々の事件を解決していくことになる加賀も、この時点では大学4年生。
就職に、部活に、恋愛に、と諸々悩みが尽きない時期であり、ここからシリーズがスタートしたことで、加賀恭一郎という人物に奥行きを生んだのは間違いないだろう。
もっとも、本作の発表は35年前。
若者文化の移り変わりをまざまざと見せつけられた形で、自分の大学時代ですら10年ではきかないレベルの過去となっている中、更に昔の大学生に感情移入するのは、正直難しかったというのが本音である。
兄弟に学生運動の参加者がいて就職が難しいとか、就職先によっては結婚がフイになるとか、そもそもみなさんそんな時期からプロポーズをご検討されているのね、などなど、変わったのはガジェットだけではないのだな、というのを痛感してしまう。
さて、主に視点人物となるのは、加賀恭一郎と相原沙都子。
ともに、暇さえあればバー「首を振るピエロ」に集まる高校時代からの仲間で、彼らを含む7人のメンバーと、恩師の南沢雅子が本作の主要な登場人物(要するに容疑者と被害者)となる。
その中のひとり、牧村祥子が、女子専用アパート「白鷺荘」の自室にて死亡しているのが発見された。
自殺か他殺が判然としないものの、発見現場は住人以外は中に入れない、広義での密室。
加賀と沙都子は、それぞれの視点から彼女に何が起こったかを探っていくが、南沢先生の自宅にて茶道部だった彼らの恒例行事、"雪月花之式"の最中に、またも異常な事件が発生する。
2つの事件それぞれが自殺なのか他殺なのか、他殺だとしたら不可能犯罪をどうやって実行したのか。
特に、"雪月花之式"中の事件は、衆人環視のもと、どうやって特定の人物だけに毒を飲ませることができたか、のトリックに重きが置かれており、儀式の過程が極めて丁寧に描写されているものの、どうしてもわかりにくさは解消できず。
映像で見れば一目瞭然といったところなのだろうが、馴染みのないゲームの解説を文章で、というのは限界がある。
そこにトリックがあるかも、と言われても、さすがに自分で考えてみようとはならなかったな。
設定の難しさや時代感のズレはネックと言わざるを得ないものの、本格推理+当時の大学生の葛藤を可視化した群像劇といった構成は、その後、東野圭吾が数あるミステリー作家の中で、頭一つ抜き出していくのも納得。
ミステリー部分よりも、7人でつるんでいた仲間の形が、事件をきっかけに変わっていくところに、強く後味を残す作品である。
【注意】ここから、ネタバレ強め。
兎にも角にも、"雪月花之式"だ。
何らかのトリックが使われたとして、作為的に何か出来たのは沙都子でなければ真犯人しかいないよね、といったメタ目線での消去法で読むしかない。
その前の密室のトリックについても、確かに伏線はあったけれど、ヒントが弱すぎたかな、と不完全燃焼(ヒントを明確にすると、犯人があからさまになってしまうので難しい判断ではあるが)である。
そんなわけで、東野圭吾作品であれば、もっと面白いミステリーがたくさんあるな、というのが率直な感想であろうか。
加賀恭一郎の作品を最初からコンプリートする気概があるなら別であるが、まず最初に読むべき作品ではないのかと。
もちろん、若手時代の作品に、今更あれこれ注文をつけるのは無粋。
著者のその後の成長や実績を知っているからこそ、まだ筆が粗いな、と言えるわけで、有象無象のミステリーの中で、当時としては、むしろ期待に満ちた目で読まれていたのだと思うのだが。
その意味では、ある程度東野作品に触れたうえで、ルーツを探るべく読むのが妥当かな。
ある種の源流的な味わいのある1冊である。
それにしても、学生時代の友情の脆さ、危うさよ。
加賀と沙都子も含めれば、7人のグループでカップルが3組。
仮に、事件が起こらなかったとしても、ずっと関係性が変わらないはずはなく、就職して家庭を持って、という中で仲良しグループが数年後まで継続していくことはなかっただろう。
とはいえ、貴重なモラトリアム期間の最後の半年を、仲間内で3人が死亡するという事件に振り回され、満喫できなかったのは不憫でならない。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
