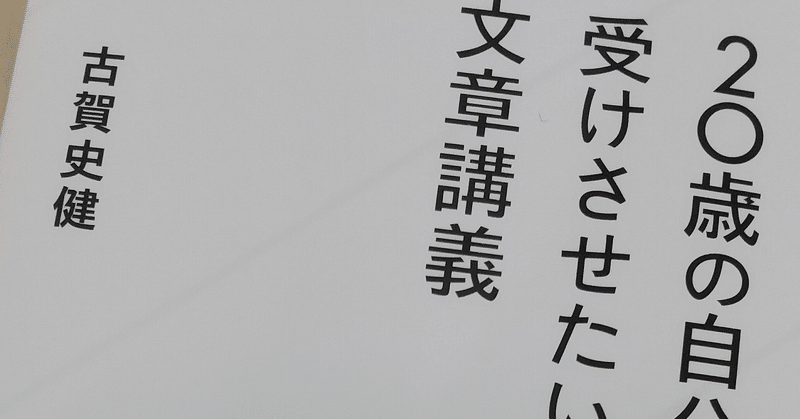
「20歳の自分に受けさせたい文章講義」① 文章のリズム
こんにちは、齋藤です。

今回は、文章の書き方についての本を紹介させて頂きます。
●弁護士=文章を書く仕事
弁護士は、日々大量の文章を書きます。
みなさまが、「弁護士」と聞いたとき、まず最初に浮かぶイメージは、裁判所で「異議あり」と声高に叫ぶ、というようなものかも知れません。
証人尋問で相手方の証人の証言の矛盾を突く、あるいは、刑事事件で検察官の誘導尋問に異議を述べる、
これらがいずれも弁護士の仕事の中で最もスリリングかつ手に汗握る、華々しい瞬間であることは、多くの弁護士が肯定するところでしょう。
しかし、実は、弁護士というのは、さまざまな種類・内容の書面を書いて相手方や裁判所を説得するお仕事、と考えるのが実態に合っている気がしています。
例えば、裁判においては、訴状にはじまり、準備書面、陳述書、証人尋問の尋問事項など、さまざまな書面を作成しなければなりません。
また、裁判外でも、さまざまな業態・ビジネスにおける契約書をはじめ、就業規則等の労務管理に関する書面、遺言書、遺産分割協議書、離婚にあたっての合意書、交通事故における保険会社とのやり取り、刑事事件の示談書、などなど、実に多様な種類・内容の書類を作成するわけです。
弁護士のメインの仕事は、「事件」を処理することです。
そして、上述の通り、事件の処理にあたって、多様な種類の書類を作成する必要があります。
そうすると、もはや、弁護士とは、様々な種類の書類を作成する仕事、と言ってよいのではないか、というのが、私の考えです。
実際、一日の時間の使い方にしても、裁判所で裁判官や相手方とやり取りする時間など、仕事全体から見るとほんの一部分にすぎず、大半の時間を、事務所で、書類の作成にあてているのが実情です(そして、たいていの弁護士が同様です)。
弁護士の仕事が書面を作成することにあるのであれば、より説得力のある書面を書けることが、弁護士の腕を決めると言っても過言ではないはずです。
さらに言えば、より良い書面を書く能力を高めることが、弁護士のスキルアップに直結することになります。
そんなわけで読み始めたのが、今回ご紹介させて頂きます「20歳の自分に受けさせたい文章講義」(古賀史健 星海社新書 2012年)という本です。
もちろん、法律文書に対象を限定した、文章の書き方の本も出版されていますし、また、弁護士になる前の司法修習の際に、法律文書の書き方の手ほどきを受けます。
司法修習では、法律文書の作成の基本として、例えば、客観的事実のみを書く、感情などの主観を交えない、過度な修飾語句は控える、一文はなるべく短くする、句読点をしっかり意識して書く、などのレクチャーを受けた記憶です。
弁護士になって7年目になり、日々たくさんの文章を書く中で、そうした法律文書の「基本のき」だけに立脚した文章ではなく、そこからさらにもう一歩進んだ文章術を会得する必要性を感じるようになりました。
そこで、あえて、法律文書に限らず、一般的な文章の書き方をもう一度イチから体得すべく、この本を手に取りました。
以下、本書のうち私がより重要と感じた部分に触れながら、より良い文章の書き方について考えていきたいと思います。
●「ガイダンス その気持ちを『翻訳』しよう」
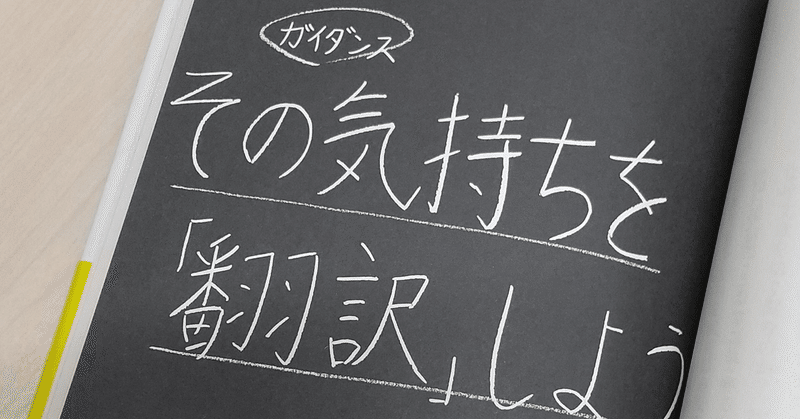
著者に言わせれば、私たちは、「文章の書き方・組立方を体系的に教わって」はいません。
「作文も読書感想文も“書き方指導”ではなく、形を変えた“生活指導”になっていた」というのです。
確かに、小学校では、文章を書くスキルより、もっともらしいことを書いていることに評価の重点が置かれていた気がしますし、句読点をどこで打つべきか、センテンスの長さをどう考えるか、などの技術論を教わった記憶もありません。
そして、著者は、「“書く技術”を身につけることは、そのまま“考える技術”を身に着けることにつながる」と言います。
さらに、「“書く技術”が身につけば、ものの見方が変わる。物事の考え方が変わる。そしてきっと、世界を見る目も変わってくる。」というのです。
つまり、文章の技術の向上により自身の世界観にまで影響が及ぶというわけです。
序文を読むだけで、この本を読んで書く技術を身につければ、自分の世界観をスケールアップさせられるのではないか、と思わずにはいられません。
期待を込めてさらにページをめくってしまいます。
●「文章の『リズム』」
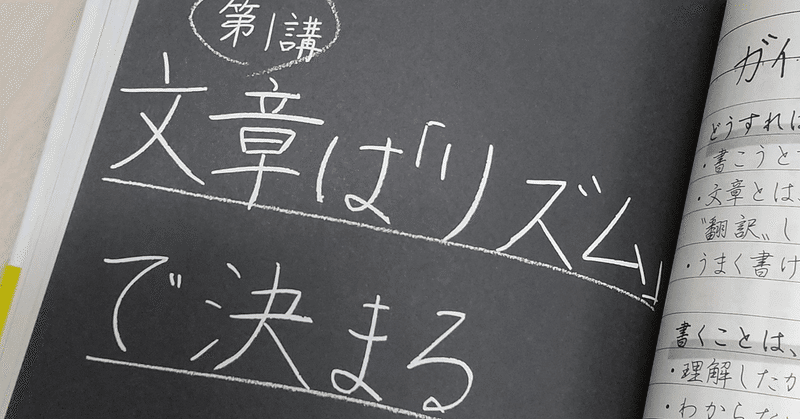
著者いわく、「文体とはリズムである」といいます。
しかし、「例えば、文章にリズムを持たせるコツとしてよく語られる、センテンスの切り方、句読点の打ち方、改行のタイミング。こんなものは「リズム」の本質ではない。」とし、「リズム」とは「どこまでも論理的なものなのだ」と言います。
どういうことでしょうか。
私が考える「文体」とは、たとえばこういうものです。
「下ろしたての爽やかな木肌の盥で、内がわから見ていると、ふちのところにほんのりと光がさしていた。そこのところだけ木肌がまばゆく、でできているようにみえた。ゆらゆらとそこまで水の舌先が舐めるかとみえて届かなかった。しかしそのふちの下のところの水は、反射のためか、それともそこへ光がさし入っていたのか、なごやかに照り映えて、小さな光る波同士がたえず鉢合わせをしているようにみえた。」(三島由紀夫 「仮面の告白」)
上記の引用は、三島由紀夫の「仮面の告白」の序盤で、主人公が、自分が産湯につかっていたときの記憶がある、と述べる部分です。
なんともまろやかな表現により、水にゆらめく日光やとろりとした水の触感などが脳裏に鮮明に活写され、昼下がりの穏やかな空気感が手に取るように感じられます。
「内側」ではなく「内がわ」としたり、「見える」・「みえる」を分けたりと、ひらがなで書く部分と漢字で書く部分とを使い分ける、黄金を「きん」と読ませることで、「おうごん」という固い語感を避ける、などのテクニックにより、こうしたまろやかさを演出しているわけで、こうした表現・文章技法を「文体」と呼ぶものと私は考えていました。
しかし、著者のいう「文体」とは、そうした表現の手法という部分にとどまるものではなく、心地よく読み進めることができる「リズム」こそが文体の本質だということのようです。
ここで、著者のいう「リズム」とは、文章の「論理展開」を指すものだといいます。
そして、著者は、接続詞を意識して、文章の論理破綻を防ぎ、「美文」よりも「正文」を目指すべきだと説きます。
著者は、主観的な「美」よりも、正しさを意識し、客観的な目線を意識した「正文」の重要性を説いたうえで、「自分の意見」という「主観」や「感情」を伝えたいからこそ、「論理を使う」ことが必要であり、「主観を語るからこそ客観を保つ」必要があると述べています。
このように見ると、著者の考える文体=リズム=論理展開=文章の構成・組み立てと考えればよいのかもしれません。
そもそも、法律関係の文書を書くにあたっては、論理展開、客観性が命です。ですので、法律関係文書においては、著者のいう文体=リズムの重要性は言わずもがなのものです。
法律関係の文章では、客観性が最重要視されますので、客観的な事実を羅列したような文体こそがよしとされます。
しかし、例えばこのブログのような日常の文章を書くにあたって、事実を羅列したような文章では、何の面白みもありませんし、読み手がつくとも思えません。
さりとて、徒然なるままに書き散らせばよいかというと、そういうわけでは決してなく、「自分の意見」という「主観」を伝えるためには、「論理」という客観に依拠し、理路整然とした文章を目指さねばならないわけです。
客観的な事実を論理的な順序で羅列すればよい法律関係文書にくらべ、このブログのような日常の文章は、定型的な書き方というものがないぶんハードルは高くなるように感じています。
●「視覚的なリズム」
また、本書では、「文章の視覚的なリズム」の重要性も語られています。
著者によりますと、読者は一瞬で「なんか読みやすそう」「なんか読みづらそう」を判断している、といいます。
これが「視覚的なリズム」の問題であり、
①句読点の打ち方
②改行のタイミング
③漢字とひらがなのバランス
から成り立っているということです。
①句読点の打ち方について、著者は、「1行の間に必ず句読点を一つは入れる」というルールを提唱します。
句読点をうつことで、文字と文字との間に物理的なスペースができ、見た目の圧迫感がなくなり、一呼吸置かせてくれる効果を持つわけです。
②改行のタイミングについて、著者は、「最大5行あたりを目途に改行したほうがいい」と言います。
改行によりやはり圧迫感を解消する効果が期待できます。
さらに、改行には、伝えたいメッセージを強調する、という効果もあるといいます。
③漢字とひらがなのバランスについて、著者は、漢字を多用した文章は第一印象が悪い、としつつ、他方、ひらがなにはひらがなの圧迫感がある、として、漢字とひらがなのバランスを整えて「字面そのもの」が持つ圧迫感を解消すべき、とします。
このように見ていくと、著者が、読者が文章を見たときの視覚的な「見た目」を重視していることがわかります。
これは、読者に読み飛ばされてしまうような文章を書いていては仕事にならない、ライターという職業によって培われた感覚というべきであり、「読ませる」文章を書くうえで極めて重要な示唆であるといえます。
法律関係の文章を弁護士が書く場合、その文章の読者も当然この書面の内容に強い関心を持っており、その文章は当然一言一句真剣に読まれるであろうことを想定しています。
例えば、相手方と書面で主張をやり取りする場合、相手方もこちらの主張の弱点を見つけるべく血眼になって一言一句書面をチェックするはずです。
このような場合、書面の「読みやすさ」はあまり問題にはならず、せいぜい、相手方の弁護士に、「この弁護士いい文章を書くなぁ」と思わせる程度の意味しかないかも知れません。
しかし、反面、例えば、裁判所に提出する書面、訴状や答弁書、準備書面では、弁護士も、訴訟のキモが裁判官に伝わるように、また、自らの主張こそが正当であるとアピールするために、文章のレイアウトなどに工夫を凝らします。
毎日大量の事件を処理しなければならず、必ずしも事件について強い興味をもって読んでくれるとは限らない裁判官に、「なんか読みづらそう」というような先入観を持たれるような書面であってはならず、書面の「読みやすさ」がとても重要となるのです。
このように、上記の「視覚的なリズム」の重要性は、法律文書においても妥当するものと言えます。
上記で引用した三島由紀夫の文章は、「見える」を「みえる」、「内側」を「内がわ」と表記するなどしてひらがなを多めに含ませることにより、ある種のまろやかさを表現していました。
他方で、私が、「美しい文体」を思い浮かべるとき、三島由紀夫のほか、思いつくのは、平野啓一郎です。
「再度ふたたび焰が下に鎮むと、眼前に現出した両性具有者アンドロギュノスは、その焦げた肉体を刑架の上で激しく波打たせ始めた。
膚はだは金属の如き黒色に変じ、僅かに艶を帯びている。人垣は鼎沸ていふつした。火は熟れ過ぎた柘榴の実のように、紅に色着き、裡より膨張する力に抗し得ずして、幾度と無く張裂ける。
流血のように緋色が迸って、暗がりの中に、それが一際けざやかに見える。」(平野啓一郎 「日蝕」)
平野啓一郎氏は、京都大学在学中に執筆したデビュー作である本作で芥川賞を受賞しており、高校生だった私は、この「日蝕」を読み、いつかこのような文章を書けるようになれたら、と身もだえしたことをよく覚えております。
平野啓一郎の文章には、とにかく漢字がこれでもかと詰め込まれており、漢字で表記出来る部分はすべて漢字で書いてあると言っていいくらいです。その圧倒的な語彙力、華麗な文体、幻想的・耽美的な雰囲気は、まさに「美文」の権化と言ってよく、プロの作家(というか超一流の作家)の技量をまざまざと見せつけてくれます。
しかし、一方で、上記の文章は、確かに、難解な漢字のオンパレードで、一見して「難しそう」に感じ(それこそが彼の文章の「格調」なのですが)、平易ではない印象を受けます。
もちろん好きな人は好きなのですが、万人受けするものでもないのかもしれません(純文学とはそういうものかもしれませんが)。
従って、こうした「美文」を目指す(目指しても書けるようなものでもないですが)のではなく、あくまで「正文」を目指し、一般的な読者を意識して、「視覚的なリズム」を整えることこそ、著者が説く、我々が書く日常の文章のセオリーということになるわけです。
「20歳の自分に受けさせたい文章講義」のレビューは2本立てです。
その1では、「ガイダンス」と「第1講」について見ていきました。
その2で、続く
「第2講:構成は『眼』で考える」
「第3講:読者の『椅子』に座る」
「第4講:原稿に『ハサミ』を入れる」
について見ていこうと思います。
お付き合いのほど何卒よろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
