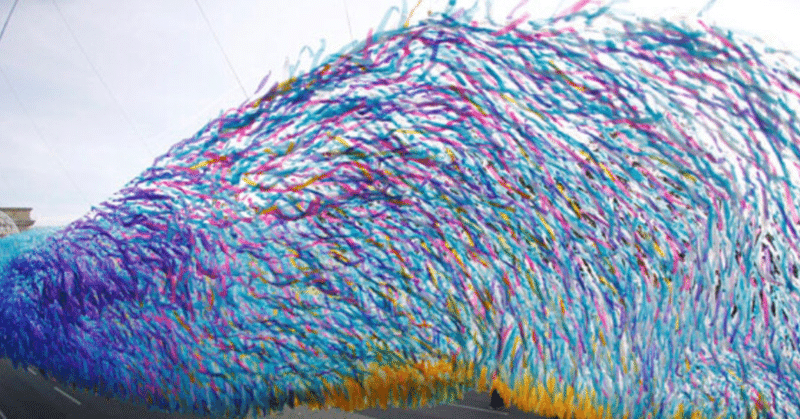
小説『シェルター』24回 第3章 2
更新しました。
前の回はこちら
ーーーーー
第3章 2 仲間 2
「噂をすれば、だぜ」
食堂の空気が急に変わった。
タロウが慌ててこちらに向かってやってくるソナから目をそらした。
わたしは構わずその顔を見た。
間違いない。
あれは確かにさっきわたしが見た空を飛ぶ青い服の少女だ。
さっき見たときは顔まではわからなかったが、ソナはものすごい美少女だった。
さっきの青いジャンプスーツから黒いセーターとジーンズに着替え、さっそうとこちらに歩いてくる。長い髪をポニーテールに結い上げ、その先が歩くたびにリズミカルに揺れている。彼女のその歩みに合わせ、まるで部屋全体の焦点が移動するようだった。
何という存在感。
わたしがその姿に見とれていると、ソナはわたしたちのいるほうへ真っ直ぐにやってきて、やがて少し離れたところでぴたりとその歩みを止めた。
その時だった。
金縛りみたいな衝撃が、わたしの全身に襲いかかった。
わたしはその場に棒立ちになり、石みたいに凍りついた。
指一本動かせず、声ひとつ出すことができない。気づくと、目に見えない触手のようなものが身体の周りを這い回っている。それは一通りわたしの全身をすみずみまでチェックすると、今度は鋭い針となってぷすぷすと内部に突き刺さってきた。
痛いなんてもんじゃなかった。
わたしは声にならない悲鳴を上げた。
ぐさり、とひときわ強い痛みが胸の中心に突き刺さり、衝撃でわたしの身体がねじ曲がった。
ここへ来てからたびたびわたしの頭を襲うあの頭痛とはまた違う、太い釣り針でえぐられたような、形容できないほどの痛みだ。
「......た」
わたしは喉をふり絞り、ようやくかすかな悲鳴を上げた。
「助けて」
「ん?」
タロウがわたしの声に気づいて振り返った。
途端に、張り詰めていた糸がぷつん、と切られるように急に身体が楽になった。
「なんだ?」
「え、あ、いや...」
説明のしようがない。
気づくと、ソナの姿はすでになく、食堂の空気もすっかり元どおりになっている。
わたしは大きく息を吐いた。心臓がまだなにかに怯えるようにばくばくと鼓動している。
「今のは誰?」
「ソナか。あれはここのエースだ」
「エース?」
「ああ。でもあいつ、食堂なんかに何しにきたんだろう」
「なに?」
「修行が進むとめしが要らなくなるんだ。あいつはもうとっくに第4段階に入ってる」
「第4段階?」
そんな、ご飯がいらないなんて、仙人じゃあるまいし。
タロウの言葉を聞き流しながら、わたしは胸を手で押さえた。
今のは、いったいなんだったんだろう。
それが幻でなかった証拠に、胸の真ん中あたりにまだ鈍い痛みがじんわり残っている。
「もしかして、この食堂に片想いの相手でもいたのかな」
朔(サク)がソナの出て行った方を見ながら、ひとりごとのように言った。
「まさか」
タロウがむきになって言った。「あいつにそんなやついるわけねえだろ」
「そんなことわからないじゃないか」
朔がわたしを見ながらうっすら笑った。
「彼女はかりにもここのエースだ。新しいタイガー・リリーがどんなものか、様子でも見に来たのかもしれない。なにしろ第4段階に入ると精神も凡人と変わってくるっていうからね」
わたしは話を聞いていなかった。たったいま見たばかりの、ソナの姿を思い出していたのだ。
すべるような足どりで食堂を歩いていくソナは、まるで重力とはなんの関係も持たない自由な人に見えた。
しかも、彼女はわたしがこうなりたい、と思えるものをすべて持っていた。美しい顔、すらりとした身体、堂々と姿勢を伸ばした、自信に満ちたその物腰。
ーあんな見た目をしていたら、さぞかし人生楽しいだろうに。
ぼんやりと考えていると、タロウがわたしに向かって言った。
「まあどのみち、新入りのおまえには関係のねえこった」
「え?」
「最初のうちに言っとくがな、ここのしきたりを守らねえといろいろ面倒なことになるぜ」
「どうして?」
「どうしてもだ。まず、おまえは質問が多い。最初にそこをあらためろ。ここでは他人の詮索はぜってーに駄目なんだ。自分の身の上話もいけねえ。みんなと一緒にいる時はリーダーの指示に従え。ここで出される食いもの以外は絶対に口にするな。 許可がねえ限り、指定の場所以外へは行かねえこと。 特に西門の外は駄目だ。 まだまだあるが、今日のところはこれぐらいにしといてやる。わかったか?」
「あのう」
わたしは懲りていなかった。
「ここってその、なんていうか、『超能力研究所』みたいなとこなの?」
「なんだそりゃ」
タロウが呆れたようにわたしを見た。
「おまえは本当に総長からなんの説明も受けてねえんだな。だいたい、おまえのいう超能力ってのはなんだ」
「ええっと」
わたしは思いつきを口にした。
「その、たとえばスプーン曲げとか」
「なんだ」
タロウはそれを聞くと鼻で笑った。「スプーン曲げ? そんなもん超能力のうちに入るか」
タロウはそう言うと、テーブルの上にあった金属製のスプーンを手にとった。
「見てな」
タロウはスプーンの柄の端を親指と人差し指でつまんでぶら下げ、その首をゆらゆらと前後に揺らし始めた。
すると驚くべきことが起こった。
スプーンの首の部分が、手を触れていないのに飴が溶けるようにねじれ始めたのだ。
(つづく)
最後まで読んでいただき、ありがとうございます! 見ていただくだけでも嬉しいですが、スキ、コメント励みになります。 ご購入、サポートいただければさらにもっと嬉しいです!
