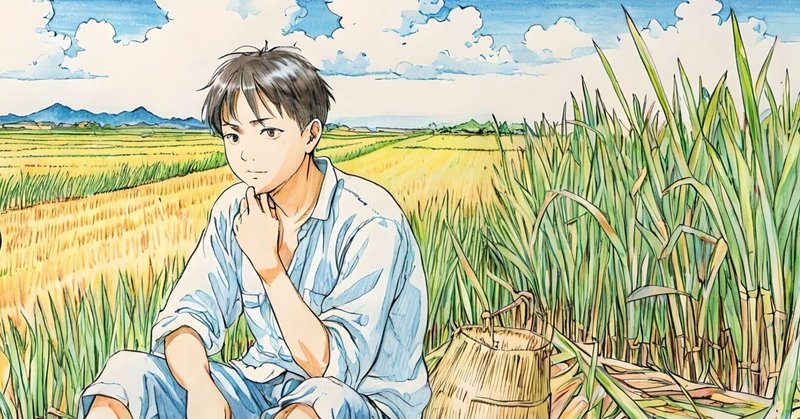
サトウキビ Ni11
農林11号 (母本:KF71-299 父本:F172 )
生い立ち
1982年沖縄で産まれ,1985年に那覇で播種された.1963年に系統名RK85-1049と命名された.1996年に品種登録された.石垣島・大東島などで普及していた.なお,親に日本で採種された系統(つまり品種ではないサトウキビ)を持つ初めての品種となった.特徴は茎数型で毛群が細かくて多い.その一言に尽きる.芽子は三角型をしておりこれはNiを冠する品種では珍しい形質である.
あまり太くなく,硬くて倒れにくく,脱葉性が良い.機械化に優れていたため大東地方で広まった.
時代背景
バブル経済がなくなり日本全体の景気が悪くなり始めた.これがどれほど沖縄の農業に影響したのか定かではないが,サトウキビだけでなく農家が少なくなり,農地面積が少なくなり,日本全体のサトウキビの生産量が落ち始めた.ただ単収を上げるだけ,栽培方法を工夫するだけでは追い付かなかった.だから糖度が低くても収量があれば収入が増えると考える農家は一定数いたようで,かつての重量型品種を高糖性品種に変更しないケースもあった.その裏でサトウキビの取引方法も搾汁糖度を測定する方法から細裂試料を測定する方法に代わった.
このような背景もあり過去の品種からの新品種への代替えが呼びかけられていた.一方で,少ない人数で今の面積を維持しようと考えた時,機械化・省力化が必要となる.育種目標にもそのための様々な性質が求められた時代である.
草型と特徴
未展開葉は直立し,先端は上を向くか先端の十数センチだけ横向きになる.展開葉も直立し,下位になるに従い中程から横へ垂れる.分げつは直立するので,株元から垂直方向に葉が多い印象を受ける.したがって葉が多い位置は最上位展開葉あたりになる.畝の上の方に展開する葉は少なく茎の周辺だけで光を受け止める構造になっている.とはいえ未展開葉も長く直立するので茎長が同じ長さのほかの品種よりは高い位置で受光出来る品種である.分げつがやや傾いた状態で真っすぐ伸びる傾向にあるため分げつ茎は畝の上に葉を展開する形になる.

以下,参考にならない勝手な考察
日中国交正常化が行われたのが1972年.それまでのサトウキビ産業は台湾や韓国からの労働者がいて各地の人口が大幅に増えて製糖期は賑やかだったといわれている.国交正常化の裏には台湾との断交もあって,ゆるやかに労働人口が減っていった.それから韓国からの人道的支援が打ち切られたのは1977年の事である.手作業から機械化への変化はこのようなことも影響したのだろう.農林1号が機械による管理作業を意識した品種だとしたらこちらは機械収穫を意識した品種となる.
毛群の多いさとうきびは手刈り地域では嫌われる.細かい棘は一度体に刺さると抜けにくく,作業中ずっと痛い思いをするためだ.機械刈りならばさとうきびに触れることなく収穫できるので大丈夫だろう,と植えてはみたものの,Ni11の棘は風に舞い,目や喉に入るのだそうで,やはり痛い思いをすることになった.Ni11が姿を消した最大の要因じゃないかと思っている.
この品種の草型はNi1に似ている.受光態勢はかなり良いと考えられる.この時代はまだ密植による収量向上が行われていたので茎数および葉面積が多くても明るい環境で育てられたのではないだろうか.多収となったのはそこも要因として考えられる.株出しは分げつの伸びる方向が畝の上であるため,受光する面積が増える.株出し単収が比較的安定していたのも受け入れられた要因の一つだろう.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
