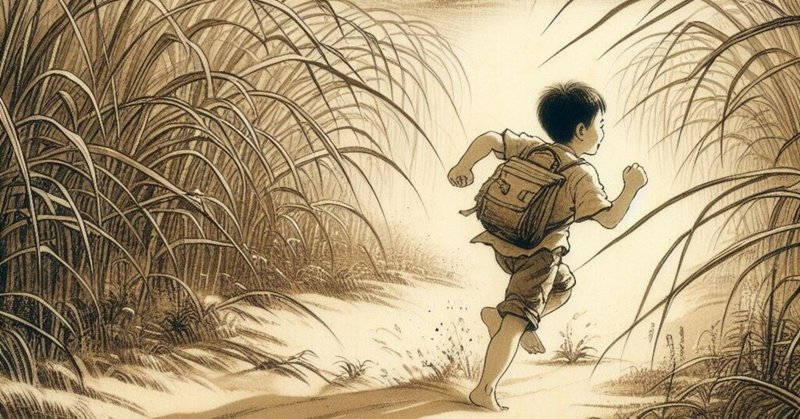
サトウキビ Ni9
農林9号 (母本:NCo310 父本: 多夫交配)
生い立ち
1979年沖縄で産まれ,1980年に宮古島で播種された.1983年に系統名KF80-1010と命名された.1991年に品種登録された.茎数型の多収性品種であり高糖性品種である.沖縄の各地で広まったが,黒穂が発生すると他の新しい品種と交代する形で衰退した.当時の試験成績を見る限りNiF8より高単収.NiF8よりも高糖.といった比較が見受けられる.しかしNi9の最大の弱点,黒穂病に弱いということが衰退の原因となった.
時代背景
昭和が終わり平成になるころ育種され,品種になった.このころ日本はまだ景気がよく,経済が安定していた.サトウキビ畑は徐々に減り始め他の作柄や住宅へと変わり始めた.さとうきびの取引の仕方も重量法から品質取引に変わりさとうきびを取り巻く環境は急激に姿を変えた.これがどれだけ育種へ影響したか分からないが,どのような系統を選ぶべきか考え方が変わっていったのは確かなようだ.これまで高糖性,ということが求められていたのに対しさらに条件が増えた「早期高糖性」というキーワードがに注目が集まり始めた時代である.
草型と特徴
分げつ茎は直立せずやや斜めに伸びる.葉幅が普通程度だが長いので細身の葉身に見える.未展開葉はやや開き気味に伸びて大きく弧を描いて垂れ下がる.最上位展開葉も直立せず,やや横へ展開し大きく弧を描いて垂れ下がる.茎よりも遠い位置へ葉を広げるが受光位置の高さで言えば最上位展開葉より低い位置である.下位葉は横向きに伸びて下へ垂れ下がる.葉は長いので地面に届いている.

以下,参考にならない勝手な考察
打倒NiF8という考えはこの品種から既に始まっていたのだろうか?それとも育種において沖縄と鹿児島が競争し始めたのだろうか?当時の試験成績を見る限りNiF8より高単収.NiF8よりも高糖.といった比較が見受けられる.黒穂に負けて姿を消したといえ,ちょっと比較してみたくなるデータである.LAIに関してNiF8との相違点は何だっただろうか?
まず葉の角度と葉が密集する位置の高さが違う.どちらも最上位展開葉よりも下の位置になるがNiF8のほうがやや高い位置になる.これはNi9の方が葉が下に伸びる部分が長いせいだろう.葉幅がNiF8の方が広い.同じLAIなら個葉面積は小さい方が受光態勢が良いので,同じLAIを確保できる栽培条件なら下の方で光を受けられるNi9はNiF8よりNARが高くなり,単収が高くなったのも想像に難くない.
畝の上の葉の量はあまり変わらないだろうが,長い葉が茎よりも遠い位置で地面に届きそうな一間で垂れ下がっている状態のところに,雨水が当たった場合なにか影響はなかっただろうか?
黒穂病が土壌病害なのでこのような形質は好ましくないとは,思うのだ.だが個人的には「土に水を届ける器官」としての葉の役割は無視できないので興味を持ち続けたいのである.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
