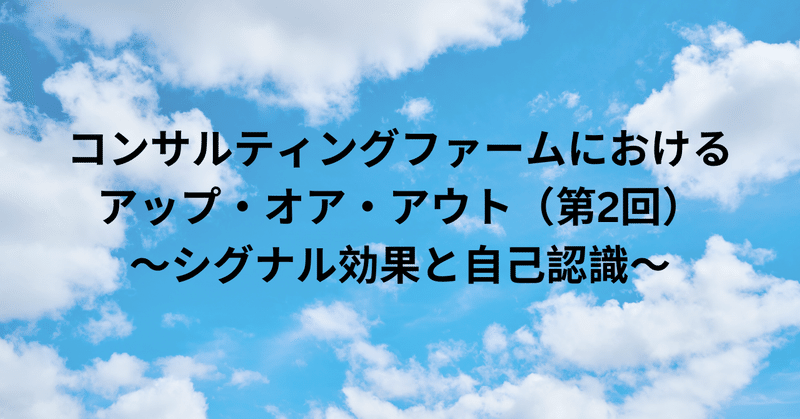
コンサルティングファームにおけるアップ・オア・アウト(第2回)~シグナル効果と自己認識~
前回のエントリでは、そもそもアップ・オア・アウトとは何かという点と、一般的に理解されている「人材の質の担保」というアップ・オア・アウトの説明の不十分さについて検討しました。
今回は、そもそもコンサルティングというサービスとは何なのかという一歩引いた視点から、アップ・オア・アウトが持つ意味や役割について考えてみたいと思います。
コンサルティングというサービスの特徴
アップ・オア・アウトというテーマを考える上で、重要なコンサルティングサービスの特徴を挙げると、以下の3点が存在します。
価格が高い
クライアントがアクセスできる情報に基づいている
「工数」で価格が決まる
1点目の、コンサルティング・サービスの価格ですが、MBB(マッキンゼー、BCG、ベイン)などのトップティアとされるファームの場合、クライアントへのチャージは月あたり数千万から場合によっては億を超えるケースもあります。
各プロジェクトにかかわるメンバーは100%でかかわるメンバーが4,5人程度+他プロジェクトをかけ持っているパートナーが1,2名、というのが典型的なチーム構成になるので、かかわっているメンバーの人数に対してその価格の高さが伺えるかと思います。
コンサルティングファームの単価の高さ、および結果(あるいは原因)としてのコンサルタントの給与の高さについては、今回とは別に独立して検討できればと思います。
2点目の、何に基づいてコンサルティングファームのクライアントへの提案は何に基づいているかですが、多くの場合はクライアントの社内データや顧客インタビュー、顧客サーベイ、業界やマーケットデータ、などが典型的です。
重要なのは、社内データはもちろんのこと、プロジェクトでコンサルタントが新規で取得するデータについても、クライアントがやろうと思えば自分たちで取得可能なケースが多い、ということです。(自分たちでリサーチ会社を通じてサーベイを実施する、マーケットデータを購入する、など)
※なお、業界知見(航空業界、自動車業界、など)や機能知見(デジタル、コスト削減、など)の深さに基づいて価値提供をするタイプのプロジェクトも増えています。
これはアップ・オア・アウトの緩和という近年の傾向と対応しているのではと感じているので、次回のエントリで触れたいと思います。
3点目の「工数」について。1点目に述べたクライアントへの請求価格がどう決まるかですが、コンサルタントはそれぞれのテニュア(役職)に基づいて月当たりのクライアントへの請求単価が決まっています。
「アソシエイトを1人/月稼働するのであればX万円」、「マネージャーを1人/月稼働するのであればY万円」という具合にポジションごとの「プライスタグ」が決まっており、プロジェクトにかかわるメンバーの単価を合算した金額をクライアントに請求することになります。
これらのことからわかるのは、コンサルティングファームの付加価値は
「クライアントでもアクセスできるデータに対して、分析を通じたインサイトを提供すること」
だということです。
そして、それは各コンサルタントという個人によって担われており、それに対してクライアントは多大なフィーを支払っているわけです。
アップ・オア・アウトとシグナル効果
上記の検討を踏まえると、コンサルティングというサービスの単価の高さは、
「クライアントの社員ではできないような分析や洞察をコンサルタントであれば提供できる」
という前提に立つことで初めて説明が可能になります。
既に触れましたが、上記に必ずしも当てはまらない業界・機能知見に基づく価値創出については別途検討してみたいと思います。ただ、そうしたケースでも上記の「コンサルタントの優秀さに基づいて創出される価値」というのは常にベースとして存在するように思います。
では、「人材の優秀さ」という不定形で曖昧な要素をどのように担保し説得的な形でクライアントに伝えることができるのでしょうか。
ここにきて、「アップ・オア・アウト」という仕組みが大きな意味を持ってきます。
継続的に高いパフォーマンスを発揮し成長し続けている人材しかコンサルティングファームに残れない、という仕組みはそこに在籍している人材の「優秀さ」を証明するシグナル効果として非常に強力だと思います。
前回のエントリで考察したように、「アップ・オア・ステイ/ダウン」であってもポジションに対応した人材のレベルは担保されるはずですが、対外的なシグナル効果は「アップ・オア・アウト」という言葉の意味合いや響きに比べると非常に弱いでしょう。
「シグナル効果」というと表層的なように聞こえてしまうかもしれませんが、コンサルティングサービスにとって「人材の優秀さ」というのはビジネスの根幹中の根幹、大前提であり、この点を説得力のある形で認識してもらえるかどうかはビジネスの成否に関わっていると言っても過言ではないと思います。
この点を傍証する話として、あるコンサルティングファームは不景気で採用予定がない年であるにも関わらず採用広告を出し続けていた、という話を聞いたことがあります。
こういったコンサルティングファームの採用広告は、潜在候補者だけではなく、むしろ(潜在)クライアントに対して自社の人材獲得への投資の大きさ(と結果としての人材の優秀さ)というメッセージングも兼ねていると考えられます。
事実、前回のエントリの冒頭でも書きましたが、コンサルティングに直接かかわっていない人でも「コンサルはアップ・オア・アウトで優秀な人しか残れない」というイメージは強く持っていることと思います。
当然、ほとんどのクライアントもこのような認識を持った上でコンサルティングファームの請求価格を見るわけで、そのような認識がない場合と比べて価格の受け取り方は大きく異なるはずです。
このように考えると、社内的かつ人事の仕組みの一つに過ぎない「アップ・オア・アウト」という仕組みが、コンサルティングのビジネスの根幹に深く根差した仕組みであることが見えて来ます。
アップ・オア・アウトとコンサルタントの自己認識
もう1点、アップ・オア・アウトが在籍している社員の認識にどのような影響を及ぼしているかという点にも触れたいと思います。
コンサルティングファームに入社する社員の多くは、入社する時点で自分自身の能力に自信があり、なおかつ高い成長意欲を持っている人たちです。
そういった社員にとって、「アップ・オア・アウトが存在する組織で生き残っている(=昇進をして複数年にわたり在籍している)」というのはそれ自体が大きな意味を持つ面があると思います。
直截な言い方をすると、「自分自身の能力に対する裏書き」であり、より大げさな表現をすれば「ビジネスパーソンとしてのアイデンティティ」を形成する大きな要素だと言えます。
これはコンサルタント自身にとってだけではなく、転職市場でも同じような意味を持っており、例えば「マッキンゼーに3年在籍して1度昇進を経験した」のであれば「マッキンゼーで通用した人材(アウトにならなかった人材)」として転職市場において高く評価されます。
「いつまでコンサルファームにいるか」というのはコンサルファーム内部の社員同士で非常に頻繁に交わされる会話ですが、コンサルの仕事に苦労していたり適性を感じていないような社員であってもほとんどの場合「一度は昇進してから転職したい」という声が多くあります。
こうした考えは、昇進を通じて自分自身の能力に対する自信を付けたいということと、それによって転職で有利になるという、上記の2つの面を背景にしたものだと思われます。
つまり、「アップ・オア・アウト」という制度は「アウトになるかもしれない」という側面に着目すると社員にとって大きなリスクですが、他方で生き残っている社員にとっては、自分自身の能力を自身および他者に証明するという意味があります。
これはさらに翻って、人材マーケットにおけるその組織の「ブランド」を高めることになります。
「この会社に入って3年生き残れれば大きな成長を得られる」という期待を醸成し、そういったイメージがさらに自信と成長意欲を持った新たな候補者を呼び寄せるという形です。
まとめと次回予告
今回のエントリでは、アップ・オア・アウトという仕組みがコンサルティングビジネスの根幹を支えるものであること、またコンサルタントの自己認識を大きく支えている面があるのでは、という点を考えてみました。
次回のエントリでは、アップ・オア・アウトというテーマの最終回として、この仕組みの近年の緩和傾向(あるいは形骸化傾向)がコンサルティングビジネスにおいて意味することについて考えてみたいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
