
第3回 特別支援教育の質向上のための実践~地域の特別支援教育実践事例共有~
子どもたち一人ひとりへの個別最適な学びの提供を目指して開発されたLITALICO教育ソフト。個別の教育支援計画・指導計画の作成をサポートするアプリ「まなびプラン」、授業で使える約7000もの教材を掲載する専用ウェブサイト「まなび教材」、特別支援教育に関する研修動画「まなび動画」の3つで構成されています。
本セミナーは、兵庫教育大学大学院学校教育研究科准教授である小川修史様より「モチベーションの支援」という観点で2人の生徒さんの実例をもとにした事例報告、またLITALICO教育ソフトを導入し、手応えを感じている明石市の特別支援教育についての取り組みについて明石市教育委員会髙田善彦様よりご報告いただきました。早速、2名の先生の発表を振り返ってみましょう!
開催日時:令和4年9月10日(土)10:00-11:30
場所:オンライン
参加者:約70名

第1部 特別支援教育質向上のための実践 誰もが楽しく学べる環境を作るには ~モチベーションの支援~
小川修史准教授(兵庫教育大学大学院学校教育研究科)

兵庫教育大学大学院学校教育研究科・小川修史准教授からは、主に「誰もが楽しく学べる環境を作るには〜モチベーションの支援」という観点から、2人のお子さんの実例をもとにした事例報告をしていただきました。
小川先生は文部科学省の委託で作られた「発達障害のある子供たちのためのICT活用ハンドブック〜特別支援学級編〜」を監修されています。講義は「Comment Screen」というアプリケーションを使った、参加者と双方向スタイルの楽しく学びある講義で、タイトルの文字通り、参加者の皆さんもモチベーション高く進みました。
見えない苦しさにどのように配慮する必要があるか?

文字がゆがんで見えたり、鏡文字化してしまうなど、読みに困難さ(ストレス)がある状態は、「プリント・ディスアビリティ(Print disability)」と呼ばれます。日本語では「印刷物障害」と表現されています。友達同士の日常的な会話は普通に楽しむなど、言語自体の習得やコミュニケーションの面では困難さがないのですが、プリントや教科書など、印刷物に書かれた文字を読んだり、文字を紙に書いたりする際に困難さが生じるのです。
講演では、実際にスクリーンに①正しく印字された文字②渦巻状に歪んで見える文字③鏡文字この3種が、同じ文章で5秒おきほどに映し出され、参加者のみなさんも障害当事者のストレスを体験しました。


なぜ特別支援教育という観点でICTが必要なのか

プリント・ディスアビリティを体験してもらったのは、「障害はこんなにつらいんですよ」と言いたいからではありません。例えば、ディスレクシア(限局性学習症/学習障害)は「読めない障害」「書けない障害」と勘違いされがちです。しかし、実際に体験して頂いてわかる通り、ストレスや時間はかかるものの、ゆがみ文字や鏡文字は読めたり書けたりするのです。
まずは過度なストレスがかかっていることを理解することが大切

障害のあるお子さんの多くは、読み書きを頑張ればできてしまうがために、過度なストレスがかかり、それをため込んでしまいます。まずはストレスを取り除く工夫をしなくてはいけません。この生徒は頑張って書いているのに自分で字が汚いというのはわかっている状態です。

書くのに時間がかかる子は、中学生ぐらいになるとノートテイクが間に合わなくなり、そのスピード感についていけなくなり、何をしてるのか、授業内容がだんだんわからなくなります。
普通、文字を読むときは内容の60%は読むこと自体にエネルギーを使い、残りの40%くらいを情景を思い浮かべることなど別のことに使います。文字を読むことに障害があるお子さんは脳のキャパシティの99%を読むことに使ってしまうので、勉強に集中できず、本来の学びが保証されていない状態です。
適度な困りは成長のためのエッセンス

私は、世の中にあるストレスをPositive StressとNegative Stressに分類しています。適度な困り(Positive Stress)は成長のためのエッセンスですが、過度なしんどさ(Negative Stress)は成長を阻害します。例えば、高校球児は甲子園などの大会に向け、三振してエラーして…と練習のたびに大変なストレスを抱えますが、一方で「練習すればうまくいく」という見通しもあります。このような「できる」という見通しを持ったうえで感じるストレスは、成長を促す適度なストレス、つまりポジティブなストレスといえます。
しかし、書字障害のあるお子さんが板書をノートに書く際、それを強いるのはそのお子さんにとってポジティブなストレスでしょうか?周りの子は書けているのに自分はかけていないという状況に追い込まれると、自分自身を卑下してしまいます。これは明らかにネガティブなストレスであり、成長を見込めないばかりか阻害してしまう要因にすらなるのです。
大切なのは過度なストレスを退避する、解消させること

本日のテーマである「モチベーション」を上げるために必要なこと、これはすなわち「ポジティブなストレスを提供すること」です。みなさんがゲームをやられる際、簡単なゲームはチャレンジせず程よく難しいゲームを面白いと感じると思います。モチベーションの源泉はそれと同じなのです。
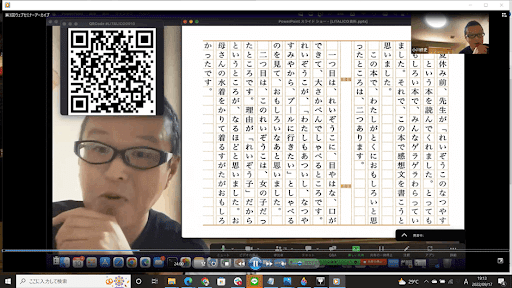
書字障害がある子であっても、キーボードのタイピングで文字を入力すれば、こんな作文だって書けるのです。今までは作文を書くことさえもできなかったのに、今はタイピングというツールを導入したため書くことができるようになったのです。ちなみにこのお子さん、作文を書く際、「何を書こうかすごく迷った」そうです。
今までと違って、頑張って書けば読んでもらえるのですから。鉛筆で字を書くという過度な困り(Negative Stress)を排除し、作文の内容を考えるという適切な困り(Positive Stress)を経験することで、成長につながり、このような成果を出すことに繋がりました。
「正しく困る」ネガティブな困りを解消するとモチベーションが生まれる

「正しく困る」ができるようになるために、ネガティブなしんどさを先に解消しなければならないのですが、通常の指導ではお子さんが直面する課題(前述の例の場合、手書き文字の練習)を先に頑張らせようとしてしまいます。
しかし、発想を転換し、先に手書きの困難さをタイピングで解消して作文が書けるようになると、今度は逆にお子さんが自分から手書きで書こうとするようになります。「先にパソコンでタイピングしておいて、後で自分でゆっくり字だけ書いて練習してみようかな」という風に、自律的に段階を追ってチャレンジするようになります。
モチベーションにフォーカスした指導

得意なことをちゃんと抑えて、そこに貯金を作って、苦手を克服していく事が大切になります。モチベーションとは単にテンションを上げて、ワーっと勢いでやるというものではありません。文部科学省の学習指導要綱もモチベーションにフォーカスして指導するよう改訂され、学習指導要領もガラッと変わってきています。ストレスの種類を部類分けするというポイントを押さえて、取り組んでいくことが大切です。
アクセシビリティ ユーザビリティ エンジョイビリティ


基本的に私は、インクルーシブ教育における指導を3つのモデル(アクセシビリティ/ユーザビリティ/エンジョイビリティ)で捉えています。
1つ目のアクセシビリティは授業に参加できるかがキーになります。2つ目のユーザビリティは分かりやすいかどうか。3つ目のエンジョイビリティはユーザビリティを前提とした楽しさ・喜び・幸福感があるか、誰にとっても面白いか、喜べるか、幸福感があるかという図式です。一見新しく難しそうに見えるかもしれませんが、まずはエンジョイビリティ(楽しさ)にフォーカスして欲しいのです。
ICT活用を難しくとらえず、まずは楽しく!

現場で教鞭をとる方は「生徒を楽しませる」といった内容を、普段全く考えていないということはないはずで、どうやって授業を楽しませようかということは日々現場で凄く考えながらやられていると思います。その延長線上にICT活用があるのです。
上記の提案は、まるっきり指導の方針を変えるというより、意識を少し変えるというだけの提案なのです。
カメラひとつでできる!「モチベーション支援」

ICT活用しなくては、と特に難しい捉え方をせずとも、もっと身近に捉えるといろんな実践で活用できます。
例えば、子ども達が掃除をしている様子をスマートフォンのカメラで撮影するだけで、「劇的ビフォーアフター」の様に、掃除をする前と後の違いを視覚的に比較できます。すると、自然に子ども達の掃除に対するモチベーションが上がりますよね。
また、自然観察でアサガオを観察する際、「アサガオには不思議な部分があります。みんなで見つけてカメラで撮ってみましょう」と伝えれば、子ども達は競うように写真を撮っていきます。このように、「子どもたちが勝手に動く」ことをどこまで尊重できるかどうかがカギになるのだと思います。
先生方は、とにかくお子さん一人一人の困りにフォーカスして、オーダーメイドの方針を先に思案します。しかし、その前に全体に使える汎用性のあるデザインを考えてみよう、という提案なのです。
カメラを使ったモチベーション支援の事例

モチベーションの支援は簡単で誰にでもできます。例えばこの生徒さんの場合、スマートフォンのカメラを構えて「ちょっと取材をさせて」とお願いしただけです。すると、自ら過去3年分の作品紹介をはじめました。

そしてカメラが回っているということを意識してなのか、突然作品作りをはじめ、頼んでもいないのにカメラの前で「どや顔」を披露してくれます。作業を始めたときは一体何ができるのかな?と思っていたのですが、たった30分でジェイソンのマスクと斧を段ボールで作ってしまいました。こちらでやったことといえば「カメラを構えた」だけです。

指導のユニバーサルデザインは思っているより簡単に作れる

こういったツールを使った工夫で叶えることができるモチベーションの支援は、担当しているお子さまの障害の有無にかかわらず実践することができます。困難さを克服する、個別のオーダーメイド指導内容を考える前に、全体で使えるデザインを考え、モチベーションの観点で先にアプローチしてみるという提案をさせていただければと思います。
LITALICOより
小川先生は、現在取り組んでいる「障害×ファッション」で世界に流行を生み出すという活動に取り組まれています。パリコレでショーを開催し近々渡仏の予定もあるとか。モチベーション高く精力的に活動されている姿は言行一致そのもの。研究の内容と重なるその姿に感銘を受けました。
第2部 教育委員会の実践取り組み事例ご紹介~明石市教育委員会・髙田善彦様

明石市教育委員会事務局・学校教育課主幹兼特別支援教育係長の髙田様より明石市の特別支援教育の取り組みやLITALICO教育ソフトの導入事例をご共有いただきました。
温暖で住みやすく行政サービスも好評な明石市

明石市は、東西に細長い小さい市ですが、人口は305247人、教育委員会管轄の学校機関は、小学校は市立28校、中学校が市立13校、それに加えて明石養護学校(肢体、知的)、明石商業高校で43校が該当します。明石市は温暖なところで、天文科学館、魚の棚商店街、明石焼きなど、美味しいものがたくさんがある、環境に恵まれたところです。人口増加率中核市第1位、住みたい自治体ランキング県内3位、全国戻りたい街ランキング第1位に選ばれています。保護者や子どもから選ばれているということですね。
明石市のやさしいまちづくり これまで、今、そしてこれから

こちらは明石市のやさしいまちづくりについての概要が分かる図になりますが、2014年から手話言語・障害者コミュニケーション条例、2015年から障害者配慮条例施行、合理的配慮の提供を支援する公的助成制度スタートさせ、2017年から共生社会ホストタウンの第一陣に推定され、2018年からは中核市に指定されました。今年度2022年は、あかしインクルーシブ条例を施行しました。インクルーシブは教育の分野だけではなく、街づくりにも活かしていくという意味合いで施行されました。

教育の分野でのインクルーシブ教育推進についても、インクルーシブ条例の12条にて謳われており、「(前略)、子どもたちが自ら多様なまなび方を選択できる環境づくりや専門的人材の育成に努める」という内容になっています。
明石市における特別支援教育にかかわる実態

毎年調査をしているLD・SLD(限局性学習症)、ADHD(注意欠如多動症)、ASD(自閉スペクトラム症)等の診断がある、またはあると思われる子どもの総数及びに肢体不自由等の子どもの数の合計は、明石市は12.4%です。全国平均の文部省の数字は6.5%とよく聞かれるかと思いますが、明石市はそれを上回る数字で令和2年度を境に高止まりが続いている状況※です。
※比較的割合が多い理由として、「(障害があると)思われる」という回答は現場の先生方の意見に基づいているということも考えられます。そのため、この数字だけが一人歩きしないようご理解いただければと思います。
また、現在の特別支援学級に在籍している子どもの数は、前年度に比べて2.7%の増加です。そして特別支援学級数も増えるに伴って新担任者も37名おり、特別支援教育に携わる先生方全体の25%を占めています。
2030年のあるべき姿(目指す10年後のまちの姿)

明石市の「SDGs未来安心都市・明石へ」というスローガンを具体的に教育ではどうするのかというところを今年度から運用されている「第3期あかし教育プラン」の中で定められています。その中にある三本の柱で教育施策を展開しています。
・誰一人取り残さない一人ひとりに寄り添った質の高い教育を行う
・子どもの学びと育ちをまちのみんなで支える
・持続可能な社会の担い手を育成する

質の高い教育とは

質の高い教育といっても人によって捉え方は千差万別です。明石市としては、子どもの充実した学びと達成感がある教育、違う学びの場であっても、特性に応じた支援や配慮を受けて、ともに充実した学びを得られる教育、違いを受け止め合い、共に生きることができる子どもを育てる教育が大切だと考えています。
明石市において質の高い教育を実現させるための施策

明石市では、確かな学力の育成を目指し、学習面での困難さを「学びに違いがある」ととらえ、背景となる特性の把握や学びに応じた支援を行います。また、学びの場の整備(教室環境整備、人的加配)教職員の専門性の向上、システムとして切れ目のない支援を行っており、個に応じた支援を可能にするクラス作りを基本に、UDの授業づくりを始めています。
明石市の特別支援教育の取り組み

令和元年度から、兵庫教育大学の井澤教授監修による「特別支援教育ハンドブック(三訂版)」の発行、令和4年度より「特別支援教育巡回指導の実施」にならんで、LITALICO「特別支援教育サポートツール」の導入しています。また、同令和4年度より「コグトレオンライン」の導入を開始し、1000アカウント付与しています。
それに加え「特別支援学級担任のためのハンドブック」の発行をしたり、特別支援指導員や介助員の配置をしています。介助員に関しては現在特別支援学級に在席する子ども6.5人に1人の割合で配置することができています。
市内全小中養護学校長が「教育相談員」に

明石市では昨年度は436件就学相談を受けています。保護者の意見と学校側が食い違っていたり、保護者が迷っていたり、客観的な根拠がない場合は、就学相談会に来ていただき、市内全学校長が「教育相談員」として関わっています。また、市内全小中養護学校長先生方には研修会に参加していただき、統一した判断をしていただいています。このように困っている保護者、お子さまの相談員として小中養護学校長が関わっているのは明石市の特長かなと思います。
子どもたちがいろんな学びの場で力を発揮できるようにこのような様々な施策を展開しています。
LITALICO「特別支援教育サポートツール」の活用


初めて特別支援教育をご担当する先生方にはいろいろな困り感があるかなと思います。教育委員会としては、保護者と子どものニーズを広く把握し、経験や専門性に頼りすぎず計画立案をすることが大切だと考えています。また、特別支援学級、通級から発信をして学校全体や明石市全体を高めていくことや、産学官との連携をして持続可能な支援体制を構築していくことを重要視しています。その背景からLITALICOが開発する「教育支援教育サポートツール」を導入、活用するに至りました。
LITALICOの会社理念と明石市が目指すところが一致

「特別支援教育サポートツール」導入の理由として、「障害のない社会をつくる」というLITALICOの会社理念と明石市が目指すところが一致したということも大きかったかと思います。また、数年前からこういったサポートプランが活用できないかと導入を検討していました。明石市にも実態を把握したデータというものは従来からありましたが、教材などを使って学びを促すツールや、研修動画などが一体で活用できるということは非常に魅力的でした。

効果検証 ~教員アンケート結果(特別支援教室の質向上)

こちらのグラフはシステムを活用していただいた先生にアンケートを実施した結果です(140名の先生より回答)。こちらを見ると、「具体的な目標を設定することができるようになりましたか?」という質問には85%の方が当てはまる/やや当てはまると回答しています。今までは、先生自ら自分が立案した考えを、実行できるのか、保護者に伝えることができるのかということに対して自信がなかった先生もいた、ということがアンケート結果を通じて理解できます。
また、特別支援教育歴3年以下の若手の先生およびベテランの先生と経験年数で分けてアンケートを取った結果、若手の先生はアセスメントと目標設定の連携の面で効果を発揮、ベテランの先生については教材の活用面で役立てていただいているということが分かりました。

特別支援学級を中心とした「質の高い教育」の実現のために

特別支援教育のハンドブックも作成して、特別支援学級から通常学級に働きかけるような取り組みもしています。「学校の中で一番困っているのが特別支援学級に在籍している子どもたち。その子どもたちが幸せでなければ、通常学級の幸せもない」という思いを込めた内容となっていると自負しています。


特別支援教育はすべての教職員で推進していくもの

なくてはならない支援策は、通常の子どもにとっても便利な支援策であるということを合言葉にしながら、教育委員会、先生方一体となって今後も頑張って参りたいと思っております。
LITALICOより
明石市での市全体でのインクルーシブ施策の全体像から教育委員会全体の施策のお話をいただきました。

髙田様よりお話しがありましたLITALICO開発の特別支援教育サポートツールである「LITALICO教育ソフト」は現在全国で50自治体様ほどにご導入いただいております。初年度は無償トライアルという形での導入が可能となりますので、「LITALICO教育ソフト」について気になる方は下記問い合わせ先よりお問い合わせくださいませ。
お問合せ先

TEL 050-3138-4614(平日9:30-17:30)
Mail iep_sys4school@litalico.co.jp
HP https://s-edu-soft.litalico.jp/
ご連絡いただいた個人情報は、株式会社LITALICOの個人情報保護方針に則って利用されます。個人情報保護方針に同意の上お申込み・お問い合わせください。株式会社LITALICOの個人情報保護方針はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
