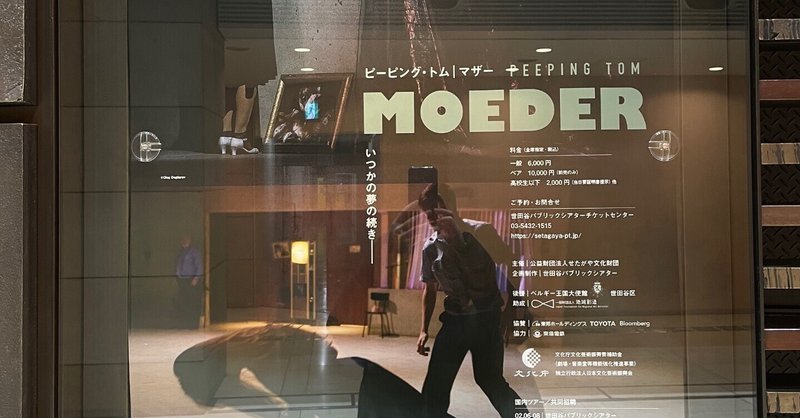
ピーピング・トム『マザー』の感想|死の絶対性が生きる者を襲い、波打つ感情は激しいダンスへと変わる
ベルギーのダンスカンパニー、ピーピング・トムの『マザー』を見た。
私は舞台芸術や演劇については素人なので、ピーピング・トムの公演を見るのは当然はじめて。まずは、ユーモアがふんだんに盛りこまれていたことに驚いた。
けれども、それと同じくらいに悲痛な感情が詰めこまれた作品で、生と死をめぐる表現は、そういう表現に対して最近、特に敏感になっている自分にとって、心理的にけっこうしんどくもあった。それほどまでに、かなしみ、怒り、苦しみ、痛みが、かなり激しく、生々しく、身体と音を使って表現されていたのだ。
『マザー』の中心にあるのは、タイトルのとおり、母、そして母性――妊娠、出産、母性愛と支配――なのだろう。実際、ちらしや劇評などではそのように説明されているのだから、明確に意図されている。おまけに、この作品は、2017年に日本でも上演された『ファーザー』と次作の『チャイルド』とで、家族三部作をなしているという。だから、今回は、「母」というわけだ。
しかし、その「母」というテーマ以上に、鮮烈に表現されていると感じたのは、生のよろこび(ジャニス・ジョプリンの“クライ・ベイビー”を歌い上げるシーン!)と死のかなしみだった。天と地のあいだを激しく上下するエモーションに、「母」というエレメントはそこまで感じなかった(ただ、これは、後述する観劇の環境の問題もあったかもしれない)。8人の主要キャスト、一般公募で参加した者を含めると16人もの出演者たちが舞台の上で表していたのは、母やその影、母性というよりも、徹底的に「感情」だったと思う。
「生のよろこびと死のかなしみ」と上に書いたものの、『マザー』には、どちらかというと、死のにおいが冒頭から濃厚に漂っていた。
死というものは、他者のものとしてしか、どうしたって経験しえない。主体が死んでしまったら、それは経験になりえないからだ。そこに、死に対する解決不可能な恐怖の淵源のひとつがある。
『マザー』では、他者の死が、生きる者にたびたび襲いかかってきていた。他者の死の圧倒的な暴力性、あるいは有無を言わせない絶対性は、生きる者たちの精神を激しく揺さぶり、波打たせる。動揺した感情は、ダンサーたちの身体で増幅されて、彼らを舞台の上で痙攣させ、転がりまわらせ、のたうちまわらせる。そういった負の感情というか、痛みやかなしみの表現のほうが、よろこびや諧謔のあたたかみよりも、ずっと強く勝っていたように思う。そのヘビーな痛みやかなしみの表現は、あまりにも痛烈で、目を背けたくなるほど、胸が締めつけられるほどだった。
それと、“F*ckin’ job!”という印象的なせりふが何度か繰り返されていたように、「労働」も『マザー』の大きなテーマのひとつだったと思う。
舞台の上に載せられていたは、掃除婦や、「展示物」として労働する者の身体だった。働く身体は、労働によって拘束・束縛されたり、逆に強制的に動かされたりする。その不毛さ、滑稽さ、奇妙さが、『マザー』では強調されていた。働く身体は、よく見るとおかしい――そんな観察が、誇張されて、ダンスにされていたと感じる。
いま触れた、「『展示物』として労働する者」の一幕が、どうにも忘れがたい。ほとんど裸だった彼が、半透明の幕を被せられて、それから床の上をじたばたと転げまわる場面があった。そこで彼を覆っていた乳白色の幕は、あきらかに羊膜のメタファーになっていて、裸の彼は新生児のようだった。幕=膜を被ったままもがき、あがくその姿は、ドレープの見事なうねりもあいまって、生身の身体のダンスとは異なる奇妙な印象を残した。
また、SCP財団のモンスターのように長い腕を取りつけた、助産師(看護師)がくねるダンスも印象的だった。『マザー』におけるホラー表現の巧みさは指摘しておくべきだろう。
照明の演出もすばらしかった。そして、それよりもすごかったのが、音響だった。飛び跳ねたり、なめらかにのたうちまわったりするダンサーたちの動きにあわせて、水を滴らせる音、金属を叩きつける音、破砕音などが、舞台上でつけられていた。これが、かなり独特な演出だった。
生々しくて緊張感のある音響を担っていた彼の役割は、フォーリー・アーティストというそうだ。フォーリー・アーティストを出演者に組みいれて、音響を壇上で演じさせてしまうなんて、他にあまり例のない試みだろう。
劇伴はノイジーで抽象的なものが中心だったが、その一方で、歓喜や弔意を表していたのは、オルガンとキャストによる歌だった。これは、実際のオペラ歌手が歌っていたとのこと。どうりで見事だと思った。
それ以上によかったのが、なんといっても、舞台美術だ。
ガラスやドア、幕など、舞台を隔てて区切る小道具が印象的につかわれていた一方で、そのベースになっていて、場面によって意味合いを変えていく壇上に建てこまれたセットが、とにかく圧倒的な存在感を放っていた。たとえば、飾り気のないステージの中央、舞台の中心は、美術館や邸宅へと場面ごとに変化していく。ガラスで仕切られていて、中が見えるようになっている奥の部屋は特に多義的で、葬儀場や分娩室、新生児室などに、激しく変容していっていた。まるで、死に場所から揺り籠へ、とでもいうように。火葬のための装置が舞台の上手でぐっと引きだされた時は、「あっ」と声をあげそうになってしまった。
そして、なによりも忘れがたいのは、めちゃくちゃ強い存在感を放っていたコーヒーマシーン。これが「マザー」のメタファーになっていると気づいたのは、かなりあとになってからだった。
ピーピング・トムの舞台美術はいつもすばらしいそうだが、それらは変幻していく空間にその都度強い説得力を持たせていて、ダンサーたちとおなじくらいに主役を張っていたと思う。美術がいやに現実みを帯びているからこそ、そのリアリティが、作品にマジカルなパワーをふりかけていたのだ。ただの真っ平なステージの上に、あれほどのものをつくってしまうなんてと、素朴に驚いた。
私はチケットを購入するのが遅かったから、席が2階席の後ろ側で、美術やセットのはたらきをちゃんと見られていたかというと、かなり微妙だ(視力の問題もあるから、パフォーマンス自体もしっかり見られていなかったかもしれない)。終演後に下に降りていって、観客がはけていく中、舞台をまじまじと見て、絵画が入れ替わっていた演出などにそこでようやく気づいたほどだった。
『マザー』については、このブログの劇評がとてもよかった。上演を見たひとは、読んでみてほしい。
2023年2月6日、世田谷パブリックシアター
帰りの田園都市線、山手線の車内で
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
