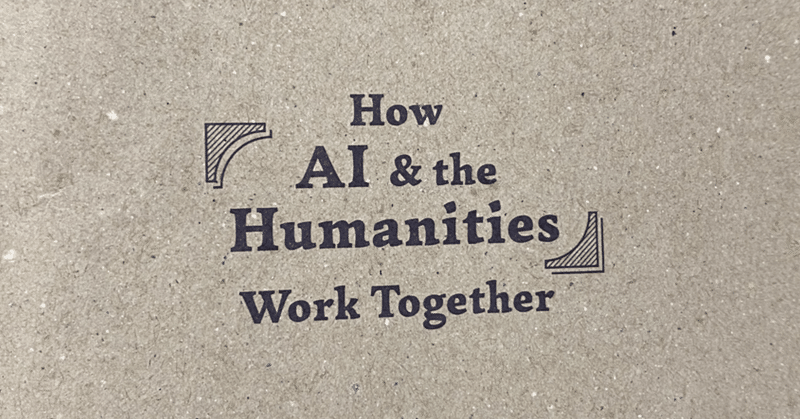
「文系AI人材」になる②
それでは前回の続きです。
前回はAIへの向き合い方、AI人材、AIの概略、キホンについて確認しました。
ではSTEP②から行きます。
◯STEP② AIの作り方
ここではAIの作り方をざっくり見ていきます。
そもそもAIとはどんなものでしょうか。
誤解されがちですが、AIはデータを丸暗記するわけではありません。数ある情報の中から法則を見つけ出すという作業をしています。
そのため、データにはないことが起きても法則に従うことで物事の対応・未来の予測(天気予報など)などが可能となっています。
つまりAIは「特徴掴みの名人」というわけです。
ではAIの作り方の手順について。
AIは「データ作成」「学習」「予測」の順でできていきます。
元となるデータをインプットし、どんな法則があるかを学習、そして与えられた課題に対して予測をはじき出すという流れになっています。
注意することとして、AIはデータに関する意味合いを理解しているわけではなく、数値で把握しています。
ここが、AIが万能ではないと言われるポイントです。感情に関しても数値化してしまえば、ある程度は対応できるのでしょうが、限界がありそうですよね。
そういった意味では、AIが本当の意味で自我を持つことは当分なさそうです。
そういえばAIが暴走する映画がありましたね。
今度見てみようかな。

◯STEP③ AI企画力
「人間が想像できることは実現する」
もしAI企画をする際はこのことを念頭に出来だけ多くの案を出すことが成功へと繋がるとされています。
またこの時に注意しなければならないのが
変化量と実現性(感性と論理の行き来)です。
そのことによってどれだけの変化を及ぼすことができるか(どれだけのコスト削減が可能か)、それは実現性が高いのかということを考え、どちらもバランス良く達成できることが望まれます。
その時、当然ながらAIを過大・過小評価しないことも重要となります。
またこの企画の解像度を上げるために、
5W1Hを考えることが必要となります。
何を、なぜ、どのタイプのAIで、どんなものを、どのようにして、いつまでにやるか。
AIに限らず、プロジェクトや企画ではこういった土台の部分を明確にしておくことで、どういうアプローチが必要になるかがわかります。大事にしたいですね。

◯STEP④ AI事例を知る
では今まで学んだことを活かして実際に企業で採用されている事例を見ていきましょう。
この本には45の事例が載っていますが、その中から一部を紹介します。
事例① ZOZO 類似アイテム検索機能
AIを活用した類似アイテム検索機能で滞在時間4倍に
→閲覧中の商品の形・色・柄などをもとにAIが似ている商品を検出し、一覧で表示
・Who 顧客のため
・Why 便利を増やす、売上を増やす
・Which 識別系AI👀×代行型
・What 類似アイテム検索AI
・AIができること
=色や形などで似たアイテムを探す
・AIによって解決されること
=これまで見つけにくかったアイテムの発見による売り上げの向上、似たアイテムの推薦による買い物体験の向上
事例② atama plus 学習指導AI
AIを使って「自分専用レッスン」を提供
得意、苦手、つまずき、集中状態、忘却度に合わせて
カリキュラムを最適化
解けない原因をAIが診断テストから特定し、原因から解消させる仕組み→10の3807乗パターンに及ぶ
・Who 顧客(学生・受験生)
・Why 便利を増やす
・Which 予測系AI📈×代行型
・What 学習指導AI
・AIができること
=1人ひとりのカリキュラムを最適化
・AIによって解決されること
=学習指導力の向上、1人ひとりに合わせた指導
◯文系AI人材が社会を変える
5G、IoTの普及によって今後ますますAIが発達していくと考えられます。データですべてがつながる社会もそう遠くない未来です。
消費者、社会、働き手に及ぼす変化は、みなさんも想像つくと思います。
例えば消費者目線だと、近いうち子供だけで乗れる車ができるかもしれません。
社会で見るとほんの30年前は手書きやFAX、公衆電話だったのが今ではパソコン、スマホ・タブレットが普通の時代になっています。
働き手で見ると営業のメール・電話は自動返答、作業もAIの指示に従うことが増えてくるかもしれません。
主にAIのメンテナンスが仕事、という可能性も。
私たちは新しい技術分野を発見したとき、そのコア技術や技術の中身に議論が偏りがちです。
しかし大事なのはそれをどう使うかということ。
AIを作る側は飽和しがちですが、使う側は果たしてどれだけいるのか、ということです。
よく考えていきたいところですね。
最後に
今回は新しい分野の学びだったので、とても時間がかかりました笑
しかし、得たものは大きかったと思います。
今までAIは自分とは近いようで遠い存在(主に仕組みなどに関して)だと思っていましたが、この本を読んでAIの種類、AIの作成方法や過程などを学んだことで、少し親しくなれたのかなと思います。
自分がする仕事はひょっとするとAIに奪われるのではないかという不安を伴った考え方が、どう一緒に働いていくかを考えればいい、に変わりました。
AIに操られないように、AIとどう付き合い、どう生きていくかをこれからも考えていきたいと思います。
では今回はここまで🙌
ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
