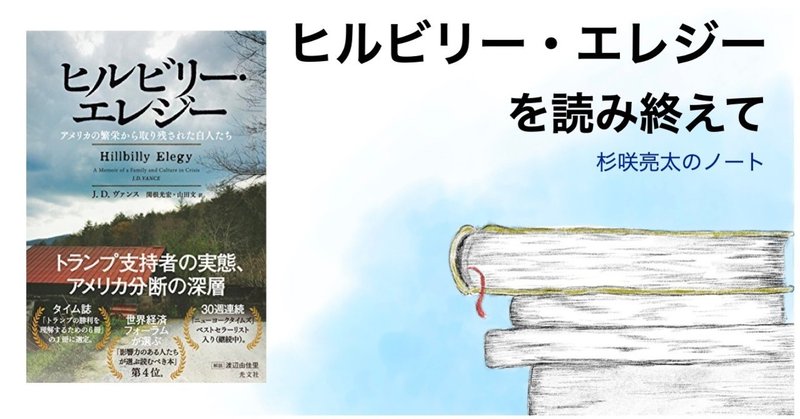
ヒルビリー・エレジーを読み終えて
こんにちは。
ヒルビリー・エレジー(J.D.ヴァンス著, 関根 光宏,山田 文訳/光文社)を読み終えました。
この本を手にとったわけ
当時(5月下旬)アメリカ社会で起きている分断の根源について知りたいと思い、本書を借りて読みました。
キッカケは、渡辺由佳里さんのTwitterを見てからです。「ベストセラーで読み解く現代アメリカ」の試し読みを読みました。当時はまだミネアポリスの事件が発生した直後で「Black Lives Matter運動」が広がりつつある背景の時期で、差別問題も格差問題も自分事ではありませんでした。
OPACで調べたところ、地元の図書館に本書があったので、大国が抱える大きな社会問題を知りたいという、極めて漠然とした興味のみで読み始めました。図書館で借りるという、今、読まなければならない環境も手伝い、のめり込む様に読みました。
読了後、本書を的確に評した渡辺由佳里さんのblog「洋書クラブ」の以下のエントリー記事を読みました。渡辺さんの記事をお読み頂ければ、アメリカ本土、現地からの生々しい実情の片鱗を感じとることが出来ると思います。
また、現アメリカで起きている大きな潮流は、渡辺さんの記事をいくつかお読みになるか「ベストセラーで読む現代アメリカ」で詳しく解説されています。
少し偏った紹介になってしまいましたが、他にもアメリカが抱える日本人が知らないカルチャー、アメリカの実情を記した新書も沢山ありますので、そちらをご参考頂ければと思います。
***
私の記事では、私が感じたことのみ述べたいと思います。
あくまでも私個人の見解であり、本書、関連する書籍、関係者とは一切関係ありません。
なお、冒頭にある「Black Lives Matter運動」に起因する社会問題は本記事では書きません。私も日本国外にカルチャーショックを受けたことはありますが、微量程度です。日本意外を知っている訳ではありませんし、アメリカは行ったこともありません。
今回の事件、デモで亡くなったり、怪我を負われた方にお悔やみと、お見舞いを申し上げます。
ただ、貧困(特に教育格差)については、いくらかの経験を持って意見出来る立場にあると思います。まずはその背景から。
私の中の貧困
少し、私の生い立ちを説明しないと説得感がないかもしれません。
私の人生背景は、以下のキーワードでなんとなく理解できると思います。
・工業高校卒
・家庭の道徳観としてのパターナムな教え
・団塊ジュニア世代、時代背景
(とくに10代を1980年後半から1990年前半に過ごした)
私は公務員の長男として生まれました。そしてきわめてパターナムな家庭環境で育てられました。父は絶対的な存在として教えられたこと、長男としての役目、家(特に名家という訳でもないのですが)を継ぐということを教えられました。裕福ではありませんでしたが、逆に景気に左右されることは無く、割と安定した家計家庭であったことは間違いありません。団塊世代のサラリーマン家庭ゆえに、資産も特にありませんでした。車とささやかな家ぐらいです。
環境的な影響として、農家と小作人時代の名残があった気がします。故に、裕福な子と、明日の食べ物もままならない子もいました。今より格差が大きく、いじめも日常的に行われているのが当たり前でした。中途半端な立場にいたことと性格も手伝い、いじめられたし、いじめる側に立ったこともありました。そして親が離婚して名前が変わった友達、引っ越してしまう友達もいました。近所まわりの大人達は地域と地域で争い事があったり、貧困による自殺があったり、夜逃げ、DVなんかも垣間見えていました。
両親は教育熱心な人ではありませんでした。逆に勉強しすぎると心を病んでしまうと考えているような人です。今でもそうした言動があり、時折そんなことは心配ないと言っているぐらいです。
今。思えば、当時養われるべきだった思慮が足りない原因がこのへんにありそうだと思います。
しかし、それは両親の責任でもありませんし、過去の私の怠慢でもないでしょう。そういう社会環境で育っただけで、今にして単に「アンラッキーだったのかも」と思うだけです。仕方ないとか、後悔も、言い訳もありません。
30歳後半まで、ろくに本も読めませんでした。「読書=漫画を読むこと」でした。2008年のリーマンショックにそれまで働いていた会社が整理され、一夜にして無職になります。
この時に行ったハローワークというふざけた名前の施設に充満した空気感は一生忘れないでしょう。就職させる気の無い役人、ピリピリ感、罵声、怒号。狭い駐車場に車が停められないぐらいに人が集まり、言い争い、喧嘩をしている景色を何度も見ました。そんな空気感に怯え、虚勢をはらないと食べることができない時代でした。
そして、なんやかんや縁があって今の会社(これまでの会社、職場に比べれば天国のようなホワイトな会社です。)に就職します。
勤めはじめた職場(異動しているので、今の部署ではありません。)で味わったのはカルチャーショックと学力コンプレックスです。周りのメンバーは大卒は当たり前、院卒、博士も何人かいました。まぁ悪くいえば軽く学歴差別されました。それでも前職より天国に思えたのは事実です。会社に対して感謝あれど恨み辛みはありません。学力コンプレックスは自分の中の当然の報いだと考えていました。
そして、会話を重ねていく過程で、就職はコネが大きいという事実を知りました。それまで、就職は実力で勝ち取るものだと思い込んでいましたが、実情はそうではないことを学びました。リクルーターという言葉を初めて知ったのも今の会社です。(このへんも本書で軽く触れていますね。)
当時、会社で生き残るためには、人一倍考え、働く必要がありました。そうしないと食べていけない環境だったのです。積極的に働きました。働くことがありがたいことでした。そんな中、会社でメンターに出会います。彼が教えてくれたことは、経験人生観と読書です。
私の人生の背景にあるのは昔からある田舎的な格差社会と学力コンプレックスを持つ自分がいるということです。今は、決して裕福でもありませんが、とくに極貧でもありません。
そして、地域も大きく変わりました。
地域で争っていた大人たちが歳をとり、私ら世代の子供が都会に離れ、ひとり暮らしのお年寄りがたくさんいます。
今も地域の寄り合いに行くと過去の武勇伝を何度も聞かされます。
地域も新陳代謝が進み、新しい家が建つ度に過去にあった格差は無くなってきました。代わりに、若い中級サラリーマン家庭が増えました。
地域も会社も社会も全てが微妙なバランスの上に立っていて、じわりじわりと寄りつつあるコロナの影響は、これから現実味を表してくるでしょう。
私は常に崖っぷちを歩いている人生です。崖から落ちたことは一度ではありません。それは今も変わりません。私のような後ろ盾が無い人間は簡単に斬られるのが世の常です。それは経験と歴史小説が教えてくれました。
本書と一番違うのはドラック問題です。私の周りでは聞いたことがありません。このへん日本はまだ平和であると感じました。
貧困が生み出す負債
本書の著者は努力と学びによって、今の生活(弁護士という職業、理解してくれる良きパートナーの存在、具体的に書かれていませんが年収も私よりはよいでしょう。)がありますが、だいぶ稀なケースであると思っています。この本はある種のサクセスストーリーです。そして貧困の本質を的確に指摘している点に、多くのアメリカの裕福な人たちが興味を持ち、読み始めたと思われます。
貧困、裕福と言葉を使いましたが、その間には中間が存在します。
中流階級、中流家庭、中流層といった言葉たちは、貧困と裕福の重なり合った部分として考えています。中流層は、貧困の属性と裕福の属性を合わせ持った層といえます。
一言で貧困といっても、複雑なレイヤー、ポジション、ペルソナ、依存性、時間的変化があり、4次元的に複雑でカオスです。(おそらく同じ様なことは裕福な人たちにも言えることでしょう。裕福になったという自覚が無いので分かりませんけど。)
一般的に、貧困を年収で括ってしまう見方もありますが、これは分かりやすくするための指標のひとつに過ぎません。年収についても本記事では本質では無いので対象としません。しかし問題を考える上で重要なファクターであることは間違いありません。
貧困について確実に言えるのは「貧困は人に宿る」ということです。
教育格差は貧困を生み、貧困は教育格差を生み出します。
貧困が人に宿ると、ある要素として言動に現れます。
貧困特有の行動パターンや感情、理論、モノゴトが見える/見えない、出来る/出来ないといったパターンであるていど見極めることができます。
あくまで私の主観であり、他の人全てが必ずしもそうであるとは考えません。ある場合もあるし、ない場合もある。ある時もあるし、ない時もある。というように、非常にあいまいで複雑な問題だと私は認識しています。
私が体験した、貧困の人は以下のような特徴があります。
・本が読めない
・学ばない、覚えない
・整理ができない(汚い)
・言葉が雑
このリストはフローになっていて、読めない→学ばない→整理できない→言動が雑につながります。これらが永遠とサイクルするときもあれば、複雑に時/場合によって、ひとつが顔を出すということもあります。
本書では、こうしたエピソードがたくさん書かれています。言葉遣い、行動、考え、教え、信条など。貧困特有の言葉が多く書かれています。
それらパターン要素が重なり続ける状態に置かれると、いくら貧困を脱出しても、心に消えない負債を背負うことになります。
本書に共感する理由
本書の概要は、原題「Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis」に書かれている「文化と家族の危機」という言葉に全てが込められています。
本書を読み終えて、一番最初に感じたことは「私もヒルビリーなのだ」ということです。
本書の私のポイントは2つあります。
・貧困から抜け出す過程における回想が細かく書かれており、
どうすれば貧困から抜け出せるか重要な事例が書かれている。
・一度体験した貧困は人を蝕み、簡単に抜けられない。
ゆえにこの本から、まだまだ学べる点があると感じ、購入に至っています。
本記事で述べたいのは、貧困の問題の複雑さ、カオス、矛盾を伝えたいと考えたからです。
私がこの本を読んで一番共感したのは、第15章の最後のエピソードです。(P381〜P383)
著者がパートナーとドライブしている時にクラクションと共に割り込みされるシーンです。自制心とパートナーの抑制によって、事なきを得た時の文章です。以下、引用します。
”車から降りなかったのは、正しい判断だったと思いながらも、その後、数時間にわたって、だが、私にとってこれは進歩なのだ。刑務所行きは、あの大ばか野郎に安全運転を教えてやる代償としては高すぎるのだから。”
この本の本質がこの言葉に全て込められています。コトから数時間、著者は考え続けます。本当にそれが良い行いだったのか?
しかし、今の自制心に照らし合わせれば、代償としては高いのは明白です。正しいことに対して悩んだあとが行間から伺えます。
例えば、その場で、加速し追い抜き、割り込みをし、相手に同じ処遇に合わせることも、追い抜きざまに中指を立てて睨みつけることもできたのです。
そういうことが出来てしまうのが貧困の負債の成せる業なのです。怪物のような闇を背負います。その怪物と対峙する時間が必要になるのです。
それが出来ないと崖から転落して、また元に戻るのにものすごい労力を伴います。
同じ場面を私自身も受け、同じ体験があるから、ものすごく分かるのです。このなんともない些細なエピソードが一番心に刺さりました。
一度受けた貧困体験は、中流層に抜け出せたとしても、一生の負債を抱えるのです。これは薄くなることはあっても消えることはありません。
何かのタイミング、例えば疲れていて、嫌なことが積み重なり、とにかく状況がどうにもいかない時に、悪魔か怪物のように心を覆い尽くす瞬間がくる可能性があるのです。
教育を受けていないものは、一生この負債と負のサイクルを繰り返し、人生を終えていきます。著者のように、勉学に励み、軍隊で自制心を養ってもなお、この負債と葛藤すると教えられたのが、本書なのです。
終わりに
本書は、貧困にある人、格差を感じた人、勉強嫌いな人にこそ読まれるべきでしょう。
貧困や格差意識の無い幸せな人が読んでも、共感も無いでしょう。興味の対象にしかならないと思います。
そして、この貧困という負債を負うのは今の自分自身であり、誰でもありません。まして過去の自分を問い正しても解決しません。その瞬間、瞬間に受け入れ、数時間悩み、それでも正解だったと自問しながら生きることしか解決しないでしょう。もしくは、今の積み上げる努力や研鑽が未来に活きて初めて解決するかもしれません。そう、信じたい自分がいます。
私がこうしてnoteに本の記事を投稿出来るのは、(程度が低くとも)本が読めるようになったからです。今の会社でメンターが出来、彼が「本は身を助ける」ことを教えてくれたからです。
馬鹿で、思慮が足りず、余計な厄介事を持ち込む、取り柄も特徴もない人間が生きていくのに、読書は助けとなり、教えてくれます。人から教わることは、読書の影響を受けて初めて理解につながります。読書が先です。そうした読書による知識がないとその人の言ったこと、行動が理解出来ないからです。
本を読みましょう。
自分を成長させるために。貧困が生み出した怪物から自分を守るために。
本書が私に与えた影響は、ものすごく大きく、そして、年下の著者の彼がこれからも時折、自分の中の怪物と戦いながら、パートナーとの生活、子育て、親との関係など、しがらみにまとわりつきながら、懸命に生きるでしょう。
そして、私も日々この怪物と戦い、そして貧困を限りなく薄めていく努力をしていかなければなりません。
貧困について、本気で抜け出したいと思うならば、本書をお勧めします。
お金が無くとも今の人生が楽しいのなら、それはとても幸せなことです。それは貧困に値しません。
---
20200620:新規作成、投稿
---
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
