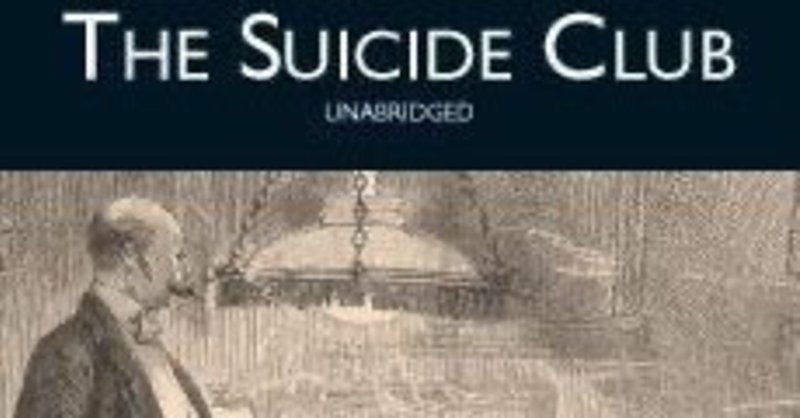
原書のすゝめ:#23 The Suicide Club
子供の頃に読み忘れた作品の一つ、『宝島』。
大人になってから読んだ気もするが、むしろ覚えているのは『ジキル博士とハイド氏』の方だ。
どちらもロバート・ルイス・スティーヴンソンの作品である。
スティーヴンソンは、スコットランドのエディンバラに生まれた。
父トマスが灯台建築技師であったためか、エディバラ大学ではエンジニアリングを専攻した。その後専攻を法律へ変更し、弁護士資格を取得する。のちに、以前養生のために訪れたことのあるフランスへ渡り、そこで十歳年上のアメリカ人の既婚女性ファニー・オズボーンと知り合った。彼女には既に二人の子供がいたが、夫が病気になり離婚、1880年二人はサンフランシスコで結婚した。
その後もスイス、フランス、イギリスと居所を移しながら、1888年ヨットで南太平洋の旅に出る。この体験が『宝島』へと繋がったのかと思いきや、フランス滞在中の1883年に出版されていた。
生まれつき病弱で、若い頃に患った結核療養のため各地を転々としたスティーヴンソンだったが、1894年脳溢血で44歳の生涯を閉じた。
今回の作品は、南仏で過ごしていた1882年に出版された『新アラビヤ夜話』に収録されている「自殺クラブ」という短編である。
The Suicide Club
One evening in March they were driven by a sharp fall of sleet into an Oyster Bar in the immediate neighbourhood of Leicester Square. Colonel Geraldine was dressed and painted to represent a person connected with the Press in reduced circumstances; while the Prince had, as usual, travestied his appearance by the addition of false whiskers and a pair of large adhesive eyebrows. These lent him a shaggy and weather-beaten air, which, for one of his urbanity, formed the most impenetrable disguise. Thus equipped, the commander and his satellite sipped their brandy and soda in security.
三月のある夜のこと、二人は霙が急に降り出したので、レスター広場に程近い牡蠣料理店に駆け込んだ。ジェラルディン大佐は、身なりと化粧で落ちぶれた新聞記者風情に身をやつし、王子の方は、いつものように太くてモジャモジャした付け眉毛と、頬に付け髯をして変装をしていた。そうするとむさ苦しく無骨な感じになるので、これは王子の洗練された雰囲気が最も見破られにくい変装なのだった。こうして変装した主従は、安心してブランデーのソーダ割りをちびちびやっていた。
ブラッド・ピット主演の映画に『ファイト・クラブ』というのがあった。私は見たことがないのでストーリーは知らないが、「闇のクラブ」というのはどうやら人の心を惹きつけるものらしい。
フランスの作家ローラン・ビネの『言語の七番目の機能』に登場する「ロゴス・クラブ」も然りで、こういう秘密クラブや秘密結社は、どこかフリーメイソンに纏わる数々の逸話を思い出させる。
さて、上記の場面について少し説明すると、ボヘミアの王子フロリゼル王子と腹心のジェラルディン大佐がお忍びでロンドンにやってきていたのだが、急な雨に降られて牡蠣料理店へ駆け込んで一杯やっているという冒頭の場面である。
そのとき、店内の客たちに無料でクリームタルトを配っている奇妙な青年から話しかけられ、興味をもった二人は青年を夕食に招く。その青年から「自殺クラブ」なる秘密クラブの存在を聞かされ、王子と大佐は自殺願望者を装って青年から話を聞き出そうとする。
* * *
“You are the men for me!” he cried, with an almost terrible gaiety. “Shake hands upon the bargain!” (his hand was cold and wet). “You little know in what a company you will begin the march! You little know in what a happy moment for yourselves you partook of my cream tarts! I am only a unit, but I am a unit in an army. I know Death’s private door. I am one of his familiars, and can show you into eternity without ceremony and yet without scandal.” They called upon him eagerly to explain his meaning. “Can you muster eighty pounds between you?” he demanded. Geraldine ostentatiously consulted his pocket-book, and replied in the affirmative. “Fortunate beings!” cried the young man. “Forty pounds is the entry money of the Suicide Club.” “The Suicide Club,” said the Prince, “why, what the devil is that?”
「あなた方こそ私が求めていた人たちだ」
と、男は浮かれすぎるほどはしゃいで叫んだ。
「お約束の証にどうか握手を」(その手は冷たく、湿っていた。)
「お二人はどういう仲間と行進を始めるのか、少しもご存じない。私のクリームタルトを召し上がったことがどれほど幸運なことだったかもご存知ないのです。私は単なる一兵卒に過ぎませんが、軍隊における一兵卒なのです。私は死神の裏口を知っている。死神の使いの一人で、儀式も醜聞もなく、あなた方を来世へご案内できるのです」
王子と大佐は、その意味するところを説明するようにせがんだ。
「お二人で80ポンド、ご用意できますか?」
と男は尋ねた。ジェラルディン大佐は、これ見よがしに紙入れを探り、できると請け合った。
「幸運な方々ですな!40ポンドというのは『自殺クラブ』の入会金なのです」
と青年が言うと、王子は、
「自殺クラブだって? 一体なんだね、それは?」
と尋ねた。
青年によると、自殺クラブというのは夜毎の会合で開催されるトランプゲームで、殺す者と殺される者を選び出すという恐るべき秘密クラブであった。自殺クラブに入会するためには、会長と対面し、誓約をしなければならないという。
こうして、フロリゼル王子とジェラルディン大佐の冒険が始まったのだった。
現代でこそ、この手の冒険小説やスパイ小説は当たり前のようにあるが、この作品が19世紀後半に既に出版されていることは驚きである。
スティーヴンソンは、他にも『The Black Arrow : A Tale of the Two Roses』や『The Master of Ballantrae : A Winter’s Tale』といった歴史小説も執筆しているが、これらについては、原書を読み終わったときにご紹介したいと思っている。
本書の邦訳は、以前岩波文庫から出版されていたのだが、なんとなく買い損ねてしまっていた。既に原書で読んでいたため邦訳は必要ないだろうと思いながら検索していると、以下ような書評を見つけて、いささかショックであった。
この商品では(中略)旧漢字使用で、文字が擦れ気味で印刷自体汚い。こんなシロモノ(商品)を安易に売りつける出版社の姿勢には疑問を感じます。この出版社は、あまりお客様の気持ちというものを考えて、商品を出版していないと思います。
ということで、このレビューを書かれた方は別の出版社の作品を購入するよう勧められているわけだが、その気持ちはまんざらわからなくもない。
しかし、そもそも岩波文庫のリクエスト復刊とはそういうものであって、読者のリクエストに応じて改版せずに重版していただけるという非常に有難い本なのだ。
実は私も過去に二度ほど重版の依頼をし、実際に復刊していただいたことがある。私個人のリクエストによるものか、ほかにもリクエストがあったものかはわからないが、出版社のサービスにこれほど感動したことはなかった。もともと発行部数が少ない同社の作品を初版のまま味わえる喜びは例えようがない。
別の日。
書店で同じ作家の出版社違いの本が、並んで平積みされていた。母親が女子高生らしき女の子にどちらの本がいいかと聞いているのを小耳に挟み、「ここは絶対に岩波文庫やろ」と密かに思っていた私は、
「あっちの表紙のデザインは暗いから、こっちにする」
と言って、彼女が別の出版社の本を手に取るのを見たとき、思わず腰が砕けてしまった。
そうなのか。
岩波文庫は暗いのか。
あの表紙の右に出るものはないと固く信じていたのに。
きっと私は少数派なのだ。
今までもそうだったし、おそらくこれからもそうなのだろう。
だから私が好きなものはいつだって絶滅危惧種に認定されてしまうのだ。
※ローレンス・スターンの『センチメンタル・ジャーニー』のリクエスト復刊↓

<原書のすゝめ>シリーズ(23)
※このシリーズの過去記事はこちら↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
