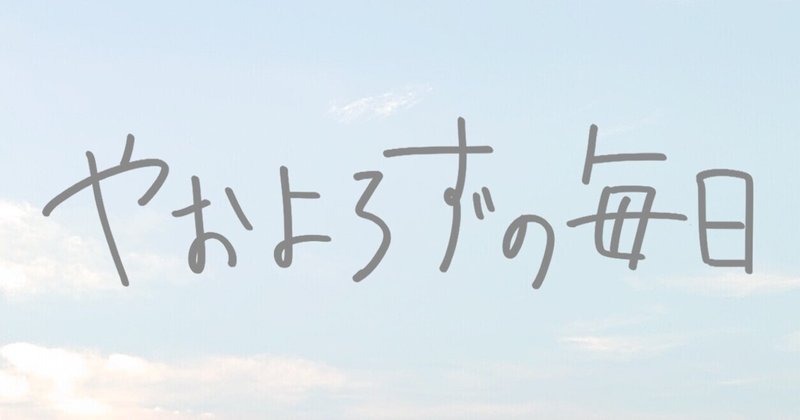
ATNコーポレーション
高層ビルの48階、大きな窓から見えるのは規則正しく並んだビル群と、どんよりとした曇り空のパノラマだ。蒸し暑い外とは違い、冷房で快適な温度が保たれたここは、オフィスの会議室である。
そこでは1人の女性社員が机の上のノートパソコンのキーボードをたたき、データをまとめている。首からは『ATNコーポレーション』、『横山』と書かれた社員証をさげていた。
コの字型に机が並んだ会議室の床には、男物の革靴が1つ落ちていた。横山は特に気にもしていない様子でパソコンと向き合っている。エンターキーをてんてんてーん、と派手に押し、顎に手を当て考え込んだあと、またキーボードを打ち始めた。
少しするとオフィスカジュアルな服装をした男が、お疲れ様と言いながら会議室に入ってきた。彼の首には彼女と同じく社員証がかけられている。違うのは名前の欄に『森戸』と書かれていることだけだった。彼は床に転げていた靴に、右足を入れた。
「お疲れ様です」
「いやぁ、しかし7月入ってから暑いなぁ」
「そうですねぇ」
横山はタイピングする手を止めずに、上司である森戸の話を聞いていた。
森戸はぱたぱたと持っていたバインダーで仰ぎ、汗ばんだ顔を少し拭う。気温はまだ真夏日というほどではなかったが、蒸し暑くてだるい。ひと通り涼むと、森戸はバインダーに挟んであった資料の1枚目を確認し、横山にそれを伝えた。
「あ、東京、H+1で。どう? 順調」
「いやぁ今日も報告遅れ気味ですね」
東京H+1。彼女はそれを聞いて、情報を打ち込む。
森戸は部屋の中をウロウロしながら続けた。
「どこ遅れてるの?」
「北海道支部です」
「まあ、あそこは広いから多目に見てあげないとなぁ」
「地域差もありますもんね」
会話をしていると、森戸は横山がキーボードを軽快に叩きながら、自分を見つめていることに気づいた。確認するためと言っては何だか、彼は必要以上にウロウロと会議室を歩いてみる。すると彼女は、じっと森戸のことを目で追いながら文字を打ち続けた。
「横山、ブラインドタッチすごいな」
「話は目を見て聞けって、学校で習いましたから」
横山はてんてんてーんと派手にエンターキーを押すと、ぱぁっとした笑顔で森戸を見た。
「そうかもしれないけど、えっぐいくらいこっち見てんな。まぁ会議始めようか」
「はい」
森戸は重なったバインダーの資料をペラペラと確認しながら話し始めた。
「社員への聞き取り調査の結果、データの不足不備、効率の低下により残業や休日出勤が増えている。ATNコーポレーションとしては、業務形態の変革を行いたいと思う。であるからして今日の議題は――」
森戸が話を進めているなか、横山はポケットに入れていたスマートフォンを取り出した。どうやら着信があったようだ。声には出さず、すみませんとジェスチャーをし、電話に出た。
「はい、もしもし。え、東京のデータが足りない? あと何件です? 2件分かりました。今データ作って送ります。はーい。おつですおつです、おーつでーす」
その様子を見た森戸が心配そうに尋ねた。
「どうした? データ2件足りないのか」
「はい、部長まだいけますか?」
そう聞かれた森戸は左足を床に打ちつけると、口の片側を上げニヤリとした。
「てやんでい、ばーろうちくしょう」
「わ、江戸っ子! 生粋の東京のデータ取れますね。ではでは……」
横山は椅子から立ち上がる。2人は会議室の端の方まで移動し、目を合わせながらこくりと頷いた。
森戸はすうっと息を吸い、せーのと掛け声をする。
『あーした天気になぁれ!』
2人は一斉に左足に履いている靴を飛ばした。2つの靴はふわりと弧を描き、床を転がり、ぴたりと止まった。どちらも表を向いている。
「晴れ2つだな」
「はい、H+2で送ります」
それを確認すると、2人は片足跳びで向かい、お互いの靴を手際よく履いた。
横山は再び椅子に座ると、資料を添付したメールを送ろうと、パソコンにデータを打ち込み始めた。
ATNコーポレーションは、日本中の靴飛ばし、いわゆる『明日天気になぁれ』の統計を集めて、天気を決定し実行する政府機関の企業である。
表では雨具を売る会社を謳い、社屋の正面玄関には、ブロンズ製のマスコットキャラクターのてるてる坊主が飾られている。
2人はその中の、明日の天気を決定する天気決定部に所属している。靴飛ばしのデータは午後6時に締め切られ、天気を決定したあとは、雲を作る部署、風の流れを作る部署など、様々な部署へと早急に繋ぐ。
「いやぁ、しかしデータ不足多いなぁ」
「残業の要因ですね。もう靴すぐ飛ばせるよう、ほら。ずっと踵踏んじゃってますよ」
横山はそっと机から足を出し、森戸に見せた。零れ落ちそうなパンプスの踵は踏まれ続けているからか、ふにゃりと柔らかくなっている。
「あーあー傷めるだろうに」
にやりと笑って横山は足を机の中に戻し、またキーボードを打ち始めた。
メールの文面の終わりには定型文として、自分の名前や部署が自動で打ち込まれる。
横山はそれを見て、ふと森戸が気になった。
「そういえば、部長は社名が変わる前からの古株ですよね?」
「あぁ。『あした天気になあれ興業』の頃からだ。あのときは下駄だけだったから、天気を決定するのも楽だったな。今じゃ流行に合わせるのも一苦労だわ」
横山はメールを送り終えたようで、ノートパソコンを閉じた。作業で固まった肩をほくずように少し伸びをした。
「下駄は飛ばしやすいうえに、安定して転がりますもんね」
「スニーカー、サンダル、スリッポン。いろんな靴が海外から入ってきたが、あれは大変だったな。クロックス」
「あれほぼほぼ表向きますよね?上の部分のクッション性高いから」
森戸はうんうんと何度か頷く。クロックスの構造を研究するため、何度も飛ばしたことを思い出した。裏を向いた方思うと、弾んで表になってしまうのだ。
「そうなんだよ、晴ればっかり。クロックスが流行った夏は、世界でいちばん暑い夏だったろ」
「わぁ〜、プリンセスプリンセス〜」
「あとグラディエーターサンダルってやつ? あれはデータとれなくて、キツかったな。何だよ、あのふくらはぎをも覆い込むやつ」
森戸は手で握るようなジェスチャーをして、眉をしかめた。
「子供にまで流行ってましたもんね」
「子供は瞬足履いとけよ〜」
「ぶっちゃけありがたいですけどね、その方が」
「だろう?お天気を決定する、これはデータが命。予報より統計だな」
森戸は持っていたバインダーを振りながら、力を込めて横山に言う。
長年勤めていると、吐露したいことは山ほどある。だが、嫌なことでありながら懐かしくも思えた。
「ただそのデータの不備が残業の原因ですけど」
横山のその言葉に森戸は、うーんと唸った。結局のところ大事なのは残業をなくすことなのだ。
「そうだなぁ……表か裏かだけにする? 晴れか雨か」
「ちょっと、今データ命って言ったばかりじゃないですか! 側面の曇りのデータ大事なんですよ! 雲の流れを見て、誰もが晴れか雨か分かったら、気象予報士が食いっぱぐれるんですよ」
「確かに仕事なくなるな。気象予報士は、曇りところによっては雨でしょう、みたいな曖昧さでTVに出るのがいいもんな」
さっきと真逆のことを言う森戸に呆れながら、横山は口を尖らせる。
そして窓の外を指さして続けた。
「曖昧こそ、んんんんまままま、予報的には、曇ってるけど晴れっちゃぁ晴れ、が生まれるんですから」
「そうだな、大事だな。折りたたみ傘を持ち歩きましょう、も最高の曖昧だよな」
「あぁ、いいですねぇ」
機嫌を損ねてしまったかと、森戸は少々焦っていたが、横山はよき曖昧具合に、にこりとしながら頷いた。
「俺、今日持ち歩いてるもん、折りたたみ傘」
その言葉を聞いて、横山は大きく目を見開き、森戸を覗いた。
「え、今日雨降らないこと決定したの、部長ですよね」
昨日のデータの統計で、今日はどんよりとした曇りに決定しており、実行されている。データの最終確認をし、決定のハンコを押すのは部長である森戸の仕事だ。
「うん今朝な、玄関出たとき降りそう、って感じたからつい鞄に、ね」
森戸は照れながらおちゃめそうに言い訳をした。部長職の照れほど、癪に障るものはない。
「確実にいらないの分かってたら、いくら折りたたみでもただの荷物ですよ!」
「いや晴雨兼用だから日傘として日差しも防げるぞ〜」
「降りそうって思ったなら、今日曇りですよね。日傘いらないですよね」
「……おうっとぉ!」
「おうっとぉ、って」
まだ少しかこつけられるかと思ったが、何も浮かばなかった森戸は、この話はここで終わりだと言うかのように、大きな声でごまかした。
「いや気分だな、気分」
気象予報士達は、この会社が天気を決定しているとはもちろん知らない。ATNコーポレーションが作り出した雲の動きを見て予想し、新聞やTVで当てたり外したりを繰り返している。もしこの事実が世間に流れたりしたら、なんと滑稽なことだろうか。
「そういえば、開発部がスマホ向けのアプリ出したことは知ってるか?」
森戸はポケットからスマートフォンを出すと、横へスクロールし、インストールしたアプリのアイコンを探した。
「あぁ、出すみたいな話は聞いた気がします」
「天気予報アプリだって」
「天気決めてるの我々ですから、100%当たりますよね?」
横山はまた怪訝な目で森戸のことを睨んだ。
「そうなのよ。ま、表向き雨具メーカーだから、そういうのやるのもいいと思うんだ。ただ当たりすぎると気持ち悪いから、きちんといい加減にするAI搭載してるんだって」
「ん? きちんとといい加減って隣り合わせでいい言葉です?」
「きちんといい加減AI、略してKIAI。そう、気合だ!」
森戸の急な大声に横山はびくりと眉間にシワを寄せ、首をすくめた。
「なんか……話入ってこないです」
「アプリの名前は『天気合予報』だって」
「うわぁ、当たらさそうですね」
森戸のインストールした、眉毛がキリッと上がり、熱血顔をしているてるてる坊主の『天気合予報』のオレンジ色のアイコンを見て、横山は顔をしかめた。
「社長の一声なんだから、しょうがないだろ」
「社長といえば気になってるんですけど、社長が変わってからゲリラ豪雨の判断増えてません?」
「あ〜前の社長はなるべくしないようにしてたんだけどな。あっても夕立って美しい名前だったし」
「文系としては、ゲリラってゴリラっぽくっていやですね」
「俺理系だけど、ゴリラっぽいと思うよ、うん」
横山はため息をつき、ノートパソコンを開いた。無駄なくキーボードを叩きながら、先程より暗い声で言う。
「ゲリラのとき毎回風神部雷神部に繋ぎますけど、またですか、って嫌味っぽくいわれちゃうんですよね。今日もゲリラになりそうですし。ほら見てください、晴れと雨だらけ」
横山は出したデータ画面を見せるため、くるりとパソコンを森戸の方へ向けた。
森戸は画面を順に左から右へ瞳を動かして確認する。徐々にそのスピードは上がり、短い時間で血走るのではないかというほど目は大きく見開いていった。
「こんなに晴れと雨ばかりで曇りがないだと……おかしい、おかしいぞこのデータ!」
机と椅子しかない会議室に、森戸の声はよく響いた。
「え?」
横山はしっかりと目線を森戸に合わせた。少し動揺しているようだった。
森戸も慌てながら横山を見た。
「まさかスパイか?」
ごっくん、と横山の喉が鳴る。
「まさか、気象予報士たちが」
ごっくん、とまた鳴った。
「気づいてデータを奪おうと」
ごっくん、とよりいっそう大きく鳴った。
「お、おい横山?」
「ごっくん。」
「横山ぁ!?」
「あぁーすみません。飲める生ツバなくなりました」
額の汗を拭いながら焦る表情の横山を見て、森戸は疑念の表情を浮かべる。
「いや、お前どうしたっていうんだ。まさかお前」
横山は机に手をつきうつむいていたが、ほんの小さなため息をつくと神妙な面持ちで応えた。
「実は、私」
「おう」
「最近パクチー食べられる側の人間だって気づきました」
「関係ねえ!」
「え?」
「何だパクチーって。割と、食べられるかの判断遅くない? じゃなくて、スパイの話をしてるんだよ!」
横山は森戸を見ながら、規則的に瞬きを繰り返す。
「スパイ? すみません、全然聞いてませんでした」
「あんなに目を見て、あんなに唾飲んで、聞いてたのに?」
「はい!」
「いい返事すんな!」
森戸は頭をかきながら、周りを見渡した。広い会議室に2人きりだが、視線を感じるような気がしている。
「まさか本当にスパイがいるかもしれないのに」
そんな森戸を横目に、横山はあまり深刻そうではなかった。見せたノートパソコンを再び閉じ、不安そうにしている森戸に尋ねた。
「そういえば部長、新しく来た男性の方ってどこの部署ですか?」
「はぁ? 新しく雇うなんてことは人事から一言も聞いてないぞ」
「え? でもさっきそこで見ましたよ」
横山はきょとんとした顔で扉の方を指さした。そして先ほど見かけた男性の特徴を思い出しながら言う。
「白のスーツに青シャツ赤ネクタイ、白のマント白のシルクハット目にはモノクル――」
「ちょっとそれ、怪盗キッドじゃない?」
「え? 怪盗キッドがうちに潜入してたってことですか?」
「いや普通変装するのよあいつ。堂々とキッドで入ってきてるじゃん」
「えぇ?! めちゃめちゃ舐めプされてるじゃないですか!」
外部からのハッキングではなく、会社に直接潜り込まれている。森戸は机に両方の手ひらをつきながら、周りを見渡し訝しんだ。
「まずいなぁ。会社の人間でないことは確かだ。横山、このこと警備の人に伝えてこい」
「わ、わかりました、すぐ伝えてきます」
横山は言うと同時に扉の方へと体を向けた。つんのめりながら駆け出した彼女の足に履かれたパンプスは、床に零れ落ちそうだった。
「靴ちゃんとはけー」
横山のいなくなった会議室は森戸だけになった。彼は扉の方をもう一度見ると、横山のパソコンを開き、鼻からふと息をもらして不穏な笑みを浮かべた。
「すまんな、横山。残業を少なくするにはこれしかないんだ。データを変えてしまえば、時間もかからんのだ。全ては会社のためだ」
森戸の画面を見る目は瞬きもせず、指はキーボードを押し続けた。HとKの文字列は、Aに書き直されていく。このデータを送信し、自らが決定のハンコを押してしまえば、明日は確実に雨になる。
森戸が必死な形相で細工をしていると、会議室の扉が勢いよく開いた。
「そこまでです! 部長!」
「よ、横山…」
扉を開けたのは横山だった。
彼女の急な大声に森戸はたじろいだ。キーボードを打つ手をやめ、扉の方へ振り返る。
「怪盗キッドは、一か八かの嘘です。まさか部長がのってくるとは思わなかったですが。データの管理がどれだけ大変でも、改ざんしてしまうのは駄目です。我々は、人々が求める真実の天気を集めてるんです」
横山は話を聞くときと同じ目で、森戸を見つめる。
その痛い視線に森戸は耐えられず、張り詰めたコップから溢れ出した水のように言葉が零れ落ちていった。
「うるさい……うるさい、うるさい、うるさい、うるさい! 毎日毎日データを集め、皆の期待に応える! 天気が何をもたらすってんだ! てるてる坊主も数えて雨データからマイナス? は? あのティッシュに何ができるってんだ。次の日ゴミ箱いるじゃん。鼻かんだやつと変わらない!」
「部長……」
横山は彼がどれだけの責任を負いながら、残業を少なくしようと頭を悩ませていたかは知っていた。どこへ向けたらいいか本人もわかっていない止まらない怨み言に耳を傾ける。
「靴飛ばしなんて、みんな所詮おまじないだと思ってる! 神に! 簡単に願うように」
噛みしめたその思いを伝えると、森戸は窓の方へとよたよたと歩き始めた。焦点の合わない目で灰色の虚空を見つめ、そして何かを思いつき、横山の方へ振り返る。
「はは、こうなったらな、こうなったら明日は、晴れのち雨のち曇のち雪にしてやるんだぁ。夏なのにな」
森戸は不気味に笑っていた。
そんな彼の目をまっすぐと、しかしながら優しく見ながら、横山は語り始めた。
「確かに、確かに靴飛ばしなんて、人にとってはおまじないかもしれません。でも、明日はデートだから晴れてほしいなー、とか、明日はマラソン大会だから雨降って中止にならないかなー、とか、希望を抱いて靴を飛ばしてると思うんです。ほら、自分の思ってる方と違ったらもう1回しちゃうじゃないですか。もちろん公平性のために、1つの靴につき1回目のデータを使用しますけど。誰かのために雨が降るなら、誰かのために晴れることもある、ですよね部長」
必要な恵みではあるが、抗うことなく左右され、共に生活していく。人間達にとって、ときに優しく、ときに激しく、神が宿ったかのような、それが天気なのだ。
だからこそ、誰かが願うなら真実を貫くべきなのか。森戸は横山の言葉に耳を傾けた。
「横山……」
「あと、雪はまじでやめてください。天変地異すぎて後世に伝えられちゃいます」
「ペンチすぎか?」
「ペンチ……? ペンチです」
先程とは打って変わって、横山の視線は鋭く尖った。しかしながら口元は緩んでいた。森戸が正気を取り戻し、落ち着いたことを確認して横山もホッとしたのだろう。
しかしながら、問題は解決していないのだ。
「でも、残業のことを考えると……」
「そんなもの気合でなんとかしましょうよ。ね」
苦し紛れではあるが、横山は彼女なりの励まし方で両の拳に力を入れた。
「――気合? そうか気合だ!」
「え?」
森戸は目を大きく輝かせ、落胆から曲げていた背中を勢いよく正した。そして思いついたアイディアをすらすらと語り始めた。
「KIAIに任せればいい! データを全てあのAIに流して、まとめてもらうよう構築すればいいんだよ!」
ん?と横山は首を傾げた。
「いいか文系。今まで手動でおこなっていたデータ管理をAIに学習させて覚えさせるんだ。俺たちはデータの不足だけを見ればいい。天気予報は、適当な日に間違える!これは真実があるからこその、きちんといい加減な嘘だ!」
「まぁ、結局何言ってるか分からないですけど、きちんと休みがとれるってことですよね」
「あぁ、これでブラック脱却だ」
「や、やったー!!」
残業や休日出社から解放されることがどれだけ嬉しいことか、横山は机の周りを飛び跳ねるように走り回った。
横山の軽く踏んだだけの右の靴が、ぽーんと軽く弧を描いて床に転がり、上向きに止まった。
2人はそれを見つめ、指をさしながら同時に言う。
『東京、H+1!』
ATNコーポレーション/やおよろずの毎日
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
