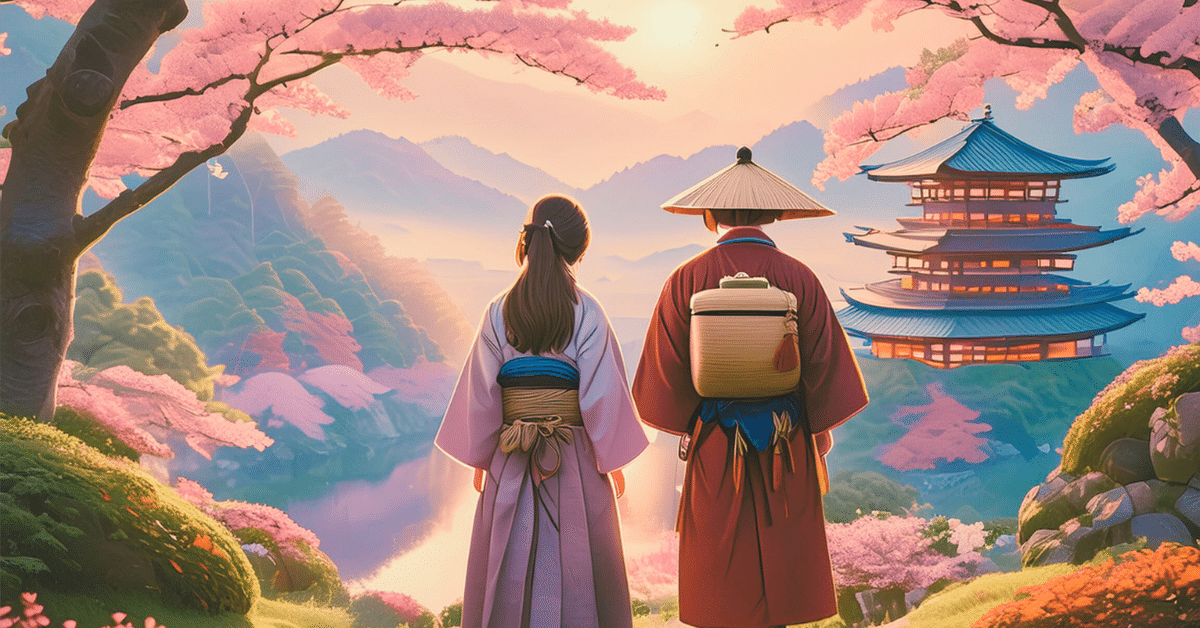
あくびの隨に 29話
前回
「ぬし? 唐突に何を――」
言いかけて、稲は急速にその場で膝を折った。
逸流の手の平を握る力がなくなり、辛うじて手を取られている状態。
しかしそれも、ぱっと放り捨てられるように投げられた。
稲は糸の切れた人形の如く、両足を外開きにする形で座り込み、隣にいた人物を見上げる。
「そなた……まさか、もう」
「ごめんよ、羅刹。僕はずっと、君に嘘をついてたみたいだ。僕は最初から君を信じていなかったし、君が神を殺すのを黙って見てるわけにはいかない。だって、今ここで神を殺されちゃったら――僕が依り代になれないだろ?」
神の依り代となるために、現世から連れて来られた逸流という器。
そこには初めから、神の意思が入り込んでいたのだ。
現世から逸流を呼び寄せる際に、神の一部はその体内に入った。しかし留包国と現世の間には、この世のどこでもない常世の隔域が存在する。
本来そこは素通りできたはずだったが、ここにはかつて送り込んだ羅刹がいた。
その想定外の力に影響を受けたためか、依り代は封節の社ではなく、常世の隔域に転移してしまったのだ。
これを受けて稲は、奇跡のようなこの好機を利用し、逸流と神との繋がりを無理やり打ち消したのである。
それでも神の意思はたしかに逸流の内で残留していた。
羅刹の力で表層に出てくることはできなかったが、封節の社まで来れば直接その影響が与えられてしまう。
百年前のときと同じく、稲は再び間違いを犯したのだ。
人間の力で神に抗うことはできない。
逸流をこの場所に連れて来るべきではなかった。
神を殺せるという彼女の驕りが、この結果を生み出したのだ。
逸流としての意識はまだ残っているが、もはやその大半はすでに神の自我が支配する。
「己を取り戻せ。そなたには、成すべき大事が残っているはずだ」
「悪いけど、僕はもう決めたんだ。たとえ僕が封印に費やす百年が気休めだとしても、世界を危険には晒せない。たとえ神のあくびの間に消えるような月日だったとしても、せめて最後のひとときまで邪なる蛇の好きにはさせない。あれは全てを食らい尽くす災いそのもの。万が一にも現世にまで影響を与えるようなことは、絶対に避けないとね」
逸流を介して、神の意思は反映される。
神は決して災いを成すわけではない。ただ、受け取る者によって善にも悪にも捉えられてしまうのが、神という存在の在り方なのである。
稲は神を善だとは思っていない。
しかし今の彼女はそれを否定せず、訴えを続けた。
「そなたはこれまで、十分すぎるほど役目を果たしたではないか。もう、人のために眠り続ける必要はない。あとのことは、私たちに任せてはくれぬか?」
「羅刹の分際で、よくもそんな戯言を。君が存在しなければ、この世界はまだ平和だったんだよ。君がいたせいで、多くの人が苦しんだ。君が全ての元凶なんだ」
「……っ」
逸流の口から発せられる響きは、必要以上に稲には堪えた。
あらゆる否定は意味を成さず、稲はその言葉を受け入れるのみ。羅刹のせいで留包国は歪んだ。それは認めなければならない罪過である。
しかし、だからこそ。
今このとき世界を救いたいと想うことは、紛れもなく人々の願いだろう。
稲はまだ諦めてはいなかった。最後の望みを託すように、そこにまだ残されている意思に呼びかけていく。
「紛れもなく、私は悪しき存在だ。されど、そなたの強いる犠牲に正当性があるとも思ってはおらん。なればこそ――ぬしならば、そのような世迷言は認めまい。なぜならぬしが犠牲となれば、たとえ救世を行えたとて、何者をも救う道とはならぬのだから」
「……っ」
一瞬、逸流の身体は身じろぎを見せたが、神の意識はこれを跳ね除けた。
「もうどうにもならないんだ。未来への道は引き返せないように、神は封印を続けるしかない。悪いが、羅刹。君との旅はここで終わりだよ」
そう言った直後、棺の中から輝きが漏れ出した。
長き責務を果たし終えたように、老人の姿が光へと昇華されていく。
それが意味することは、そこに収まるべき新たなる依り代の到来であった。
「でも……そうだな」
はたとして、逸流は木棺に刺さった刀を抜く。
「君を、また隔域に閉じ込めるのも可哀そうだ。君には神としては殺されかけたけど、世多逸流として一緒に旅をしてきたよしみでもあるからね。せめて、この生き地獄から解放してあげるよ」
刀を構えた逸流は、稲の首筋に剣先をあてがった。
その場で力なく座り込む稲は、逸流を見上げるばかりで刀を意に介さない。
見据える先は、その眼差しの、さらに奥。
描く想いは、そこにある者への悔恨。
「すまぬ……私は、ただ……ぬしを救いたかったのだ」
「気にしないでくれ。僕は礎になるんだ。この留包国を永く繁栄させるための」
稲を見下ろして、逸流は刀を持つ手に力を籠める。
切っ先が稲の首筋に触れ、微かに赤い滴りが肌を伝った。
あと少しで、彼女という存在は羅刹の呪縛から解放される。
もう無意味に、この苦しみの世を生き続ける必要はないのだ。
「さよなら、羅刹」
逸流は、繊月を振るった。
「――っ」
しかし、稲の首は変わらずそこにあった。
なぜなら唐突に逸流の身体がふらついたのだ。
刀を持つ手が揺れ動き、焦点が定まらずに彼女の肩を掠める。
そう、神は失念していた。
呪封符札を飲んだ逸流の身体は誓約に縛られている。繊月を振るおうとすれば直ちに硬直が走り、全身の自由が利かなくなってしまうのだ。
重心のぶれた逸流は、案山子のような棒立ちで態勢を崩し、階段を転げ落ちていく。
「ぬしよ!」
身動きのできない稲は、何とか力を振り絞って階段の下を見やる。
逸流は最下段で倒れており、手から刀は離れていた。意識はあるように、呻きながら手を地面について立ち上がっていく。
かぶりを振って祭壇を見上げ、逸流は稲と真っ直ぐ視線を交差させた。
「……稲」
逸流は稲の名を呼びながら、足元に転がっている刀に目を向ける。
その何気ない仕草に、稲は何かを悟るように表情を歪めた。
「ぬしよ、それでは駄目だ……」
稲は沈痛な面持ちで階下の逸流を見つめる。
されど逸流の心はすでに決まっていた。
繊月を拾い上げる。両手で刃の部分を握りながら、白刃の切っ先を自らに向ける。
「神様は君を信じてないけど、僕は違う。こうすれば、邪なる蛇の封印が解けても、きっと君が何かやってくれるんだろ?」
「……戯け者。ことこの場において、ぬしの行いは何も救えぬと分からないのか。それを行ったところで、この道が閉ざされて全ては露と消えるだけなのだぞ」
言葉は荒げず、諭すように稲は言う。
しかし、逸流は感じていた。
それは昔からあった、根拠のない直感によるものではない。あえて今から行うことに意味をつけるとすれば、それは――
「僕は死ぬまで君を信じるから、君も僕を信じて欲しいな」
稲という少女に対する、揺るぎない信頼だった。
「やめろっ!」
彼女の悲鳴が聞こえた瞬間。
逸流は手の平から血が溢れるまで繊月の刃を握り締め、これを一気に自らの胸元へと突き入れた。
「ぐっ」
痛みは最初の一瞬だけだった。
冷たい刃が自らの内を抜けて、背中から飛び出ていく。
三日月状の独特な形状から、体内でも弧を描いている感覚があった。前と後ろの傷口から滲み出る生暖かいものを覚え、だんだん逸流は呼吸が辛くなっていく。
「たしか……抜けば良いんだっけ」
一生知りたくもない触感とともに、逸流は繊月を胸から引き抜いた。
刹那、飛び散る鮮血が辺りに撒かれる。流動する血液は勢いよく傷口から噴出し、痛みよりも寒さが逸流の総身を支配していった。貧血のように立っていられなくなり、刀を取り落としながら無造作に床へと倒れ込む。
「ぬしは……なんたる、ことを……」
身の束縛が解けたように、稲は静かに階段を降りてくる。
それを遠く聞きながら、逸流は視界が霞んできた。
眠るような感覚は、恐ろしくも心地よいものがあり、喉の奥から湧き出す催し。
この今際の際ですら、飛び出そうとする生理現象に逸流は苦笑した。
「なんか、久々に……眠れそう……」
逸流は薄れていく意識の最中、走馬灯のように祖母の言葉を思い出す。
「あくび……かみ……ころさ、ない……と…………」
生じたあくびを噛み殺し、逸流は闇に沈んでいく。
これを見届ける者は、たった一人。
冷たくなっていく彼の身体を、腕にそっと抱き――
「それでは、駄目なのだ……逸流よ」
稲は彼の名を虚しさに乗せながら、目元に光るものを湛えていた。
【続】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
