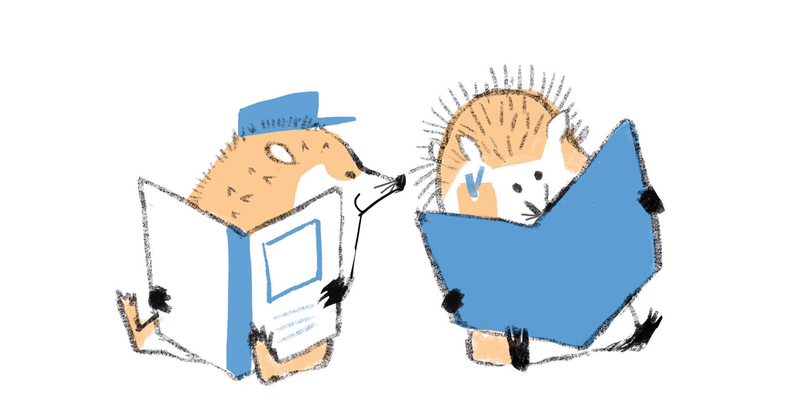
お説教に意味はあるのか
説教というのは、そもそも牧師さんや和尚さんが説いてくれるありがたいお話のようですが、今回は、日常でよく目にするお説教について書きたいと思います。
仕事をしている人であれば上司にお叱りを受ける機会や、学生であれば先輩や教師にダメだしされる機会があります。説教されてみてどうだったかを尋ねてみると、ほとんどの人が態度を変えるどころか、「くど過ぎる」とか「自分のことは棚にあげて」と不満を口にします。一方、お説教した側も、態度を変えない人に対し「あんなに言ってやったのに」と不満を口にします。
□ お説教する側の視点では、関係性がポイント
ではお説教なんて全く意味がないのか?というと、そうでもありません。少数ですが、態度を変える人もいるからです。
態度を変える人と、変えない人の違いは何でしょうか?もちろんお説教の仕方にもよるのですが、見落とされがちなのは関係性です。態度を変える人は、説教する人との間にある程度の信頼関係が出来ています。「タバコはやめろ」と教師から言われるのと、友達から言われるのは響き方が違いますよね。信頼関係がないと、ただただ相手にとって不快なものになりうるのです。本当に響くお説教をしたければ、相手との関係性を考慮に入れてみてください。信頼関係が築けていれば、自ずと響き方が違ってきます。
□ される側の視点では、主体性がポイント
じゃあ、不快感が募るだけのお説教には意味がないのか?というと、そんなこともありません。全く意味がない物事は続かないからです。ただその意味は、説教される側ではなくて、どちらかと言えばする側にとって大きいようです。説教は、することによって自分の考えや意見を存分に語れます。それを無批判に聞いてもらえるのは、気分がいいものです。ですから、説教をする人は癒され、される人は癒している側面があるのだと思います。実際、頻繁にお説教される人は、癒し系の人が多いです。
ここまでの文章でもそうですが、説教は「してもらった」とは言わないで、ほとんどの場合「された」と表現します。体験としては受け身に感じられているのです。受け身でいると、説教されるたびに心が削られます。しかし、今日も癒してやったと思っていると、主体性を持てます。お説教に限らず、主体性を持てているかどうかは心にとって大きな違いがあります。お説教にも主体性を取り戻せると、心が削られず、いくらかマシになりますよ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
