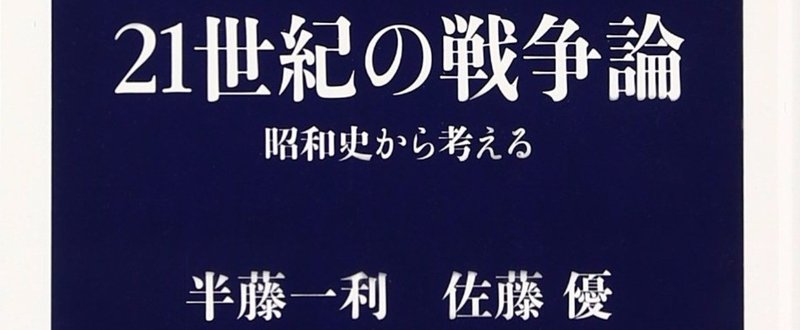
昭和史を貫く「悪の構造」〜『21世紀の戦争論』
◆半藤一利、佐藤優著『21世紀の戦争論 昭和史から考える』
出版社:文藝春秋
発売時期:2016年5月
昭和史に詳しい作家・半藤一利と元外務省主任分析官の佐藤優による対談集。書名からもわかるように、ここで議論されているのは戦争を軸としてみる昭和史です。具体的には、七三一部隊、ノモンハン事件、終戦工作、軍事官僚機構などが検証・考察の対象となっています。
歴史的事実から思考を組み立てようとする二人の対話は「神は細部に宿る」の格言を地でいくがごとく時に細かな議論にまで立ち入ります。薄味な対談が多いなかではそれこそが本書の一つの特長といえるでしょう。
七三一部隊にいた人物が戦後エイズ問題で物議を醸したミドリ十字の社長になったという話はよく知られていますが、半藤は帝銀事件に関しても松本清張を参照しつつ七三一部隊関係者の関与を示唆しており、歴史の読物としても退屈することはありません。
ソ連軍との戦闘に惨敗したノモンハン事件に関する議論は本書の読みどころの一つといえるでしょうか。とりわけ私が驚いたのは敗戦処理にまつわる事実です。作戦を立案した参謀は陸軍の方針ということもあって厳しく責任を問われることはなかったのに、現場の指揮官たちはみな戦場で自決させられたといいます。半藤が自決した指揮官の名前を一人ひとり挙げてそのことを指摘したのを受けて佐藤は次のように述べています。
軍法会議で敗因を究明するのではなく、自決を強要したというのですね。現場の指揮官に自決させるというのは戦史研究の上では非常にマイナスです。負け戦に関して徹底的に聴取して、教訓を得なければならない。口封じに殺してしまっては、何の意味もありません。(p234)
こうした事例に象徴されるように、対話をとおして浮かびあがってくるのは、戦争を遂行した日本のエリートたちがいかに負け戦=失敗から学ばなかったかというあまたの史実です。そのようなマインドは現代の官僚組織にも受け継がれているという点でも二人の認識は一致しています。とくに言及されているわけではありませんが、原発事故から抜本的なことを何一つ学ぼうとしない政治のあり方などは、その典型といえそうです。
そうした観点からすれば、戦後の日本が外見上は全体主義体制から戦後民主主義に変革を遂げたように見えても「日本に破滅をもたらした因子が、温存されることになってしまった」(佐藤優)ことは否定できません。昭和時代は戦争によって断絶があったというよりも、むしろ見事なほどにつながっているのです。佐藤の外交官時代の挿話を「陸軍そのもの」と半藤が返すやりとりなど、なかなか興味深いものです。
昭和時代の連続性に着目し、そこに組み込まれている「悪の構造」を顕在化させるという本書の狙いは充分に実現されているのではないでしょうか。日本の行方を決める立場にいる公権力者たちには昔も今も「失敗学」という発想が欠落しているのだなとあらためて感じた次第。逆にいえば、そうした悪しき昭和の精神をいかに自覚し改善していくかが、21世紀ニッポンの大きな課題だといえそうです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
