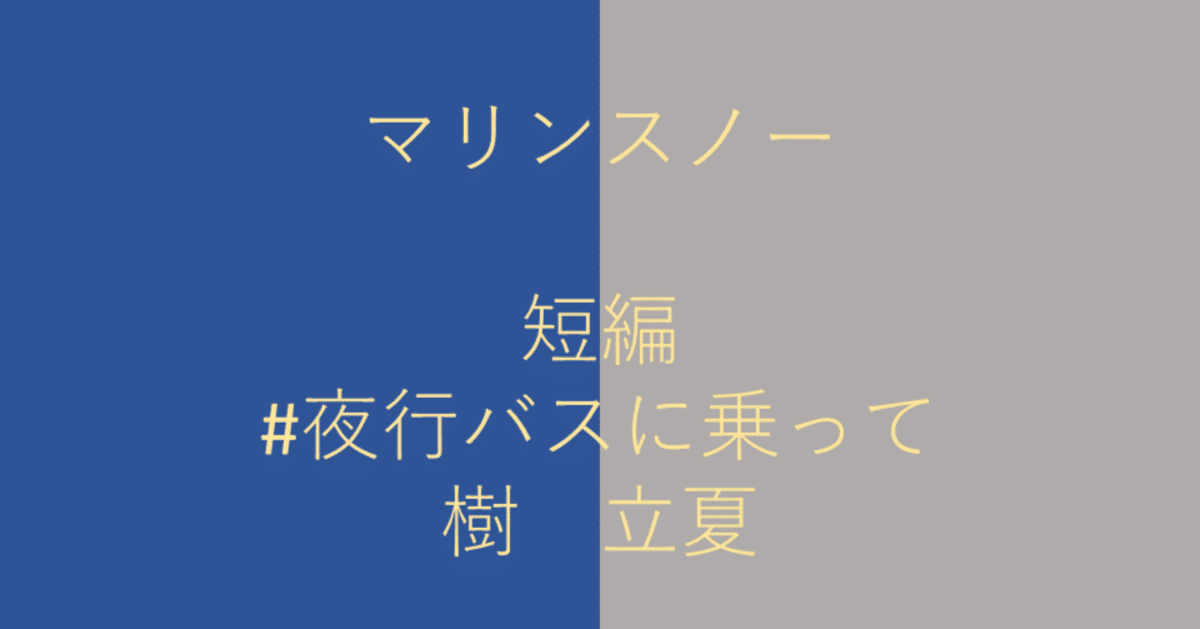
マリンスノー【#夜行バスに乗って】
2024年、3月8日の午後7時。スマートフォンが震えた。東京に住む姉が、緊急入院したという。姉は、僕にとっては、たった一人の「生存している」血縁者だ。ここ、帳面町は、日本の東と北の間にある、小さな町だ。空港も、鉄道も無い。それに、もう夜も更けた。今から夜通し車を走らせるよりは、夜行バスに乗った方が安全だろう。明日は忙しくなる。バスの車内で少しでも仮眠をとっておいた方がいい。
幸いなことに、切符はまだ残っていた。財布から金を取り出した時、手が震えていることに気付いた。
姉さんは、体が弱い。
慌てて頭を振り、考えていたことをかき消す。とにかく、東京に行こう。
21時。発車時刻となり、ドアが閉まりかけた時、慌てた様子で男性が一人乗り込み、トイレの左側、バス中央付近の座席に座った。男性は、ぜえぜえと荒い呼吸をしている。突然、膝に抱えたトートバッグの上で、指を動かし始めた。何かを奏でているかのように。自分を落ち着かせようとしているかのようにだ。
僕は、一呼吸して、男性の斜め左後ろ、バス後方の窓側の席に背中を埋めた。シートはゆったりとしていて、乗り心地が良い。これなら、少しは仮眠をとれそうだ。
今週末は、南岸低気圧の発達により、このあたりでも夜から雪が降るという予報だった。予報通り、雪は降って来た。渋滞だけは勘弁してほしい。この時間だから、大丈夫だとは思うけれど。
バスは、高速に乗るまで、暫し海岸線を走る。真っ暗な海と、降りしきる雪を、ぼんやりと眺める。眠気が僕を侵食していく。
ああ、そうか。
此処は、深い海の底。
雪だと思っていたこれは、雪じゃない。
マリンスノーだ。
「間もなく このバスは ○○サービスエリアに停車いたします ○○サービスエリアでは 20分の停車となります」
女性運転手の凛とした車内アナウンスの声に、はっとして目を覚ました。時刻は23時で、バスは最初のサービスエリアに停車していた。眠っていた間に高速に乗ったらしい。このまま眠ろうかと思ったが、目が冴えたのでバスを降り、体を動かすことにした。
雪は、まだ降っていた。
天を仰いだ。
顔の上で、雪の結晶たちが融解していく。
温かいココアを自販機で買い求め、座席に戻ろうと、した。
ああ。
こんな日に限って。
ずぶ濡れの、髪の長い女性が、僕の座席に座っていた。当然、顔面は蒼白で、俯いている。
僕には、「彼ら」が見えるのだった。
『どうしましたか』
僕は、心の声で彼女に語りかけた。
『あなたになら、解ってもらえると思って』
『お役に立てるといいのですが』
彼女は、俯いていた顔を上げると、僕が座れるようにと、席を立った。僕は、心の中で礼を言って、席に座った。彼女は、通路に体育座りをすると、僕を見つめた。黒一色の眼球が、彼女がこの世の者ではないことを否応なしに訴えてくる。
扉が閉まり、バスが走り始めた。僕以外には、彼女は見えていないようだった。沈黙が続く。
『この雪』
彼女が口を開いた。
『まるでここ、深海みたいじゃありません?』
『マリンスノー、ですか』
『やっぱり、あなたにはお伝えしようかしら』
『何でしょう』
彼女は、斜め前に視線を固定した。
『私の上に、降り積もっているんです』
『何が?』
『マリンスノーです』
彼女の視線の先で、発車間際に乗り込んできた男性が、トートバッグの上で、指を動かしていた。
その横顔を見た時、僕の中で、何かが閃いた。
『マリンスノーが、降り積もっているんですか? あなたの上に?』
『ええ』
『まさか』
『そう』
彼女は、斜め前を指さした。
『あの人に、沈められたんです。海の底に』
『それは、つまり』
『私、殺されたんです。あの人に』
『じゃあ、あなたは、今も』
『ええ。私の体は、今も海の底に』
僕は、ずきずきと痛むこめかみを指で押さえた。
彼女は、少し間をおいて、ぽつぽつと話し始めた。亡くなった時、彼女は音楽大学のピアノ科の2回生だった。当時付き合っていたその男は、同じピアノ科の3回生だった。表面上は、とても優しく振舞うが、根は相当に嫉妬深い性格だったそうだ。去年の秋、彼女と男は、同じコンクールに出場した。彼女は入賞し、男は鳴かず飛ばずだった。一週間後、男は3D プリンターで作製した簡易的な拳銃で、彼女を銃殺した。殺された彼女は、海の底に沈められた。
『あの人、実家が帳面町にあるの。これから、大学のある東京に向かうのよ。次の獲物を仕留めにね』
『ちょっと待って、それって』
『そうよ。あの人、また殺す気よ』
『でも、まさか』
『疑ったって駄目。今にわかるわ。もうすぐよ』
彼女は、斜め前を睨むと、微かに目を細めたように見えた。
「間もなく このバスは △△サービスエリアに停車いたします △△サービスエリアでは 20分の停車となります」
午前2時。乗客のほとんどは眠っている。会話も聞こえない。
カシャン と音がした。
眠りかけていた例の男が、トートバッグを落したのだ。
袋から、何かがはみ出して見える。
拳銃……?
男は、慌てた様子で周囲を見渡し、急いで中身をトートバッグにしまい込んだ。
『ほらね。これでわかったでしょう』
『あなたの言ったとおりだ』
彼女は、ふわりと浮かび上がると、男のところまで飛んでいった。
次の瞬間、彼女は男の首を絞めた。無論、彼女は物理的実在ではないので、男の首は絞まらない。
『お前に! お前に殺されなければ! 私はあこがれのピアニストになれたのに!』
彼女の慟哭が、無機質な車内に無残に響き渡った。男に彼女の叫びは聞こえない。男は、眠り込んだ。
『ねえ、あなたの名前は?』
僕は、取り乱す彼女に問うた。
彼女は振り返ると、真っ黒な目で僕を見据えた。
『普通、幽霊に名前なんか聞く?』
『あなたに協力してほしいんだ。名前を教えて』
『ミヨ』
やはり、そうか。この人は。
『ミヨ。魔法使える?』
『……夢に出るくらいなら』
『十分だ。あいつの夢に入り込んで、できるだけ夢を引き延ばしてくれ。東京に着くまで、目覚めないように』
『どうして?』
『いまにわかるさ』
ミヨは、頷くと、男の頭を両腕で締め付けた。そのまま、ミヨは動かなくなった。
明け方4時。次の〇△サービスエリアに着いた。ほとんど乗客は降りない。まだだ。まだ起きないでくれ。
静寂を破ったのは、前方の座席から聞こえて来た、「ワッショーイ!」という大きなくしゃみだった。数人の乗客が目を覚ました。冷や汗が噴き出る。しかし幸運にも、男は起きなかった。ミヨが夢を引き延ばしているのだろう。
気づくと、車窓の風景は一変していた。高層ビルの群れが、飛び交っていく。夜明けだ。ミヨはまだもつか。
『ごめん、もうそろそろ駄目そう』
ミヨの絞り出すような声が聞こえる。
『ありがとう、平田美代さん。もう十分だ。僕たちは、もう二度と君のような被害者を生み出したりしない』
『あなた、どうして?』
『僕は……』
バスが停車した。時間きっかりの朝6時に、バスは新宿に到着した。
「終点 新宿です」
バスのドアが開く。
ばたばたと、騒がしい足音を響かせ、男たちがバスに乗り込んできた。
「はい、動かないで!」
僕は先陣を切った。
「お兄さん、これちょっと見せて」
寝ぼけ顔の男から、トートバッグを奪い取った。
「むにゃ、な、何だよ!」
トートバッグの中に、3Dプリンターで作製したものと思われる、簡易型の拳銃を確認した。
「てめえ! 何しやがる!」
男が殴りかかって来た。
「はい、アウトね。あんた、深水新だな?」
僕の後ろに控えていた私服の警察官たちが、男を取り押さえた。
男――深水新は、ピアニストばかりを狙った連続殺人事件の重要参考人だった。
「佐伯! お手柄だぞ」
上司の坂崎さんが、僕の肩を叩く。
「それにしても、すごい偶然だな。お前が、深水と乗り合わせるなんて。それに、深水がずっと眠っててくれるなんて。一生分の運、使い果たしたんじゃないかあ?」
「はあ……。」
「そういや、佐伯、姉さんは大丈夫か?」
僕は、スマートフォンを操作し、メッセージアプリを開いた。
「この通り、母子ともに健康です!」
画面の中では、姉さんと、ぼくの新しい血縁者、赤んぼうの甥っ子が、すやすやと眠っていた。
「お前は、苦労したからなあ」
坂崎さんは知っている。姉と僕を残して、僕の家族が殺害された事件の、担当刑事だったからだ。
「それにしても、よかったなあ、佐伯!」
「日ごろの行いが良いんですよ」
うそぶいて、バスの方を振り返った。
ミヨの姿は、なかった。
<終>
この小説は、豆島圭さまの下記企画に参加させていただいております。
#夜行バスに乗って
豆島さま、参加させていただきました!
ホラー要素のあるミステリーに挑戦しました。
途中のサービスエリアで聞こえて来たくしゃみは、コッシ―さまの下記小説に出てくるあの方のくしゃみですよ!
楽しく書けました。豆島さま、素敵な企画をありがとうございました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
