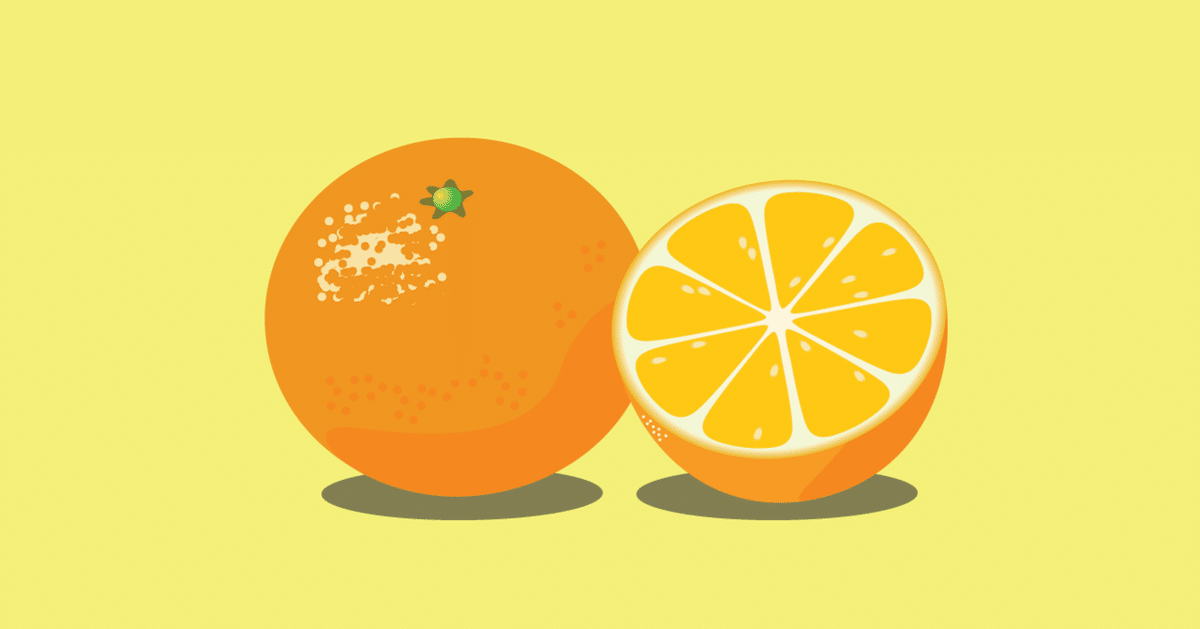
自分軸で決断ができる子に育ててあげないといけないと思います
昨年はステイホーム!とかgo to!とか、一体、どうすることが正しいのか?という判断を個々に求められた年でした。
今もそうですよね。
どこまで自粛するのか、とか、これは行かないで止めとこう、でもこれは参加しよう・・・って。緊急事態宣言が出ている地域の方ならなおさらです。
誰々に言われたから、○○する、誰々に言われたから、○○を止める。という価値観から
自分が○○だと思うから、○○する。
自分が○○だと思うから、○○しない。
という自分軸での判断が求められる時代にようやくなってきました。
ということは・・・これからの子育ての中に「自分の頭で考えて答えを出せる力」が育つように盛り込んでいかないといけないのですよね。
私の教室ではずっと前から、子どもたちとのレッスンの中や日々の何げないやり取りの中にこの「自分の頭で考える」ということをこつこつ盛り込んできました。
たとえば、出席シールを選ぶ、という作業での例
レッスンを受ける親子は、来室したらすぐに自分の席を見つけて、出席シールを一つだけ選んで日付の書いてあるところに貼る、という作業があります。
大人にしてみたら、何でもない行為で、その一連の動作の中にあまり思考は入らないと思います。「先週はミカンのシールだったから、今週は大根のシールにするかな」くらいのもんでしょう。
けれども、子どもにしてみたら、シールをたった1枚選ぶ、だけでも、ものすごく時間がかかることなのです。
どれを選ぼうかな?の前に、「これ何かな?」から始まって、
「あ、これ、昨日食べた甘いやつや~。美味しかったな。また食べたいな。どこで買ってきたんかな? あれ? おばあちゃんにもらったんだったかな? そういえば・・・昨日おばあちゃんと電話でお話ししたなあ・・おばあちゃんの家のワンちゃん、今何してるかな?・・・・・・」
って、延々イメージが膨らんで続いていくので、シールを選ぶのに長く時間がかかってしまうのです。だから、親さんは待ってあげて欲しいのです、じっくりと。
けれども、そこで、
「はい、これにしなさいね。おミカン昨日たべたでしょう、はい、これね」
と親が横やりを入れてイメージはそこで途絶えさせ、子どもの意志を聞かずに、親がすすめられたシールを貼らせてしまう。
↑これをしてしまうお母さんの多いこと多いこと。
たとえレッスンがスタートしてしまっても、次の取り組みに移ってしまっていても、今子どもが、まさに、答えを出さんとイメージを巡らせている時は、その流れを強制終了させてはいけないのです。
その繰り返しが「自分の頭で考えて自分で答えを出す力」につながっていくと思うのです。些細なことですけど。
いただいたサポートは教室の絵本購入に使わせていただきます。
