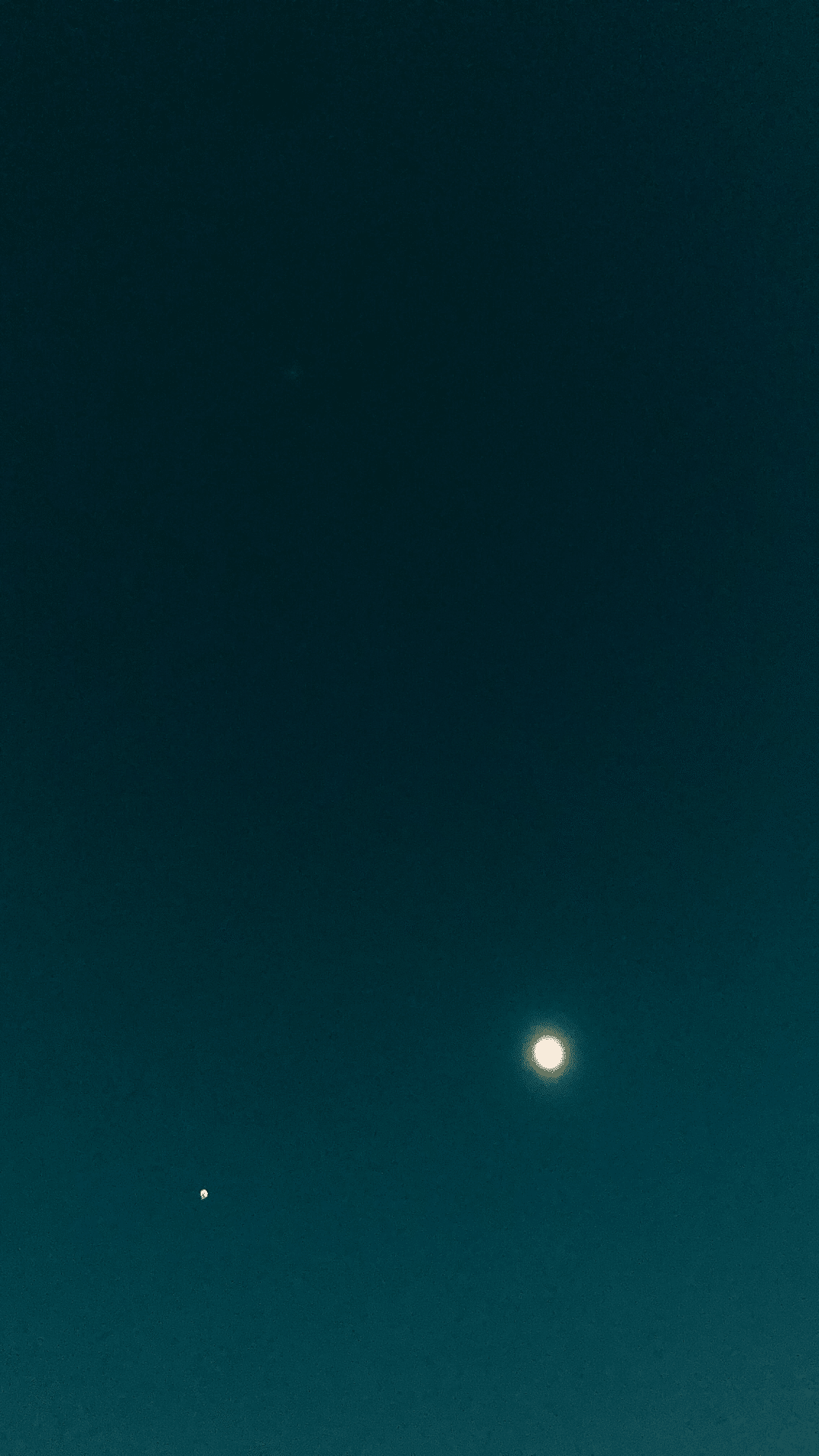「先生」
髪をばっさり切った。
頬をすり抜けていく風は冴え、あっという間に冬の形相だが、しかし髪が触れ耳と首に少しかかるだけで思いのほか温かい。
冬はなんだか少し寂しい。
さびしいし寂しい記憶が多い気がする。
だからほんのちょっとでも温もりが欲しくなる。
冷たい指先で来た道をなぞりながら思い出を掘り起こして探してみると、結局のところ温もりも寂しさも同じところにあのだったと、気がついしてしまった。
・
唐突だが、これまで出会った先生のはなしをしようと思う。
と、言うのも、先生という存在に出会わずに大人になった人間はおおよそいないと思うのだが、それは考えたらちょっとすごいことだし何というか不思議な存在だと思う。
親や、祖父母、いる人は兄弟姉妹、付き合いがあれば親戚果ては一族まで。
人間が生き育まれる環境構成には必ずしも(人間)が存在するが、初めて出会う他人の大人はもしかしたら先生という存在なのかもしれない。
学校という枠組みの中では、子供たちには子供たちのコミュニティがあり、それとは別に先生という大人から学びや教えを得る。
教科書通りの勉強はもちろん、自分にも家にもないものに出会う時、そこに灯台のように立つのが先生なんじゃないだろうか。
とはいえ先生だってただの人間だ。
自分が子供だとしても大人だとしても、相手はとるにたらない人間のひとり。正しさや正解だけがそこにあるわけではない。
それが世の中的に、教本的に、正解だとしても、自分にとってどうなのか、考えるところまでが学びであり、それを経て本当の関わりと呼べるような気がする。
例えば習い事の先生や、学校のクラス担任、部活の顧問など、自分から選べるものばかりではない。巡り合わせやタイミングで舞い降りてくる出会い。
目の前に提示されたところから、私たちは何を学びにするのか。
どれだけを教訓にできるか。
ある種先生という存在に出会う時から、それは試されているのかもしれない。
・
小学校の帰り道、まだ大きなランドセルを背負ったまま家の方向とは真逆へ曲がる。
友達のおじいちゃんがやっている書道教室に、近所の子たちと何人かで通っていた。
明るく元気で躍動的な彼女のおじいちゃんもまた、快活でユーモアのある人だった。
生徒は地域の子どもたちだけでなく大人の人たちも来ていたし、学校帰りに集まれば他学年とも膝を合わせる。
お習字だけでなく水墨画も描く先生からは、歳を重ねても新しいことを学び挑戦する姿を見せてもらった。
愚直に美しい字を、友達と遊ぶように、そんな学舎であった。
そういえばそのおじいちゃんの家で友達と遊んでいる時、初めてナウシカを見た。
昭和建築の琥珀色を帯びた家と、画質の荒いテレビに映る蒼き衣が今も鮮明だ。
おじいちゃんが亡くなったのももうだいぶ前だが、誰もいなくなった家は今も夜、小さな庭のライトに淡く照らされている。
賑やかな声は遠い記憶になってしまった。
小学生も高学年になると勉強が段々とこ難しくなる。
そうなると周りの同級生たちも塾通いが始まったりするものだが、私も例外なく家の近所の塾へ通いはじめた…と言っても、宿題をしにいく場所の様なところで、受験先への高いモチベーションやカリキュラムがあるようなところではない。
ゆるくアットホームな帰り道の集合場所みたいなものだ。
先生は自分のおばあちゃんと似たり寄ったりの年回りだが、教養があり真面目だがおっとりとした、所謂天然な人だった。
それゆえに、怒っても怒って見えない、柔らかいものを纏っていた。怒られるようなことをするのは大抵男子たちだが、本性がやんちゃなのは女子の方で、きっとどちらにも手を焼いていただろう。
けれどそこへ集まることで、勉強モードになり家ではなかなか達成できないことをここで済ませることができた。
小学校の卒業祝いに、夜のドライブへ連れて行ってもらったのだが、先生の頼りない運転はまるで絶叫マシーンのような刺激と興奮があった。
狭い車内で食べたマックのポテトSは、小さくて特別な喜びだった。
穏やかで天然な先生からは、礼儀と丁寧を教わった。
私が大人になり、先生とは近所のおばあちゃんという距離感になっていったが、つい先日旦那さんを亡くして程なく逝ってしまった。
先生の家も芝生の庭も玄関も、いつも静かだったから、今もまだ二人はそこにいるような気がしてしまう。
残された高枝用の高い梯子がいつのまにか片付けられていて、ようやく誰もいなくなってしまった。
子供時代は、奇遇にも地域で触れ合う先生が多く、どこか遊びながらという感覚と距離感があった。
学校と家以外の世界には遊びと好奇心があり、そこで得たのは技術や階級や知識よりも、触れ合いという温もりだったのかもしれない。
・
小中高それぞれに恩師と呼べるような先生、記憶に残る先生がいる。それはもしかしたらとても恵まれていることなのかもしれない。
小学校に入学した時の担任の先生は、母よりすこし年上で大きな縁のメガネが印象的な人だった。子供にとって長い時間机に向かい静かに集中する、それ自体が挑戦と対峙の連続だろう。
その人は教科書を開く授業にユニークな視点を加えてくれた。例えば足し算の授業なら、1が5つで5になる、その5を(ゴンタくん)という名で呼ぶ。6はゴンタくんと1、7はゴンタくんと2だ。
様々な授業の中で冒険を感じた。
その先生のもとで私は自由にたくさんの作文を書いた、それがとても気持ちよくて楽しかったのをよく覚えている。わくわくすること、好奇心は人をいつまでも躍動させる源になる。
小学校はマラソン大会だけでなく、毎日朝マラソンがある特殊な学校で、とにかくその時間が大嫌いだった。
毎日同じ道を走って、みんなの背中を見送って、いつもビリで。負けず嫌いだから最後まで走り切るものの、待たれるのも応援されるのも苦手だった。
ある時、他の学年の先生だから名前も顔も忘れてしまったがその人が、早くに友達たちを見送って後ろの方でひとり走る私に並走し、声をかけてくれた。
その先生は道端の花や田園から広がる景色、晴れ渡る青空を指差して、綺麗だね素敵だよ美しいよ、と。
そういうものを見ることを楽しんで、どんなに遅くても一歩一歩進めばちゃんといつかゴールするからと言ってくれた。そのやりとりがとても記憶に残っている。
目的は順位じゃなくていいんだ、速さを競わなくていいんだ、自分だけの理由を持って良いんだと。
高学年になると委員会に所属し、子供ながらに役割が増えてくる。
保健委員はとりわけやることが多いから、なり手が少なく2年連続になることが殆どだった。例外なく私も2年とも保健委員だ。
そのため保健室の先生とはやりとりも多く、その活動はとても濃厚なものだった。
学校保健委員会という情報交換や意見発表の場があり、子供たちはテーマに合わせた発表を年に何回もやるのだ。
演劇から新聞作り、映画も撮った、発表には至らなかったが漫画も描いた。
そういうことを子供だちにさせてくれる貴重な経験の場所だった。
避けられがちだったところにも、そんな面白いことが待っている。行ってみなければわからないものだし、案外とそんな時間から得たものは長く自分の中に残ったりするのだろう。
誰かと同じことをしてても、見えなかった景色だ。
・
中学に入ると急に自分も世界も大人びて、みな背伸びをし始める。
先輩や各授業の担当の先生、関わる人も所属先も増え複雑化していく。
中学の先生はどこか小学生の時の先生とは、違う気がした。
1日目に担任の男の先生を見てそう思ったのだが、メガネの奥は眉間に皺がより、スーツにネクタイと大変硬い印象。
そして自分の姿を見れば決められたみんなと同じ制服に身を包むわけで。何もかも型にはめられた世界は明らかに空気が違う。
本性がやんちゃな女子、と書いたがそれは中学でも健在であった。
私たちはスカートのウエストをバレないよう織り、色付きのコンバースを履き、おしゃれな髪留めで長い髪を括った、少しでも(自分)でいようとした。
そういうことを注意もされるのだが、文化祭や合唱コンクールなどといった、小学校にはない行事と部活動によって先生との距離や関係というのは、友達ではないが大人より自分たちに近い、そう思っていた。
部活の顧問は女の子の日を気にしていて、こっそりスカート大丈夫かな?と聞かれたことがあった。先生も女の子なのね、なんてしみじみ思った。
卒業式には生徒への激励に、先生たちがバンドを組んでTSUNAMIを演奏してくれた。
なぜか旅行なんかの行事が雨になることが多かったせいか、「思い出はいつの日も雨」が妙にしっくり来た。
教壇ではなく舞台で演奏する先生たちは、どこかいつもと違って楽しそうで、やはり友達ではないがただの大人でもなかった。
先生との距離も感覚も近くなっていく、それは自分たちが子供からどんどん大人に近づいているからなのだろうか。
もちろんこんなふうに先生に対して好意的に、好奇心を持って、見ていた子供達ばかりではないだろう。全てが良い思い出でもないし、かと言って悪い記憶ばかりでもない。
小さな地域で、同世代の顔ぶれが変わらないからこそ、先生という大人との出会いは貴重だったのだと後になって思う。
褒められることも厳しくされることも、自分に対しても誰かに対しても、その心の機微の中で人と自分を知ることを学んでいったのかもしれない。
・
とりわけインパクトの強い人がいる。
高校の部活の顧問なのだが、これがとんでもなくユニークな人でとんでもなくアーティストな人でつまるところとんでもなく変な人だった。
この先生から得たものはとても多い。
合唱部としては県内弱小、だけれどダークホースになってやろうぜ!と鼓舞する姿は映画「天使にラブソングを2」の聖フランシス高校のようではないかとワクワクした。
先輩も同級生も個性派揃いで部員も変わり者の集まりみたいなところだったが、どう考えても先生が断トツで風変わりなのだ。
真面目でお堅いイメージの強い合唱部界において、スカートが短く派手な私たちを注意することもなくとうの本人はカンカン帽にステッキを持ったサスペンダーのおじさんなのだ。もう刺激しかない。
変わり者とは褒め言葉で、音楽家としても表現者としても私はその先生に信頼を置いていたし、高校生という学校と社会の狭間で出会うべくして出会った人だと思っている。
先生の指揮からは、躍動する魂を学び、心と対話すること、伝え届けることのエネルギー性を教わった。身体と心が連動し、湧き出て生まれる(これ)を認め信じる術を知った。
それは先生が、私たちが発する歌声を信じてくれたからだと思う。
若い君たちにしかない、瑞々しい煌めきがその声にはある!そう高らかに言われたことをよく覚えている。
その先生とは芸術学科専攻だったことで、授業でも関わることが多かった。
職員会議ででんぐり返りをするような人だから、楽典の授業でオカリナを作らせたり(専門科目が多いおかげでたまたま焼き窯も校舎内にあった)、器楽の授業で民族楽器を作らせたりしたのだろう。
卒業の花向けに「ベティーブルー愛と激情の日々」を見せたのも、何を隠そうこの先生だ。
やりたいことを、やりたいように。
他の学校ではどんな授業をしていたのかは知らないが、これらの経験は他では得られないものとなった。
あるがまま、思うまま、表現者である私のまま、生きていくことを最初に許してくれた人だ。
どの学舎にも私を認めてくれた先生たちがいた。これらの出会いは当たり前ではない、感謝すべきものだと思っている。
・
言葉には魔力がある。
発した人が思っているより、時にその威力はとてつもなく強く重く痛い。
私を解き放った人がいれば、私を縛り付けた人もいた。
高校は専門科目を選択していくシステムで、学科棟にいることが多かった私は、そのせいでクラスメイトとも担任とも思いの外親しくはならなかった。
だが一年と三年は同じ人が担任だった。私のことをよく見てくれていたのだと今はなんとなく思う。
やりたいことも多かった、その分その時に何を選択するべきなのか当時は答えに自信が持てなかった。それでも時間は待ってはくれない。
タイムリミットのうねりの中で、ジタバタしながら見出した進路という結末に、迷いや不安が無いわけがない。それでも自分らしく生きていくことと表現することを自分の真ん中にして、なんとか辿り着いた答えだ。
とは言え、正解のルートが無い偶像を具現化する正しい答えなんて本当は誰も持ち合わせていない。
高校三年も残り何日もないある日。
薄光だけが差し込む、校舎の階段の上から見下ろされ、その担任は私の選択に
「裏切られた」
と言った。
こちらを見て逆光に立つ先生の顔は、覚えていない。
泥濘のような静けさに生まれた息苦しい影と、未来に震える18才の心の影が重なって、それはとても暗く冷たかった。
その後もしばらく長いこと、その先生の言葉は纏わりつき、首を絞められ、足を絡め取られた。
気にした、気にし続けた。
言葉は呪いだ、愛と憎しみは表裏一体だ。
一年の進路面談の時、先生は私の夢に対してこんなことを言った。
やりたいことがたくさんあるのは良いことだが、まずひとつ幹になるものを育てる、そうすればいずれその木は大きくなり、いくつも枝葉をのばしていくから。そうすればなんだってできるから、と。
奇しくも人生は繋がってしまっている。何度も巡って螺旋の様に進んでいく。それは人生というたった一つの道だからだ。
十六歳の三者面談から十八歳の階段の光景と、今もまた繋がっている。
(裏切られた)は(期待していた)とほぼ同一なのかもしれないと、ようやく今は思える。
それでも私はあなたのように「先生」を振りかざして人を見下したくない。
あの時私が頭の中にイメージした大きな大きな木は、風に揺れ枝葉の切先まで命そのもので、それはとても緩やかで静かな光の粒に包まれていた。
その木陰は、きっと今も寂しくて切ない。
それでいいと思う。
今その木が、自分自身を導く標になってくれているからだ。
・
まだ小さかった木は、雨に濡れ風に吹かれ揺れて震え何度も折れ、やがて本当に木になった。
皮肉にも、あれからもあの木は私の中で生き続けていた。
学校の先生はこれで全部。
いよいよ大人と呼ばれるようになり、私は自分のたったひとつの幹になるものを選んで邁進した。
そのターニングポイントは、ある作品との出会いだったのだが、その作者である杉浦志保先生との出会いがなければ私の木は、今は土の一部だったかもしれない。
もう折れて死んでしまったようだったその木から、小さな芽が息を吹き返したのだ。
先生の生み出した物語に、生きることを許され、恩返しのように駆け出した漫画家への道。
たくさんの人、たくさんの作品との出会いがあり、走り抜けた時間はある種、青春でもあり、それはとても生き急いでるようにも見えていた様だ。
その熱量は、時に炎のように、時に光のように私を駆け抜けた。
自分の身体と心の全てをかけて、育て上げた木は、やはりあの頃のイメージ通り命そのものだったのだ。
木は大きくなればなるほどその影を広げ、濃く深くなる。
それでも私は突き進み、先生と呼ばれることはなかったが、漫画家として杉浦先生にお会いすることもできた。その時はなんだかふっと肩の力が抜けて、安堵と誇らしい気持ちだった。
先生とは呼ばれないまま、筆を置くことになるのだが、おかげで今もこうして生きている。
あの木があったからこそ、だ。
言葉は本当に、力を持っている。
何度も伴走してくれた担当編集さんの言葉にも支えられ救われた。
私の生み出したものに触れ、命のこと、生きること、明日のことを話してくれた読者の人の言葉に励まされ守られた。
一度この手から生まれた彼らの言葉は、今も生き続けている。
ふとどこかで出会った誰かを救う、魔法になっていたらいいのに。
・
それでも今ここに至るまで、何度も挫けそうになった。ある日ふと折れてしまうような、そんな時間がたくさんあった。
その時出会った言葉の先生が、ガンジーの「明日死ぬかのように生きろ、永遠に生きるかのように学べ。」だ。
生きることは、自分を生きていくことは過酷で残酷だが、その悲しみの中に喜びがあって、深い影からしか生まれない光があることを知った。
今もそれを追いかけている。
私は誰かの前に立ち、何かを説くような先生にはなりたくない。
学びはきっと少し先の方で学びだったんだと気づけばいい。その時に生きていたらラッキーだ。
・
唐突に先生の話をしたのにはわけがある。
そんな先生のような立場に興味のない私が、友達の子どもたちと対話しながら表現や創作でクリエイトしようという場を持つことになったからだ。
とは言え、先生を名乗りお教室を開いて、持ち合わせた技術や知識をお教えしましょう、などというものではない。先生と言っても、またしてもそんな名前で呼ばれないであろう、「先生」だ。
それは私らしくていいじゃないか、とその機会を了承した。
子供も大人も分け隔てなく、私は私の言葉で対話ができるか感覚を理解し合えるか同じ類の人間かということをものさしに、己を大切にしている。
子供たちには、自由に生きていいんだ、自分という生き方を信じていいんだ、と思ってもらえる大人でありたい。
いつか彼らが子供と呼ばれなくなった時、可能性や選択肢や許しの前で思い出してもらえたら。
お手本や憧れにはならなくていい、ただこんな風にあるがままでもいいんだよと、伝えたいと思う。
だから教えるなんて大それてなくていいし、ママとパパと兄弟と学校の先生と同級生以外の人間も世界にはいるからどうか安心してほしい。
そんな特別で風変わりな、遊び場のともどちになれたらいいなと思っている。
・
誰かに教えを説きたくないと思うのには、理由が二つある。
一つは偉そうにものを教えるほど、知識を学んできたわけではないから。誰かに教えられる人はこれまで得てきた学びと知識に自信を持っているからではないだろうか。
そこにはきっと先生がいたはずだ。
私がこれまでやってきた事には直接教わるような先生はおらず、独学と感覚と助言で、我流の力技で、信念だけでやってきた。
それは人に教えるようなものでもなければ、渡せるものでもないからだ。
もう一つは、誰かになにかを強要したくないから、それはつまるところ自分が強要されたくないからという事なのだと思う。
教わることや学ぶことは強要されることとは違う。ちがうのだけれど、もし私から学ぶものがあるのなら勝手持って行ってほしい。
それが必要かどうかはあなたが見極めてほしい、そういう意味で強要したくないのだ。
随分勝手な言い分だ、やはり私には先生は向いていない。
・
何年かぶりに中学の頃の先生が所属する地域楽団の演奏会を聴きに行った。
偶然にも開場ロビーで団員の方々がお出迎えをしており、これまた数年ぶりに先生と話す機会を得た。
あまり変わっていないような、何十年も前から比べれば当たり前に老けてもいるのだが。出会った時から大人だった先生という存在は、不思議なもので幾つで再会してもあまり変わらないように感じてしまう。
なんだか自分だけがとても大きくなってしまったようで、少し気恥ずかしい。同じ時間が、経過しているというのに。
変わらずこんなことをやっているよ。
そう言って笑う眼鏡の奥の顔は、よく見れば皺も増え、やっと同じだけ時が過ぎたことを感じる。
派手な髪色を少し笑われて、そういえば中一の時に大きなシルバーの可愛い髪留めをしていたら、先輩にいちゃもんつけられたら困るだろと廊下でこっそり注意されたことを思い出した。
なんじゃそりゃと思った私も、やっぱりあの頃からあまり変わっていないのかもしれない。
変わらずやり続けていること、それならばきっと次の誰かに教えを説くこともできるだろう。
だから私が教えられることと言えば、自分らしく生きること、心の声に耳を傾けること、こんな人間もいるという事、それくらいなのだ。
・
今年最後のクリエイトな子ども会で私が描いた絵を、すごい!飾らなきゃ!と喜んでくれた子がいた。
絵を描く仕事をしたい!と言ってくれた子がいた。
なんだか泣きそうになった。
人前で描くのは昔から苦手だった、だから実は子供達の前で絵を描くのは少しどきどきしていた。
私が描き続けていたあの時間と、今の表現は私の中では地続きでも、それは私以外の人にはきっとどうでもいいことで。
あの頃どれだけ欲した優れた画力も、作家として存在し続けられる場所も、今はもう持ち合わせてないけれど、それでもこんなに幸せだよと…あの頃の私に伝えたらどんな顔をするだろうか。
子供たちからもらったこの気持ちが、心の中で灯った時、大切なことを思い出した。
幾多の評価より、たったひとりの生きる力の一部になれたことが嬉しかった、あの時の感情を。
行き場を無くした私そのものではなく、私が生み出してきたものたちが誰かの救いになったことが、どれほど私の救いだったかを。
ひとり歩んできた荒れ地にも、たくさんの種と星が芽吹いて満ち満ちていた。
だから私は変わらずこんな生き方で立っていられるのだ。
そこにはたくさんの寄り添いと眼差しがあり、それこそが私は師だと思うのだ。
これからも私は先生と呼ばれなくていい。
ただ、自分らしく生きてきたこととこれまでやってきて積み重ねてきたことが、この子らの未来のために何かになるのなら、そんなに嬉しいことはない。
・
その日、君の描いたカラフルで大好きな植物たちも、君の描い可愛い瞳の赤い女の子も、たったひとつの素敵な表現だった。
どちらも今のありのままの彼らから湧き出る、豊かなイマジネーションだ。
誰にも真似できない、誰かを真似する必要のない、ピュアな情熱。そういうものから自分自身を信じる勇気に繋がってくれたらいい。
それらを見せてくれる場所には、普段は厳しくも優しく抱きしめ全てを愛してくれるお母さんたちの眼差しがあることを、いつか子どもたちに話して聞かせたい。
きっと見えずらい世界に、なってしまっている。
だけど見えないものは、無いものとは違う。
そういう部分を想像する時、誰かのことや過ごした時間やいくつもの言葉が浮かんで、生まれたり育まれたりする。
それらを素直に表現できると、きっとまた誰かを愛し救う手立てが生まれるはずだ。
何よりも自分自身と大切な人を。
そのためには、素敵な遊び場と、そこにしかいないともだちを持つといいはずだ。
空気の冷えた冬のある夜、温かさに胸がぎゅっと包まれていた。
外は闇深く、凍てつく風も吹くだろう。
ままならないことは増えていくばかりかもしれない。
子供たちの行く道に、何ができるだろう。
そこにまだ私たちがいるのなら。
その道の暗がりで足元を照らす、純粋な星の瞬きを邪魔しない程度の、小さな光くらいにはなれないだろうか。