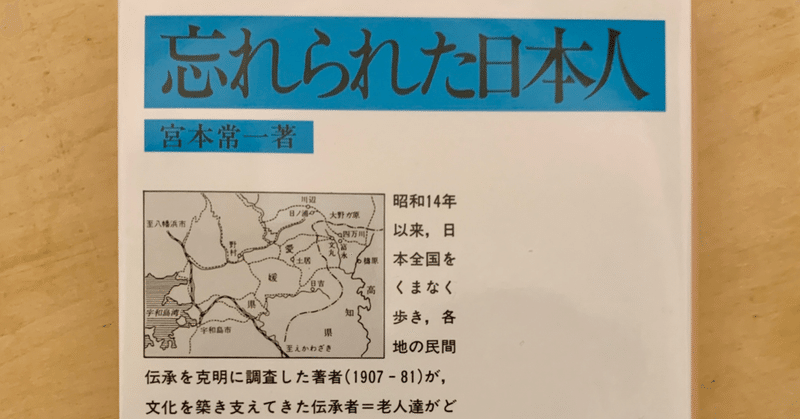
勝手に書評|忘れられた日本人
宮本常一(1960/1984)『忘れられた日本人』岩波書店(岩波文庫)
採集者として伝承者として
宮本常一(1907-1981)自身があとがきにも書いているように、この本の大半は雑誌『民話』(1958年に創刊された「民話の会」の機関誌)に隔月で連載された「年寄たち」という文章が元になっている。彼は、昭和14年(1939年)から全国各地を歩いてみてまわり、その遍歴は生涯続くこととなる。戦後しばらくは郷里である山口県周防大島で百姓仕事をしながら、西日本を中心に各地の庶民の生活について記録し、昭和27年頃からは約2年間療養生活を送ったため旅は一時中断するも、その後は山村を中心に再び全国を歩き回っている。本書は、こうした中で採集された人々の生活の話を一冊にまとめたものである。採集と言っても、客観的な記録や写真を隈なく取るといったようなものではなく、自らの足で村中を見て回り、文献があればそれを手で写し取り、旧家や農家の人々の話を半日や1日かけてじっくりと聞く、という自らの両手両足、両目両耳を使ったやり方である。彼自身が百姓として農業に造詣があったことから、村の生活の詳細が瞬時に想像され、人々とすぐに打ち解けることができたことは想像に難くない。こうして彼の身体を通して得られた人々の記録や伝承が、文章を通じてありのままに描かれている。本書のほとんどが各地の年寄りが語った昔の風俗や出来事について書かれたものであるが、そうして出来上がった本書もまた、今となっては忘れ去られてしまった文化を伝承する貴重な記録となっており、宮本自身も各地の年寄りたち同様に、一人の伝承者として、自らの見聞を語り継いだ実践者であったことを本書が証明している。
「忘れられた」普通の人々
「歴史」というのは、後の時代になって歴史家を中心に取捨選択によって切り取られた一枚の青写真に過ぎない。従ってその裏には、あるいはそれを支えるものとして、歴史家の手からは取りこぼされていった普通の人たちのなんていうことのないありふれた日常がある。そうした有象無象の生活を丁寧に汲み取った人が宮本常一である。
本書で描かれるような村は、都会の人や現代の人、つまり外からやって来た人にとっては、日々山や畑での仕事の繰り返しで退屈なように見えるかもしれない。それは文化的にも乏しい生活のように見えるかもしれないが、実際はその中にも深く奥行きのある世界が広がっている。また日々の生活は決して単調なものではなく、ことあるごとに人々が集まって歌い踊ったり、様々な噂話やエロ話をする機会がある。
ラジオも新聞もなく土曜も日曜もない、芝居も映画も見ることのない生活がここにはまだあるのだ。「働くだけだろうか」「そうでもないな。みんなで重箱つくって、中山(海岸部落)へ磯物をとりにいったり、魚をとりにいったり、やっぱりたのしみはあるもんだね」と老人がいった。(p.27)
とりわけ本書では「エロ話」というものが度々出てくる。男も女も、こそこそと、しかし時には楽しげに明るく、下世話な話をする。こんな話は、歴史の中では真っ先に切り捨てられてしまうものだろう。しかし、各地で生きる人々にとっては、一つの共通の楽しみであり、生活を面白くするものである。宮本常一はそれを下品な話だからと切り捨てるのではなく、村人たちの立場に立って、おおっぴろげには言わないものの、でも生活の一側面としてそれらを描こうとしたのではないだろうか。
一つの時代にあっても、地域によっていろいろの差があり、それをまた先進と後進という形で簡単に割り切ってはいけないのではなかろうか。またわれわれは、ともすると前代の世界や自分たちより下層の社会に生きる人々を卑小に見たがる傾向がつよい。それで一種の非痛感を持ちたがるものだが、御本人たちの立場や考え方に立って見ることも必要ではないかと思う。(p.306)
現実を生きる人々の持つエネルギー
こうして汲み取られた普通の人たちの生活から描かれたのは、彼らの持つ生命力であり、明るさであり、エネルギーである。
私の一ばん知りたいことは今日の文化をきずきあげて来た生産者のエネルギーというものが、どういう人間関係や環境の中から生れ出て来たかということである。(p.309)
このエネルギーについて、村の人たちは決して意識をしていない。外からの視点だからこそ、気づくものなのである。例えば、宮本が訪ねた高木さんという年寄りは、朝別れた宮本に会うためだけに、夕方、わざわざ山を越えて甥の家までやって来て、座敷にも上がらずに一言二言だけ言い残して、再び暗い夜道を火も灯さずに帰っていった。それに対して、甥である和田さんは以下のように言う。
「伯父はああいう人ですよ。伯父のしていることは伯父にとっては何もかもあたりまえのことですよ」和田さんは高木さんのかえったあとそういって笑った。(p.301)
村の人たちにとっては、自らがすることは全て当たり前のことであり、いちいちそうしたことについて言及したり自慢したりすることはない。
高木さんは単なる田園のロマンチストではなかった。りっぱな現実者であった。(p.285)
そう、ここに描かれている人たちは、ただ現実を生きているだけなのであり、著者もそれをロマンチックに描こうとはせず、ありのままに、しかし生き生きと描く。現実主義者は現実を第一として、理想や空想を退けようとするが、ここでいう現実者は、ただ現実をありのままに受け止めて生きている実践者のことなのではないだろうか。現実者の方が素朴で勇敢だ。
底抜けの明るさやあっけらかんとした様で、時代の荒波や日々の嫌なことも次々と乗り越えてしまう。もちろん、労苦がないと言ったら嘘になる。しかし、そうしたことも後から見ればやはり些細なことになってしまう。そういう飄々とした様子が共通して描かれている。なんていうことのない村々の生活をありのままに描くからこそ見えてくる人々のユーモアやエネルギーが、知らぬ間に私たちを勇気づけてくれる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
