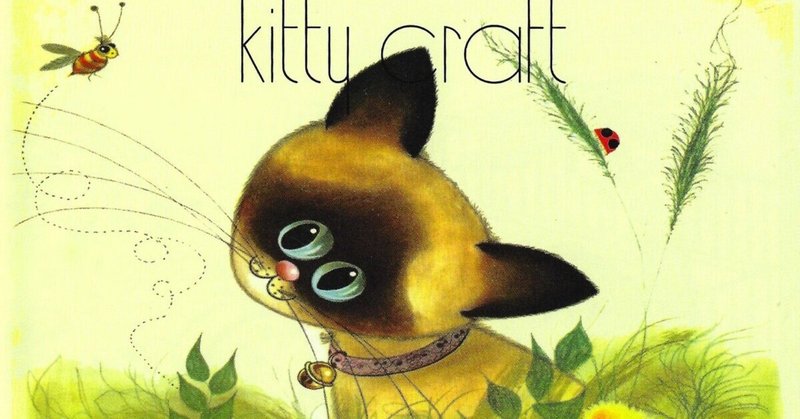
連続パンク小説『ババアイズノットデッド』 最終話
この世の全てのおばあちゃんと全てのおばあちゃん子に、そして最愛の祖母・笑子に心からの心を込めて本作を捧げる。
最終話 ババアイズノットデッド
9月30日、午後4時53分。
“孫と私”の出番までいよいよ一時間を切っていたが、ヒナタはまだ深いかなしみの中にいた。楽屋の片隅にじっとうずくまり、他の出演者のライヴさえ観ずにいた。床に腰をおろし、膝小僧に額をくっつけて、張り裂けるような胸の痛みにただ耐えるばかりだった。母親から報を受けてからスマホの電源はずっと切りっぱなしにしていた。もし、また母親が泣きながら電話をしてきたり、もしくはウメの逝去を知った誰かから連絡がきたりしたら、そのときこそ、もう耐えられないと思ったからである。そうしてヒナタがまんじりともせず過ごしているとき、誰かが楽屋の扉をノックした。
「すみませーん。いまだいじょぶっスかァ」
スタッフの確認か何かだろうか。ヒナタは顔を両手でぬぐい、こわばった身体でゆっくり立ち上がると、かすれた声で返事をした。
「……はい、どうぞ」
「失礼しゃっす」
そうして扉を開けて入ってきたのは、派手な格好をした長髪の青年だった。オーヴァー・サイズのペイズリー柄のシャツに袴のような太さのジーンズをはき、背中ぐらいまで髪を伸ばしたその青年は、人好きのする笑みを浮かべながらヒナタのところへやってくると、右手を差し出した。
「初めましてー、オレ、SAWAGASHIの主催の金子っていいます」
「ああ……どうも……」
「いやー、“孫と私”出てくれてめっちゃ嬉しいッスよー。今日マジでめっちゃ楽しみにしてるんでー、よろしくお願いしますわー」
「は、はい。がんばります……」
「頑張らなくていッスよ、楽しんでください。どの出演者より、どのお客さんより、自分が一番楽しむぞっていうガッツでヨロっス」
そして金子は握り拳を顔のまえで作ってニカッと笑った。ヒナタが愛想笑いを浮かべると、金子は長い髪を掻き上げながら続けた。
「ていうか、“孫と私”のライヴ映像ー、超衝撃でした。マジでめっちゃくちゃウケた」
「うけた?」
「いや、ウケるって別にー、なんかバカにして笑うとかじゃなくてー、もっとスーパーでハイパーな意味っスよ。あのー、正直世の中ってめっちゃつまんないじゃないッスかぁ。世の中つまんなすぎてヤバくないスか?」
「……まぁ、そうですね」
「“フツーはこうする”とか“みんなやってる”とかそういう価値観に縛られて、好きなこともできなくて、最終的に何が好きなのかもわかんなくなって終わってく人ばっかじゃないですか、この国は。まぁ実際日本だけかわかんねーけど。海外行ったコトねーし」
「……はい」
「でもー、ホントは“フツー”なんてどこにも存在しないし、“みんな”は絶対なんにもしてくんないんスよね。“孫と私”は、そーゆーのを本能的に理解してるヒトたちなんだなって思ったんスよ。こういうヒトたちが世の中に存在してるってゆーその事実だけでオレはめっちゃくちゃ嬉しかったし、こういうヒトたちが存在するってゆーコトをもっと知らしめなきゃいけねえって思ったんスよ。だからー、あのー、何つーか、やっちゃってください。やってやって、やりまくってください。マジかっけーって叫びながら爆笑できる音楽がいちばんサイコーだと思ってるんで、オレは」
金子は顔をほころばせながら愉しそうにそう語った。ヒナタは胸がかあっと熱くなるのを感じた。ソレは、こんな自分でも誰かに何かを伝えることができたのだ、心を揺り動かすことができたのだという感動であった。この瞬間、ヒナタはじぶんの音楽の力の一端というものを初めて知った。What a Wonderful World。ミュージシャンはこうした言葉に何より励まされるものである。そして金子は腰に手を当ててカラカラ笑うと、楽屋を見回した。
「そんでー、えっと、おばあさまは今どちらッスか?」
「おばあちゃん……は……」
ヒナタはうつむいた。SAWAGASHIサイドにはウメが入院したことも、ヒナタひとりで出演するつもりだということもずっと伏せていた。そしてついさっき、ウメが亡くなったということも……。下唇を噛み締めたまま黙っているヒナタに、金子は不思議そうに首を傾げた。
「ン? どうしたんスか?」
「おばあちゃんは……おばあちゃんは……」
ヒナタが言葉をつぐんだそのとき、スマホが鳴った。
「あー、すんません。ちょっと電話出ますね」
金子は袴のようなジーンズの巨大なポケットからスマホを取り出して画面を見た。
「お、脇殴さんだ」
その名前を聞いてヒナタは思わず肩をぴくんと揺らした。金子はスピーカー通話に切り替えると電話に出た。
「うすうすー。どーしたんスか?」
『どうもっ、夫がいつもお世話になっとりますっ、“ナイスガイズ”のベースの脇殴ジローの妻っ、アズキですうっ!!』
……ラウドでキュートな関西弁が楽屋に響き渡った。ヒナタはまたぞろ肩をぴくんと揺らし、金子は若干戸惑い気味に眉を寄せながら頭を掻きつつ答えた。
「あ〜、ドモドモドモドモ、こちらこそめっちゃお世話になってます、ワッサです」
「ちょおジロちゃん運転中やからウチが代わりに伝えさせてもらいますっ。あんな、話せば長くなるねんけど、いま、“孫と私”のドラマー乗っけてそっち向かっとるとこやねん!」
『え?』
ヒナタと金子、ふたりの声が同時に重なった。ヒナタは大いに混乱した。どういうこと? さっき死んだはずのおばあちゃんが、なんでジローさんの車に乗ってるの? 真相を尋ねようとヒナタが声を発しかけたとき、アズキの関西弁がふたたび炸裂した(二の句を継がせぬとはまさにこのこと)。
「んで今、めちゃめちゃクルマ飛ばしてんねんけど、正直出番にギリ間に合うかどーかって感じやねん! だからあの、関係者用駐車場使わしてもらえんやろか?」
「あーあー、とりあえず了解ッス、いや事情とか全然わかんねーけど了解ってことにしとくッス。なるほど遅れて来る感じだったんスね。いまちょーど楽屋来てたんですけど、おばあちゃんの姿見えねえからどうしたんだろ〜って思ってたんスよ」
「頼むわ! スバルのインプレッサWRX、色は赤っ、ナンバーは……」
そうしてハイテンションでまくし立てるアズキに割って入るかのように、その背後から重厚かつリヴァーヴのかかった野太い声が聞こえてきた。
『そこのスバルのインプレッサWRXっ、そこの赤いスバルのインプレッサWRXっ、品川ナンバー330 しの420っ! 止まりなさーいっ! 速度超過にも程があるぞ! 危険運転も大概にしなさい! いますぐ車を路肩に止めなさーいっ!!』
「ちっ、うざいなぁ。いつまで追ってくんねん」
心底ダルそうに舌打ちするアズキに、金子が慌てて尋ねた。
「え、ど、どーゆーコトっスか? いまどういう感じになってんスか?」
「んーと、中継やってるっぽいからTVつけてみて」
金子はスマホを手に持ったまま、楽屋に備え付けられた小型TVのスイッチを入れた。やがて画面にあらわれたのはヘリコプターによって上空から撮影された中継映像で、幹線道路を爆走する赤いクルマとそれを追うパトカー群のカーチェイス模様が映し出されていた。画面右上には『LIVE時速160キロ暴走車 警察追跡中』とテロップが出ており、アナウンサーが“警察の呼びかけも無視して暴走を続ける乗用車、いったい何が目的なのでしょうか”と深刻な声でしゃべっていた。金子とヒナタがあんぐり口を開けてそれを注視していると、アズキが平然とした声でいった。
「観た? とりあえず今はそんな感じや」
ふたりはしばし口もきけずにいたが、やがて金子が相好を崩し、笑い声をあげた。
「……うはっ」
その笑い声はたちまち爆笑へと変わり、金子は両手を叩いて本当に嬉しそうに笑った。
「うっははははははははははは!!!!! ぎゃははははははははははははは!!!!!!!!! やベー! 超やっべー! めちゃくちゃ盛り上がってんじゃん! もうこれ映画じゃん!」
「せやろ、映画みたいやろー。クライマックスには絶対間に合わせるから、感動のエンディングのためにそっちも対応よろって感じー。ほいじゃ、もうそろ電池切れそうやからまた後でな」
「うっす、ワッサでーす」
そのとき、ずっと黙っていたヒナタがついに口を開いた。
「あ、あ、あのっ、アズキさんっ!」
「お? その声はお孫ちゃんやな?」
「は、はいっ! あのっ、おっ、おばあちゃんはっ……い、生きてるんですかっ!?」
「おー、めちゃめちゃ元気そうやでー。後部座席でクソクソにはしゃいでるわ」
「ちょっと、電話、変わってもらっていいですかっ!?」
「ん、おっけ。はーい、おばあちゃん……」
そして受話器の向こうでガサゴソ音がしたかと思うと、唐突に電話はプツンと切れた。
「えっ、あっ!? も、もしもしっ! もしもしっ!?」
狼狽するヒナタの隣で、金子はくつくつ笑いながら肩をすくめた。
「あー、電池切れたっぽいスねー。にしてもマジでやべーなー。こんな風に会場入りするバンド初めてッスわー。めちゃくちゃ炎上すんだろーなー」
「え、炎上とか、そういうレベルじゃないでしょ……」
「まぁウケるからいいッスけどね。最終的にはウケりゃいいんスよ、全部。少なくとも、こんなん伝説確定ッスからね」
「でんせつ……」
ヒナタは訳も分からず、ただ首を振るばかりだった。ただ、胸の中で渦巻いていた悲しみはいつのまにか消え、ハートは強く、強くときめいていた。
※ ※ ※
一方その頃、時速160キロで疾走する車の中では、ウメが首を傾げながらアズキにスマホを返していた。
「……アズキしゃん、これ、電池切れとる」
「ありゃー、充電器忘れちゃったんよねー。ごめーん」
「いえいえ。それより、ヒイちゃんは……孫は、元気そうですかねえ」
「うん? んー、少なくとも声は迫力ある系やったで」
「さいですか」
「あ、おばあちゃん、カリカリ梅食べる?」
「ありゃありゃこれはこれはどうもどうも、いただきます」
そうしてウメとアズキがカリカリ梅を頬張っていると、追走するパトカーがふたたび拡声器越しに呼びかけてきた。
『そこの車っ、止まりなさい。今すぐ止まりなさい、即刻止まりなさい、大至急止まりなさーい。このままだと大変なことになるぞー』
アズキは助手席の窓から顔を出すとパトカーに向かって叫んだ。
「止まるワケないやろボケが! それにもう、とっくのとうに大変なことになっとるわ!」
そしてアズキは舌打ちしながら頭を掻きむしると、運転席のジローを見やった。
「なぁジロちゃん、あいつらうるっさいわー。ええ加減なんとかまけへんかな?」
ジローは血走った目でまっすぐ前を見据えたまま答えた。
「まかせろベイビー」
そしてジローはいきなりハンドルを切って右車線へと突っ込んだ。そしてそのまま道路沿いの金網をブチ破ると、舗装工事途中の砂利が敷き詰められた広い工事現場を走った。横並びになっていたパトカーはすぐさま縦列編成となり、金網を突破してジローたちを追ってきた。砂埃を舞い上げながら車は爆走をつづけた。
「しっかりつかまってな!!!」
そう叫ぶとジローはハンドルを思いっきり切って車をドリフトさせた。急旋回した車に反応しきれずパトカーが一台、地面から突き出した消火栓に衝突した。激しく噴き出す水柱を横切り、ジローはさらにもう一発ドリフトをかまして砂埃を舞い上がらせた。噴き出した水によって濡れたフロントガラスに砂が付着し、突如として視界を奪われたパトカーはそのまま現場隅のプレハブ小屋へと突っ込んだ。
「チェケラ!」
ジローは小さくガッツポーズを取ると再びアクセルをベタ踏みして急加速し、そのまま工事現場を爆走するとふたたび道路に突っ込んだ。間髪入れずにパトカーも道路へと乗り入れると猛追を続けた。平坦な山道をアクセル全開で突き進むうち、やがて見えてきたのは踏切であった。踏切では赤いライトが点灯し、遮断機がゆっくりと降り始めており、左手のほうからコンテナを積んだ長い貨物列車が今まさにやってこようとしていた。パトカーの群れは後方からぐんぐん迫ってきており、貨物列車が通過するまで停まっていれば一網打尽になることは火を見るより明らかだった。
「クソっ、くそっ、ちくしょうっ!!」
ジローは拳でハンドルを叩きながら顔を歪ませた。アズキはサイドミラーに映るパトランプの光を睨みながら唸り声をあげた。
「あ〜〜〜っ、んもうっ!!!」
ついに遮断機が降り、甲高い軋轢音を響かせる貨物列車が行く手を完全に遮った。もはやこれまで、絶体絶命。車中の三人が肩を落としかけたその刹那、アズキが何かに気づいたように声を張り上げ、前方を指差した。
「ジロちゃんジロちゃんっ、あれっ、あれ使おっ!!」
「アレ!?」
指し示されたほうを見やると、踏切の手前の道路現場で、パワー・ショベルが砂利をスロープのようにして積んでいるのが視界に飛び込んできた。アズキが何を言おうとしているかを瞬間的に理解したジローはしかし、声を張り上げた。
「おいおいおいおいっ、本気で言ってんのかよっ!?」
「本気も本気、リアルでガチにマジで本気やっ!」
「いくら何でもそりゃ無理だよ!」
「無理やないっ! さっき金子さんも言うとった、映画みたいやって! なら、とことん最後まで映画みたいなことしようやっ! だってこれがもし映画やったら、ここで必ずそうするやろっ!?」
「……っ! だぁっ、クソっ、イチかバチかだ!!」
ジローは緩めかけていたアクセルを再び底まで踏み込むと、大声で叫んだ。
「我が生涯にッ!!!!!! 一片の、悔い、ナシっっっ!!!!!!!!!!!!(!!!?)」
車は風を切りながらまっすぐに突っ込んで行った。砂利製の“ジャンプ台”に狙いをさだめて。
そうして車は、右側のタイヤをかろうじて“ジャンプ台”に乗っけたような形で砂利を駆け上り、そのまま高く宙を舞った。時間が弾力を帯び、ゴムのように長く引き伸ばされた。ゼリー状の空気を泳ぐように車がゆっくり(素早く)空を飛んでゆく。
バランスを欠いたまま射出された車は宙でぐんぐん左側へと傾いていった。貨物列車に積載された鉄製のコンテナの、乾いたペンキがめくれたところから覗く赤錆びた箇所さえ、はっきりと視認することができた。コンテナがぐんぐん近づいてくる。
「〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ッッッッ!!!!!!!!!!!!!!」
ジローとアズキとウメは声にならない悲鳴をあげた。全開になった脳細胞が発火し、ニューロンが興奮して、『死』だの『激突』だの『生きたい』だの『責任』だの『愛』だの『光』だのいう単語がいちどきに脳の裏側で狂い咲いた。
——そして、奇跡は起きた。
宙を飛びながら傾き続けた車は完全に垂直になり、積まれたコンテナとコンテナの間、そのわずか二メートル弱の隙間をスルリと潜り抜けた。そうして車はそのままくるりと一回転し、激しい衝撃と共に道路へ着地した。そうしてパトカーの追走を振り切り、走り続ける車中にてジローもアズキもウメも口を半開きにしたまましばし呆然としていたが、やがてジローが気の抜けた声で言った。
「……おしっこ、もれるかと思った……」
アズキがそれに追随した。
「うちも……」
後部座席で顎をなぜていたウメが、トドメをさすようにつぶやいた。
「……わたしはもう、とっくにもらしとります」
車が突き進むその先に広がる空は、いつのまにか灰色の雲が立ち込めていた。まさに文字通りの“嵐の予感”であった。
※ ※ ※
9月30日、午後5時52分。
SAWAGASHI会場は、突然の大雨に見舞われていた。昼時の快晴が嘘だったかのように激しく降り注ぐ大粒の雨は、集まった観客ならびにスタッフや出演者を大いに混乱させていた。それでもスタッフの尽力によってフェスは今のところほぼオンタイムで進行しており、観客たちは雨合羽や長靴を装備して悪天候を必死に耐え忍んでいた。そうして泥まみれのスタッフが走り回りながら必死にステージをセッティングする様子を、ヒナタは舞台袖から固唾を飲んで見つめていた。“孫と私”のスタート時間を迎え、もういつ号令がかけられてもおかしくない状況だったが、ウメはまだ姿をみせていなかった。ヒナタはあのあとすぐに母親からかかってきた電話で、亡くなったはずのウメが病室から消失した話を聞いていた。母親は半狂乱になっていたが、ヒナタはウメが警察とカーチェイスを繰り広げながらこちらに向かっているということは言わずにおいた。そんなことを伝えればなおさらパニックになるのは明らかだったからだ。その後のニュースによれば、ウメたちの乗った車は警察の追走を振り切って行方をくらまし、上空から撮影を続けていた報道ヘリも悪天候によって撤退を余儀なくされたため、その動向はまったく不明のままとなっていた。
——おばあちゃんはいま、どこでなにしてるんだろう。
ヒナタの頭の中でぐるぐる渦巻くのはそればかりだった。目前に迫った本番への不安や、ひとりでステージへ出て行くことへの恐怖などもないまぜになって、ヒナタは初ギグのときとは比べ物にならないぐらいの強い緊張におそわれていた。親指の爪を無意識に噛みながらステージを見つめていると、肩からタオルをかけて頭からつま先までずぶ濡れになったスタッフが声をかけてきた。
「“孫と私”さん、準備オッケーです。よろしくお願いしまーす」
ヒナタの心臓がひときわ強く波打った。それでもヒナタは大きく息を吸って吐くと、拳をぎゅっと握りながら絞り出すような声で答えた。
「……はい」
ヒナタは逸る鼓動をなだめるように右手で胸を抑えながら、ゆっくりと、ステージの中央へと向かって歩いていった。そうしてマイクスタンドのところまで来ると、ヒナタは前を向いた。そこには降りしきる大雨の中、ゆうに千人をこえる客が集まっていた。そしてそのいずれもが、ヒナタに対してまっすぐ視線を向けているのだった。人生で経験したこともない、大量の視線が肌に突き刺さるのをヒナタはひしひしと感じた。全身の筋肉がたちまち強張り、喉の奥が“ひゅっ”と鳴った。ヒナタは震える手でスタンドに立ててあったTOYOTAのギターを取ると、それを肩にかけた。そしてマイクに向かって何か言おうとして、とくにいうべき言葉も思いつかなかったので、かわりに小さく頭を下げると、ヒナタはゆっくりと歌い出した。
——じゃらん、じゃらん。
コードをストロークしながら、ヒナタは大きな声で歌おうとした。おじける自分を奮い立たせるかのように、凄まじい雨音に負けないように、できるだけ大きな声で歌おうとした。けれど、大きな声を出すことはできても、リズムや音程をうまくとることができなかった。そしてそのズレを必死に修正しようとすればするほど、ますます歌はちぐはぐなものになっていくのだった。その歌はさしずめ平均台の上で今にも落ちそうになりながらも右に左に必死にバランスを取ろうとする体操選手のごときであった。
——じゃじゃん。
どうにか一曲を歌い終えたヒナタがあらためて前方を見たとき、詰め掛けた観客たちの顔に浮かんでいたのは困惑だった。苦笑や溜息があちこちで起こり、程なくそれは失意を帯びたざわめきへと変わった。ヒナタは立て続けに二曲めを歌おうとしたが——声が、出なかった。指がもつれてギターを弾くことさえままならなかった。たったひとりでステージに立つという重圧に、ヒナタの心はもうすっかり折れかけていたのである。ヒナタは泣き出したいような気持ちだった。
——おばあちゃん、ごめん。おばあちゃん、ごめん。やっぱ、無理だった。
そしてヒナタが目を閉じた瞬間だった。
背後からエイトビートが鳴り響くのが聞こえてきた。
ヒナタがはっと振り返ると、ドラムセットに座ったウメが、枯れ枝のような細腕でリズムを刻んでいた。
ウメは手術着姿で髪もぐちゃぐちゃ、顔もドロドロだったが、そのリズムは力強く、しなやかだった。そうしてポカンとしているヒナタと目が合うと、ウメは歯を見せてニカッと笑った。
その笑みは、たったひとつのメッセージをヒナタに伝えていた。
——ブチカマセ。
ヒナタはこくんと頷くとふたたび前を向き、ギターをかき鳴らして歌った。力のかぎり歌った。リズムも音程も声量も、もはやどうだってよかった。ただ今この瞬間を全身で呼吸しようと思ったのだ。音楽の中に深く潜りこんで、誰よりも何よりも愉しもうと、ただそう思ったのだ。初めてギターを持ったあの日のような純粋な気持ちで、ヒナタは歌い、演奏した。
二曲めを演奏しおえて再びヒナタが前を向いたとき、目に飛び込んできたのはパトスだった。千人がとこの観客たちはみな一様に感情を爆発させ、“孫と私”の演奏に快哉をさけんでいた。激しい雨音をかき消すほどのその咆哮は、ヒナタの皮膚をびりびりと震わせた。これまで感じたことのない強い気持ちが胸の中で炸裂し、全身が張り裂けるのではないかと思うぐらいだった。ライト・マイ・ファイア、ヒナタのハートはメラメラと熱く燃えていた。
それからも、ふたりは立て続けに楽曲を演奏した。何度も目を見合わせ、笑いながら、ギターを弾き、ドラムを叩いた。全身を突き抜けるような強烈な歓びを味わいながら、ヒナタはたったひとつの確信を持っていた。
音楽とは、それが演奏されているその場所だけに存在するものではないということだ。
いま、ここで鳴っている音楽は、いつかの、ここではないどこかにも届いている。
ここにいるわたしたちとあなたたちにも、ここにはいないわたしたちとあなたたち以外にも、この音楽はきっと、きっと響いている。
すべてに向けて歌をうたおう。
ギターを弾こう。
ヒナタは祈るような気持ちで演奏を続けた。観客のヴォルテージはどんどん高まるばかりだった。
そうしてどんどん時は過ぎ行き、ついに最後の曲を残すのみとなったとき、ふたりはどちらからともなく手を止めた。雨は依然として強く降り注いでいたが、会場の熱狂は凄まじかった。そして観客の数は三倍にも四倍にも膨れ上がっていた。ウメは眼前を埋め尽くす大観衆に手を振ると、コーラスマイクを握って、こういった。
「人は、いつか死にます。絶対ぜったいぜえええ〜〜〜〜ったい、死にます」
およそフェスには似つかわしくない、あまりに縁起の悪い言葉。興奮状態だった会場の空気に少しだけ靄がかかったが、ウメはまったく気にしないそぶりで話し続けた。
「……けんども、それでええんです。いいや、だからこそ、ええんです。
もし、わたしたちがいつまでも永遠に生きられるとしたら、愛なんてモンは無えでしょう。
喜びも、感動も、何かを考えることも無えでしょう。
いつか死ぬから、いつか必ず終わりがくるから、いまこの瞬間を大事にできるんです。
誰かを思いやって、愛することができるんです。
いまここにいる皆さんは、それぞればらばらな人間です。
背の高いひと、お金持ちのひと、病気しているひと、恋に悩んでいるひと、
ほんとうにそれぞれ、いろいろあることと思います。
けんども、皆さんにたったひとつ、たったひとつだけ、共通していることがごぜーます。
それは、生きている、ということです。
あしたのことはわかりません。
ただそれだけが、ゆいいつ、はっきりしていることです。
とにかく、皆さんは、生きておるんです。
生きていれば、生きてさえいれば、
なんにだってなれるし、どこへだって行けるし、どんなことだって出来るんです。
これは、生きているひとの特権です。
人生は、大変です。
ええことなんかほんのちょびっとで、つらいこととか、苦しいことのほうが多いかもしれません。
けんども、それでもきっと、楽しく生きることはできます。
そのために、ドキドキする何かを、見つけてくださいな。
じぶんにとことん素直になって、
いま楽しいこと、いま興味があること、いま大切なことに、
思いっきりのめり込んでみてくださいな。
いつか必ず、わたしたちは死ぬんです。
だったら最期は、ああ面白かった、と笑って死のうじゃありませんかえ。
それが、それこそが、ハッピーエンドなんだと思います。
ハッピーエンドまで、突っ走りましょうや」
そしてウメがマイクを離すと、一瞬ののち、会場全体から万雷の拍手が鳴り響いた。ヒナタとウメは顔を見合わせると、互いにうなずき合い、笑みを浮かべた。そうしてヒナタはギターを軽くつま弾いたあと、マイクに向かっていった。
「……はい、今日はどーもありがとうございました。
“孫と私”でした。
なんかいろいろ喋ろうかなって思ったんですけど、
言いたいこと、ほとんど全部、おばあちゃんに言われちゃったんで。
だから、最後の曲のタイトルだけ言います。
そのタイトルが、いま、わたしが本当に言いたいことです。
それじゃ、最後の曲です。
“ハートを燃やせ”」
そして、ウメのカウントののち、ふたりは演奏になだれ込んだ。爆発的で、感動的で、剥き出しの生命そのもののような演奏と、会場の熱気については、このフェスの名前が一番ぴったりくるだろう。
SAWAGASHI。
最後の最後の最後の瞬間までふたりは騒がしを続けた。そうしてふたりが演奏を終えてステージから去った後も、会場は激しい熱狂に包まれたままで、もうどうにも止まりそうにもないのであった。
ステージ袖を抜け、楽屋へ続く通路を歩きながら、後ろをついてくるウメにヒナタはいった。
「……ったくもう、おばあちゃん、ほんとに、ホンットーに心配したんだからね」
「ああ、すまなんだ」
「どーゆー奇跡が起きたらこーゆーコトになるのかぜんっぜんわかんないけど、でも、とりあえず元気ならそれでいいや。すぐ病院に戻って、事情説明しなきゃね。みんなびっくりするだろうな。死んだと思ってたヒトがフェスでドラム叩くなんて、そんなの、前代未聞でしょ」
「ヒイちゃん」
「なに?」
「……ありがとうね」
「……っは。なに今更、ヘンに改まって」
照れ臭くなったヒナタが前を向いて肩をすくめると、ウメは優しい声でつづけた。
「……おばあちゃんは、ずっと、ずうっと、ずううっと、ヒイちゃんの味方だからね」
ヒナタは頭を搔きむしりながら振り返った。
「〜〜ッ、だからっ、なにっ、そういう恥ずかしいコト突然言うのやめて……よ……?」
そしてヒナタはうろたえた。さっきまでいたはずのウメの姿はどこにも見当たらず、祖父の形見のドラムスティックが地面に落ちているばかりだった。ヒナタはキョロキョロあたりを見回したが、どこにもウメはいなかった。ウメは忽然とその姿を消していた。
※ ※ ※
十年後。
アンティークのシャンデリアや壁の照明器具がなんとも落ち着いた雰囲気を醸し出す、古めかしい喫茶店の片隅で、音楽雑誌『アントン』の若手ライターは、信じられないといったふうに目をパチクリさせながら取材相手に尋ねた。
「……ええと、つまり、それ以来、おばあさんは消えてしまったと?」
ライターの向かいに座った取材相手は、短く切ったベリーショートの赤髪を撫でると微笑みながら答えた。
「そうです。家にも病院にもスタジオにもどこにもいなかった。未だに行方知れずのまま」
「……その話、ホントーだったんですねえ……」
「アタシも、ウソだって言いたいぐらいなんですけどね。本当なんだから仕方ないです。生きてるとも死んでるとも言えない。ノットデッド、ですね」
「たった二回のギグをやっただけで、正規音源のリリースもないのに、音楽史でもオカルト史でも伝説になったバンドって、他にいないですよ」
嘆息まじりにいうライターに、赤髪の女性は八重歯を見せて笑った。
「そうですよね。ソロデヴューしてもう五年、や、六年になりますけど、その伝説とはずっと戦いっぱなしです。どこ行ってもその話ばっかり。きっと、ずっと超えられないんだろうな」
「……お嫌、ですか?」
「ううん。だって、いい思い出だもん。間違いなく、アタシの人生最高の夏だった。もしアタシの人生が映画だとしたら、きっと予告編のほとんどはあの夏の出来事になっちゃうと思う」
「……あの、実はわたし、あのバンドの大ファンなんです。今朝もラストライヴの映像を観て、号泣してきたばかりで」
「あはは。ありがとうございます。アタシもたまにアレ、観ますよ。自分でいうのもなんですけど、元気出ますよね」
「はい。もう百回ぐらい観てますけど、本当に、ドキドキします。いわゆるあのう、末期癌で死亡認定されたはずの患者がカーチェイスの末にフェスに出て、その直後に忽然と姿を消したっていう伝説。その伝説を抜きにしても、ほんとうにいいバンドだと思います」
「えへへ、嬉しいな。アタシもそう思います。でもアタシのソロもなかなかいいんで、そっちもしっかり取り上げてくださいね?」
「もちろん、もちろん。ところであのう、おばあさんを乗せてカーチェイスを繰り広げたご夫妻って、その後はどうされてるかご存知ですか?」
「はい、いまも仲いいですよ。こないだも家に遊びに行きましたし。お子さんも最近は結構大きくなってきたんで、そのうち楽器覚えさせて一緒にバンドやろうかな、なんて」
「百万を超える嘆願書によって、あれだけの追走劇を繰り広げながら無罪放免になったというのもまた結構すごい伝説ですよね」
「あはは、ほんとだ。奇跡に奇跡が積み重なってますね。つくづく滅茶苦茶な夏だ」
「ええと、本日は、伝説のロックバンド、“孫と私”について色々詳しいお話を聞かせていただき、本当に感激しております。それでは最後の質問です」
「おっ、どんとこい、です」
「春野ヒナタさん。あなたはコンサートのMCで毎回必ず、話をしよう、と観客に呼びかけます。あれには何か意味がおありなのでしょうか?」
ヒナタははにかみながら頰を掻くと、ライターの目をまっすぐ見て答えた。
「ええと……そのままの意味です。人とおしゃべりするのってすごく素敵なコトだと思うんです。最近観た映画の話とか、友達の家で飼ってる猫がすごく可愛かったとか、そんな話でいいんです。他愛もない話をして繋がり合う時間が大事なんです。誰かと繋がりたいっていう気持ちが世界を動かしてると思うんです、音楽もそういう気持ちから生まれたと思うんです。アタシの音楽を聴いて、誰かとなんでもない話をしたくなってくれたら、すごく嬉しいです。なんでもない話をしたくなる人っていうのはきっと……なんでもない人じゃないんです」
そしてヒナタは微笑むと、ゆっくりとピース・サインを向けた。
(完)
♪Sound Track :Par 5 / Kitty Craft
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
