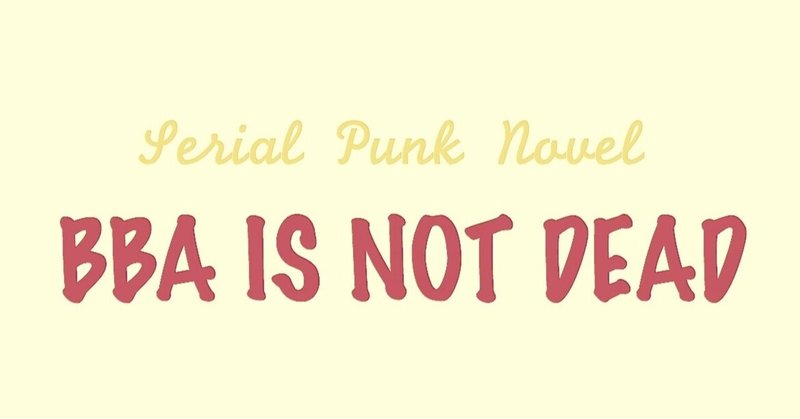
連続パンク小説『ババアイズノットデッド』 第一話
この世の全てのおばあちゃんと全てのおばあちゃん子に、そして最愛の祖母・笑子に心からの心を込めて本作を捧げる。
第一話 ババアイズデッド
御年71歳の春野ウメは、都内の某医科大学病院の一室にて、いままさに息を引き取ろうとしていた。五感はすでに遠のき、白い光につつまれながら、ウメはしだいに弱まっていく己の鼓動を、どこか他人事のようにながめていた。自分は死ぬのだ——と思ったし、ごく当たり前にそれを受け入れることができた。そして鼓動の間隔がしだいに長くなり、ついに完全にビートがとぎれたとき、突然、それは起きた。
ウメは、生涯に起こったすべての出来事を同時に体感した。幼いころに母親の背中におぶわれて見た真っ赤な夕焼けだとか、小学校へ通う道すがらで野良犬に噛まれたこととか、中卒で就職した洋裁工場で同僚にさそわれて初めて夜の盛り場に繰り出したこととか、人生のあらゆる瞬間が波のように一気に押し寄せてきた。それは単に過去の記憶を思い出したとかそういうことではなかった。花の香りも、頬を撫でる風も、ひとつひとつが鮮やかで生き生きとしていた。
いわゆる“走馬灯”というヤツである。
ウメはとてもおだやかな気持ちで満たされていたが、やがてそれが過ぎ去ると、真っ暗闇がやってきた。それも、今にも何かが起こるその一拍手前のブレイクという感じの、どこか不穏な暗闇だった。そのとき、ウメがかんじたのは、あるひとつの後悔であった。たったひとつだけやり残したこと。急速に溶けゆく自我をふるいたたせ、ウメは、最期に、思いっきり叫ぼうとした。
それは世界にたったひとりの、愛する孫娘の名前だった。
……話は半年前にさかのぼる。
よく晴れた四月某日の朝、ウメはI市の自宅リビングで家族とともに食卓を囲んでいた。大きな窓からはお天道様の光が差し込み、可愛らしいメジロのさえずりも響いていたが、リビングの風景は朗らかな朝の団欒とは程遠いものだった。嫁のビワコは頬杖をついて足を組み、だぶついた象牙色のカーディガンの袖から出した指先で、せわしなくテーブルをコツコツ叩いていた。
「ねえお義母さん、早く食べてくれない? ワタシ今日は町内会の草むしりがあるの。それまでに掃除も洗濯も一通り終わらせておきたいの。早く片付けちゃいたいから急いで食べてちょうだい」
そういってにらみつけてくるビワコに対し、木綿の格子柄の着物をきたウメは箸をもったまま小さく頭を下げた。
「すまなんだ。これでも一生懸命食べとるんだけども……」
「それにお義母さん、きょうは健康診断の再検査で病院予約してたでしょ。早く支度しないと間に合わないでしょ」
「ああ、うん、わかっとる。わかってます」
「あ、ちょっと、シャケの骨まで食べるのやめてって言ったじゃない」
「や、どうも勿体なくてなあ」
「ビンボー臭い。意地汚く見えるからやめてちょうだい」
「すまなんだ……」
ピリピリした雰囲気の中、ビワコの夫、つまりウメの息子であるミチハルはタブレットを見ながらコーヒーを飲んでいた。その顔は覇気がなく無表情で、まるで何に対しても関心がないようだった。ウメは冷奴を食べようとしたところで、テーブルの中央に位置する醤油がすこしばかり遠いことに気づいた。ビワコに頼んで取ってもらおうかと思ったが、そういう些細な頼みごとでも決まって何かしら文句をつけてくるのはわかっていたので、ウメはテーブルの上に身を乗り出して手を伸ばし、みずから醤油を取ろうとした——が、指先がもつれ、ウメは醤油のビンをひっくり返してしまった。
「わちゃあ」
ウメが顔をしかめると、ビワコはすかさずヒステリックに怒鳴り散らした。
「何してるの!!」
「やってもうた。いま、ふきん持ってくるから」
そうして立ち上がりかけたウメを、ビワコは大声で制した。
「いいから! 動かなくていいから! わたしがやりますから! お義母さんはさっさとご飯片付けちゃってください! まったくもう!」
「すまなんだ……」
ビワコは全身から怒りを発散させながらどしどしキッチンまで歩いていった。ウメは肩を落とすと向かいの息子をちらりと見た。ミチハルは相変わらずどこ吹く風で、無表情のままタブレットを注視していた。
「……なぁ、ミチハルやい」
ウメの問いかけに、ミチハルは顔も上げずに答えた。
「……なに?」
「けさは、ヒイちゃんの姿が見えんようだけど。今日は学校じゃないんか?」
「……もうソレは何回も話しただろ。ヒナタは学校には行きたくないんだよ」
「学校行かんだら……困らんか」
「ヒナタは中学生だ。単位が足りなくたって卒業できる」
「家におるんなら、いっしょにめし食ったほうがいいんでなかろか」
「あの子は、そういうのも煩わしいんだよ」
「……さみしくないべか?」
「知らないよ。とにかく複雑な年頃なんだ、好きにやらせとけばいいさ」
「ほうかぁ……」
ウメはそう一人ごちるとしょんぼりうつむいた。中学二年生の孫娘・ヒナタは今年に入ってから学校に行かなくなっていた。家の中でもほとんど顔を合わせることもなく、ちかごろは一緒に食事をとることもまれになっていた。醤油のかかっていない冷奴をつつきながら、ウメは、最後に家族みんなでご飯を食べたのはいつだったろうかとぼんやり考えていた。
※ ※ ※
医科大学病院へと向かうバスに揺られながら、ウメは流れゆく外の景色を眺めていた。道沿いの桜並木は豊かに咲き誇り、すこしサイズの大きな制服を着た学生たちがその下を連れ立ってはしゃぎながら歩いていた。新生活を始めたばかりの学生諸君はみなイキイキとした顔をしていて、はちきれんばかりの若さを全身から発散していた。きっとあの子たちは眼に映るものが何もかも新鮮で、日々目まぐるしく変化するすべてに胸をときめかせながら駆け抜けてゆくにちがいない。その光景をしんそこ微笑ましく思いながらもしかし、ウメの胸中ではもの哀しい羨望が渦巻いていた。
ウメは視線を落とすと自分の手のひらをぢっと見つめた。皺だらけで土色の、枯れ枝のような手。年月はかくも残酷なものだ。
自分があの子たちの歳のころは、なりたいものも、したいこともたくさん、たくさんあったはずなのに、いまはそのひとつだって思い出せない。
もうなんの情熱も感動もない。愁いを共有できる友人すらない。ただ、色褪せた日常を繰り返して朽ち果ててゆくだけ。
そうしてウメが小さく溜息をついたとき、バスが停留所に停まり、ひとりの青年が乗り込んできた。派手だが安っぽいスーツに身を固めたその青年は、車内を大股でずんずん歩きながらスマホで誰かと電話していた。
「だからぁ、言ったっしょ。オレ言ったよね? なんでわかんないワケ?」
そして青年は車中をキョロキョロ見回し空席を探したが、ウメの隣席しか空いていないことに気づくと舌打ちをしてウメの隣にどっかり座った。キツい香水の匂いがプンと漂い、ウメは身体を強張らせると同時に顔をしかめた。そんなウメの様子などまるで目もくれず、バスが走り出してもなお青年は電話を続けた。
「だからさぁ、ショーコねえだろショーコ。なんなの、それがオレのガキってショーコあんの? ないでしょ?」
車中の視線が一斉に青年に注がれたが、青年は気にするそぶりも見せず大声で電話を続けた。車内はたちまち重苦しい空気が漂い、ウメは身体を縮こまらせながら波打つ心臓を手でさすった。
「なにお前泣いてんの? 泣いてんじゃねーよ泣きてーのこっちだよ。どうせ構ってもらおうと思ってまたくだらねーウソついてんだろ。エイプリルフールとっくに終わってんぞ」
ウメは下唇をぎゅっと噛み締め、一刻も早くバスが病院に着くようにと祈った。青年は野太い声で電話の相手を口汚く罵り続けた。とても聞くに耐えない、ひどい言葉遣いだった。
「ふざけんのも大概にしろよクソが。二度とそんなくだらねー話すんじゃねーぞ。死ね」
そして青年は電話を切ると、大きく舌打ちをした。
——死ねとか言うな。死ねとか言うな。死ねとか、言うな。
ウメはそう叫びたかった。けれど、そんなこと出来るワケもなかった。病院に到着するまでの道すがら、ウメはずっと泣きたいような気持ちだった。
※ ※ ※
それからウメは、重たい気持ちを引きずったまま病院で各種の検査を受けた。はたして高血圧か、糖尿か、高脂血症か。いずれにせよ、この歳の再検査で芳しい結果など出るワケもない。待ちに待たされてようやく通された診察室で、髪を後ろに固めた中年の医者はレントゲン写真を見ながら、とがった顎を撫でて軽薄な声でいった。
「ガンですねー」
「……は?」
「胃ガン。昔だったらさ、こういうのは本人には伏せておいて胃潰瘍とか言うんだけどさ、いまはそういう時代じゃないからさ」
「それ、って……な、治るんですかい?」
乾いた唇を震わせながら尋ねるウメに、医者はこめかみをボールペンで掻きながらいった。
「んー、どなたかご家族、今から来てもらえたりします? それから説明したほうがいいと思うんだけど」
「あ、あのう、息子は、会社で。よ、嫁も、町内会の草むしり出てて。孫も……とにかく、いま、聞かせてほしいんだけども」
「えっとねえ……ざっくりいうとステージ4。転移がだいぶ進んでるねー」
「しゅ、手術とかで、取れんもんですか?」
「これだけ広がっちゃってると手術じゃ取りきれないねー。むしろガンを暴れさせちゃう。寝た子を起こすなっつってね」
「じゃあ……つまり……わたしは……し、死ぬ……んですか?」
「そうだねえ……このまま何もしなければ、もって半年ってとこかな」
その言葉にウメは目の前が真っ暗になった。心臓が不規則に打ち、暑くもないのに汗が噴き出した。ウメは膝の上で拳をぎゅっと握り、ただ黙って、医者の話にうなずくことしかできなかった。
ふらふらと病院を出ると、朝はあんなに晴れていたというのにいつのまにか空は真珠色の雲に埋め尽くされており、小雨がパラパラと降っていた。傘の準備はなく、また傘を買う気力も起きなかった。ウメは両手で顔を覆うと、深く溜息をついた。
※ ※ ※
家に着いたのは夕方だった。リビングに入ると、ソファに寝転がってワイドショーを観ていたビワコが、ずぶ濡れになったウメを見るなり悲鳴のような怒鳴り声をあげた。
「なにその格好!? びしょ濡れじゃない! 今朝あれだけ傘も持ってくようにって言ったでしょ!」
もちろんそんなことは一言もきいていない。きいていないが、そんなことはどうでもよかった。それでもウメは反射的に頭を下げた。
「……すまなんだ」
「またそれ! すまなんだ、すまなんだっていっつも言うけど、どーせ何にもわかってないんでしょ!? まったく、ご近所さんに見られたらどう思われるか! 自分でお風呂沸かしてすぐ入って!」
「……ぁ、あのう……」
「なに! なんかあんの!?」
ウメは、病院で余命宣告を受けたことを伝えようと思った。しかし鬼のように目を吊りあげてヒステリックに騒ぐビワコの顔を見ていると、そんなことを切り出す勇気さえなくなってしまった。
「……や、その、疲れたで……風呂入ったら、今日はもう、休ませてもらいます……」
風呂に入り、パジャマに着替えて、二階の自室へ入ると、ウメは洋服箪笥のうえに立ててある、若いころの自分と夫の写真を見た。新婚旅行で行った伊豆で撮った写真。旧天城トンネルのまえで並んで写るふたりは若々しく、ウメは白いワンピースを着て溌剌とした笑みを浮かべており、その肩に手を回した夫は、ティアドロップ型のサングラスをかけて歯をみせ笑っていた。
「……キイチロウさん……」
ウメは、かすれた声で、夫の名前を呼んだ。十五年前に脳溢血で突然亡くなった夫の名前を。中卒で勤めた洋裁工場で同僚にさそわれてはじめて繰り出した夜の盛り場で出会った夫の名前を。盛り場のハコバンのドラマーで、縦横無尽にスティックを操り不敵に笑うその姿をひとめ見た瞬間から、まっさかさまに恋に落ちた夫の名前を。
「ふっ、く……う、ぐ……ううっ……うぎ、うう〜……っ……!」
ウメは、写真を胸に抱くと膝から崩れ落ち、嗚咽した。大粒の涙をぼろぼろこぼしながら、嗚咽した。たとえようもない孤独感で身体が引き裂かれそうだった。夫が亡くなったときは悲しかったけれど、それでも孫が生まれたときは幸せだった。この子の成長を夫のぶんも見守っていきたいと心から思った。しかし年月が経つにつれ、少しずつ、いろいろなものが失われていった。息子はすっかり無気力な中年になり、嫁は事あるごとに冷たい態度を取るようになり、孫は顔すら見せなくなってしまった。なんとかしようとあがいたときもあったけれど、全ては無為に終わった。そのうちじぶんは卑屈になった。とにかく怒られないように、とにかく迷惑をかけないように、気にすることはそればかりになった。湧き上がる感情に蓋をして、口を噤んで身を謹んで生きるうちに、情熱も感動も忘れてしまった。それでも生きているだけましだと思い込んできたけれど、ついにそれすらも失われてしまった。
——じぶんにはもう、何もない。ほんとうに、何もない。
ウメは布団に倒れこむと、写真の中の夫に頬を擦り付け、泣いた。泣いて泣いて泣き果てて、全身の水分が抜けてしまうのではないかと思うぐらい、涙を流し続けた。
※ ※ ※
その夜、ウメは夢を見た。気がつくとウメは堤防に立っており、暖かい夕映えでふくらんだ煉瓦色の海をみつめていた。水平線の向こうから吹いてくる風がやさしく頰を撫で、潮騒がささやくように響きわたっていた。ウメがぼんやりと立ち尽くしていると、ふいに隣でだれかがぽつりとつぶやいた。
『まったく、ハートが熱くならぁ』
声をした方向を見やると、そこには、夫のキイチロウが立っていた。亡くなったときの姿のままだった。長い前髪を真ん中で分け、麻の白いスーツを着ていた。いかめしい鉤鼻も、優しい目も、昔とまったく同じだった。死んだはずの人間が隣に立っているということを、なぜかウメはごく自然に受け入れられた。キイチロウは前髪をかきあげると、ポケットに手を突っ込みながら言った。
『きれいだ。ほんとうに、きれいだぜ』
キイチロウのしみじみした口調に、ウメはこくんと頷いた。
『ええ、ほんとうに、きれいな海』
『海の話じゃねえよ。オマエのこと言ってんだよ』
『わたしが?』
びっくりして尋ねると、キイチロウは口元を歪めて気障に笑った。
『ああ、オマエはいつ見てもサイコーにイカしてる。ハートが熱くなるぜ』
『……バカいえ、そんなワケねえべさ。わたしはもう老いぼれの、皺くちゃの、梅干しババアさ』
『いいや、オマエはきれいだよ。初めて会ったあの夜から、ずっとな』
若い頃からまったく変わらないその気取った口調に、ウメは思わず苦笑した。
『……へ。キイチロウさんはいいなぁ、若いまんまでよ』
『死んじまったらなんの意味もねえや。死んだヤツより、生きてるヤツのほうが偉えんだよ』
『わたしも、もうすぐ、死ぬんよ。もってあと半年ってお医者さんが言っとった』
『半年もあるじゃねえか』
『半年で何ができるんだい』
『できるかどうかは問題じゃない。やるかやらないかだ。やりたいことをやりゃあいいだろ』
『こんなババアが、今さら、好き勝手にしたら……メーワク、かかるべしゃ』
ウメがもじもじ答えると、キイチロウは、ハッ。と声を出して笑った。
『かけりゃいいだろ。どーせ死ぬんだから。死んだヤツのことは誰も悪く言わねえ』
『……アンタが言うと、説得力があるなぁ』
『遠慮と後悔ってのは比例するんだよ。遠慮ばっかしてたら後悔は募るばかりだ』
『……けんど、わたしゃね、もう、自分が何をしたいのかも、よくわかんねえんだよ』
ウメが哀しげに目を伏せると、キイチロウは拳で胸をどんと叩いた。
『自分の胸に聞いてみろ。答えはいつでも胸の中にある。胸に手を当ててビートを感じるんだ。心臓はな、“ぶちかませ!”って叫びながら年中無休でビートを刻んでんだぜ』
『……でも……もし、何かに挑戦して、失敗したら……どうすんだい』
『どうってことねえよ。ミスしたらもう一回、同じミスをすりゃあいい。そうすりゃそれはミスじゃなくなる』
キイチロウは不敵な顔で両手をひらひらさせた。ウメは肩をすくめて笑った。
『ハ……まったく、よく口が回るもんだ』
『ああ、何たってジャズメンだからな。口八丁手八丁ってヤツよ』
そしてキイチロウは真正面からウメの顔を見つめた。ビー玉のように透けたその瞳は、泣き出しそうなぐらいに美しかった。キイチロウはウメの鼻先に人差し指を突きつけて言った。
『人は好きなだけ自由になれる。人生も、世の中も、思い通りに行かねえことばっかりだけど、それでも自分の身体だけは、自分の思い通りにできる』
『……そんなこと言うても……』
『よし、わかった。オマエにパワーをやる』
キイチロウはそういうと、ウメを抱きしめた。両腕で、つよく、つよく抱きしめた。いつもつけていたオーデコロンの香りが鼻をくすぐり、身体がかあっと熱くなるのを感じた。ウメはキイチロウの背中に手を回すと、額を胸に擦りつけた。
『……キイチロウさん……』
『これまでのオマエは死んだ。つぎに目覚めたとき、オマエは生まれ変わってる。新しく人生をはじめるんだ。とりかえしのつかないことをしでかせ。何だっていい、とにかく自分にとって意味あることをやって、ハートを燃やせ。愛してるぞ、ウメ』
——そして、ウメは目覚めた。
まだ両腕には彼の体温がのこっていたし、オーデコロンの匂いさえも感じられた。パジャマの上から胸に触れると、心臓が強く波打っていた。ぶちかませ、ぶちかませ、ぶちかませと叫びながら、心臓はビートを刻んでいた。ウメは拳をぎゅっと握ると、布団から這い出て、歩き出した。
「ハートが、熱くなる……」
全身にかつてないほどのパワーがほとばしるのを感じながら、ウメはポツリとそうつぶやいた。
階段を降りると、リビングではビワコと孫娘のヒナタが口論していた。ヒナタはグレーのスウェットの上下を着て、寝癖だらけのショートヘアを振り乱しながら、小さなからだを震わせて叫んでいた。
「っ、お母さんには、カンケーないでしょっ!?」
「カンケーないわけないでしょ! 夜中に楽器持ってひとりでふらついてるって、きのう町内会で聞いたんだからね! 学校は行けないくせに、遊びには行けるのね!」
ビワコはエプロン姿のまま、両手を振り回して金切り声で叫んでいた。妻と娘がこれだけ争っているというのに、ミチハルはソファに座ってコーヒーを飲みながらタブレットを見ていた。自分には関係ない、とでも言いたげな、冷ややかな顔をして。
「学校はっ、行けないんじゃないっ! 行かないことにしたのっ!」
「あなたまだ中学生でしょう! そもそもね、中学校っていうのは義務教育なの! 義務って意味わかる!? しなくちゃいけないことなのよ!」
「それは親の義務で、アタシの義務じゃないっ!」
「まったく、ああ言えばこう言う! アンタなんか、産まなきゃよかったっ!!」
ビワコがそう喚くと、ヒナタは途端に言葉を失い、顔を曇らせてうつむいた。ビワコは肩でふうふう息しながら、リビングにやってきたウメの姿を見つけると、またぞろ金切り声をあげた。
「ちょっと、お義母さん、パジャマでリビングに来ないでっていっつも言ってるじゃない! だらしないったらありゃしない! 同じこと何回も何回も何回も言わせて、これだからババアってイヤなのよっ!」
——そのときである。
突然、ウメは全速力で走り出した。猛スピードで走り出した。ぺたぺたぺたぺた、裸足で踏まれたフローリングの床がまるでドラムロールのように鳴った。突如として展開したこのアクションに、ビワコも、ヒナタも、ミチハルでさえも、口をあんぐり開けて硬直した。
そしてウメは床を蹴ると、高く、高く跳び上がった。
焼き鮭やおからの煮物や佃煮が並ぶテーブルを飛び越えながら、ウメは空中で両足を綺麗に揃えた。
そうしてウメは、硬直したままのビワコの顔面に、渾身のドロップキックをぶちかました。
ビワコは鼻血を噴出しながら真後ろへ倒れ、そのまま気を失った。
耳が痛くなるほどのすさまじい沈黙がリビングに広がり、ヒナタもミチハルも息を呑んで倒れたビワコをまばたきもせず見つめた。
床に転がったウメは、フローリングの上に大の字になると、天井を仰ぎながら荒い息遣いでいった。
「ハートが燃える……」
♪Sound Track :Explain/Papas Fritas
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
