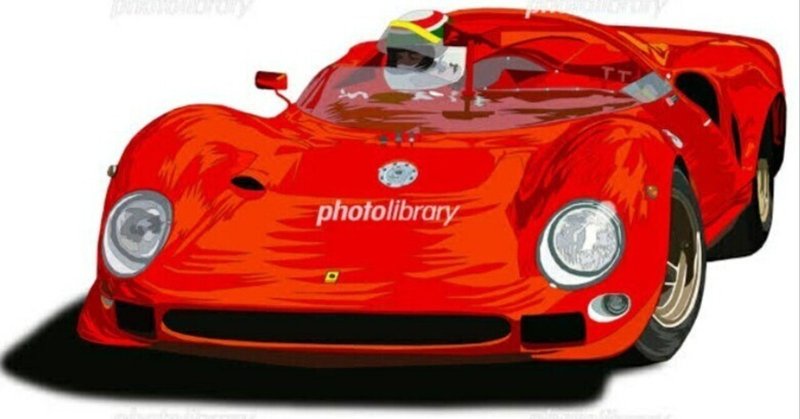
世界史と地図 (1679文字)
世界史の学習をしていると、地図的知識の必要性を感じます。
「地図的知識」といってもおおまかな場所の特定とか、目印になる湖や山や平原のおおまかな位置を頭の中で描ける程度で十分です。王朝の存在した場所や範囲などは時代とともに変化するので、まずは目印になる自然物を覚えるようにします。
世界史では、ユーラシア大陸でいろいろな出来事が起こりますから、まずはユーラシア大陸の地理的知識が必要になります。
古代文明からイスラーム世界そして遊牧民の時代、ヨーロッパの中世以降など、アフリカ北部のエジプト文明の他はだいたいユーラシア大陸で展開されますからね。
人類の先祖の発祥といった話ならアフリカ大陸で、大航海時代なら南北アメリカ大陸で話が展開されますが、世界史の本ではそっちの方の話の分量はあまり多くありません。
さて、ユーラシア大陸です。
ユーラシアは、ヨーロッパとアジアの総称です。
かなり古い話ですが、テレビ番組『進め!電波少年』の「猿岩石のユーラシア大陸横断ヒッチハイク」では、香港からロンドンまでというコースでした、このイメージがユーラシア大陸の東西です。
で、ユーラシア大陸の地図の目標物です。
ユーラシア大陸の西側の方には、黒海やカスピ海という目印があるので、場所の特定に「カスピ海の東南400キロメートルあたり」などとノートや参考書などに書き込むことができます。
山や高原は地図帳には書かれていますが、世界史の本の略地図には書かれていないので、やはり湖があると助かります。湖は略図にも書かれていることが多いし、自分で書き込むこともできるので目印として便利です。
ところがユーラシア大陸の中部や東部には湖があまりありません。
ユーラシア大陸の東側(東アジア)には、黄河や揚子江という大きな目印がありますが、「黄河(か揚子江)の西側」というより、「黄河(か揚子江)の流域」と書くのがしっくりくるので使い方に制約があるように思います。
遊牧民はユーラシア大陸で大活躍しますが、その活躍の場を文字で書くときには困難が伴います。
そういうわけで結局、「ロシア南端の近く」みたいに苦しい特定の仕方をしています。
ヨーロッパの中世に差し掛かる時代では、黒海を中心とした地図を多く参照することになります。ここは、バルカン半島とかイタリア半島とかイベリア半島がありますし、西ヨーロッパには様々な河川があるので地図上の目印には事欠きません。
ただ、「アナトリア」とか「小アジア」とか書かれている半島があって、そこがどこなのか分かりませんでした。その場所は現在はトルコ共和国のアジア側と呼ばれる場所なので(トルコは20世紀にできた国なので、19世紀以前の事柄を記述する際には使わないそうです。)、私は「今のトルコ」などと書くようにしています。(アナトリアは半島なんですがアナトリア半島といわずアナトリアというのは、ヨーロッパでの呼称に倣っているそうです。また、小アジアというのは、かつてはここ(アナトリア半島)がアジアと認識されていましたが、その後アナトリアの東にもっと広大なアジア(大アジア)があることが分かり、そこから従来のアジア(アナトリア)を「小アジア」と呼ぶようになったそうです。)
黒海といえば、2024年現在、ロシアのウクライナ侵攻がどうなるか注目されていますが、ウクライナは黒海の上の方(北側)、トルコは黒海の下の方(南側)と考えると、地図上の場所と国際問題とがリンクしてより考えやすくなるのではないでしょうか。
余談ですが、第二次世界大戦の印象からか、私には海戦といえば太平洋そうでなくても北海などの外海で行われるものというイメージがありました。
だから、第二次対戦中のドイツ海軍と日本海軍の規模を比較して「ドイツの軍艦の数は少なすぎないか?」と違和感を覚えてきましたが、ヨーロッパには黒海やエーゲ海やバルト海などこじんまりとした海があるので、あれはあれでいいのかと思い返したりします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

