
人生の短さについて セネカ by エシモの備忘録 哲学ver.
●人生の短さについて
セネカ
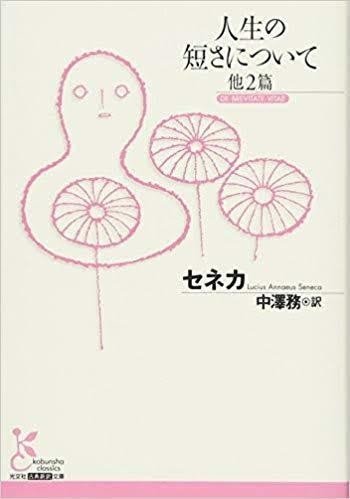
・人生とは閑暇を生きること
真の閑暇(かんか:暇のこと)は、過去の賢人に学び、英知を求める生活の中にある。
→教養をつけるから過去の教訓を生かせる。歴史、哲学、文学、科学など教養を身につけていない者は己の経験を頼りに生きるから過去の人々と同じ過ちを繰り返す。世界史から勉強せよ。
・過去・現在・未来の生き方
時が過ぎ去った。賢者はそれを記憶の中に包み込む。時が、今ここにある。賢者はそれを使いこなす。時がやってくるだろう。賢者はそれを予測する。賢者は、すべての時をひとつにつなげる。そうやって、自分の人生を長くするのである。
→ギリシアから現在まで人間社会の歩みを学び、彼らの考えを学び、自分のことのように想像する。その知識を活かして今やるべきことを夢中で行う。社会情勢を読み、トレンドを把握することでやるべきことがよりはっきりする。歴史を学び、現代の社会情勢を学び、人々にとって良い行いを今日やること。
●心の安定について
・仕事や友人の選び方
自分の仕事に打ち込み、状況に応じて、閑暇の中に避難せよ
→多忙は自分の人生を生きていないということ。そういう人は死ぬ間際になってやっておきたかったことを山程上げて後悔するのだ。
・多忙から逃げたときの過ごし方
隠居するときには、気をつけるべきことがある。すなわち、どこに隠れて自分の閑暇を過ごすにせよ、知性と言葉と助言を使って、個々人はおろか、人類全体の役に立ちたいと言う思いを持つことだ。
→ただぼーっと過ごす暇人は一番罪深い。しかし、あえて暇を作り、世の中のために勉強したいことを学び、自分の持てる力を全て使ってやりたいことをやるのなら、それは立派な人生となる。
・時間>お金
時間を大切に使うものもいれば、無駄に使うものもいる。時間の終止符をきちんと示せるように使うものもいれば、残高がなくなるまで使い切ってしまうものもいる。高齢な老人が、長く生きた証として、自分の年齢しか示せないこともよくあることだ。
→長寿だからといって偉いわけではないので誰でも彼でも敬う必要はない。時間を無駄にする者たちとは縁を切るべし。
・哲学が求められる時
国家が存亡の危機にあるときには、賢者にも、その存在を示す機会がある。だが、国家が繁栄し、幸福なときには、金銭欲や嫉妬心のような無数の卑劣な悪徳が、人々を支配するのだ。
→70年代の日本は戦後復興の繁栄を享受した。誰もが金銭欲や嫉妬心にまみれた。しかし今は減退期。若者たちが哲学を求めるのは国の存亡の危機にあるということ。いつの時代と国を追われる時は必ずやってくる。異民族の移住や敗戦などによって、人間は移動を繰り返してきた。国を追われたからといって嘆く必要はない。過去の賢人たちから知恵を学び、自然から食料を得る技術さえあればどこでも幸福に生きていける。勉強してサバイバル力もつけよう。
・仕事について
仕事において我々が吟味しておくべき3つのこと
第一に、自分自身を吟味するべきである。
第二に、自分の仕事の内容を吟味するべきである。
そして第3に、その仕事を誰のために、また、誰と一緒にするかを吟味すべきである。
考えるべきは、君の性格が実務的な活動に向いているのか、それとも閑暇の中で学問や施策をすることに向いているのかということだ。
→自分は後者だが、現代で生きていくには実務的な労働も欠かせない。なぜなら奴隷はいないから。自分の創作時間を優先するが食べていけるだけの最低限のお金も稼ぐべきだし、そのための金融知識も学ぶべきだ。
人間の才能と言うものは、無理強いをしても、うまく答えてくれない。持って生まれたものに逆らうと、努力も無駄に終わるのである。
→まずは自分の才能を知ること。才能とはそれをやっている時は時間があっという間に過ぎてしまうもののこと。僕の場合は絵を描く、文を書く、チェスをする、陶器を作る、カクテルを作る、人と対面で話す、場を盛り上げるなど手を動かして何かを作ることや人とのコミュニケーションが得意だ。逆に頭で数字を処理する仕事や単調なPC作業の繰り返しは向いていない。確率の計算も苦手だ。
手を出していいものは、終わらせることができるか、あるいは少なくとも、それを期待できる仕事だ。そして手を出すべきではないのは、やればやるほど際限がなくなっていき、決めたところで終わらない仕事なのである。
→自分の身の程を知れということ。できないことはできないというべき。やればやるほど際限が無くなり、決めたところで終わらない仕事は日本のサラリーマンな気がする。
友は選べ。陰気な人とか、いつも愚痴ばかり言っている人などは、特に避ける必要がある。たとえ、いつも誠実で親切であったとしても、一緒にいる仲間が不安げだったり、ため息ばかりついていたりしたら、それは「安定」の敵でしかないのだから。
→愚痴は怠惰で無知な証拠。文句や悪口ばかり言って自分で考えない人といる時間は最大の無駄。しかも、感情は伝染しやすいので友達選びは常に更新していくべき。
・財産との付き合い方
質素な生活を心がけよ
持たない方が失うよりもはるかに苦痛が少ない。貧乏な方が失うものが少ない分、苦しみも少ない。
金銭の理想的な量とは、貧困に陥ることも、貧困から遠く離れてしまうこともない程度の量なのである。
→貧困とは明日寝る場所も無く、食べるものもない人のこと。そんな人、今の日本にいるのだろうか。いや、いない。自分が月いくらあれば十分暮らしていけるだろう。8万円あれば十分だ。あと60年生きるとしても生涯で6000万円を稼げば良いのだ。年間100万円稼げば、本当は十分暮らしていける。
・倹約の生き方
衣服や生活の流儀は、流行を追いかけるのではなく、父祖の習慣に従うことを学ぼう。たとえ多くの人に恥だと思われようとも、自然の欲求は、安価な手段で満たしてやることを学ぼう。度を超えた望みや、未来の方ばかり見ている心を、鎖で縛るように押さえ込む術を学ぼう。幸運の中にではなく、自分の中に富を探し求める術を学ぼう。自然が食べ物を与えてくれる。自然と徳さえあれば人は豊かに生きられる。本当の貧乏とは必要最低限以上の悪徳を求める者のこと。あれもこれも欲しいと贅沢な生活を送る精神状態のこと。アピキウス(ローマ帝国時代の貴族)は珍品を世界中から集めた贅沢な晩餐会(1回の予算100億円)をしすぎて財産が10億円ほどになった時、絶望して自殺した。このような贅沢を軽蔑できる人であれば、貧困は決して害にはならない。欲望は、決して満足しません。しかし、自然は、わずかなものでも満足します。貧困は悪ではなく、精神のあり方の方が大切である。
→人と比べるのではなく、自分の指針を持って生きるべき。自分はどんな環境があれば十分暮らしていけるのか、少し考えただけでも必要以上にお金がかからないことを知るだろう。人とご飯を食べる時、恋人とデートをする時、そのお金は自分にとって浪費か、それとも投資か、考えるべきだ。
・賢人か、それともコレクターか
書物は十分に買う必要があるが、しかし一冊たりとも飾りにしてはならない。
富裕層が書物や美術品を収集したのは、学問のためではなく、見せ物にするためだったのだから。たくさんの無学な人々にとって、書物は、学問の道具ではなく、宴会場の装飾と変わらないものなのだ。
→大きな本棚に読まない本を並べるのは宝の持ち腐れ。肖像画も同じ。全ては承認欲求。では現代アートのマーケットは?これは知識とイズムを作品に落とし込むことであたかも歴史的価値があるように見せかけるパフォーマンスだ。有名作家の作品を富裕層が欲しがるのは、約2000年前も今も変わらない。アートは富裕層向けのパフォーマンスビジネスなのだ。本当に歴史的価値があるものは今の時代、アートではなく私たちの生活にリアルに結びついているもの。そう、スマホのように。
また、モノはいずれ廃れて跡形もなく消えてしまう。コロッセオやパルテノン神殿も現在はボロボロだ。しかし、セネカたちが残した叡智は依然として現代にも通ずる人類の宝となっている。一冊の哲学書と、豪華な装飾としての絵画、どちらが我々にとって価値あるものか、もうお分かりだろう。
・運命への対処法
どんな仕事をする時でも、必ず一定の目的を設定し、その目的を見据える必要がある。仕事に専念すれば、心がぐらつくことはない。そうしないと人は物事に対する誤った思いにとらわれて、まともな判断力を失ってしまうのだ。
→給料のため、生活のためと考えて毎月忙殺されている人は心がぐらついて、いずれはまともな判断力をも失ってしまう。まさにぼくがそうだった。安定した給料とステータスを求めて入った会社は自分の才能と真反対の環境だった。そのためいくら努力しても無駄に終わった。
・不測の事態に備えよ
われわれは、心を柔軟にして、自分が決めた計画に、過度に固執しないようにしなければならない。不足の事態が生じて、我々を取り巻く状況が変化していくのなら、それに身をまかせれば良いのだ。いずれにせよ、まったく変われないことも、まったく辛抱できないことも、どちらも心の安定の敵なのである。
→宇宙は数々の偶然が折り重なって成り立っている。人間社会も同じで無数の人々と偶然で繋がっている。計画通りに進むことなどない。不測の事態が起こることを前提として行動していけばいいのだ。変化を恐れず行動し、不測の事態にも辛抱する覚悟を持っておくのが心の安定につながる。
・大切なものを守るためなら喜んで命を捧げよ
不測の事態は自分の命をも奪う時がある。その時に慌てふためき、恐れおののくのはみっともない。自分の強い意志を守るため、自分の家族や誇りを守るためなら喜んで首を差し出せ。過去に学び、未来を見据えて今を生きてきたのなら、たとえ命が尽きても、自分の精神は永遠と生き残るだろう。
→セネカは暴君ネロに死刑を言い渡された時、素直に従い手首と足の血管を切り自殺した。彼は過去の偉人たちから学び、暇を作って自らの好奇心と関心から賢人の生き方を探求したからこそ、自分の精神が後世にも通ずることを確信していたのだろう。彼の精神は2000年以上経った現代の我々の中にも生き続けていく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
