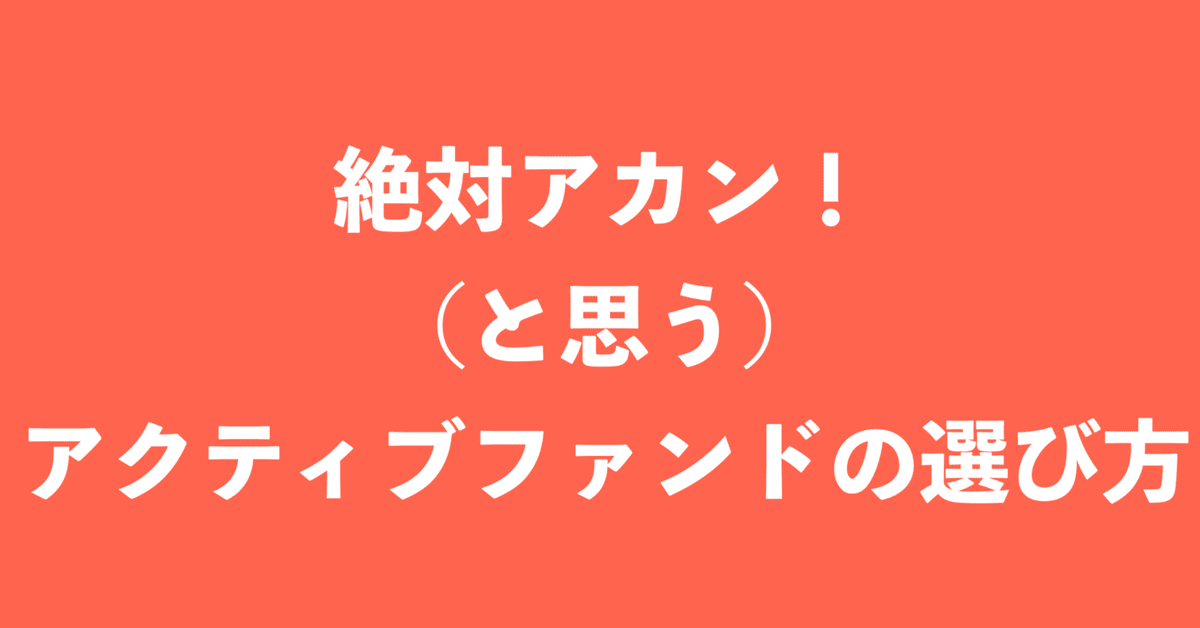
絶対アカン!(と思う)アクティブファンドの選び方 第3回 フィー
2022年ゴールデンウィークの毎日更新(予定です)シリーズ。
絶対アカン!(と思う)アクティブファンドの選び方
こちらの3日目、第3回です。
前回は⏬
前回、特に強調したかった点を3つ挙げておきます。
アクティブファンドをパフォーマンス「だけ」で選ぶのは、絶対アカン
ランキングはある一期間のスナップショットに過ぎない
アクティブファンド選びは、長い旅を一緒に進む、相棒・バディ選び
さて、今回のテーマは フィー です。
アクティブファンドをフィー「だけ」で選ぶのは
絶対アカン!(と思う)
アクティブファンドについてあれこれ言っている人、僕も含めてですけど、そのほとんどの人たちが注目する2本柱が
パフォーマンス と フィー(コストとか手数料とか呼ぶ人多数ですけど)。
今日のテーマは フィー です。
僕がコストではなくフィーと表現している理由は次の記事をご覧ください。
世間の人はフィーではなくコスト。人によっては手数料と呼んでいます、特にSNSでは手数料という表現をやたら目にします。投資信託を保有していると、毎日基準価額から控除されている信託報酬のことを指すことが多いと思います。買付時に販売会社に支払う販売手数料というのも存在します。
アクティブファンドをフィーで選ぶ人たちの代表格
=金融庁
アクティブファンドをフィーで評価、選択している代表格、筆頭格が金融庁です。
つみたてNISAの対象になるアクティブファンドの設定基準に「フィー」を設けています。フィー以外の基準も存在していますが、「フィー」の基準を満たしていなければ例外なく選外となります。
情報開示、パフォーマンス、投資内容、これらの点において非常に素晴らしいアクティブファンドと評価しているのがこのファンドです。
このファンドは、つみたてNISAの「フィー」の基準を満たしていません。ですから、どう逆立ちしてもこのファンドでは、つみたてNISAの課税優遇措置を享受することはできません。
つみたてNISAに採用されることをスパークスさんが意図されるなら、フィーを引き下げる(それに加えてファンド期限の無期限化等の変更)を実施しなければなりません。それってあるべき姿なのだろうか、と思います。スパークスさんには、現在のフィーを受け取るだけのサービスを提供しているという自負をお持ちだろう、と想像します。
このフィーが高いと感じるなら別に結構です、どうぞヨソへ行ってくださいまし。そんな投資会社としてのプライドをスパークスさんから僕は感じています。
地下3階のドグマ
金融庁のこの判断には、僕が”地下3階のドグマ”と呼んでいる頑な考えがベースにあると考えています。
地下3階のドグマ とは:
インデックスファンド、アクティブファンド、その中身を問わず、
最も大事なのはフィーである、という教条。
インデックスファンドにはこの教条がよくあてはまるのは、僕も100%同意です。
しかし、アクティブファンドにこの教条を押し付けるのは同意できません。

投資信託の投資家、受益者の手元に受け取るリターン、ネットリターンと呼ぶことにします。
そのネットリターンは、グロスリターンからフィーを控除したものです。
グロスリターンとは、ファンドの保有資産から生み出されるフィー控除前のリターン。インデックスファンドの場合、ベンチマークが同じであれば、グロスリターンにさほど大きな差は出来ません。グロスリターンに大きな差がないのであれば、ネットリターンは、フィーの多寡が左右するのは当然でしょう。
しかし、グロスリターンがファンドによってマチマチ、大きな数字を叩き出すファンドもあれば、ダメな、残念な数字になるファンドもあるのが、アクティブファンドです。そんなアクティブファンドを選ぶ、評価するのにフィー「だけ」に注目するというのはナンセンス、馬鹿げている、と僕は思います。
お金を託す側、投資家が納得しているなら、受け入れているなら、フィーはいくらでもいいはずです、アクティブファンドは(その内容を納得しないままに投資家がそうしたファンドを買ってしまっているケースは大問題だと思いますが、それはちょっと別の問題でしょう)。フィーにふさわしいサービスが提供されていない、そう感じたら投資家は「そっと」解約すれば良いだけの話です。
大きなリターンを叩き出しているファンドも、時間の経過と共に平凡な、平均的な成績になっていく、平均に回帰するんだ、ということで、この地下3階のドグマを強調されるかもしれません。いずれ平均に回帰していくのだから、フィーは低廉な方がいい、と。
でも、グロスリターンが平均回帰するか否か、はまた別の問いであって、一緒くたにするのは馬鹿げていると僕は考えています。
アクティブファンドを見る、選ぶにあたって、フィーをまず確認してみる、というのはオカシイと思いませんか。
最初に見るべきは、グロスリターンがどのように生み出されているか、でしょう。つまり、投資先、ポートフォリオの中身、また、それがどのように変化しているか、です。そして、その投資先、ポートフォリオになるに至った投資哲学、価値観、意思決定のプロセスです。
フィーは重要ではない。そんなことを言ってるのではありませんよ。
フィー「だけ」を見て、もしくは、フィーに強い関心を寄せて、アクティブファンドを評価する。これが絶対にアカン!ということです。フィーよりも先に見るべき、注目すべき要素がもっと沢山あります。
この点で、鎌倉投信さんの説明を、僕は高く評価しています。
上記の説明で云うグロスリターンは年率5%を目標として置きます、と。
そのグロスリターンからフィーを1%、鎌倉投信は受け取ります、と。
結果、受益者の手取りリターンは年率4%となります、と。
もちろん、毎年決まったように年率5%のグロスリターンを出せるものではありません。上下します。でも、考え方としては投資先の(時価の損益+配当)で年率5%のグロスリターンが生まれ、それを、投資会社:受益者=1:4で分け合うというイメージですね。このイメージを投資会社、受益者が共有、相互に分かり合えていると、ファンドの結束、共創力は高まるものと思います。
適正なフィーがいくらなのか、というのは、ファンドごとに異なっているはずで非常に難しい問いのように思います。というのも、中小型の規模の会社を主たる投資対象にしているファンドにとっては、ファンド規模の制約があるはずだからです。ファンドの規模がある金額で頭打ちとなったら、ほとんどの場合、そのファンドの投資会社の収入も頭打ちになります。そうしたことを踏まえて、フィーが設定されているという側面はあると推測します。こうした面からも金融庁のつみたてNISAの基準には首を傾げてしまうんですよね。
昨日のお話の通り、アクティブファンドを運営してくださっている投資会社は、投資家にとって、長い旅を共に進むバディである、と僕は考えています。であれば、双方が長く関係を続けられるようなグロスリターンの分け合い方があって然るべきだろう、って思います。
ここから先は
サポート頂いた際は、TableforKidsへの寄付に使わせていただきます。 https://note.com/renny/n/n944cba12dcf5

