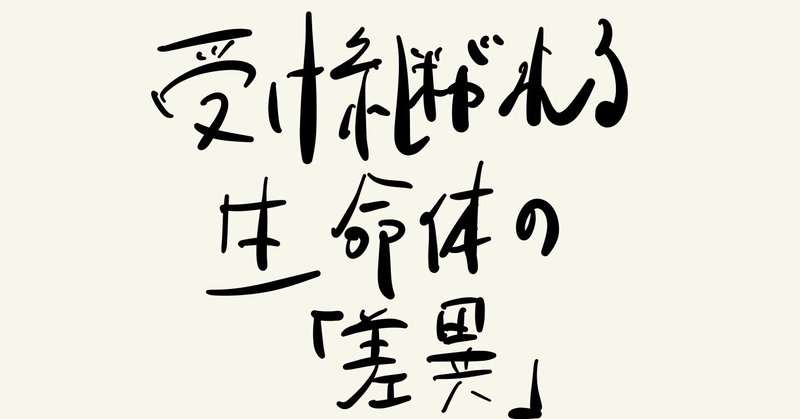
『生命体の織物』の中で変化を生む限り、肉体的な死を迎えた生命も「生きている」のかもしれない
最近『死』って何なんだろうかって考えている。
僕が5歳ぐらいの頃、初めて人が火葬されて、白骨になってしまうのを見た。
たくさん世話をしてもらったおばあちゃんが病気で亡くなった。
僕はその変わりはてた姿を見て、言葉が出なかった。
よくわからない感情のまま母と、重い箸で納骨したのを鮮明に覚えている。
その時漠然と、「人は死ぬ」ということの意味を理解した。
それから僕は、小さい頃時折、両親や兄妹が死んでしまった時のことを想像して、悲しくなって一人枕を濡らしていた。
家族が骨になって、もう会えなくなることがたまらなく悲しかった。
それから僕はずっと、「死ぬこと」は、その肉体やら物理的な実態が動かなくなることだと思っていた。
僕は死ぬ。その心臓が鼓動をやめた時。
僕の家族の犬は死ぬ。その体が動かなくなった時。
でも本当に、その時『死ぬ』と言えるのだろうか?と最近思うようになった。
肉体が動かなくなったと同時に死ぬと思うのは、
『生』の単位が皮膚で囲まれたその肉体の中で閉じているからではないだろうか?
生命体の『生』の単位が、生命体一個体だけで完結していると思うから、そう思うのではないか。
生命体の「生」というものは本当に一個体の中で完結しているのだろか?ー生命の関係性が作る『生命の織物』ー
例えば、僕は毎日たくさんの命のおかげで食事をし、生きている
僕は毎日たくさんの人が電力を供給し、
インフラを整備しておいてくれているおかげで生きている
何かのおかげで生きている部分はこれらにとどまらないだろう
僕個人ではなく、人間という種も他数多の種のおかげで生きている
数多の種が形作る地球という生態系の繋がりの中で生きている
海洋と森林などの自然環境が、空気中の構成比が急激に変化しないように調整し続けているから、僕は当たり前に呼吸をして生きることができるのだ。
そして日々の生活では、よく知り合った家族から名前も知らないコンビニの店員さんといった、無数の他者との繋がりを体験している。
僕は他の無数の人間、生命体、環境と日々数え切れないほどの相互作用を通して「生きている」と実感する。
だから、全ての生命体の「生命の単位」はその個体だけで完結してはいないのだ。一つの生命とは、関係性の織物の中で生きる。
その織り目一つ一つに確かに命が宿っているが、そこが仮に動かなくなったとしても、その瞬間から生命の織物全体が停止するわけではない。
その織物はその動かなくなった部分の「記憶」を確かにとどめているはずだ。
僕達の生は個人で完結するのではなく個々が結ばれる生態系の中で成立している。
生命の織物の部分である生命個体が残した『差異』は消えることなく「生態系に記憶」される
生命の織物である、巨大な生態系の中では、その部分である生命の肉体が活動をやめたとしても、その肉体がそれまで産んできた『差異』が、また別の差異を生み続ける限り、生きているのではないだろうか?例をあげて考えてみる。
5歳の頃、僕のおばあちゃんはあの時確かに死んでしまったが、おばあちゃんが僕にかけてくれた愛情は、僕に変化ー『差異』ーを生み続けているだろう。
そして、おばあちゃんの子供である僕のお父さんは、おばあちゃんから受けた愛を変換して、僕に愛を注ぐ。
おばあちゃんから間接的にも受けた愛によって、僕はまた変化する。
その変化によって僕が及ぼす周りの生命の生態系への影響は、部分的には死んだおばあちゃんから受けた愛による変化が発端になっているのだ。
その意味でおばあちゃんは、今日もどこかで生き続けている。
人が遺す作品や発明や言葉にも、同じことが言えるだろう。
もし人が、本や絵を描き、それを遺せば、それをみて心を動かされる他者がいる限り、その人は生命の織物の中で生き続けている。
その人の発明品が他の人や、他の種の生命体に、そしてその生態系に恩恵や害、さまざまな刺激を与え続ける限り、その人は生きている
その人の『言葉』が誰かに影響、活力を与え、その誰かがまた別の誰かの心にまた新たな活力という差異を与える限り、その人は生きている
巨大な生命の織物のどこかに差異をもたらす限り、その生命体は「生きている」のだろうか
『生』の単位とは、皮膚で囲まれた生命体一つではなくてそれら数多の生命体が
形作る、一つの生命体の織物、生態系である。
そしてその織物においては、一つの生命体が死んでもその生命体が産んだ『差異』が、別の『差異』を生み続ける限り生きていると捉えられるのではないだろうか。
そう想うことができれば、僕は死への捉え方を少しだけ、心安らかに向き合うことができるのではないのだろうか?
夜、家族が死んでしまうことを想像して一人枕を濡らしていた時の僕が抱いていた感情とはまた違った感情で、肉体的な死と向き合うことができる
確かに、もし家族が死んでしまったら悲しさのあまり一晩中泣くだろう。
でも、その家族が本当に死んだわけではない。
その家族の声が、言葉が、愛が心に残って、僕に変化を与えるづける限り、死んではいないのだ。
そしてその変化を源に、僕がまた次の世代へと変化を遺すのだ。その限り僕も僕の家族も、どこかで生き続けていると思える。
そう思うことができれば、死というものと、完全なる恐怖以外の感情で向き合うことができるかもしれない。
そう思うことができれば、『死の境界線』が曖昧になるのだろうか。僕たちは肉体的な死後の後、いろんなところでまた死に、そして生き続けているのだから。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
梅雨が明けて、暑い日が続いてますね。
最近は毎日ポカリスエットを飲んで熱中症対策をしています
朝起きた時に飲むと、その後の何とも言えない気だるさが抜ける感じがするのでおすすめです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
れんてん
ただ、ありがとうございます。 きっとまた、「なにか」を届けます。
