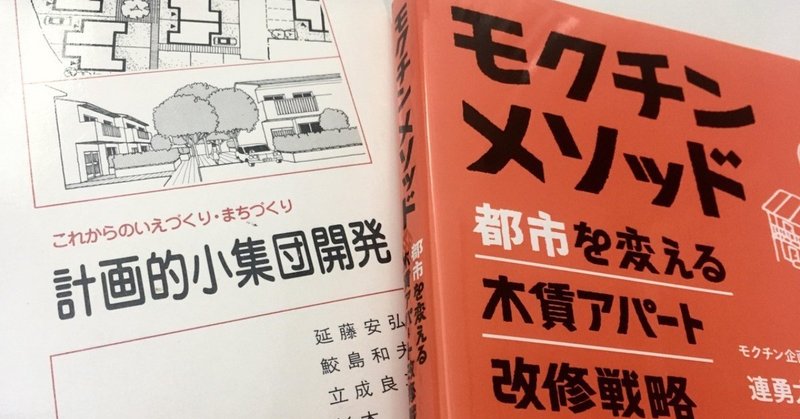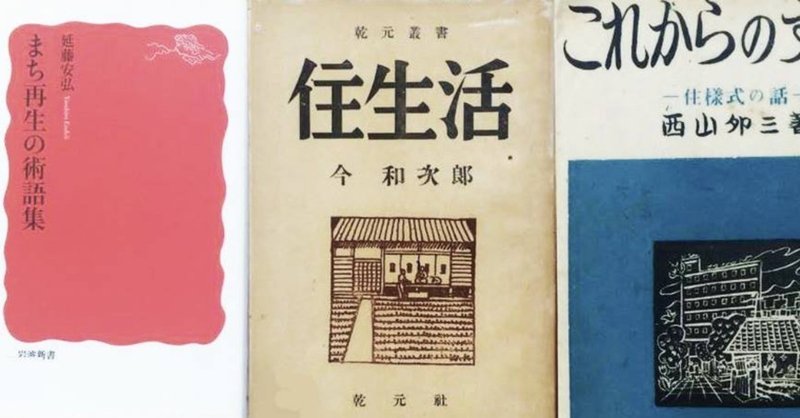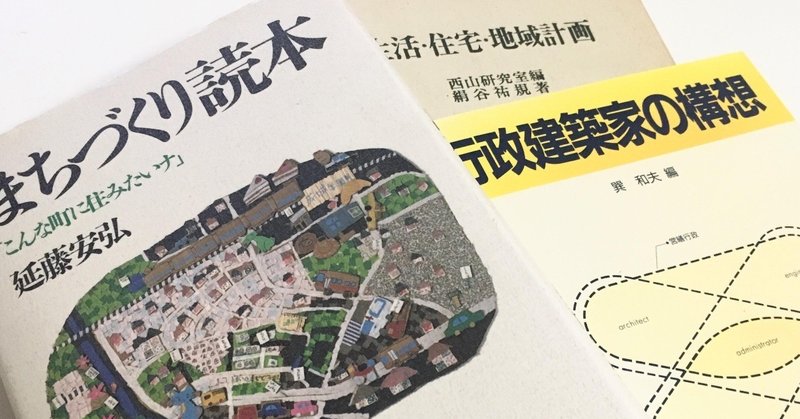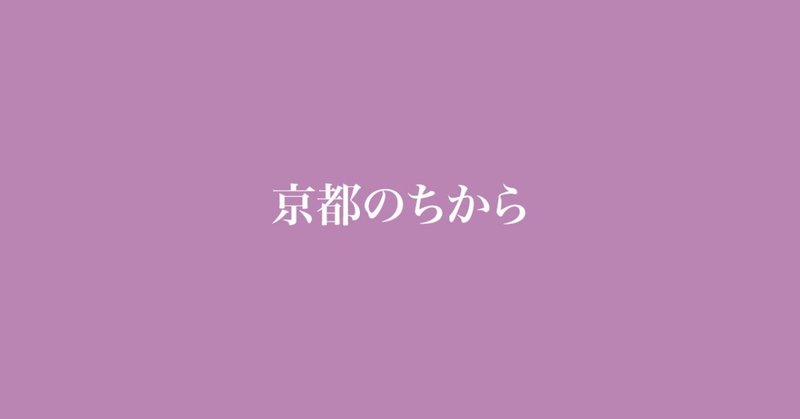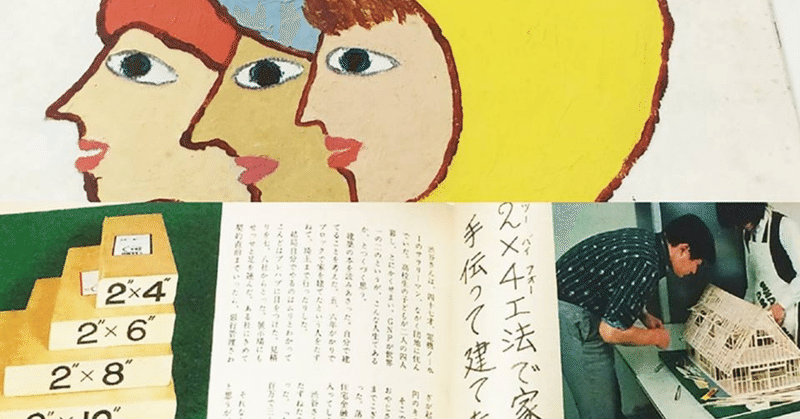#まちづくり

知ってます?「サードプレイス」の本当の意味。8つの条件をクリアして、社会的・経済的価値を、より高める。次の時代のカギはココ!
「サードプレイス」って言葉、聞いたことあります? 巷では「家と職場・学校との間の第三の居場所」のような意味合いで、カジュアルに使われるようになっているようです。けど、改めて調べてみたら、実はほとんどの人が、その意味を把握せずに使っていることがわかったんです。というわけで、今回は、一緒に「サードプレイス」とは何かを学び、考えましょう。 なぜ今、サードプレイスを考えたくなったのか?そもそも、どうして今さら「サードプレイス」という言葉が気になったのか。「喫茶ランドリー」をオープン