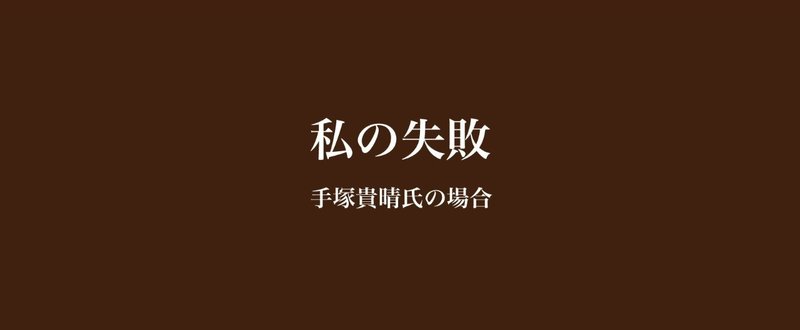2018年3月の記事一覧

Apple Michigan Avenue, Chicago: 川のほとりのランドスケープと一体化した Apple Store
Appleが2017年10月にオープンしたシカゴの新しいフラッグシップストア、Apple Michigan Avenue。人がつながる空間を目指した店舗は3層構造になっており、川に向かって設置された大画面が拡がるフォーラムが印象的です。 そのフォーラムを2階部分のソファから見下ろすと、背後には行き交う黄色い水上タクシーと、ミシガン・アベニューに架かる橋の風景が拡がり、河岸のランドスケープと一体化されたダイナミックな風景が目に飛び込んできます。 まずは簡単な、ビデオクリップ
¥300