
『こちらの事情』(森浩美)と不器用#読了
いつからだったろう。
私は親が大嫌いだった。
だからいうまでもなく、「家族」といる時間がまるまる幸せな時間とはいえなかった。新潟の田舎生まれである私は、父・母・弟のほかに祖母・曾祖母・叔母と暮らす10人家族だった。特に父と母といる時間が辛かったので、必然的におじいちゃん子となっていた。おいしい焼き芋を焼いてくれる“お芋のおじい”とゴルフが好きな“ゴルフのおじい”が大好きだった。
どのくらい嫌いだったか。
酢豚にはパイナップルが欠かせないといって、あろうことか大盛りトッピングしてくる人。
ディ○ニーランドのアトラクションや園内風景なんかより、耳カチューシャやシュシュを装着したくてたまらない人。
とある曜日の番組におけるクロちゃんの立場に、好き~♡とかほざきあがる人。
どうだろうか。目の前にそんなヤツがいたら。
そう。
大嫌いになる。

いや、大嫌いならまだよかった。
振り返ると実際は恐怖だ。ぎこちないくらいの恐怖。
そうだ、思い出した。保育園の頃からだ。
いま振り返ると些細なことなのだが、ある日から親に対して「こころ」を開きたくなくなった。
それは高校三年までつづく。
「こころ」を塞ぎ込んだ私は、卒業後の進路や進学先について親と話すことが嫌だった。上手く話せなかった。とても困難。自分なりにその“異常”の名前を模索した日もあった。診断名を自分なりに探した。それを告げれば、少なからず普通の子どもとして扱われなくなると思ったから。
まぁ、実際は意味なかったんだけどね。
おかげで母親は、蜂の巣をつついたように癇癪を起こすようになり、父親は力尽くでも私と話そうとした。
あれは私に対する、親の精一杯の働きかけだったのは言うまでも無い。反省すべき過去だ。
悪いことをしてしまった。
今ではそう思う。当時は思えるはずも無し。

さて、長くなったが本題。“家族”とは不思議なものだ。
家族=もっとも身近にあるはずの、居場所であるはずの人間関係である。
なのに、すべからくそれは不安定だ。
煩わしく、面倒くさく、しつこく、恐ろしい。
生まれることは、無条件で家族に属すことだ。
受け取り拒否不可能のハッピーセット。いや、アンハッピーセットかも。
果たしてどれほどの人が、生まれた瞬間からつづく自分の家族を、一から十まで肯定できるだろうか?受容できるだろうか?疑問なく過ごしきれるだろうか?
『こちらの事情』(森浩美)はそんな“家族”にまつわる短編8作が収録されている。

登場する人物はさまざま。
母であったり、父であったり、息子であったり、娘であったり、ペットも含む。
それぞれ、異なる家族に属している。
ある話では父が、ある話では母が、ある話では子どもが、ある話では親が。
十人十色というが、十人もいれば一つの家族だ。
でもそれは、十の色をもつ。決して一つの色に混ざりきらない。
家族とは、煩わしく、面倒くさく、しつこく、恐ろしい。
だからこんなにも「温かい」のだ。
だからこんなにも「思い出」にのこってしまうのだ。
この一冊に描かれる家族の姿とは、
「ありがとう」さえ伝えられない不器用なコミュニティだ。
1.【葡萄の木 】p105~
『葡萄の木』で描かれるのは「家族喧嘩」だ。
菜津子(母親)を主人公に、父(夫)・夕夏(姉:中1)・遼太郎/遼(弟:小3)の4人家族。
ちょうど、『あたしンち』と同じ構図だ。

この物語はぶどうが大好きな息子の発言から始まる。
「オレ、一度でいいからピオーネ、死ぬほど食べてぇ」
突拍子もない弟の言葉に「ばーか」と反応する娘。
その言葉づかいが汚いことを「もうっ!」と叱りつける私。
「パパさぁ、一生のお願い」
息子の切り札・“一生のお願い”を頼みこまれて笑う父。
和やかないい一コマですよね。うん。
そんなこんなで久々の家族旅行が決まった。息子の短い一生を掛けたお出かけ、ぶどう狩りに行くことになった。
遼はもちろん待ち遠しくてたまらない。が、「ばーか」とイジっていた夕夏も、「しかたないな~」と言いくるめられた態度の夫も主人公も、なんだかんだ言って、息子の一言で決まった久々の家族旅行を心待ちにしていた。
しかし、前日に事件は起こる。
旅行前日の晩に仕事から帰ってきた夫の機嫌が悪かったのだ。きっと職場で何かがあったのだろうと察しはつくのだが、食卓に漂うピリついた空気にさえ娘は気づかない。
些細なことだった。娘が食事中にケータイをいじっていることを注意しただけだった。少し口答えをしただけだった。夫は娘のケータイをボキッとやってしまう。
......とうとう起きてしまった。
普段であれば、たしなめる態度で向き合えたはず。いつもは冗談も言ったりする人だった。だったはず。
だが、運悪く夫の機嫌は斜めだった。
楽しみにしていた旅行。家族みんながそろって過ごす旅行。
その前日のできごとである。
さて、では肝心の旅行はどうなったのだろうか?個人的に『こちらの事情』の中でトップクラスの名作であると思うので、実際に読んでもらいたいなぁ。
だが少し引用しよう。ぶどう園での遼の発言だ。
ふと気づくと、息子は隣り合った房ばかりにハサミを入れている。
「ねぇ遼、もっといろんな所の葡萄を見てから穫らなくちゃ」私は声を掛けた。
「いいんだよ」
「だけど、他の場所にも美味しそうなのがあるかもよ?」
「うん。だけど可哀想じゃん」
「可哀想?」
「ほら、みんな同じあの木から伸びてきてるんだ。」
息子は一本の木を指差すと、枝、蔓、房の順番に指先で辿った。
「この葡萄はさぁ、たぶん家族なんだよ。だから別々にしたら可哀想じゃん」
この発言をしたのが、四人家族で一番年下の立場にある遼のものであることが重要だ。家族というキーワードを使っていることも注目できる。
些細なことでぶつかってしまうのも、少しのきっかけで嫌いになってしまうのも。家族が一本の木でつながっている共同体だからなんだ、と改めて教えてもらった。
あと、シャインマスカット食べたくなった。
2.【妻のパジャマ】p45~
この物語の主人公は、ある男である。
子どもは大きくなって家を出ているので、妻の紀代子と二人暮らしだ。夫が「あれ」といえば、妻は新聞紙なのかコーヒーなのかメガネなのか、聞き分けて持ってきてくれる、長年連れ添った熟年夫婦である。
「あ、そうそう……。ちょっと相談があるのよね」
妻の言葉からドラマは起きる。
いや、正確にはその言葉と同時に差し出してきた一枚の紙切れが火を付ける。
三行半で済んでしまうペラ一枚を「はい、これ」と。
三行半で済んでしまうはずがない重厚な夫婦生活の精算書。
離婚届である。
「あ、え、まさか、お前、男か?」
男の困惑はさておいて、妻の意図はなんてことはない。
「え、男?ははは。もう、やだ。あーはっは」
「自由になりたいのよね」
「靴の中にちっちゃな石があることに気づくのよ。そうするとね、楽しい気分が半減するわけ」
「もう、あなたは私のこと、何も分かってないのね」
長く続いた子育てが一息ついてから、時間とお金に余裕が出始めた熟年夫婦が、それぞれ自分の好きなように別居をしはじめる。そんなことは今ではよくあることだし、価値観も分かる。
だが、まさか自分の妻が……。男のショックはそこだった。
振り返れば、長年連れ添った時間は一丁前でも、中身に関しては反省ばかりだと考える。「もう。靴下と下着は裏返しに脱がないでって言ってるのに」とか、妻はことあるごとに小言をもらしていた。
自由になりたい、といっていたのも、そんな日頃の不満について漏らした言葉だったのだろう。大好きなバウムクーヘンや、友達と旅行に行ったりもしたかったのかもしれない。それに気づけてなかっただけで。
幸せだと思っていたのは自分だけで、もしかしたら妻にとっては不満の毎日だったのかもしれないと、走馬燈のように振り替える。
数日後、妻がぎっくり腰を起こす。「あー、こりゃぎっくり腰だな」と声を掛けると「何で、そんなに落ち着いているんですか、もうっ。あなたはホントに優しくないっ」。怒られた。
ぎゃーぎゃー言うので救急車を呼ぼうとするも「ご近所に知られたら恥ずかしい!」といって止められた。ワガママ。
結局、妻をタクシーで運び入院ということになった。ここからタイトルの回収がされる。
入院中の妻に、着替えのパジャマを持って行ってあげなければならない。
男は家の押し入れから、地味めなベージュ系の下着とグレーのパジャマを詰めてもって行く。「これでよし」
「これ、冬物じゃない。もう、こんな簡単なお使いもできないんだから」
怒られた。もう一度取りに帰ろう....... ションボリ
だがしかし男は、
妻の“どの”パジャマを持って行けばいいかわからないのだ。
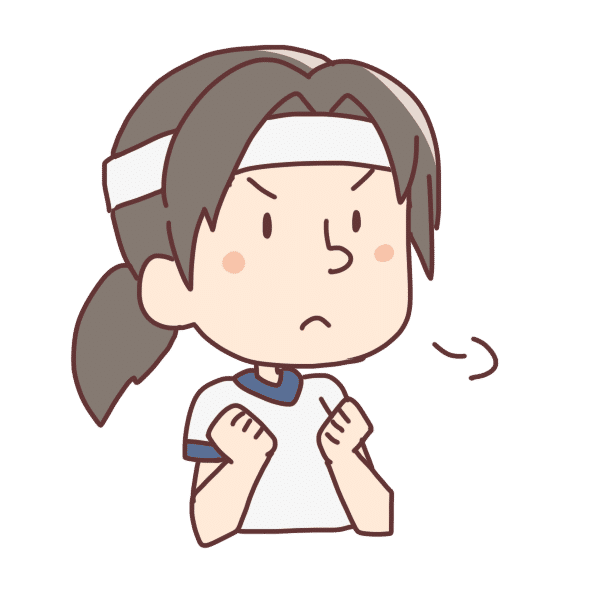
ここから男の奮闘が始まる。わざわざパジャマを取りに帰ったのにも意味がある。
男は、妻が着るパジャマが分からないのではない。
妻が“喜んでくれる”パジャマが分からなかったからだ。
入院中の妻のために、喜んでもらうために、男はがんばるのだ!!
この話の大好きな点は、この二人のかわいさにある。「あれこれ気遣ってあげても、不器用だからなかなか上手くいかない夫」と「そんな夫に不満も言いながらも、ちゃんと気づいている妻」いいカップルだよね~。
ある男は、家族の中では父であり夫である。がしかし、遡るとふたりは文字通り愛し合ったカップルなのだ。些細なことで気づくことがある、目の前にいるこの人は「自分が選んだ人」なんだったと。
この話はこう〆られる。
「オレがお前のこと、何も分かってないって言ったよな?」
「ええ」
「でも、ひとつは確実に知っているぞ」
私は紀代子の方へ向き直った。
「は?」
「お前のパジャマのサイズはMだ」
「ふふふ、ばっかみたい」紀代子は笑いながら、バウムクーヘンのかけらを口へ運んだ。
3.【短い通知表】p191~
先に書くと、この話は「泣いた」。なぜ映画化していないのだろう。
主人公はある会社の上役。部下と年の瀬に飲み行くところから始まる。
普通、この時期は早く家に帰って「家族」とともに過ごす。または年末年始に向けて「家族」と準備するために帰路につく。帰るべきコミュニティの大切さが身に染む季節だな。
でも今年、男は部下と“語る”ことで過ごすことにした。
ちょうど春の頃に、妻の潤子が亡くなったからだ。
同じ部署の奥さんが入院したらしい。
それが亡くなる前の日に妻と交わした会話だった。日常の何気ない話題と、とりとめもない軽い気遣いでしかなかったが、時折「胸が痛い」とか「頭痛がする」とかいう妻の姿を目にしていたからこその気遣いだった。
「一度、しっかり検査しておけ」
「はいはい、分かりました。その内、行ってみるわ」
それから一ヶ月後に、深夜トイレに立った妻はそのまま冷たくなっていた。
「だから、早く検査に行けと言ったんだ......」
どうしたってもう遅い言葉しか、かけてあげられなかった。
男は部下と焼き鳥を食べながら、妻がいた頃の家庭について語る。「通知表制度」という、オリジナルの家族ルールだ。
息子・娘が持って帰ってきた“通知表”を悪用した、父親の思いつきなのだが、要は「日頃の行いの成績ポイントで、誕生日やお年玉の内容を決める」というものだった。こういう、限定的な遊びがあるというだけで、家族の内が明るい物になっていくから素晴らしい。
だが、それが自分にも向くとは思わなかった。
娘が妻と共闘し、「お父さんだけ何もないのはズルいー」と言い出す。おかげで、女性陣を中心にした主張から、主人公も日頃の行いをチェックされることになったのだ。
主人公は会社では局次長という評価を得ているベテランさんだ。
だが、こと家庭の中では評定員が悪い、何せこの制度の第一の被害者である子供たちが復讐をはらんだ目で注視しているからだ。“食事中にオナラをした”、“遊びに連れて行く約束を守ってくれなかった”、などなどマイナスポイントを重ねてしまう。自分が妻や子供たちに渡す通知表には「80点、合格」などと記しているが、向こうから自分に渡されるものは不平不満でいっぱいだった。
「さんざんな赤点三昧だったよ」と部下に愚痴をこぼす。おもしろいことをやってたんですね、と部下は聞き入っている。100点の家族姿に見えたのかも知れない。
「だが今年、オレが通知表を女房に書くとしたら“0点、バカヤロー”かな」冗談交じりのトーンで、男はそう続けた。
次の日は子供たちと大掃除の日だった。子供と言っても今や二人とも、大学を卒業した成人である。
3人で1年間散らかした一軒家のあちこちを綺麗に片付ける。この郊外の新興住宅地にある家も、妻と一緒に決めたんだったと思い出す。ドラマやバラエティでたびたび目にしていた、おしゃれな郊外に憧れていた妻の願いを叶えるために、会社からは遠くなってしまう葛藤を振り切って購入した一軒家だ。あの頃は、子供たちもまだお腹のなかにいたんだったな、と妻がいなくなった家で思い出が湧いてくる。
そして、大掃除も終わる頃、最後にクローゼットを片付ける。妻の洋服でいっぱいのクローゼットだ、宝石や小物なども箱にしまってあり、片付け好きの主人公でも手を焼くエリアだ。だから最後に回していた、のかもしれない。
ため息交じりに整理整頓していると、3段引き出しの小さな木箱をみつける。そこには「明日やること帳」と書かれたノートが入っていた。パラパラとめくると、日付と共に次の日にやることのリストが箇条書きで記されていた、いわば妻・潤子のTo Do リストだった。
どうやら、随分前から忘れっぽくなっていたようだ。脳の部分に不安があったようだ。自分が心配するよりもずっと前から、その気配はあったようだ。
“午前中、美容院の予約をすること”、“清水さんとお茶”などなど。
亡き妻の日常で、「忘れてはいけないこと」がつらつらと記されていた。
「ん?これは......」
男はそのノートにあることに気づいた。
それはあの時、娘と「お父さんだけ何もないのはズルいー」と言っていた日を思い出させる。そう、自分にも通知表をつけることを決めたのは潤子だった。子供たちが大きくなって通知表が必要なくなっても、妻だけは続けていた。

この感動は、私の読了記録に残すべきと思いピックアップした。
『こちらの事情』には他にも、「晴天の万国旗」や「福は内」、「甘噛み」など全8篇が収められている。
冒頭でさんざんなことを記したが、結局は反省しているので咎めないで欲しい。そんな私でも感動したから💧
ぜひ一読してみて、家族というテーマに温かくなってみてはどうだろうか。
〆
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
