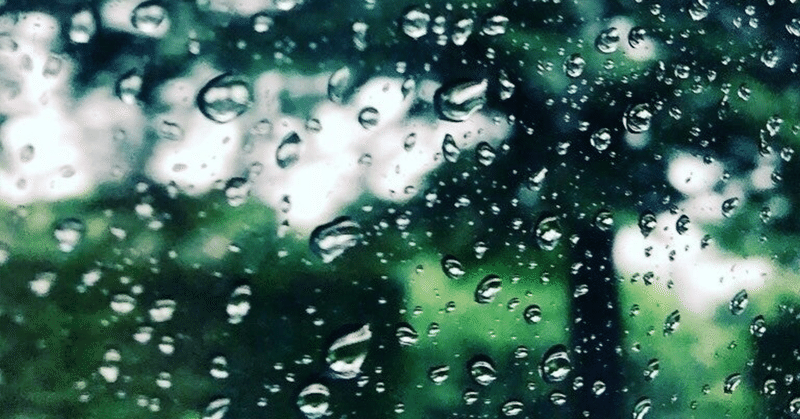
美しい瞬間には、名前がある。 〜雨編〜
雨の日が続いている。
あなたにとって「雨」はネガティブなものですか?
それともポジティブなものですか?
・ ・ ・
日本語の「雨の表現」を調べると、たくさんの種類がある。
いつの時期の、どんな雨にでも、名前をつけて愛でる。
そんな日本人のセンスが好き。
今回は、「雨」を切り口に素敵な言葉をご紹介します。
・ ・ ・
桜の季節に降る 花時雨(はなしぐれ)
ただの「時雨(しぐれ)」は、冬の季語。
秋の末から冬の初めにかけて、ぱらぱらと通り雨のように降る雨のことを指す。冷たく寒いイメージ。
「春時雨(はるしぐれ)」は、暖かくなって木々が芽吹いた季節の時雨。
「花時雨(はなしぐれ)」は、桜が咲く頃の時雨。
季語で使う際は、立春〜桜が咲く前までが「春時雨」、桜が咲いたら「花時雨」。
時雨に「春」や「桜」がつくだけで、暖かい春が近づく嬉しさが伝わる。

旧暦5月 梅雨に降る 五月雨(さみだれ)
五月雨とは梅雨の雨のこと。長く続く雨。「さつきあめ」と読むこともある。
ここでいう「五月」は旧暦なので、現代の暦でいう「六月頃」にあたる。夏の季語。
ちなみに、「五月晴れ」も梅雨の時期(六月頃)の晴れ間を意味する。ゴールデンウィークの晴れの日に使いたくなるけどご注意を。

夏の日照り後に降る 雨喜び(あまよろこび/あめよろこび)
日照りが長く続いたあとに降る雨のこと。
同じような意味に、「恵みの雨」「慈雨(じう)」「喜雨(きう)」という表現がある。いずれにも、自然への敬意を感じる言葉。

七夕に降る織姫彦星の涙 催涙雨(さいるいう)
七夕の日に限って雨が降る。
昔の人は、その雨に「催涙雨(さいるいう)」と名付けました。
催涙雨には諸説あり、大きく分けると3つの解釈がある。
1つ目は、織姫と彦星が一年ぶりに出会えて嬉しくて流した涙。
2つ目は、七夕の夜に再会した織姫と彦星が再び別れることを悲しむ涙。
3つ目は、雨で天の川の水かさが増し、会うことができないことへの涙。
あなたは、どの涙だと思いますか?

富士閉山の祓い清め 御山洗(おやまあらい)
富士山は7月前半に山開きをして、9月中旬ごろに閉山する。
その閉山のタイミングで降る雨のことを「御山洗(おやまあらい)」と呼ぶ。
多くの登山者で汚れた霊山富士を洗い清める雨という意味。
「清めの雨」という言葉もあるけど、雨は神道においては縁起の良いものともされている。水や雨には、きっと何かしらの力があるに違いない。

神事 神嘗祭の翌日に降る 伊勢清めの雨
こちらは、まさに清めの雨。
旧暦の9月17日に行われる神嘗祭(かんなめさい)は、天皇がその年の新穀でつくった神酒(みき)と神饌(しんせん)を伊勢神宮に奉納し収穫の感謝を捧げるお祭り。その翌日に降る雨を「伊勢清めの雨」と呼ぶ。
参拝の際に降る雨は、お清めの力があって縁起が良いとされるらしい。

山茶花の時期のぐずつく雨 山茶花時雨(さざんかしぐれ)
山茶花が咲く秋から冬にかけて、連続して降る雨のことを「山茶花時雨(さざんかしぐれ)」「山茶花梅雨(さざんかづゆ)」と呼ぶ。
他の季節と比べると、色味の少ない冬。そんな季節に咲く鮮やかな赤い山茶花は、特別な花だったのでしょう。
冬の雨に「山茶花」の名前をつけるセンス、たまりません。

・ ・ ・
日本語には、雨にまつわる言葉が1200以上あるという。
季節や情景によって、雨の呼び名を変えてきた日本人。
自然との距離の近さ、愛、ユーモア。
独自のセンスを感じます。
雨の言葉を知れば知るほど、雨の日の楽しみも増えていく。
こういった素敵な表現を、未来に受け継いでいきたい。
参考図書:
=== お わ り ===
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
