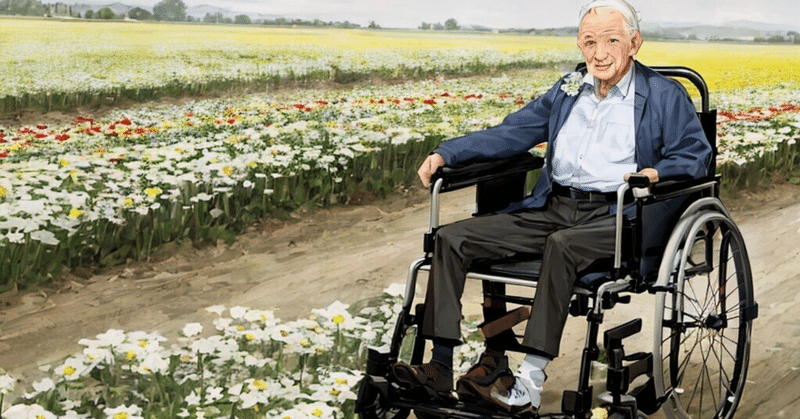
これからの高齢者として考えること
これからの高齢者として考えること
高齢者とは、人生の先輩であり、年齢の上の方でありますが、ここでいう高齢者は、年金受給をされて悠々自適に余生を過ごされている方です。
これから、年金受給が数年後に始まるような、50代の自分のようなものは、今の高齢者の方と違って、おそらく仕事をリタイアするということがないのではないかと思うのです。生涯、死ぬその時までおそらく多くの方が現役です。それは生活のためと、社会の風潮がじわじわと整ってきているのもあります。
これは、仕事をしていたいからというよりも社会構造が、ご存知のように若い世代が減少し、お年寄り世代の増加の少子高齢化だからです。
若い人が少ないならば、自分で働いて自分たちで支え合う仕組みが必要です。
しかしそれにはいろいろと環境も整えないといけないでしょう。
そして、若い世代、体力のあるうちにできる仕事と、年齢を重ねてからの仕事内容は得意不得意が違うのは明らかです。しかし、さまざまな経験を持っているのが人生の先輩たる高齢者のかたの強みです。
現在は65歳から国民年金が開始され、75歳からを後期高齢者として位置付けています。下記の経済産業省の資料の中でも65歳からをみんなで支えるから75歳からを支えるに変えれば、例え30年以上先の未来でも2.3人で一人の高齢者を支えられるとしています。それが今のままだと、1.3人で一人の高齢者の負担を持つことになるとのことです。
実際、健康だ元気な方も増え、仕事を本当は続けたいのにうまく雇用に結びつかなかった高齢者の方も多いようです。
それならばと、政府もご自身で就業の機会を作ることも含め、支援制度も打ち出してもいます。
今、高齢者の方に何か支援を提案しても最初に聞かれることは無料か有償かです。別段こちらも仕事として責任を持って提供するか、無責任と言っては語弊がありますが、提供度合いをその返答で考えるのと、相手を軽く見てるかどうかも伝わってきます。聞き方が本来は違うはずです。
一方、リタイア世代だから無償でというなら、最後まで現役で皆がお互いを過ごし、お互いに必要な時に支え合いの仕組みを作る方がよりよいのではないでしょうか。
ずっと同じキャリアでいれないからこそ、自分のできることを常に考えて、ブラッシュアップして、また新しい環境で自分の役目を誰かのために生かす社会になると今よりもQOL(人生の質)が上がるのではないでしょうか。
政治家の方は長いこと、高齢の方がキャリアを積んでこれた数少ない仕事でしょう。これからは若い方が政治家となり、高齢の方は他の仕事の選択肢の幅が広がると、そどのせだいももっと生活しやすくなるかもしれません。
今のままの社会だともうすぐ高齢者になる一人として考えます。
(参照)2024/5/9
経済産業省 2050年までの経済社会の 構造変化と政策課題について 平成30年9月
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/2050_keizai/pdf/001_04_00.pdf
内閣府
第2章 多様化する職業キャリアの現状と課題(第1節)
https://www5.cao.go.jp/keizai3/2017/0118nk/n17_2_1.html
リ・そうるけあ
高山和 たかやまあい
